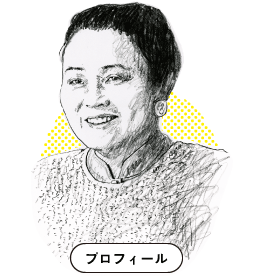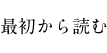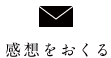| 米原 |
通訳は、あくまでも「家来」なんですよ。
「ご主人」は、話し手と聞き手です。 |
| 糸井 |
そうですよねえ。
それが、どこまで行っても、矛盾を生みますね。 |
| 米原 |
そうなんです、絶対に‥‥。
でも、
「従属している者を抱えてはいるけれど、
実は支配している者が従属している」
という関係は、いつも、あるでしょう? |
| 糸井 |
マゾが強気のサド・マゾとかね。
「もっといじめて!」って。
言われてるから攻撃しなきゃいけない。
|
| 米原 |
そうそう。
結局、通訳がいないと、
何にも通じないわけですから。
通訳が下手だと、
どんな高邁なことをいっても、
すごく幼稚なこととしてしか、
伝わらないわけです。
だから、
本当は支配しているんですけれども、
でも、通訳は、個人の主体としては
何にも言えないんですよね。 |
| 糸井 |
ひどい立場だよなぁ。
米原さん、通訳に向いていたんですか? |
| 米原 |
いや、ぜんぜん向いてないですよ。
「わたしには向いてない」と思っていました。
向いてないと思っていたけれども‥‥。 |
| 糸井 |
でも、いますよね、ここに。 |
| 米原 |
そうですね。
やりはじめたら、とてもおもしろいと思った。 |
| 糸井 |
あぁ、「向く」「向かない」じゃなくて、
興味の方がグッと前に出たんですか。 |
| 米原 |
はい。
最初はもちろん、
そのままでは食べていけないから、
通訳をはじめたんですけどね。
だから、
「本当は私に最も向いた別の職業が
この世の中にあって‥‥」というか、
そういうことは、最初は思っていました。
そんな「天職」に出会うまで、
通訳は時間の割にはお金がいいし、
私はロシア語というのもある程度できるから、
「これでまずは食いつないで、
食いつないでいる間に天職に出会おう」と。
そう考えていたら、
何か食いつなぎの仕事が、
すごくおもしろかったという。 |
| 糸井 |
もうちょっとさかのぼって、
これはもう何度もお答えになっていることで、
面倒くさいかもしれないですけど、
ロシア語との出会いについて
直に聞いてみたいんですけれども。 |
| 米原 |
私が小学校3年、9歳のときに、
父親の仕事の都合で
チェコスロバキアのプラハに移り住みました。
そこで結局、
5年過ごすんですけれども、
最初、親は私を、地元の学校に
入れようと思っていたそうなんです。
しかし、よく考えると、チェコ語だと、
教科書も先生も、日本に帰ってから手に入らない。
「ロシア語なら
ずうっと勉強が続けられる」というので、
ロシア語の学校に入ったんです。
ソ連の外務省が経営する
チェコスロバキア在住のソ連人のための学校でした。
だから、すべて授業はロシア語で、
ソ連からやってきた先生が教えるという学校です。 |
| 糸井 |
そのときの戸惑いが
やっぱり聞きたくなるんですが‥‥。 |
| 米原 |
もうすでに、3年生でしたから…… |
| 糸井 |
とんでもなくツライですよね。
|
| 米原 |
とんでもないです。
だって、ロシア語は
ぜんぜんできなかったんですから。
まったくできないところにほうりこまれて、
毎日通わなくてはいけないでしょう?
私、学校へ行くのが毎日ツラくてツラくて、
本当に行きたくなかったですね‥‥。
だって、何にもわからないのに、
一日じゅう教室に座ってなくちゃいけなくて。
ときどき意地悪な子がいて、
日本から持ってきた私の筆箱なんかを
取り上げちゃったりするんだけど、
それに抗議もできないでしょう?
言いつけもできないでしょう?
それから、みんなが笑っているときに
一緒に笑えないでしょう? |
| 糸井 |
9歳の子がねえ‥‥。 |
| 米原 |
あれはつらいですね。
本当に、
「いつこの地獄は終わるのか」
と思いましたね。
‥‥で、肩凝りと偏頭痛。 |
| 糸井 |
カラダに来ちゃう。 |
| 米原 |
体に来ちゃうんですね。
きっと大人だったら、自分で荷物をまとめて
帰っちゃうと思うんです、あんな状況に置かれたら。
でも、子供は、しょうがないですね。 |
| 糸井 |
親はそのときにどういう立場をとりました? |
| 米原 |
親は、私が学校から宿題を持ってくると、
その宿題を全部辞書引いて、
日本語に翻訳してくれましたね。 |
| 糸井 |
支え棒になってくれたんだ。 |
| 米原 |
そして、だんだんだんだん、少しずつ
薄皮がはがれるようにわかってくるんですね。 |
| 糸井 |
僕らみたいに外国語が全く苦手な人間にとって、
その薄皮までには何があるんだろう、と思うんです。 |
| 米原 |
日本語だって、
結局ほんとうは少しずつそうやって
覚えてきたわけですけれども。
例えば名詞は、コップとかそういうものは
だんだんだんだん、わかってきますよね。
それで、本当に必要な単語というのは
人間頻繁に使うから、学習というのは
ドリルで何度も何度も繰り返すことですよね。
何度も何度も耳にしたり、
何度も何度も文字で目に入ったりすると、
自然に身についていくんですよ。 |
| 糸井 |
接する機会を
圧倒的にふやしていくということですね。 |
| 米原 |
ふやしていく。
だから、それは、外国語の才能あるなしは
全然関係ないんですね。 |
| (つづきます) |