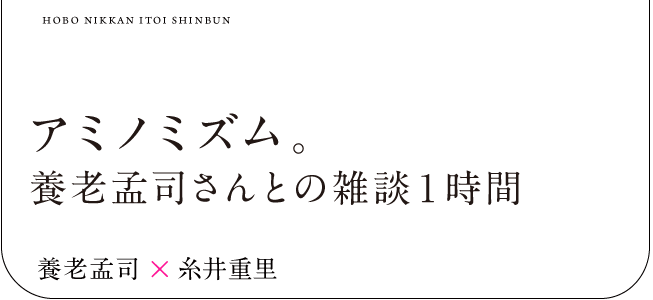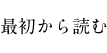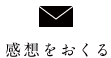| 糸井 |
ツイッター文化に慣れてくると、
最後は、瞬発的な悲鳴の
連続になっていくんですね。
で、圧倒的にそっちが強いんですよ。
ロジックをしゃべろうとする人は
そこに嫌気が差しちゃうんです。
悲鳴に巻き込まれて。
これは気をつけなきゃいけないな、
と思ってて、
カギはなんだろうなと考えたけど、
それをつなぐのはアートなんですよね。
アート&サイエンスなんですよ。
まさしく。 |
| 養老 |
うん。 |
| 糸井 |
で、文学の領域が、両方を見渡せる
唯一の高台じゃないかなぁ、と思っていて。
悲鳴は文学じゃないですから。
いま、インテリが
いままでさんざん悩んできたテーマばっかり
ずーっと書き続けてる理由は、
そこの高台で見てるのかなと思って。
じゃあちょっと、うちはゆっくりに進めて、
ツイッター的な悲鳴から一回、
距離を置こうとしてるんですけど。 |
| 養老 |
大事なことだと思います。
アートとサイエンスの話でいうと、
例えば、意識の問題を
議論しようとすると、
たいていね、いわゆる
エセ科学になってしまうんです。 |
| 糸井 |
ああー。 |
| 養老 |
当たり前でね、
きちんとした論文書いて
研究費をもらって論文書いて、
給料で仕事をしてる科学者は、
左脳を重視するんですよ。 |
| 糸井 |
そうでしょうね。 |
| 養老 |
そうやって働くためには、
論理的に一度決めたらそれで進める、
というようなやり方が前提になるんです。 |
| 糸井 |
うん。 |
| 養老 |
だから、
目の前の現実を吟味できないんですよ。
そうすると、自分の範疇以外のことに結び付けて
なにか創造していくことができなくなる。
「俺たちみたいにきちんと仕事してないから、
あれはエセだ」と言うんですよ。 |
| 糸井 |
うんうん。
なるほど。 |
| 養老 |
わかるでしょ(笑)。
左脳でばかり考えるとそうなってしまう。 |
| 糸井 |
ああー。 |
| 養老 |
でも、システムは必ずそうなっていきます。 |
| 糸井 |
うーん。 |
| 養老 |
だから、いまのアートとサイエンスの話は
文学や感性といった、
右脳の領域になると思いますよ。 |
| 糸井 |
うんうん。
で、ただの原始人じゃないから、
科学者の言ってること理解するっていう脳を
もう1つ持ってますから、
引き裂かれるわけですよね。
文学っていうのは、その引き裂かれがないと、
通用しないっていうことですよね。 |
| 養老 |
左右の大脳半球が分かれる
「分離脳」って知ってますか?
左右の脳は、脳梁という線でつながってるんです。
それが切れている状態です。
そうすると、右と左が別々に動くわけです。
一見しただけではわかりません。 |
| 糸井 |
ああー。 |
| 養老 |
ところがね、おもしろい患者がいて、
前に、アメリカ人で、
左右の脳を分離した人がいるんです。
血管腫を外科の手術で取ったときだそうです。
すると、外に出るとき靴下を履くのに、
10分ぐらいかかってしまった。 |
| 糸井 |
ほう‥‥。 |
| 養老 |
で、本人は脳をやられたから、
手がうまく動かないとかね、
勝手な理屈を後から考えるんです。
それをテレビカメラを横に置いて、
何をしているかずっと撮すんですよ。
で、解析するとよくわかるんです。
左脳は右手に、外に行くために
靴下を履くよう指示を出していますから、
右手は一所懸命に足を持ち上げて
靴下を履いているんですよ。
ところが、同時に左手が脱がしているんですよ。 |
| 糸井 |
えっ(笑)。 |
| 養老 |
だから、履けない。 |
| 糸井 |
手伝ってくんないんだ。 |
| 養老 |
手伝ってくれないならまだしも、
逆さまのことをやっているんですよ。 |
| 糸井 |
あ、そういうことか。 |
| 養老 |
そう。
だから10分も掛かっちゃうんですよ。
なんとか悪戦苦闘の結果、
靴下と靴、履くでしょう。
で、外出しようとするわけですよ。
そうすると、住み慣れたうちなのに、
ドアノブを掴んで、「開かない」と言うんですよ。
録画を見ると、
本人は気がついてないんだけど、
右手がドアノブを開けようとしてるのを、
左手が押さえてるんですよ。 |
| 糸井 |
へぇー! |
| 養老 |
右脳と左脳はおそらく
多くの場合、競合の関係にあるんですよ。
この場合は、左右の情報交換ができなくなって、
それぞれが別のことをしてしまう。
中枢での
競合関係で、
一番よく知られているものに、
両眼視野闘争があります。 |
| 糸井 |
うんうん。 |
| 養老 |
左右の目に違うものを見せたときに、
どちらかだけ意識に上ることです。
時間が経つと上がってくるものも変わる。
1つの物を両目で見ますよね。
同じ物を、右脳でも、左脳でも見るわけです。
しかも、たとえば左手前にあるものを、
ぼくが見るときに、
右目の外側の視野に入ると同時に
左目の内側の視野にも入ってるはずですよね。 |
| 糸井 |
はいはい。 |
| 養老 |
わかりますでしょ。 |
| 糸井 |
わかります。 |
| 養老 |
左目の内側の情報は、右脳の方に入って、
右目の外側の情報も、同じ脳に入る。
同じ像が脳に入ってくるわけですけど、
右と左から、右左、右左、右左、右左
って、1ミリぐらいの幅で、
皮質が順繰りに入ってるんですよ。
問題が起こるのは、
眼軸がずれている場合で、
ずれている方の目が競争で、
負けてしまうんです。
そうすると、左がずれているとすると、
互い違いに右左、右左、右左
ってなってたのが、右、右、右‥‥、
になってしまう。見えない部分が出るんです。 |
| 糸井 |
はい。 |
| 養老 |
そんなふうに目を例にしても、
左右は案外、競争関係にあるんです。
一番おもしろいのは、意識的に考えている以上は、
われわれが論理的に考えて
正しいと言っている答えは、
あくまでも左脳の働きなんですよね。 |
| 糸井 |
うんうん。 |
| 養老 |
意識の限界までくると、
正しいか、正しくないか、
よくわかんないわけですよ、結局。 |
| 糸井 |
最後に、なんらかの形でジャッジが
あるわけですよね。 |
| 養老 |
そうそうそう。 |
| 糸井 |
ジャッジは、両方の矛盾のままになされてる。 |
| 養老 |
だから、人間が悩むという場合は、
まさにその競合なんです。
結局、あっちこっちで抗争が起こって、
それを悩むと呼んでいるわけですよ。 |
| 糸井 |
うんうん。 |
| 養老 |
論理的にはこうしなきゃいけない、と、
左脳は納得していても、
実際にそれをやると、
血圧が上がって入院するようなことになっちゃう。 |
| 糸井 |
なっちゃう、なっちゃう。
ジャッジは何がしてるかというと‥‥ |
| 養老 |
わかんないんですよ。 |
| 糸井 |
わかんないんですか。 |
| 養老 |
ジャッジがあるって考えが
おかしいんじゃないですか。
網の目なんですよ。
全体としてこうなったというしかないんです。 |
| 糸井 |
つまり、“仕方なく”っていう
形を取ってるわけですね。 |
| 養老 |
よく言えば“必然”ですね。
全体としての必然で決まってくる。 |
| 糸井 |
だから立場をどかないんですね、みんな。 |
| 養老 |
(笑)。どうなんでしょうね。
歴史が入ってますからね、
立場となると。 |
| 糸井 |
そうですね。
そこに依拠しないと
自分としては決められないから。 |
| 養老 |
そうそう。
できるだけ判断を外に預けておいて、
左脳的に言えばシステムや法律で、
がんじがらめにしていくでしょう。
だから、ぼくは文明というものが滅びるとしたら
考えによってはその自縄自縛が原因になる気がします。
同じシステムを踏襲して
ずーっとやっていくことになるから。 |
| 糸井 |
おもしろ怖いですね。 |
| 養老 |
人間の作り出すものには、
肝心なところにどこか必ず穴がある。
その穴は本人にはわからないんです。
だって、機械を見ても、
今日は顔色が悪そうだな、
とかわからないじゃないですか。
それが多少出ている世界でないと
人間とはものすごく、折り合いが悪いんですよ。 |
| (つづきます) |