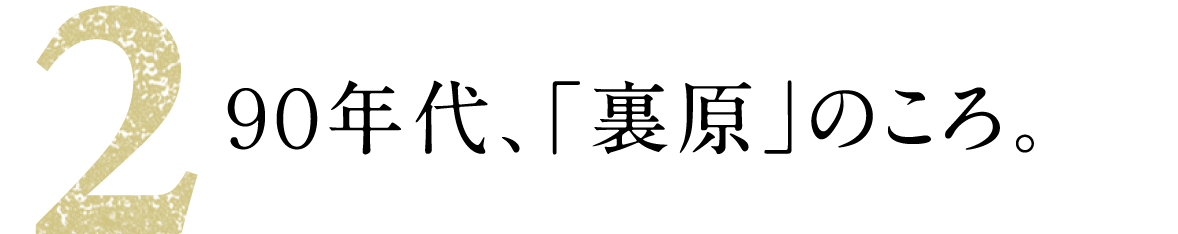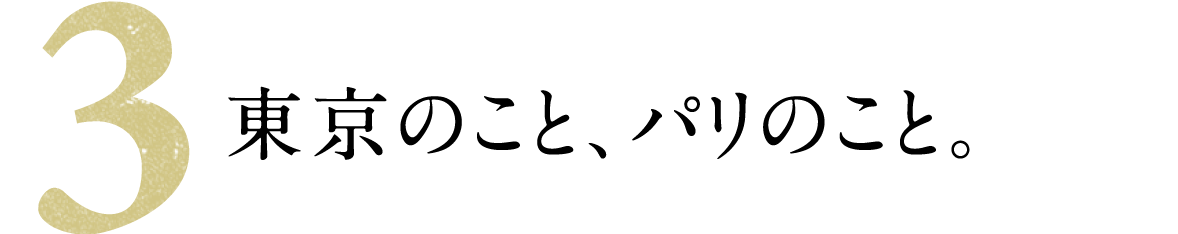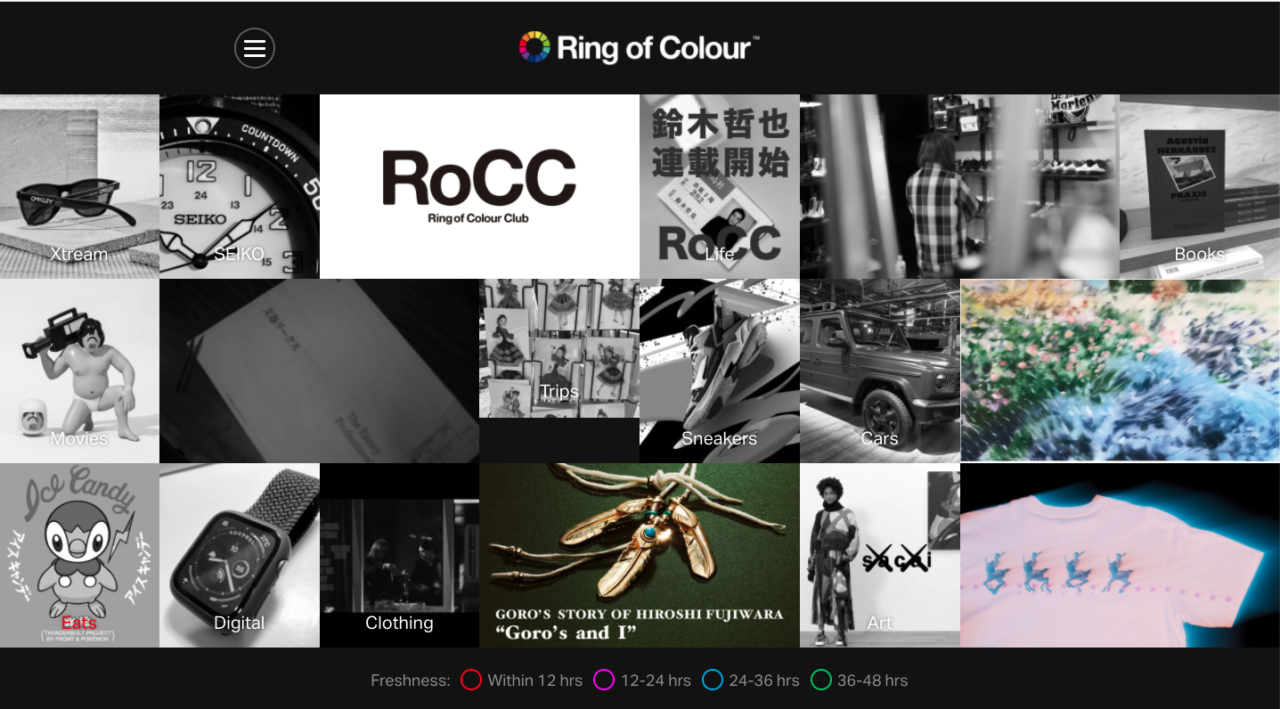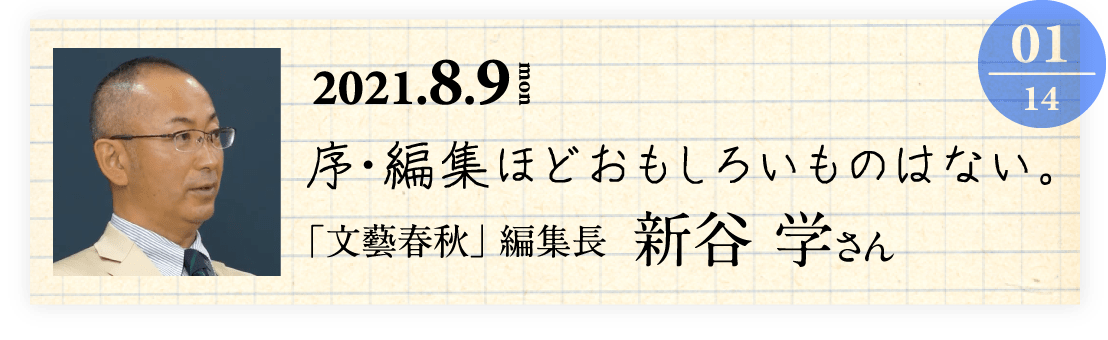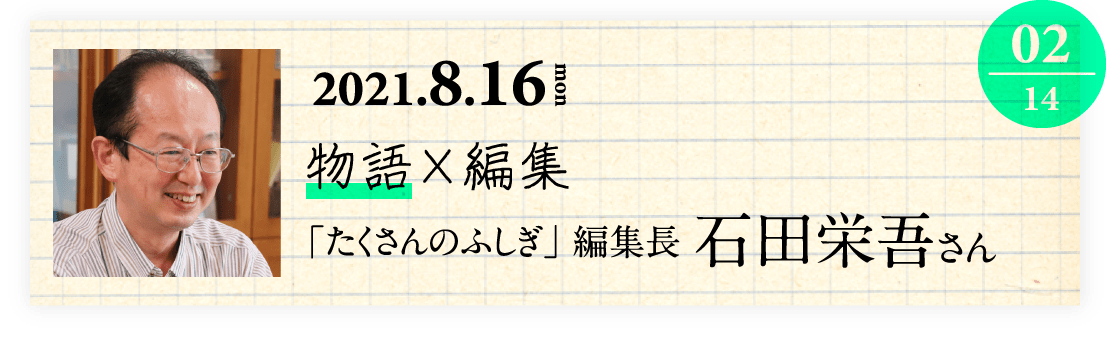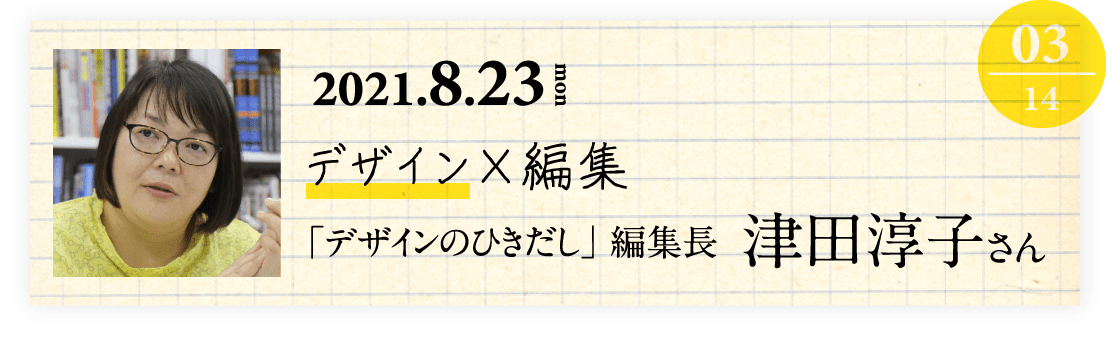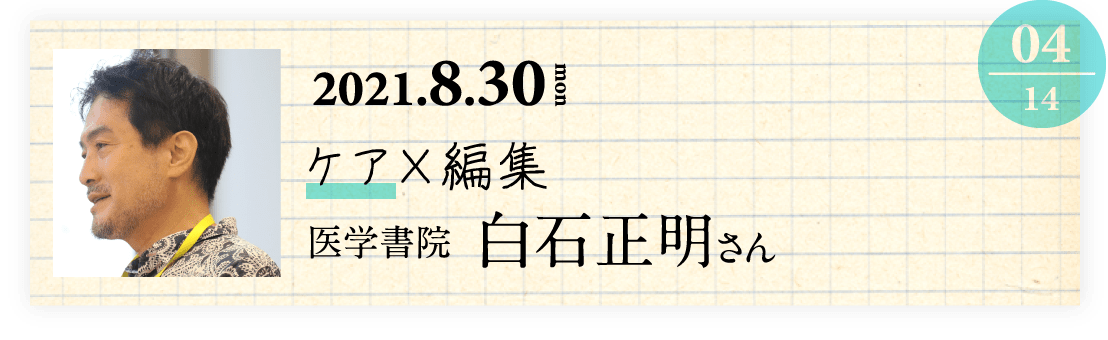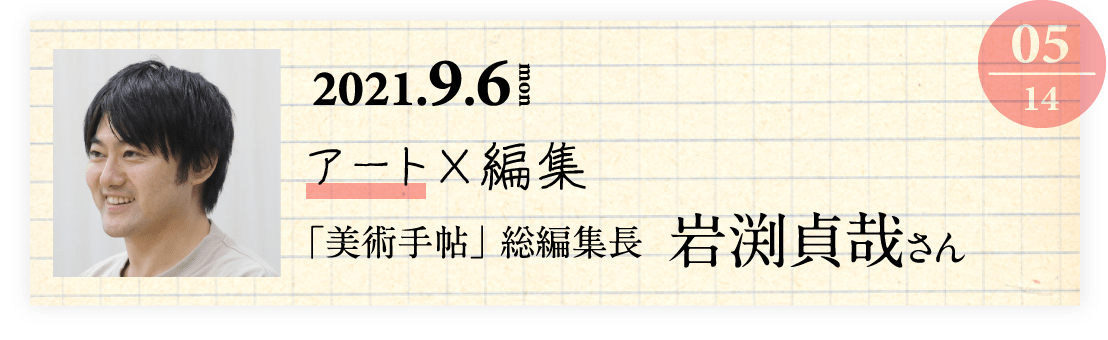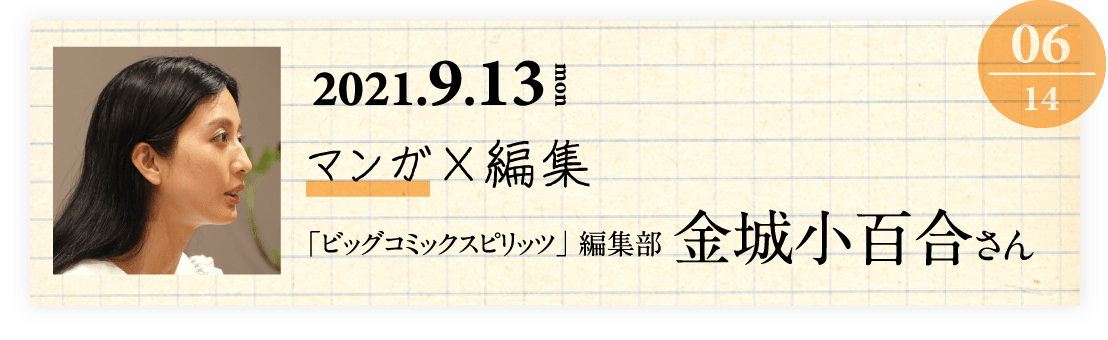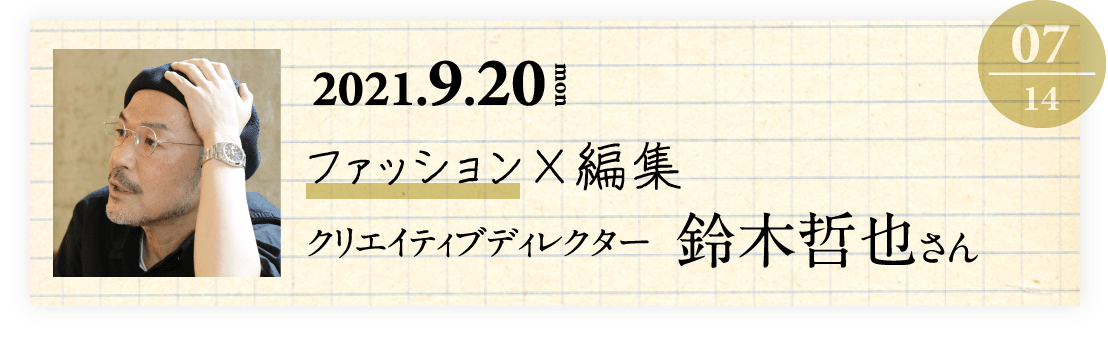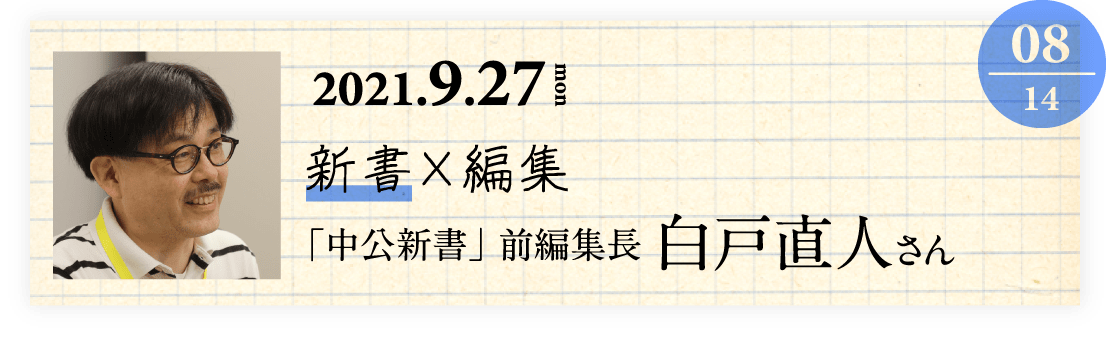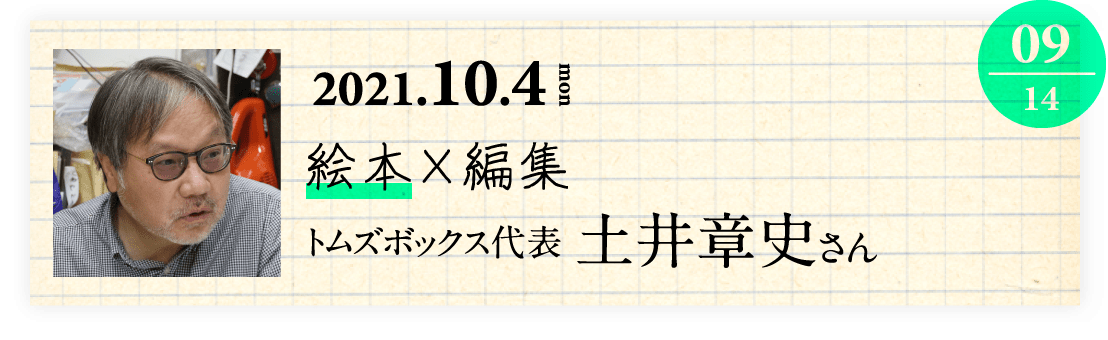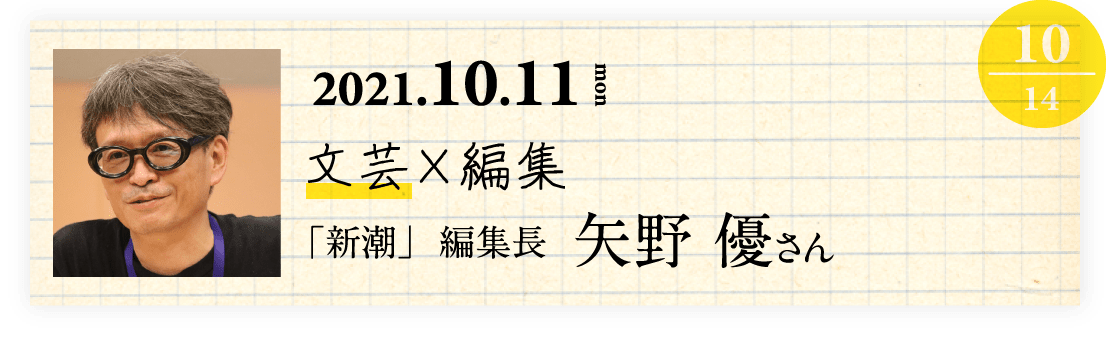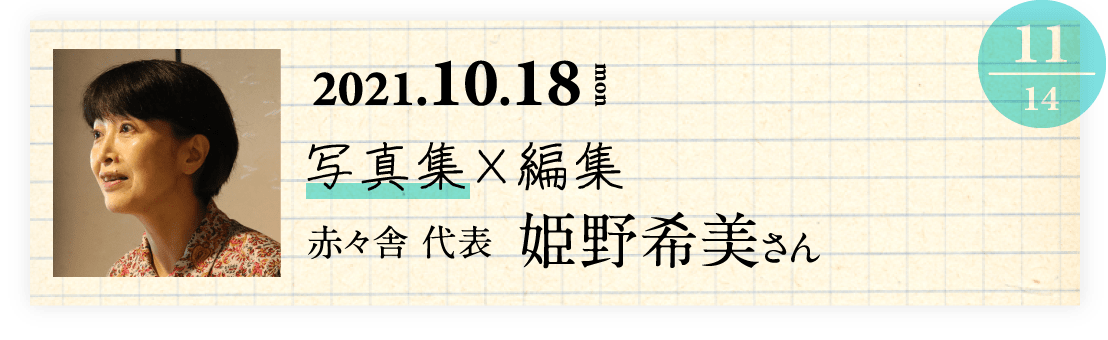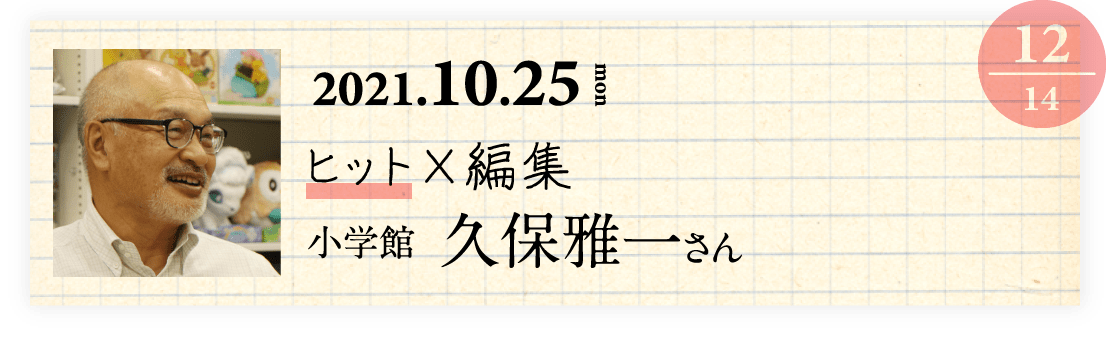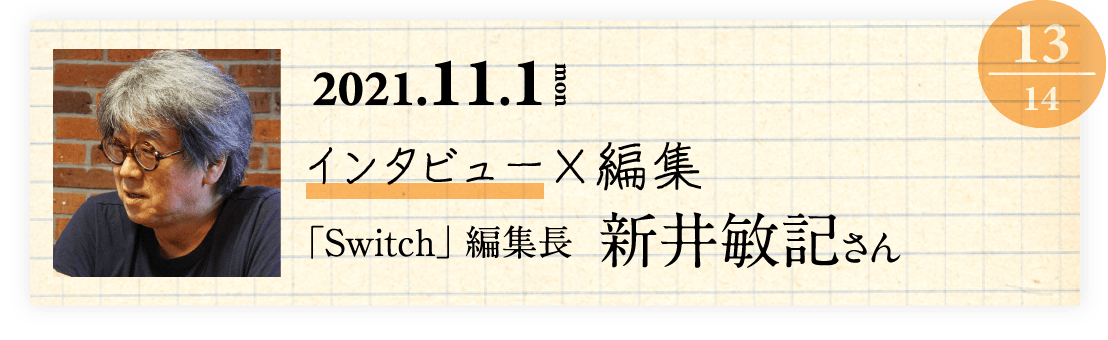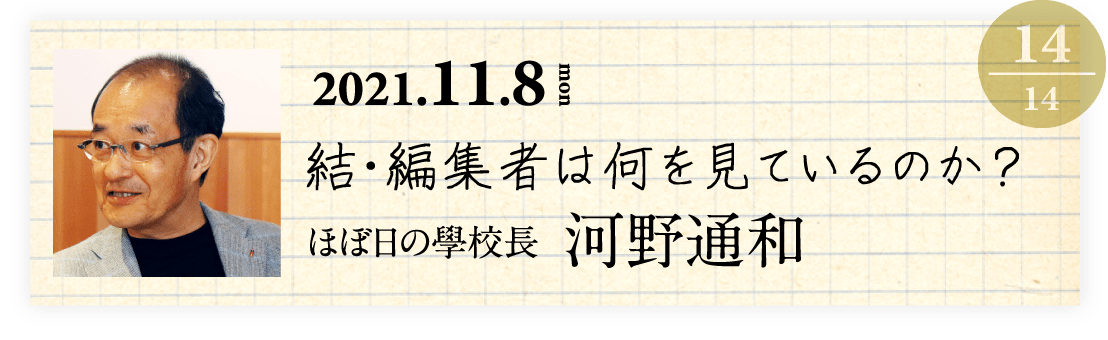特集「編集とは何か。」第7弾は
「ファッションと編集」。
1990年代「裏原」に端を発する
東京発のストリートブランドから、
誰でも知ってる
世界のラグジュアリーブランドまで、
幅広く扱ってきた
『honeyee.com』の創刊編集長・
鈴木哲也さんにうかがいました。
ちなみに鈴木さんは、
この記事の担当「ほぼ日」奥野の
雑誌『smart』時代の大先輩。
もう20年くらい前、
撮影の現場で、真夜中の編集部で、
ときに怒られたりしながら(笑)、
雑誌の編集を教えていただきました。
鈴木哲也(すずき・てつや)
1969年生まれ。株式会社アップリンク、株式会社宝島社を経て、2005年に株式会社ハニカム設立に参加。同時に同社の運営するwebメディア『honeyee.com』の編集長に就任(後に株式会社ハニカム代表取締役も兼任)。2017年に株式会社ハニカム代表取締役並びにwebメディア『honeyee.com』編集長を退任。現在は企業、ブランドのコンサルティング、クリエイティブディレクションなどを行う。
- ──
- 自分が『smart』に入った2001年ころは、
ドメスティックブランドでは
「Number (N)ine」とか
「SOPH.」「A BATHING APE」などが、
インポートでは、
イギリスの「SILAS」とか
アメリカ西海岸の「STUSSY」なんかが
人気だったんですが、
『smart』を立ち上げた当初って、
どういったブランドが人気だったんですか。
- 鈴木
- まず、雑誌のなりたちが
「『CUTiE』のメンズ版」だったということで、
「MilK」とか
「ヒステリックグラマー」のメンズラインが
誌面には出ていたよね。
- ──
- なるほど。
- 鈴木
- 一般的には、「ポール・スミス」や
「アニエス・ベー」が人気だったんで、
そのあたりも取り上げつつ、
当時『CUTiE』で連載を持っていた
(藤原)ヒロシさんや、
やっぱり『CUTiE』や『宝島』に出ていた
(UNDERCOVERの)ジョニオ(高橋盾)さん、
(A BATHING APEの)NIGOさんなんかを、
フィーチャーしようとしていた。
- ──
- 当時、いわゆる「裏原」への流れって‥‥。
- 鈴木
- すでに、できあがっていたよ。
- ──
- 若き日の高橋盾さんとNIGOさんが、
原宿にオープンした
「NOWHERE」という伝説的なショップで、
手刷りのTシャツを売って‥‥
という「はじまりの物語」が有名ですが、
そこから「A BATHING APE」もうまれて。
- 鈴木
- うん。
- ──
- 高橋盾さんは「UNDERCOVER」で、
藤原さんは「GOOD ENOUGH」で‥‥。
- 鈴木
- そうそう、
はじめに「ブランド」があったんだよね。
- ──
- と、言うと。
- 鈴木
- まず、モノをつくって、それを面で見せるために
ブランドとしての立て付けをはじめるんじゃなく、
ブランドとしてのアイディアや
世界観のほうが先にあって、
そこを起点に
アイテムをつくっていった‥‥というのが、
「裏原」の画期的だったところじゃないかと
思うんだけど。
- ──
- つまり、ふつうは逆ってことですね。
- 鈴木
- 逆というか、
比重としてはモノを優先しがちでしょ。 - でも、彼らは当時すでに、いまで言う
「クリエイティブディレクター」
として、個々のプロダクトより、
コンセプトや世界観を重視していたと思う。
そして、
その世界観をグラフィックに落として、
Tシャツにプリントした。
- ──
- その姿勢が新しかったし、カッコよかった。
- 鈴木
- いまふうに言えば、
メディア性を持ったプラットフォームとして
ブランドをつくり、
そこにTシャツというコンテンツを並べた、
というか。
- ──
- 裏原というのは、その発明だったんですね。
- 鈴木
- じつは、スケシンさんが、
そういう方法論を
かなり意識していたと聞いたことがある。
- ──
- のちに、NIGOさんのA BATHING APEで
グラフィックを手掛けることになる、
SKATE THING(スケートシング)さん。
- 鈴木
- スケシンさんが
匿名性にこだわっているのは、
本人がシャイだから、ということも
あるだろうけど、
でも、それもひとつの表現というか
世界観の表れだし、
なにより、その存在感がカッコいい。
- ──
- その一方で、当時のハイブランドの状況は、
どういう感じだったんですか。
- 鈴木
- 95、6年だから、ルイ・ヴィトンもまだ、
プレタポルテをはじめていない時期だね。
- ──
- えっ、既製服のラインがはじまったのって、
そんなに昔のことじゃないんですね。
- 鈴木
- そうだよ。プレタポルテをはじめたのは
90年代の終わりに、
クリエイティブディレクターに
マーク・ジェイコブスが就任してから。 - 90年代半ばだと、
モードマニアみたいな人たちは、
マルタン・マルジェラとか、
ラフ・シモンズに注目していた。
アントワープ出身デザイナーが騒がれてた時期。
- ──
- ベルギーの有名なファッション校を出た6人で、
ドリス・ヴァン・ノッテンや、
ダーク・ビッケンバーグなんかもいましたよね。 - そういう海外の新進ブランドも、
当時の『smart』では取り上げてたんですか。
- 鈴木
- 積極的に取り上げてた。
- ヘルムート・ラングなんかも
わりと扱ってた気がする。
- ──
- へええ‥‥そうなんですか。
- 胸にちっちゃく「HL」ロゴのシャツとか、
なつかしいです。
- 鈴木
- プラダのメンズもはじまったころだね。
90年代的なミニマル感がカッコよかった。
- ──
- 青山のプラダのお店なんて、
昔から建っているお城みたいに見えますけど、
メンズのスタートも、そのころですか。
- 鈴木
- あのショップが完成したのは、
2000年代に入ってからだと思うよ。 - 長いこと建築中だったけれど。
- ──
- 90年代って、海外のハイブランドと、
原宿でうまれたドメスティックブランドとが、
入り混じってましたよね。 - 何というか、ストリートでも、雑誌の上でも。
- 鈴木
- プラダのアウターに古着のジーパン、とかね。
- ぼくも、マルジェラのニットに、
ナイキのスニーカーを合わせたりしていたし。
- ──
- ぜんぜん文脈のちがう洋服が、
原宿の路上で交差していたってことですかね。
- 鈴木
- 当時は、みんながいまより
オシャレに飢えてたのは間違いなかったから。 - その結果とは言えるかもね。
- ──
- ファッションの文脈において、
ストリートという言葉はもうあったんですか。
- 鈴木
- 80年代以前からあるにはあったと思うけど、
ちょっと変わった若者のスタイルの総称、
という感じだったんじゃないかな。 - ファッションのひとつのジャンルとして、
ストリートという言葉が使われはじめたのは、
裏原ブーム以降だと思う。
- ──
- ムーブメントの揺籃期から原宿にいて、
鈴木さんはいま、
あの狂想曲は何だったと思ってますか。
- 鈴木
- 「創造する天才があるように、探す天才もあり、
書く天才があるように、読む天才もある」
という
ポール・ヴァレリーの言葉があるじゃない。 - 受け取る側の感性に優れた「探す天才」たちが
探しても見つからない
自分たちの「欲しいもの」を
かたちにしたんだと思う。
- ──
- それが、裏原。
- 鈴木
- 「こういうものを、つくりたい」ではなくて、
「こういうものを手に入れたい」
という気持ちから
「創造」がはじまったというか。 - それがあの時期、多くの共感を得たんだよね。

- ──
- 大きなアパレル会社のつくった洋服を、
消費する人の話じゃなくて。
- 鈴木
- あくまでも、選ぶ側、買う側の目線で、
モノをつくっていたんじゃないかな。
- ──
- なるほど。
- 鈴木
- たしかに、流行というか、
「現象」が先行した部分もあるけれど、
その「現象」も、
やっぱり
彼らのクリエイションの一部であって、
裏原のブランドが、メディアを使った
ブランディングも上手かったのは事実。 - ただ、その「副作用」というか、
予想以上の盛り上がりに
いちばん困惑していたのも、
裏原のブランド自身だったと思うけど。
- ──
- 当時、現場にいた鈴木さんの体感でも、
ファッションというものが
ガラッと変わったという感じでしたか。
- 鈴木
- ちょっと大げさだけど、
決定的な線が引かれたと思った。
- ──
- 鈴木さん自身、裏原でうまれた
ストリートブランドのどういうところが、
カッコいいと思っていましたか。
- 鈴木
- まず、80年代的なスタイルを
「大げさ」で「わざとらしい」ものに
感じさせてしまう
微妙で繊細なセンスに共感した。 - あと、自分たちの世代の「カルチャー」を
つくろうとしていたんじゃないかな。
ファッションだけで完結させるのではなく。
- ──
- 音楽はじめ、スケートボードとか、
グラフィティアートとか、トイとかも、
混じっていましたよね。
- 鈴木
- 音楽でいうと、
ヒップホップやハウスが隆盛になって、
DJ感覚、
サンプリング感覚が当たり前になって。
- ──
- ああ‥‥。
- 鈴木
- 代わり映えしないオリジナルをつくるより、
もう他人の曲でいいじゃん、
そこから、かったるいサビメロを抜いて、
カッコいいブレイクやリフだけ
ループさせればいいよね‥‥というところに、
ぼくらの世代の価値観があったかも。
- ──
- 自分がいたころの『smart』でも、
音楽情報の欄では、
クラブミュージックの情報ばっかり
載せていた気がします。 - ロックとかって言うよりも。
- 鈴木
- そっちのほうが洗練されてる、
先へ行ってるように感じていたからね。 - そういう気分を、
裏原は、ファッションで表現していた。
デザインの凝ったわざとらしい服より、
Tシャツでいいじゃんって。
- ──
- ええ。
- 鈴木
- ただし、そのTシャツには、
自分たちの価値観とセンスをあらわした
グラフィックが載っている、という。
- ──
- 世間ではバブルは崩壊していましたけど、
当時の原宿では、やっぱり、
新しいものがボコボコ生まれるような、
何が起きるかわかんないような雰囲気が
あったという感じでしたか。
- 鈴木
- そうだね。
- 音楽でもファッションでも、
上の世代とは
別の価値観が生まれてきていたと思う。
当時の『smart』のおもしろさは、
そのあたりにあったんじゃないかな。
- ──
- 当時、自分はまだ20代前半だったので、
みなさん年上ではありましたが、
たしかに、すごく年配の大御所の人とは、
あまり仕事をした記憶はないです。 - 藤原ヒロシさんの特集のときに、
小暮徹さんにお写真をお願いしたくらい。
- 鈴木
- スタイリストやカメラマン、ヘアメイク、
誰とやろうかって考えると、
自然と「同じ世代の人」になってたよね。
- ──
- 世代の価値観を共有していたから。
- 鈴木
- そうだね。
- ──
- で、その価値観って、
読者の価値観ともそろっていましたよね。 - 当時、雑誌をつくる編集部の人と読者が
同じ格好をしているのは
『smart』と『LEON』だ‥‥という話を
聞いたことがあります(笑)。
- 鈴木
- もともと、着る側の価値観だったからね。
- それが
ストリートファッションの本質でしょう、
きっと。
- ──
- 自分は鈴木さんのつくる特集やページに、
ずっと憧れを抱いていたんですが‥‥。
- 鈴木
- あ、そうですか。
- ──
- もう、いまでもハッキリ覚えているのは、
『smart MAX』でやっていた
「COMME des GARCONS SHIRT」特集。 - 洋服をモデルに着せて撮るだけじゃなく、
ユナイテッドアローズの栗野宏文さんを
ナビゲーターに立てて、
「COMME des GARCONS」を
音楽や映画などのポップカルチャーと
関連づけて、分析して、紹介してまして。

- 鈴木
- そういうのが好きだったんで。
- ──
- あの特集のおかげで、
「COMME des GARCONS」の重要性を、
いっそう理解できたと思ってます。
- 鈴木
- ぼくも自分が読んでおもしろいページを、
つくろうとしていたから。

- ──
- ずーっと「雑誌が大好きだった人」として、
自分の好きなようにページをつくる。 - でも、最大40万部とか出てた雑誌で、
それをやっていたのも、すごいことですね。
- 鈴木
- たしかに。
- ただ『smart』は40万部以上売ってたけど、
残念ながら『smart MAX』は、
その10分の1くらいだったけどね(笑)。

(つづきます)
2021-09-21-TUE
-
オンラインサロン「RoCC」で、
90年代東京カルチャーを描く。
現在、鈴木さんは
ウェブメディア「Ring of Colour」が主宰する
オンラインサロン「ROCC」で、
90年代東京カルチャーについてのエッセイ
「2D (Double Decade Of Tokyo Pop Life)」
を執筆中とのこと。くわしくは、こちらから。
なお、オンラインサロン「RoCC」は、
アート、本、車、ファッション、
食、映画、時計などを軸に情報発信中。
藤原ヒロシさんや
梶原由景さんとも交流できる場所だそうですよ。
ご興味あったら、アクセスしてみてください。 -
<取材協力>
PRETTY THINGS
東京都世田谷区駒沢5-19-10
-
「編集とは何か。」もくじ