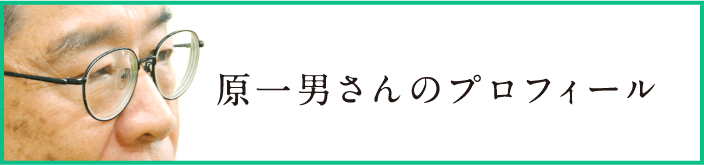06人は、わかってほしいもの。
- ──
- 監督にとって、
ご自身の撮ったドキュメンタリー作品は、
どういうもの、でしょうか。
- 原
- あのね、映画1本をこの人で‥‥つまり、
『(さようなら)CP』
『(極私的)エロス(恋歌1974)』
『(ゆきゆきて、)神軍』
『全身(小説家)』という初期の4作は、
ある価値観を軸にして、
ひとつずつ、積み上げてきたものです。
- ──
- と、言いますと?
- 原
- つまり、どれもヒーローを描いています。
自分では、その4作を
「スーパーヒーローシリーズ」って
呼んでいるんですけど、
やがて時代が変わると、
その方法が通用しなくなってくるんです。

- ──
- スーパーヒーローが、いなくなった?
- 原
- そう。なのにわたしは、無意識のうちに、
その延長、その続編をつくりたがっていたし、
探し続けていたんです。
奥崎さんや、井上さんみたいなね、
スーパーヒーローを。
そんな人は、もうどこにも存在しないのに。
- ──
- そうだったんですか。
- 原
- で、そんなふうに
撮るべきテーマを見つけられずにいたとき、
「泉南をやってみませんか」
と言われて、アスベストの原告団の企画に
飛びついたわけです。
もう、自分は、映画に飢えていましたから。
ところが、回しはじめたカメラの前には、
かつてのようなヒーローは、一人もいない。
- ──
- ええ。
- 原
- 撮影をはじめて、すぐに後悔しましたよ。
「こんな、ふつうの人たちを撮って、
おもしろい映画になるわけがない」と。
- ──
- その思いは、どこで変わったんですか。
- 原
- 結局、その気持ちを克服できないまま、
8年に及ぶ撮影を終えました。
2年かけて編集しているあいだ中も、
「こんなもの、
おもしろくなるわけがない!」って。

- ──
- 思い続けながら?
- 原
- そう、で、編集を終え映画として仕上げて、
はじめて山形の映画祭で上映したら、
「おもしろかったです!」
って、ふた桁の‥‥数十人もの人が、
直接、わたしに言いに来てくれたんですよ。
それで「この映画、おもしろいのかあ」と。
- ──
- お客さんに、教えてもらった。
- 原
- そうなんです。だから、そこからなんです。
自分のつくったドキュメンタリーを、
肯定的に、評価できるようになったのって。
- ──
- え、つまり、それまでは否定的だった‥‥?
何十年も映画監督をしてらっしゃるのに。
- 原
- たぶん、作品が生き方を教えてくれたんです。
わたしは、生き方を求めて
ドキュメンタリーをつくってきたけど、
この歳になってね、
映画が、生き方を導いてくれたなと思います。
- ──
- 生き方を求めて、つくってるんですか?
- 原
- たとえばね、あなたの場合、
こういうインタビューって「職業」でしょう。
- ──
- そうですね‥‥はい。
- 原
- わたしには、職業という意識が稀薄なんです。
何ていいましょう、
わたしは、ドキュメンタリーをつくることで、
「生き方を探っている」感じがある。
- ──
- ご自身の生き方を?
- 原
- そうです。ようするに、
「この人」という人にカメラを向けながら、
一生懸命に、
相手と、相手の言葉に食らいついていくと、
ああ、自分はこういう人間なのか、
だったら自分は、
こうやって生きていくんだということがね、
はんたいに、わかってくるんです。

- ──
- 具体的には‥‥?
- 原
- 泉南の映画では、出自のことを、思いました。
あの映画に出てくる人たちって、
撮ってるときは、
そんなに強く意識していなかったんですけど、
みんな貧しい地域から出て来て、
流れ流れて、
少しでもお金がたくさん稼げるところをって、
アスベスト工場にたどり着くんです。
そのことを、しみじみと思ったんですけどね。
- ──
- ええ。
- 原
- そしたら、「あ、自分だって、そうだな」と。
わたし炭鉱育ちなんですけど、
もう消えていくしかない故郷から外に出たら、
彼らと同じように、
流れ流れるしかなかったわけなんです。
- ──
- なるほど。つまり、
ここに映っている人は「わたし」だ‥‥と?
- 原
- わたしはね、若いころに、
そういう貧しい生活者なんか撮らないぞって
自分で決めて、ヒーローばかりを撮ってた。
でもね、
そういうおまえさんが切り捨てた人たちは、
まさにおまえさん自身だったんだ、
ということに、
この歳になって映画が教えてくれたんです。
- ──
- 大きすぎる質問かもしれないのですが、
原監督にとって、
人間って、どういうものだと思いますか。
- 原
- 人ね‥‥人ってね、どうしてもね、
「自分の人生をわかってもらいたい」という、
そういう本能を持ってるものです。
- ──
- わかってほしい。誰かに。
- 原
- そう、自分のことや自分の人生のことを、
わかってほしいと思ってますよ。
そりゃあ、人によって強弱はありますが、
誰しも、そういうものだと思います。
- ──
- たしかに、
自分は誰にもわかられなくていいやって、
本気では、思えないかもしれない。
- 原
- だから、聞き手がきちんと興味を持って、
真正面から向き合いさえすれば、
気持ちを素直に話してくれるってことを、
信じてるんです、わたしは。

- ──
- それが、監督の信念。
- 原
- ほら、「その人って誰、どういう人?」
って聞かれたときに、
観念で考えたって、わからないでしょ。
その人の具体的な人生に直に向き合って、
自分の身体を張って、
ひとつひとつ、確かめていかなければね。
- ──
- はい。
- 原
- そこで「言葉」に出会うんです。
相手と、ときにギリギリやり合いながら、
出会うんですよ、その人の言葉に。
- ──
- 自分は、こういうインタビューのとき、
はじめての人と言葉を交わすことに、
有名無名問わず、「怖さ」があります。
監督は、どうでしょうか。
- 原
- 怖いですよ。わたしだって。
初対面の人って怖いもんですよ、それは。
- ──
- 監督は、インタビューのおもしろさって、
どういうところにあると思いますか。
- 原
- わたしにはね、他人の人生を見ることが、
たまらなく、おもしろいんです。
で、他人の人生をのぞいたつもりが、
いつの間にか、自分の人生を見つめてる。

- ──
- はい。
- 原
- そういうおもしろさがあると思いますよ。
ドキュメンタリーだとか、
インタビューだとかっていうものにはね。
<終わります>
2018-05-02-WED