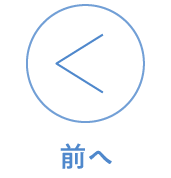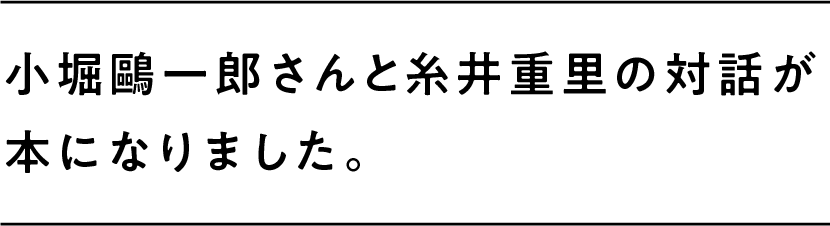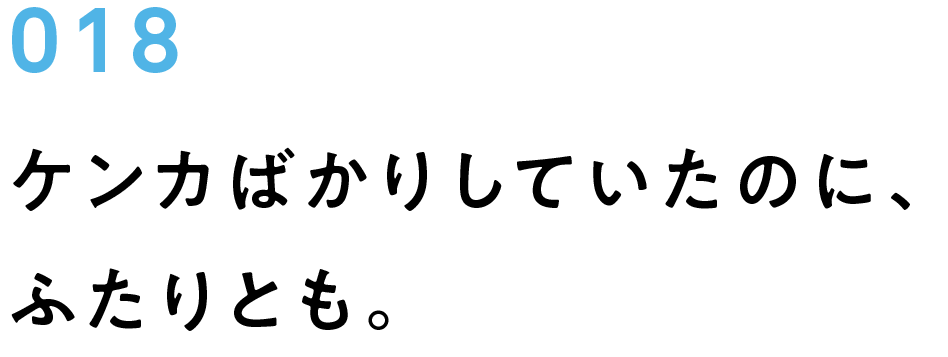
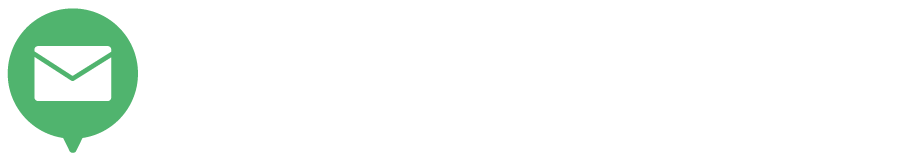
母親を早くに亡くし、家督を継いだ姉に遠慮して
中卒で都市へ集団就職に出た。
生真面目で、他人さまに笑われたり、
後ろ指たてられないようにと気丈に生きてきた人。
父は下町の次男。職人仕事の家で、
なぜか太宰治かぶれの文学青年に育ち、
そこそこの高校を出て勤労者となった。
気むずかしい性格で、勤めには真面目だった一方、
賭けごとが止められず、母とよくケンカになった。
ふたりとも生家では何だかアウトロー、
その屈折があったと思う。
このふたりの長女(下に妹一人)であった私は、
いまそれなりに信頼を得て仕事をしていて、
この人格の基礎を作った両親には感謝している。
ただ、思い返すと母は厳しく、父は不機嫌で、
あまりほのぼのした子ども時代ではなかった。
思春期以降、母とは確執があったし、
父のだらしなさ、両親のなかがよくないことは
恨めしかった。
友人のご両親と比べたりなんかして。
なんだかんだと修士を出してもらい、
やっと就職した4月。
父が入院したと聞いていた病院から、
なぜか私に電話がきた。
両親とも末期がんだった。
父が最初に体調を崩して入院、
付き添った母も調子が悪く、ついでに受診して発覚。
病院側も「ふたりとも」ということに驚いて、
本人告知が一般的でなかった時代、
伝えるべき相手は子の私だったらしい。
「あんなにケンカしていたのに、
こんなときだけなかがいいなんて‥‥」
数か月後、父の悪化の速度を追い越して、
母が先に「いよいよ」となった。
痛みや不安やモルヒネで意識が混沌とするなか、
母がよんで求めたのは父だった。
傍らにきて父は、
「おまえは俺の宝だ」とベットの母を抱きかかえた。
「いまごろになって‥‥」
真っ先に浮かんだのはこの言葉だった。
「私の辛かった時間を返してよ」くらいまで、
はっきり思ったかな。
お互い思い合っていたことがわかったのは
うれしかったし、
私も母を愛していた気持ちがあったけれど、
だからこそ、もっと早くにこの気持ちを
出し合ってくれていたらと思えた。
母が亡くなる季節に、真っ先に思い出す光景。
その後結局2年生きた父は、
最期まで意識ははっきりしていたけれど
何を言うでもなく真っ黒な痰を吐いて逝った。
病室には私しかいなくて、
父にとって最後を見せていいのは
私だけだったかと思っている。
母に「へその形までそっくり」と言われた父と私。
今年、母の逝った年になる。
おかげさまで、健康で配偶者とふたり、
なかよく生きてます。
(R)