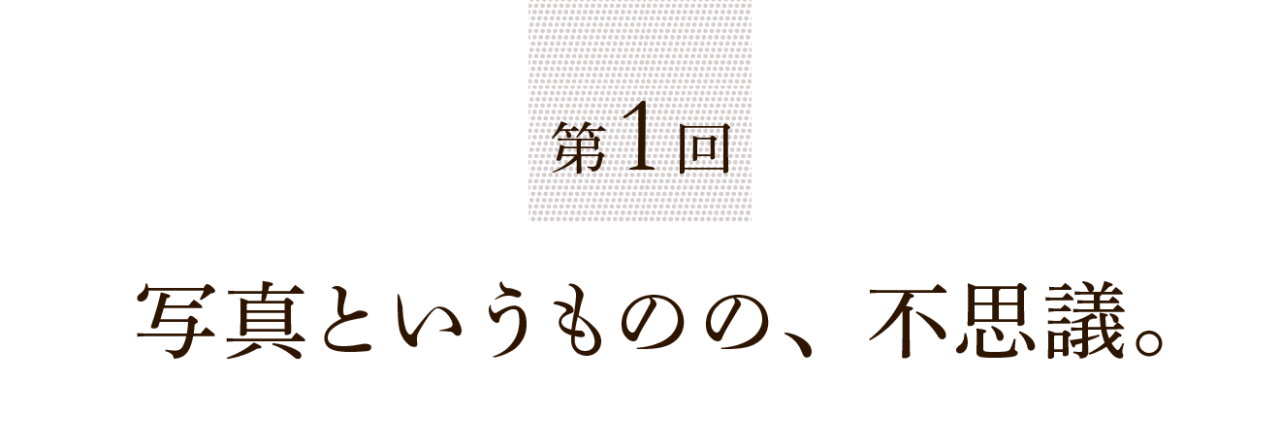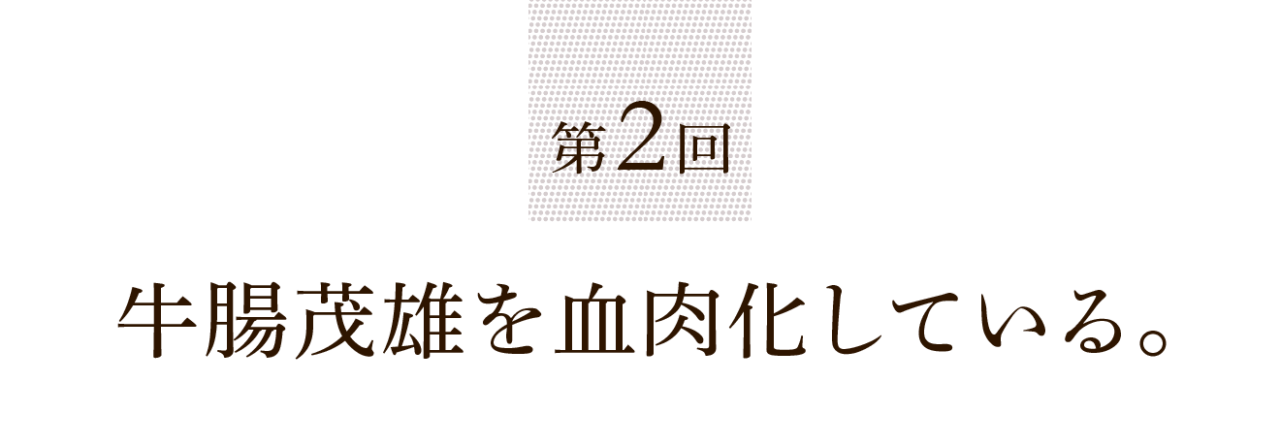ゲルハルト・リヒター、マーク・マンダース、
川内倫子、野口里佳、牛腸茂雄。
ざっと名前を挙げただけですが、
これら、そうそうたる内外の作家の展覧会や
作品集に関わってきたのが、
デザイナーの須山悠里さんです。
インタビューしたときに
完成間近だった『牛腸茂雄全集』のことから、
須山さんのデザイン観、
その職業哲学のようなものにいたるまで、
ひろく、おもしろいお話をうかがいました。
全5回、担当は「ほぼ日」奥野です。
須山悠里(すやまゆうり)
デザイナー。1983年生れ。主な仕事に、エレン・フライス『エレンの日記』(アダチプレス)、鈴木理策『知覚の感光板』(赤々舎)、「長島有里枝 そしてひとつまみの皮肉と、愛を少々。」(東京都写真美術館)、「マーク・マンダース―マーク・マンダースの不在」(東京都現代美術館)など。2022年6月より東京国立近代美術館で開催された「ゲルハルト・リヒター」の図録を担当。2022年11月19日より一般発売される『牛腸茂雄全集』(赤々舎)の装丁も手掛ける。
- ──
- 先日まで国立近代美術館で開催されていた
ゲルハルト・リヒターの展覧会図録など、
最近、須山さんのお名前を、
いろんなところで拝見しているんですけど。
- 須山
- いえいえ。
- ──
- いま、オペラシティアートギャラリーで
開催されている川内倫子展や、
東京都写真美術館での野口里佳展などの
写真の展覧会も、ですよね。 - こんど出る『牛腸茂雄全集』もそうだし、
そもそも須山さんって、
写真に関連するお仕事って多いんですか。
- 須山
- 多いほうかもしれません。
- 展覧会にあわせて図録をつくったり、
作家と一緒に作品集を
つくることもありますが、そのなかでも、
写真がいちばん多いかもしれないですね。
- ──
- そうなっていくことの理由って、
何かあるんですかね。きっかけというか。 - たとえば、映画関連のお仕事が多い
大島依提亜さんは、
もともと映画が大好きだったそうですが、
須山さんも「写真が好きだった」とか。
- 須山
- いや、どうなんだろう。
- とりわけ写真が好きだったわけじゃなく、
「見る」ことと
「複製」に興味があったんです。
- ──
- 見ること、複製。
- 須山
- そうですね、美術‥‥絵画でも写真でも、
まずは「見る」こと、そして、
「見た」ときに何が起きているのか、
それをどう複製していくのかに、
いちばんの興味があるような気がします。 - 結果、その興味がデザインという仕事に
つながっているのかもしれないです。
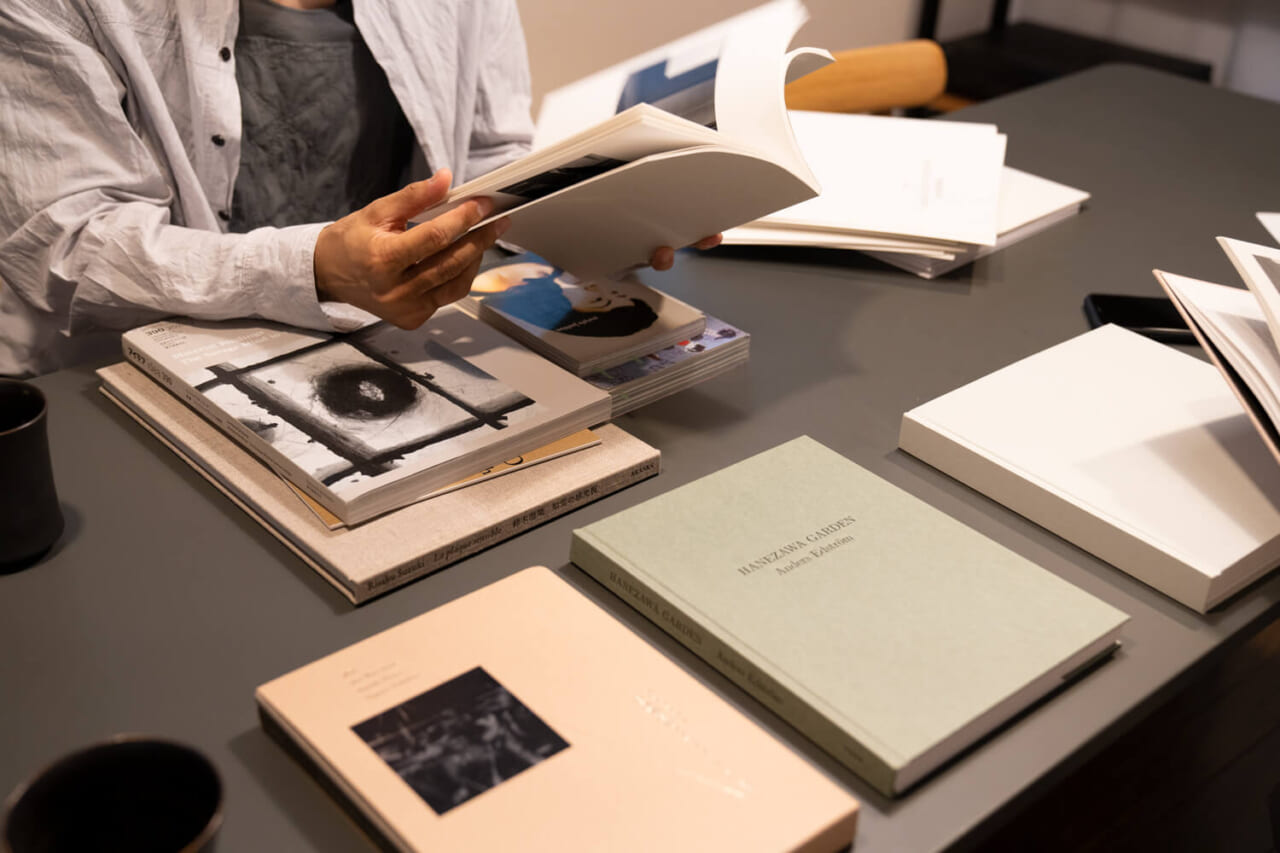
- ──
- はあ‥‥その興味には、興味があるなあ。
- おいおいうかがっていくとして、
まずは、好きな写真家さんっていますか。
ぼくでもわかるような‥‥どなたか。
- 須山
- アンダース・エドストロームって、
スウェーデンの写真家がいるんですけど。
- ──
- あ、すいません。存じ上げません。
- 須山
- ずっとファッションを撮っていた人で。
- いまは、スウェーデンに戻っていますが、
一時期、日本にも住んでいたんです。
今もファッションの仕事をしていますが、
他にも、
自分の写真集を出したり映画を撮ったり。
- ──
- 多才な方なんですね。
- 須山
- 彼の写真は、好きです。
- ──
- ファッションフォトって言うと、
いろんなテイストがあると思いますけど、
どんな写真を撮る人なんですか。
- 須山
- はい、彼は、
90年代の(マルタン・)マルジェラを
撮っていたんですけど、
当時は、雑誌の『PURPLE』が刊行され、
既存のメディアとは異なる価値観が
いろんなところで芽生えていた、
そんな時期だったのだと思います。 - アンダースも、
それまでのファッションや広告写真とは
ぜんぜんちがう‥‥
たとえばプロのモデルを使わなかったり、
街に出て、何の変哲もない雑踏の中で
パッと撮っちゃうとか。
- ──
- 自分は微妙に世代がズレてるんですけど、
『PURPLE』の出てきた
90年代前半って、
日本でも雑誌の『CUTiE』が
「ストリート」という
新しい価値観を発信してた時代ですよね。 - エスタブリッシュされた何かに対する、
若い世代からのアンチテーゼっていうか。
- 須山
- そうですね。マルジェラも『PURPLE』も、
衣服や雑誌、美しさといった枠組みを
再構築していった人たちだと思います。 - この写真なんかは、アンダースが
広尾に住んでいたころに撮ったものかな。
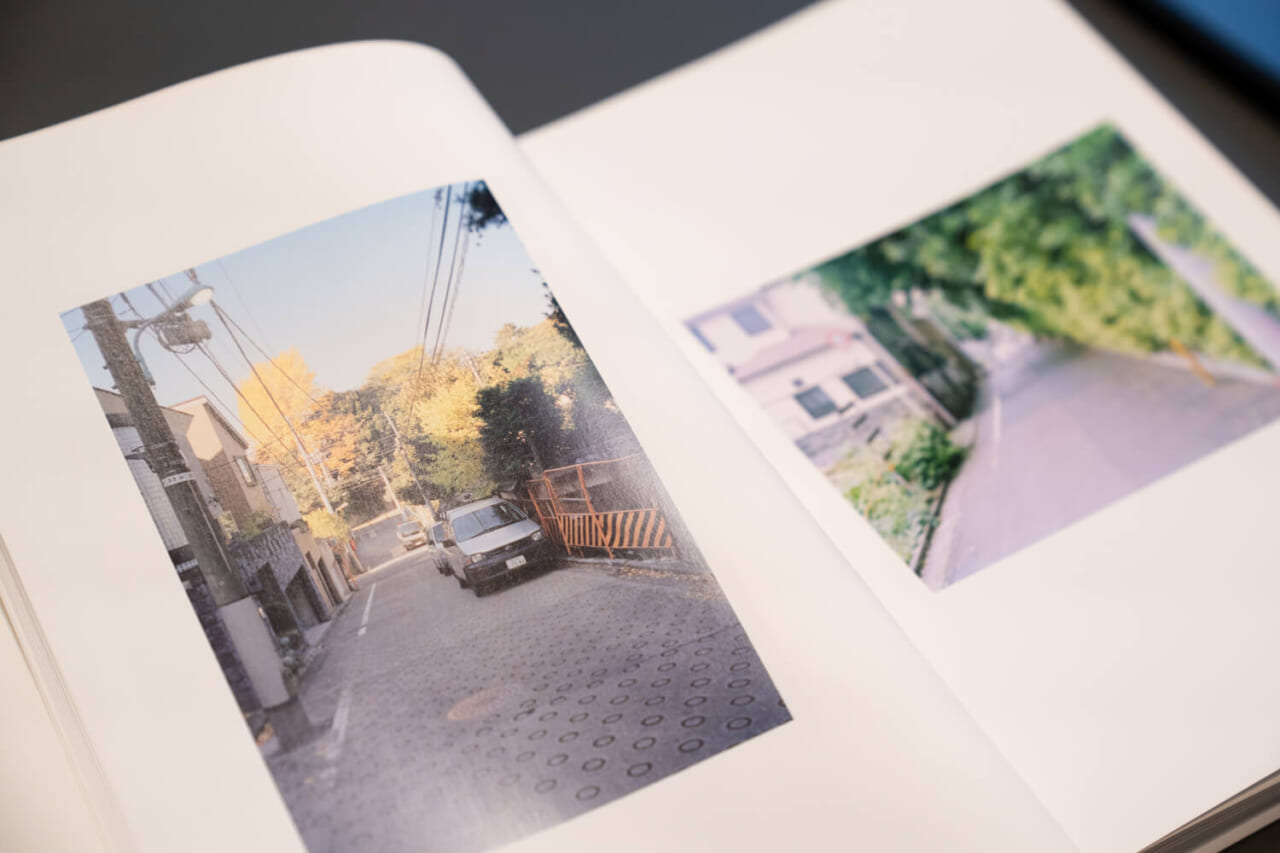
- ──
- ああ‥‥いいですね。
こっちは、わりと田舎。どこなんだろう。
- 須山
- もしかしたら、京都かもしれないですね。
- 彼の最新作の映画が、
パートナーが住んでいた京都のあたりを
撮っているので。
何か8時間くらいあるって言ってたので、
まだ見れていないんですけど。
- ──
- はあー‥‥いいですね。すごくいいです。
アンダースさんの写真は、
当時もリアルタイムで見ていたんですか。
- 須山
- リアルタイムではないですね。
- 次第に
『PURPLE』が巨大なメディアになって、
マルジェラ本人も、
ブランドの一線から退いたあとくらい。
そこから遡って、初期の号を手に入れて、
読んだりしました。
- ──
- なるほど。
- 須山
- おもしろいことに、その後、
彼らの活動をいち早く日本で紹介していた
林央子さんと仕事をすることになり、
『PURPLE』をつくった編集者のひとり、
エレン・フライスの本をつくったり、
その時代と不思議な縁があります。
- ──
- いや‥‥それにしても、
アンダースさんの撮る写真は、いいなあ。
- 須山
- なんてことない風景の写真だったりして、
ファッションフォトだとは
パッと見ではわからない、
素っ気ない感じが、よくて。 - 後ろ姿だったり、
ただ道を歩いているところだったり‥‥。
「洋服を着たモデル」を
写しているというより、
その服を着た人のいる風景を撮っている、
そういう感じの写真ですね。
- ──
- お仕事をしたこともあるんですか?
- 須山
- はい。彼がまだ日本にいたころ、
雑誌の『装苑』で、
あるブランドの大きな特集のデザインを
担当したときに、
撮影をお願いしたことがあったんですね。 - ダメもとで提案したら受けてくれました。
- ──
- おお。
- 須山
- わたしは、会ってすぐ、
立ち振る舞いから、彼のことが
好きになってしまったのですが、
やっぱり、
創作の部分では妥協のない人なんですね。 - そのときも、
「受けてもいいんだけど、
撮影のときに人がゾロゾロついてきたり、
ああしろこうしろ言われると、撮れない」
って、はじめから。
- ──
- なるほど。
- 須山
- できれば撮影立ち合いもしてほしくない、
服だけ借りてこっちで撮りたい、
レイアウトも自分で決めたいって言って。 - わたしは立ち会わなくてもよかったのですが、
ブランドから、現場で何も言わないから
立ち会いはさせてほしいと言われ、
渋々だけど「いいよ」と。
で、フタを開けたら、撮影の日が大雨で。
- ──
- なんと。
- 須山
- 白金の自然教育園で撮影をしたんですが、
傘もささずに撮るんです、アンダース。 - 古そうなカメラが壊れるんじゃないかと、
こっちが心配になったんだけど、
おかまいなしに、バシバシ撮ってました。
寒かったから、終わったあと、
ふたりで熱燗を飲みました(笑)。
- ──
- おお(笑)。
- 須山
- 写真は、すごくよかった。
- ただ、後日、
編集部とかブランドとかをすっ飛ばして、
いきなりわたしのところに、
写真が、
レイアウトした状態で送られてきまして。
これで‥‥みたいな感じで(笑)。
- ──
- それ、びっくりするやつですね(笑)。
- 須山
- 当然、編集部やブランドからは、
他の写真も見てみたい‥‥という要望が
出たんですけど、
「そういう要望に応えたことは一切ない、
今回も応えるつもりはない、以上」
みたいな(笑)。
- ──
- どうしたんですか。
- 須山
- 結局、そのままのかたちで世に出ました。
- ──
- おお‥‥アンダースさんもすごいけど、
編集部やブランドの側のふところの深さ、
ということでもありますね。 - もう日本にはいらっしゃらないんですか。
- 須山
- 基本的にはスウェーデンだと思いますが、
たまに来てるみたいです。撮影で。
- ──
- こう言ったらちょっと語弊がありますが、
こういう写真って、
ぼくら素人が撮ろうと思ったら、
一瞬、撮れそうな感じに思えるんですよ。 - 何気ない日常の風景だし、
カメラさえあれば撮れるんじゃないかと。
でも、無理ですよね。
- 須山
- おそらく、難しい。
- ──
- それって、何なんでしょうね。
写真については、いつもそこが不思議で。
- 須山
- 勝手な解釈ですけど、アンダースの場合、
最後まで
どこか日本になじめない部分があって、
それが、写真にも出ている気がしますね。 - 技術的なことを抜きにして、
青っぽくて、どこか鬱屈した感じがある。
- ──
- 日本に住む外国の人としての視線‥‥が。
なるほど。 - 魅力的なのはたしかなんだけど、
なぜ魅力的なのか言葉にできないことが、
写真の場合、すごく多い気がして。
ゴッホの描いた「絵」なら、
「このタッチが」とか言えたりするけど。
- 須山
- どうしてこの写真をセレクトしたのかも、
よくわからないですよね、アンダース。 - でも、この分厚い写真集を、
ついつい、見てしまう感じがある。
美しい写真‥‥というのともちがうし。
- ──
- 自分は、ファッション誌の編集から
社会人がはじまってるんですが、
最初の何年かは、
写真というものが何もわからなくて。
- 須山
- あ、そうなんですか。
- ──
- はい、審美眼と言っていいのか、
写真を味わえるだけの素養がゼロで、
あの当時、
このアンダースさんの写真を見たら、
「何なんだ、この写真」
と素人の失礼さで思ったと思います。
- 須山
- わかりやすい写真じゃないですしね。
- ──
- だから、いまでも写真というもの全体に
ある種の「不思議さ」を感じてるんです。
- 須山
- それは、ありますね。写真の不思議。

(つづきます)
2022-11-07-MON
-


36歳の若さでなくなった
写真家・牛腸茂雄さんの遺した作品を
一気に見られる本ができました!
生前に刊行された作品集
『日々』『SELF AND OTHERS』
『扉をあけると』
『見慣れた街の中で』に所収された全作品、
さらには
連作〈水の記憶〉〈幼年の「時間 」〉から
全作品を収録しています。
インタビューでもたっぷり触れていますが、
須山さんがデザインしています。
ヴィンテージ・プリントを確かめるために
山口県立美術館へ通ったり、
作品集ごとに紙を変えていたり、
1%とかの精度で色味を調整していたり‥‥
渾身の一冊です。素晴らしい出来栄え。
Amazonでのおもとめは、こちらから。
一般発売は、11月19日からとのこと。
なお、版元・赤々舎さんのホームページと
渋谷PARCO8階「ほぼ日曜日」で
11月13日まで開催されている写真展
『はじめての、牛腸茂雄。』の会場内では、
一般発売に先行して販売中です。
展覧会は会期も終盤、ぜひご来場ください。
展覧会について、詳しくはこちらをどうぞ。