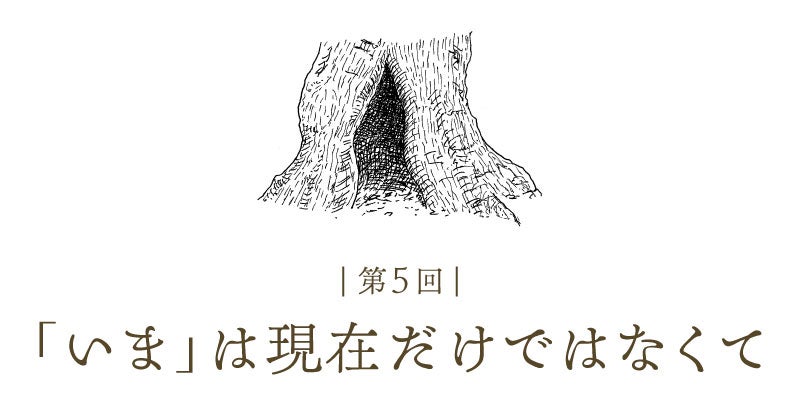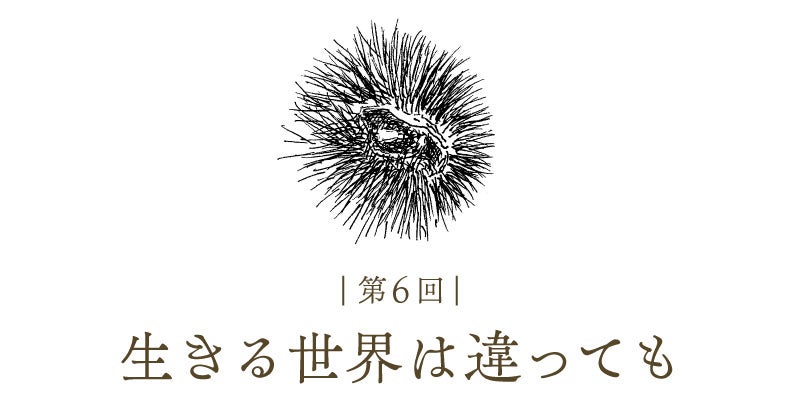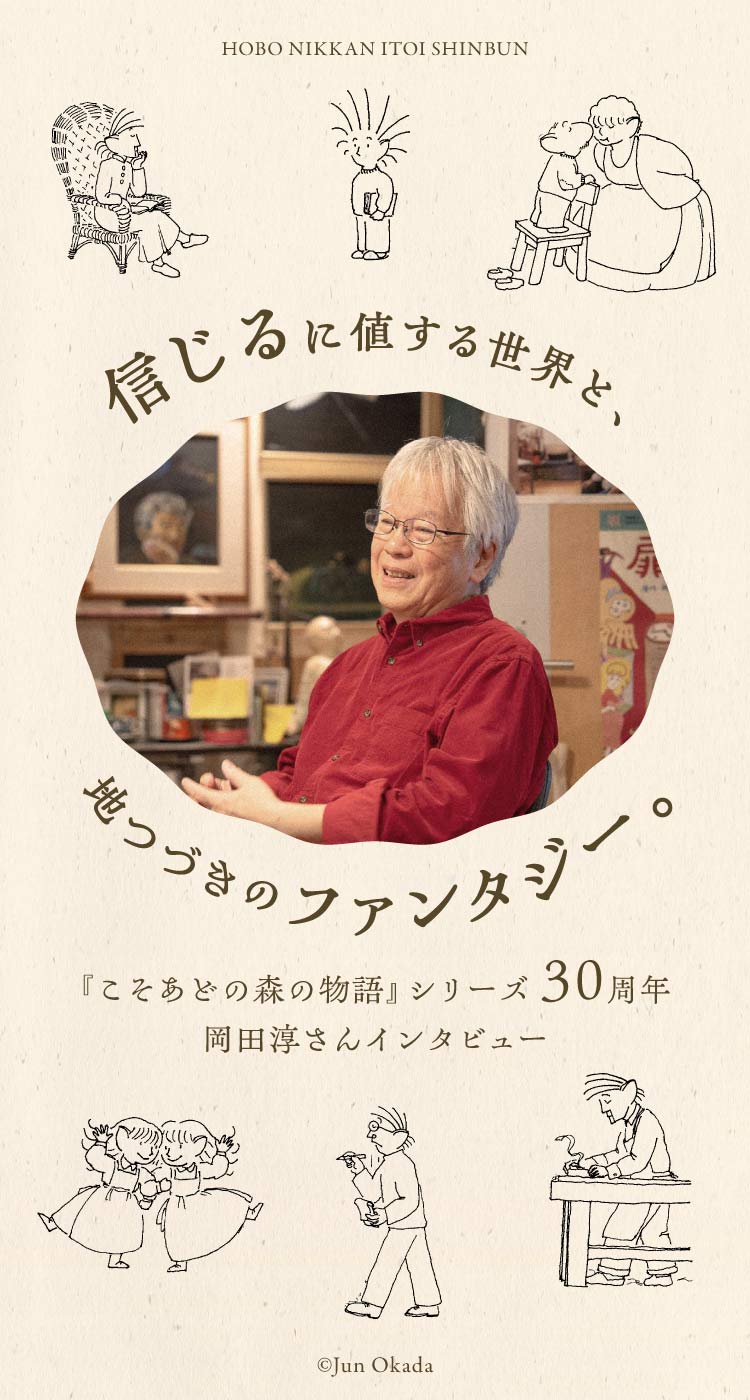
「あの場所に帰りたいな」と思うとき、
頭に浮かんでいるのはどんなところでしょうか。
私、ほぼ日の松本にとってそれは、
子どものころに読んだ物語の舞台
「こそあどの森」です。
どこにあるのかわからない、ふしぎな森。
しかし、作者の岡田淳さんに
お話をうかがって感じたのは、
「『こそあどの森』は、
私たちの現実と地つづきなのかもしれない」
ということでした。
ファンタジーのたしかなちからを感じるお話、
精密な原画とともにおたのしみください。
岡田淳(おかだ・じゅん)
1947年兵庫県生まれ。
神戸大学教育学部美術科を卒業後、
38年間小学校の図工教師をつとめる。
1979年『ムンジャクンジュは毛虫じゃない』
で作家デビュー。
その後、『放課後の時間割』
(1981年日本児童文学者協会新人賞)
『雨やどりはすべり台の下で』
(1984年産経児童出版文化賞)
『学校ウサギをつかまえろ』
(1987年日本児童文学者協会賞)
『扉のむこうの物語』(1988年赤い鳥文学賞)
『星モグラサンジの伝説』(1991年産経児童出版文化賞推薦)
『こそあどの森の物語』
(1~3の3作品で1995年野間児童文芸賞、
1998年国際アンデルセン賞オナーリスト選定)
など、子どもが大人になってからも
心に残り続ける作品を、たくさん生み出している。

- ──
- 『こそあどの森の物語』シリーズは、
「ふしぎな森のなかだけで完結するお話にする」
と決めて始めたとうかがいました。
そのとおり、全巻をとおして
物語の舞台は変わらないですが、
「時間」の行き来は多い印象があります。
森の人々が、
100年前に生きた海賊の願いを叶えるお話や、
神話の時代からやってきた子を助けるお話など‥‥
そういった、過去や未来とのつながりは
意識して書かれているのでしょうか。

- 岡田
- そうですね。
ひとつの場所や、ひとりの人は、
「いま、ここにいる」だけの存在ではなく、
「ずっと昔からつながれてきたものがあって、
ここにいる」ということには、
意識的でありたいです。
だから、
約束を果たすため何百年も生きていた人のような
キャラクターは、
折に触れて出してきましたし、
これからも出したいと思っています。 - 僕自身、大学生のときに
本をつくった自分がいなければ、
いま『こそあどの森』を書いている自分は
いませんからね。

- ──
- 児童文学というもの自体、読んだ子どものなかで、
長い年月を生き続けるものだと思います。
子どもが大人になってから、
「あの本を読んだからいまの自分がある」
と感じたり‥‥。
そのような意味で、子ども時代に本を読むことは、
大人になってから読むのとは
また違う意味がある気がします。
岡田さんは、子どもに向けて本を書くことについて、
とくに重視なさっていることはありますか。
- 岡田
- 「難しすぎる言葉は使わないでおこう」
といったことは考えますが、
あまり「子どもに向けて」とは考えていないです。 - たとえば『こそあどの森の物語』3巻の
『森のなかの海賊船』は、ある海賊が、
亡くなってしまった大切な女性にもう一度会うため、
100年ももつ魔法をかけるという話ですが‥‥
いま振り返ると、
ぜんぜん子ども向けではないです(笑)。
- ──
- 言われてみれば、そうですね。
- 岡田
- ただ、子どもであるスキッパーの視点をとおして
「大切な人がいなくなってしまって寂しい」
「もう一度会えてよかった」
といった感覚を書いているから、
かろうじて児童書として読んでもらえているのかなと
思います。
「子どものころに読んだときは、
意味がよくわからなかったけれど、
大人になってから読んだらおもしろくて、
何度も読み返すようになりました」
といった感想をいただくことがあるのは、
はじめから子どもだけを対象に書いているわけでは
ないからかもしれません。
- ──
- 子どもにも受け入れられ、
大人も心を動かされる物語のアイディアは、
どんなふうに生まれてきたのでしょうか。
- 岡田
- 『森のなかの海賊船』の場合は、
もともと「海賊船」というモチーフが、
僕のなかに強くあったんです。
「人はそれぞれ、一隻の海賊船なんじゃないか」
というイメージをずっと持っていて。
そこから話が広がっていきました。

- ──
- 人が、海賊船。
- 岡田
- ちょっと皮肉な見方ですが‥‥
人と人が関わることには、ときに
「相手を傷つけてなにかを奪い、
自分のものとして生きていく」
という部分があると思うのです。
- ──
- ああ‥‥たしかに、海賊船と重なります。
『こそあどの森』のキャラクターたちは
みんなやさしいけれど、
現実の人間関係と同じように、
自分にとって理解しやすく
相手の言動を解釈したりすることは、
きっとありますよね。
ずっとひとりでいたら、
人と関わる痛みはないけれど、
それでも他者と関わって、
奪い合うだけでなく与え合うこともあって‥‥
というテーマが、
シリーズ全体に流れているように感じます。
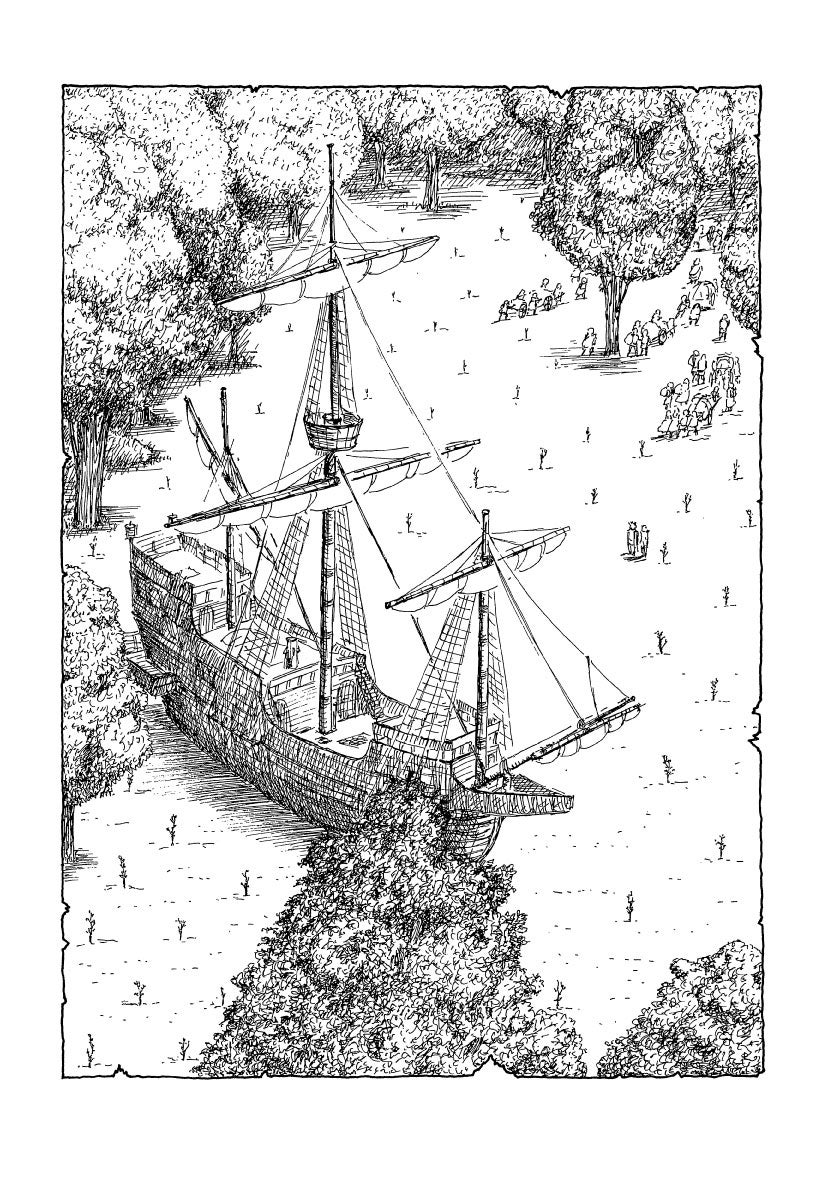 「こそあどの森の物語」第3巻『森のなかの海賊船』p.68
「こそあどの森の物語」第3巻『森のなかの海賊船』p.68
- ──
- では、岡田さんのなかでは、
子どもと大人の明確な違いはないのでしょうか。
- 岡田
- ないです、ないです。
僕自身が、あまり大人になった気がしないんです。
図工の先生をしていたとき、
ほかの先生が僕の授業を見て
「岡田さんは、僕たちとしゃべるときと、
子どもとしゃべるときの口調がまったく一緒や」
と言ってきたくらいです(笑)。
もしかしたら、子どもたちは、
そういうところをおもしろがって、図工の時間を
たのしんでくれていたのかもしれません。
- ──
- そうですね。
自分が子どもだったとき、
大人と同じように接してもらったら、
うれしかったです。
- 岡田
- そういえば、
先ほどお話しした『ドリトル先生』シリーズでも、
ドリトル先生はトミー少年を
子ども扱いしないんです。
ふつうは「トム」とか「トミー」とか、
名前で呼ぶようなところを、
「ミスター・スタビンズ」と呼ぶんですよ。
- ──
- 『こそあどの森』の大人たちも、
スキッパーや「湖のふたご」のような、
森に住む子どもたちに
しっかりと接してくれますよね。
守るところは守ってくれるけれど、
子どもたちの意思を汲んでくれるときもあって。
- 岡田
- そう受け取ってもらえるように描けていたなら、
よかったです。

(つづきます)
2025-04-15-TUE
-
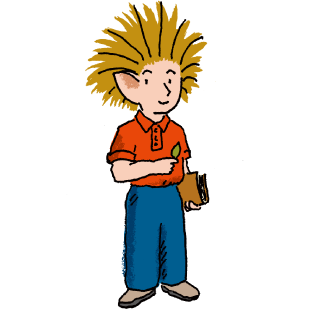
『こそあどの森の物語』シリーズの概要
「この森でもなければその森でもない、
あの森でもなければどの森でもない」
ふしぎな森で起こるできごとを描いた、
12巻+番外編3巻のシリーズ。
森には、内気な少年「スキッパー」をはじめ、
もてなし好きな「トマトさん」と
「ポットさん」夫婦、
遊んでばかりの「湖のふたご」、
少し皮肉屋な「スミレさん」と
寡黙な大工の「ギーコさん」姉弟、
作家の「トワイエさん」が住んでいる。2025年4月18日(金)〜5月11日(日)
TOBICHI東京で
岡田淳さんの原画展を開催します。

『こそあどの森の物語』の原画を、
TOBICHI東京で展示させていただけることに
なりました。
物語の挿絵や、精密な設定画、
ストーリーのもととなった
スケッチブックなど、
『こそあどの森』の世界観を
存分に感じていただける内容です。
あたたかく、やさしい色合いの作品から、
息を呑むほどの精密さが迫ってくる絵まで。
すみずみまで眺めたくなる原画の数々を、
ぜひご覧にいらしてください。入場は無料、
グッズ販売もございます。
くわしくは、
TOBICHI東京ホームページをご確認ください。