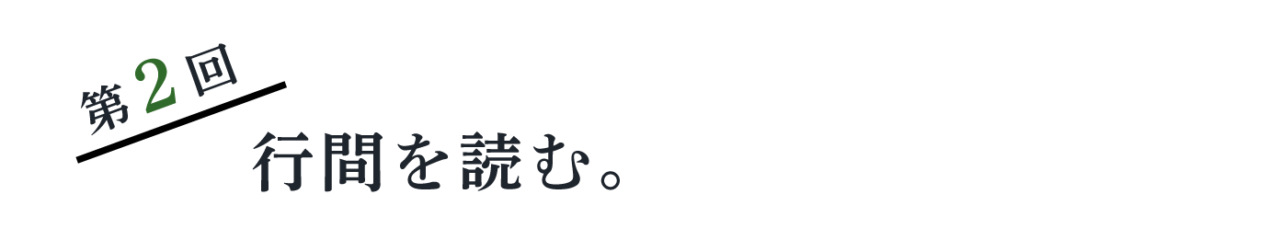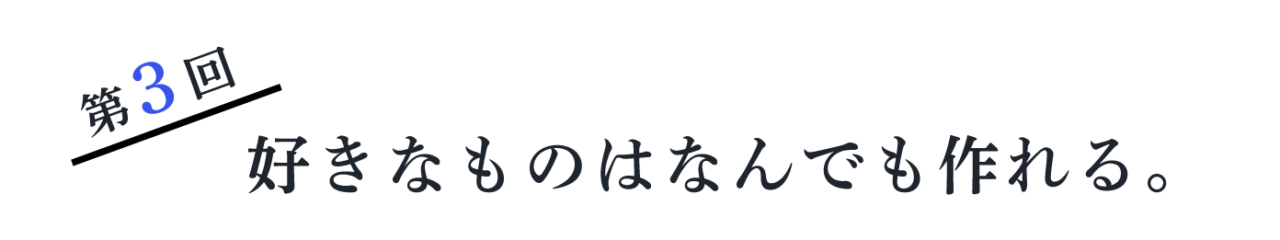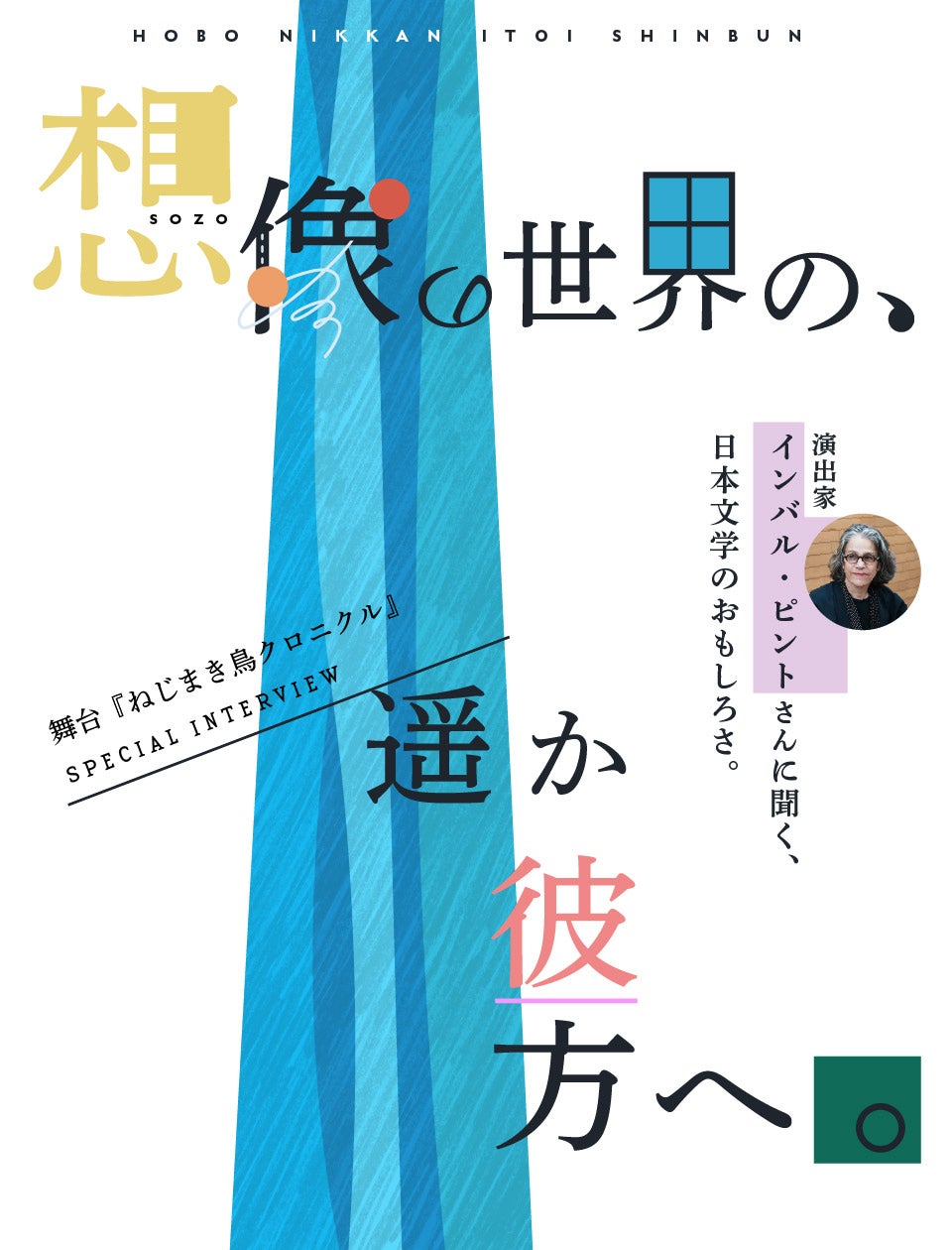
イスラエルを拠点に、世界的に活躍する
演出家、振付家、美術家のインバル・ピントさん。
これまで様々な日本の文学作品を題材に、
舞台を製作してきました。
佐野洋子さんの『100万回生きたねこ』、
芥川龍之介さんの『羅生門』、
そして、11月から再演されるのが、
村上春樹さんの『ねじまき鳥クロニクル』です。
マジカルでいびつな舞台は、
観る人を不思議な世界に引き込み、
初日をみた村上春樹さんは
「美しい舞台でした。ありがとう」と
言葉を残されたそうです。
どのように、日本文学を
身体で表現しようと考えてきたのか。
舞台の稽古中に時間をいただき、お話を聞きました。
担当は、インバル・ピントさんの作品の
大ファンであるほぼ日羽佐田です。
(いんばる・ぴんと)
1969年生まれ。国立ベツァレエル美術アカデミー卒(グラフィック・アート)。 バットシェバ・アンサンブル、バットシェバ 舞踊団を経て 92 年に自らのカンパニーを結成。以来『オイスター』、『ブービーズ』など革新的で想像力に満ちた傑作を発表。
2000 年『WRAPPED』でニューヨーク・ダンス&パフォーマンス賞ベッシー賞を受賞。2007 年には、彩の国さいたま芸術劇場とカンパニーの共同製作により「銀河鉄道の夜」をモチーフとした『Hydra ヒュドラ』を世界初演。2016 年にはカンパニー作品『DUST』をさいたまで公演。オペラや演劇、CM の分野でも活躍。ミュージカル『100 万回生きたねこ』(2013)、『WALLFLOWER』(2014)、2020年と2023年には村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』の演出・振付・美術を手掛けており日本でも積極的に活動を展開。
- ─
- 『ねじまき鳥クロニクル』など読まれて、
村上春樹さんの作品に
どのような印象を持ちましたか?
- インバル
- 勝手ながら、
私と創作の出発点が近いと感じました。
村上さんも自身の“体感”から
物語を書いているのではないかと想像します。
- ─
- インバルさんも体感をキーにしていると
おっしゃっていましたもんね。
- インバル
- 私は舞台を通して、
村上さんは書くことを通して、
体感からインスピレーションを受けた
恐怖、情熱、喪失、みたいなものを
限りなく羽ばたかせていると感じました。
- ─
- 羽ばたかせると、
どこに行くのでしょうか。
- インバル
- そうですね‥‥
現実離れしたもの、
魔法的な想像上のなにか。
つまり、マジカルでいびつなものにまで、
飛んでいけます。 - ですが、村上さんの作品がおもしろいのは、
マジカルでいびつなものの大元は
「人間である」ということが、
しっかり描かれていることです。
- ─
- 奇妙な世界と人間はつながっている。
- インバル
- そんなイメージですね。
- 想像の世界の遥か彼方、という話をしましたが、
結局は我々人間の頭から生まれている。
なので、どれだけマジカルでいびつでも、
感情とつながったところから書かれているから、
どこか実感を伴って読めるのではないかと思います。

- ─
- なるほど。
- インバル
- そのときの感情や状況によって、
物語のとらえかたが大きく変わるのは、
その物語が感情とつながっているからだと思います。 - 私も、はじめて読んだときと、
イスラエルの心苦しい状況を前にして、
今は物語のとらえ方が変わりました。
- ─
- 自分自身の状況によって、
物語のとらえ方が変わることはありますよね。
- インバル
- はい、だから今の私の体感も大事に、
小説のどの場面を選び取って
身体で表現するのか、ということは
長い時間をかけて試行錯誤してきました。 - どんな踊りをするのか。
表現の質感はどんなものがいいのか。
どんな音楽で踊るといいのか。
そんなことをずっと考えています。
- ─
- 途方もないプロセスですね。
- インバル
- そうなんです。
村上さんの作品の感情を表現するために、
たとえば「苦痛」と対峙している登場人物の
感情を表現するためにどうすればよいのか、
ここ最近ずっと考えていました。
苦痛の根源は、あらゆる理由がありますよね?
象徴するなにかを身体で表現するために、
見せ方を非常に工夫しました。
そういうことがあちこちにある舞台です。
- ─
- セリフではなく、あくまでも身体で?
- インバル
- セリフに託すこともありますが、
身体は言葉以上に表現できることがあるんです。
小説のなかで身体で表現すべきシーンを見つけては、
舞台にしています。
- ─
- 過去に上演された『羅生門』は古典作品ですが、
現代と古典の作品では
表現する際に違いがあるものでしょうか?
 ▲舞台「羅生門」撮影:渡部孝弘
▲舞台「羅生門」撮影:渡部孝弘
- インバル
- すべての文学作品からことなる体感を得るので、
時代のくくりで表現の違いはありません。 - ただ、今の質問で気づいたのですが、
ある”くくり”で表現の違いが発生するとしたら、
それはヘブライ語や英語と日本語という
言語のくくりは大きいかもしれません。
- ─
- ヘブライ語や英語と、日本語では、
表現の特徴がことなるということですか?
- インバル
- 表現というより文学や言葉の特徴として、
日本語は「行間」が特徴的だと思います。
だから、小説を読むときも、
行間を読む力が自然と必要とされる。
- ─
- ああ、なるほど。
- インバル
- 日本の文学作品は行間がものすごくあるんです。
なので、日本の文学作品を
ヘブライ語や英語に訳してしまうと、
平易になってしまうというか行間が伝わらない。 - 日本語という言葉自体が
想像をふくらませてくれる言葉で、
行間そのものを内包していると感じます。
それは素晴らしいですよね。
- ─
- 言われてみれば、たしかにそうですね。
行間や余白を感じることは多々あります。
- インバル
- 「行間」を「身体」で表現できるのは、
私にとって最高なことなんです。
相性がいいんですよ。
- ─
- その話を聞いていて思ったのは、
私はインバルさんの舞台を観るようになってから、
作品に対する触れ方が変わりました。
詩集や小説を読んでいると
「この作品をインバルさんなら
どうやって表現するのだろう」と
想像するようになったんです。
- インバル
- 最高の褒め言葉。
とても、うれしいです。

- ─
- 日本の文学作品ではないのですが、
たとえば『星の王子さま』を読んでいたとき、
そんなことを思いました。 - どうしてなのかうまく言葉にできなかったのですが、
インバルさんが「行間」を大事に創作されていて、
『星の王子さま』も行間がたっぷりある
作品だから共通点を感じたのかもしれないと、
お話を聞いていて思いました。
- インバル
- 作品に対する触れ方は、どう変わりましたか?
- ─
- そうですね‥‥
書かれた言葉以上のことを
想像するようになったかもしれません。
あと、読んだときの感覚として、
もっとカラフルになりました。
なので、読んだあとに
絵を描きたくなることがあります。
- インバル
- 素晴らしい。
私も、作品を読んだあとに必ず絵を描きます。 - 演出のほかに舞台美術も手がけるのですが、
舞台美術を考えるときのアイデアソースは、
読んだあとに描いた「絵」からきています。
そのあとに立体物をつくることもありますが、
まず絵を描くことからはじめる。
物語と対話するような感覚で。 - そうすると絵を通して、
自分の体感を認識できるんです。
- ─
- 言葉ではなく絵で体感を認識するんですね。
- インバル
- ときには言葉にすることもありますが、
絵のほうが、想像がつかないところまで
飛び立つことができるんです。 - とりあえず描くと、
直感的に「これだ」とクリアな感情を
見つけることもあれば、
長いプロセスを経ることもあります。
たくさんスケッチをして
自分の体感を整理しながら、
創作のはじまりにたどり着きます。
(つづきます。)
2023-11-13-MON
-
インバル・ピントさんが手がける舞台、
『ねじまき鳥クロニクル』が11月より開幕。
イスラエルの鬼才とよばれる、
演出家・振付家のインバル・ピントさんによる
舞台『ねじまき鳥クロニクル』が
11月に東京芸術劇場で上演されます。
原作は、村上春樹さんによる長編作品。
脚本を、共同演出も務める
アミール・クリガーさんと、
「マームとジプシー」の藤田貴大さんが、
音楽を大友良英さんが手がけます。
また成河さん、渡辺大知さん、門脇麦さんなど
舞台で力を発揮している名優が
演じ、歌い、踊ります。
2020年に一度上演されましたが、
コロナウィルスの蔓延により
公演が中止になり、
3年の時を経て、再演が決まりました。
また、新しい視点で探求された舞台を、
ぜひ劇場でご覧になってください。