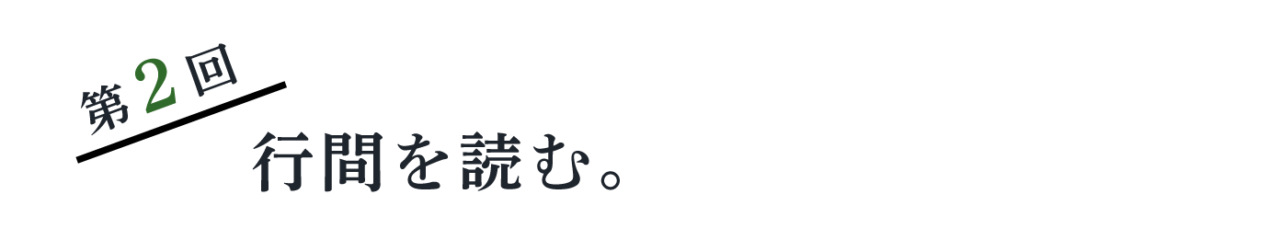イスラエルを拠点に、世界的に活躍する
演出家、振付家、美術家のインバル・ピントさん。
これまで様々な日本の文学作品を題材に、
舞台を製作してきました。
佐野洋子さんの『100万回生きたねこ』、
芥川龍之介さんの『羅生門』、
そして、11月から再演されるのが、
村上春樹さんの『ねじまき鳥クロニクル』です。
マジカルでいびつな舞台は、
観る人を不思議な世界に引き込み、
初日をみた村上春樹さんは
「美しい舞台でした。ありがとう」と
言葉を残されたそうです。
どのように、日本文学を
身体で表現しようと考えてきたのか。
舞台の稽古中に時間をいただき、お話を聞きました。
担当は、インバル・ピントさんの作品の
大ファンであるほぼ日羽佐田です。
(いんばる・ぴんと)
1969年生まれ。国立ベツァレエル美術アカデミー卒(グラフィック・アート)。 バットシェバ・アンサンブル、バットシェバ 舞踊団を経て 92 年に自らのカンパニーを結成。以来『オイスター』、『ブービーズ』など革新的で想像力に満ちた傑作を発表。
2000 年『WRAPPED』でニューヨーク・ダンス&パフォーマンス賞ベッシー賞を受賞。2007 年には、彩の国さいたま芸術劇場とカンパニーの共同製作により「銀河鉄道の夜」をモチーフとした『Hydra ヒュドラ』を世界初演。2016 年にはカンパニー作品『DUST』をさいたまで公演。オペラや演劇、CM の分野でも活躍。ミュージカル『100 万回生きたねこ』(2013)、『WALLFLOWER』(2014)、2020年と2023年には村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』の演出・振付・美術を手掛けており日本でも積極的に活動を展開。
- ──
- イスラエルの情勢がたいへんななか、
こうしてお話しできる時間をいただき
ありがとうございます。
- インバル
- こちらこそ、ありがとう。
私の作品をよく観てくださっていると聞きました。

- ──
- そうなんです。
私はコンテンポラリーダンスが好きで、
よくご一緒されている森山未來さんをきっかけに
インバル・ピントさんのことを知りました。 - 初めて観たのが『100万回生きたねこ』でした。
読んだことがある絵本が題材なのに、
私が想像していた物語とは全く違っていて、
衝撃的な観劇体験でした。
- インバル
- うれしいです。
- 再演もふくめると、
日本でのクリエイションは再演もふくめて
5回上演をしているのですが、
はじめてオファーをいただいたのが
『100万回生きたねこ』でした。
- ──
- インバルさんは本や絵本など、
既存の物語を題材に
舞台をつくられるんですか?
- インバル
- いえ、こういう作りかたははじめてでした。
- 私はコンテンポラリーダンスやオペラなど、
いろいろなジャンルの舞台を手がけています。
でも、どれも私のオリジナル。
なので、既存の作品を自分なりに解釈して
舞台にするというのははじめてでした。
- ──
- 日本文学はもともと読まれていたんでしょうか?
- インバル
- いえ、『100万回生きたねこ』が
日本の文学作品に触れた、はじめての体験でした。
ですが、この本ですごく衝撃を受けました。
 ▲舞台「100万回生きたねこ」。中央)成河、左から)石井正則、田口浩正、近藤芳正、銀粉蝶、藤木孝。撮影:渡部孝弘
▲舞台「100万回生きたねこ」。中央)成河、左から)石井正則、田口浩正、近藤芳正、銀粉蝶、藤木孝。撮影:渡部孝弘
- ──
- 衝撃を受けられたんですか。
- インバル
- まず、子ども向けの絵本で、
「死」をテーマに描いていることに驚きました。
なぜなら「死」は、
多くの人が恐れていることだから。
ネガティブなものと受け取られることが多いですよね。
- ──
- そうですね。
- インバル
- しかし、死を自然なこととして、
子どもたちに向けて物語っていることに
驚いたんです。
ポジティブではないけれど、
怖いものとしてもとらえていない。
ナチュラルに死を語る姿勢は、
日本独自の文化だと思いました。
- ──
- なるほど。
言われてみればそうかもしれません。
- インバル
- 『100万回生きたねこ』をきっかけに、
さまざまな日本の作品や文化に触れましたが、
他の作品でも「死」を取り扱っているものが、
いくつかありました。
目をそらさずに物語る、
それは素晴らしいことだと思います。
- ──
- 村上春樹さんの『ねじまき鳥クロニクル』は、
どういうところに心が動きましたか?
- インバル
- 村上春樹さんの小説は、
「想像の余地」を
たっぷり残してくれていると思いました。
- ──
- 想像の余地ですか。
- インバル
- はい。
ものすごく現実的な描写もあります。
嫌というほど具体的に書いて、
読者にリアルを見せつけるような鋭い文章もあれば、
対局で、私たちの無意識のさらに先、
現実世界では決して触れられないような
もっと超越したところに導いてくれる文章もある。
Reality(現実)とImagination(想像)が
共存しているんです。
- ──
- おもしろいです。
私も、村上作品は人間の生々しい感情と
想像の世界が混在していて、
あっちこっちに連れて行かれて惑うような
読後感になる印象がありました。
- インバル
- すごく、わかります。
- 読んだ後の体感としていちばん残ったことは、
脳の中に回廊があるとしたら、
道筋が何方向にも延びていて、
それぞれの道を違う私が歩いているんです。
つまり、自分自身が分裂して存在している
かのような感覚になりました。
- ──
- なるほど。
- インバル
- なので、今回舞台では、
ひとりをふたりの役者に演じてもらいました。
それは、精神が分裂している状態を
視覚的に表現したかったから。 - ひとりはフィジカルな身体を担い、
もうひとりは精神的な何かを演じる。
心と体が分裂していて、
複雑な世界を生きているように
見せたいと思いました。
- ──
- 「ねじまき鳥クロニクル」は長編小説なので、
舞台にまとめるのは大変でしたよね。
- インバル
- 私は小説をそのまま舞台にすることはありません。
ディコンストラクション(解体)して、
リコンストラクション(再構築)することが、
文学を舞台化するには必要です。
- ──
- 小説を解体して、再構築する。
- インバル
- はい。
小説のアイデンティティを持ったまま、
「舞台芸術」として一から作り直すんです。

- ──
- リコンストラクションするときは、
なにをヒントにするのでしょうか?
- インバル
- 作品によってやり方はさまざまなのですが‥‥
たとえばダンス劇をつくる場合は、
読み進めているときの”体感”がキーになります。
- ──
- 体感。
- インバル
- 本を読むと、心や身体が刺激を受けますよね。
なにかしら感覚や感情が突き動かされる、
その”体感”から創作がはじまります。 - 自分の体が直感的に感じたことは何か、
体は私になにを語りかけているのか、
体感に耳を澄ませるんです。
さまよいながら体感を確かめる時間は
非常に長いプロセスですが、
文学を身体で表現する始まりはそこにあります。
- ──
- なるほど。
- インバル
- しかし、そこに執着しません。
体感をベースにしつつ、
自分自身をリリース(解放)する。
そこからは直感で作っていくのですが、
勇気を持って、小説の構造を崩すことが大切です。
- ──
- どこに行くかわからないけれど。
- インバル
- そうです。
どこに行くかわからないけれど
飛び込んでみる、さまよってみる。
直感のまま旅路を歩んでみる。 - そうすると、
あちこち行くことになるので、
想像の世界の遥か彼方まで
連れて行ってくれる感覚になります。
- ──
- 想像の世界の遥か彼方ですか。
- インバル
- そうです。
行ってみたいでしょう?(笑)
- ──
- 行ってみたいです(笑)。
でも、インバルさんの作品を観ていると、
連れて行かれる感覚になります。
- インバル
- そうですか。
それは、とてもうれしいです。
- ──
- ダンスという表現は、
想像力をかき立てることと
相性がいいのかもしれませんね。
正解が提示されるものではないですし、
それぞれの感性で受け止めるしかないので。
- インバル
- まさに、その通りだと思います。
ダンスは”サブコンテキスト”を
あたえてくれるものです。
つまり、セリフとして言語化されない、
別の意味合いを表現することができる。 - 言葉としてまとめることができない
体感やイメージをふくらませて、
観る人の想像力をかき立てることは、
ダンスが得意とするところだと思います。
(つづきます。)
2023-11-10-FRI
-
インバル・ピントさんが手がける舞台、
『ねじまき鳥クロニクル』が11月より開幕。
イスラエルの鬼才とよばれる、
演出家・振付家のインバル・ピントさんによる
舞台『ねじまき鳥クロニクル』が
11月に東京芸術劇場で上演されます。
原作は、村上春樹さんによる長編作品。
脚本を、共同演出も務める
アミール・クリガーさんと、
「マームとジプシー」の藤田貴大さんが、
音楽を大友良英さんが手がけます。
また成河さん、渡辺大知さん、門脇麦さんなど
舞台で力を発揮している名優が
演じ、歌い、踊ります。
2020年に一度上演されましたが、
コロナウィルスの蔓延により
公演が中止になり、
3年の時を経て、再演が決まりました。
また、新しい視点で探求された舞台を、
ぜひ劇場でご覧になってください。