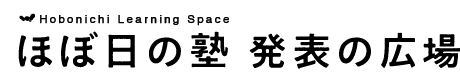まるで標準装備されているかのように、
「いつか、犬を飼うんだ」という思いがあった。
それがいつどういうきっかけで生まれたかを
考える余地がないほど当たり前にあったから、
「きっと前世で犬と深い縁があったんだ」
くらいに思っていたところがある。
いやいや、待て待て、それでは乱暴すぎるだろう。
ということで、記憶をたどってみることにした。
生まれてから3歳まで、私たち一家は、
東京の下町に建つ父の勤める会社の社宅に住んでいた。
4階建てが2棟。私たち家族の住まいは3階。
社宅の敷地内にはスペースがふんだんにあり、
あっちでは男の子たちがチャンバラごっこに興じ、
こっちでは女の子たちがお姫様ごっこで
気取ったセリフの応酬をする、
というように、年齢の近い子同士が
ひとかたまりになって遊ぶ日常があった。
そばに大人の姿はなかった。
敷地内なので、家事を片付けながら、
なんとなく子どもの様子を見守る、
ということはあっても、
今みたいに、子どもに付き添ってその場にいる、
ということの必要のない時代だったのだ。
人も社会もいろいろな意味でおおらかだった。
その代わり、というわけではもちろんないが、
子どもたちとは少し距離をおきながら、
スペースを共有するものたちがいた。
野犬だ。当時は野犬が群れになって町中をうろついていた。
縄張りがあるのか、見かけるのはいつも同じ軍団。
そのうちの1匹を子どもたちが「ボス」と呼んでいたから、
怖がるばかりの存在ではなかったと思う。
もちろん、一緒に遊ぶ仲でもなかった。
当時は「野犬狩り」というものがあって、
野犬にとって人間はうかつに近づくには
危険な存在だったのだ。
小さい頃に出会うのは野犬のみ。
さすがにそれで、「いつか、犬を飼うんだ」という
思いが芽生えるとは思えない。
だとしたら、その思いはどこから?
もしかして、と思ってネット検索したら、
案の定な情報がヒットした。
コリー犬を主人公にしたテレビドラマの『名犬ラッシー』。
このアメリカのドラマが日本で放映された時期と
東京下町の社宅時代が重なっていたのだ。
なーんだ。テレビの影響かあ。
今どきの男の子が将来の夢に変身ヒーローをあげるのと
ちっとも変わらないではないか。
(前世説が消えてちょっと残念)
野犬との思い出は、4歳で引っ越した先の
海沿いの町でのほうがカラフルだ。
そこでも私たち家族の住まいは社宅だったが、
幼稚園児だったある日、敷地内の芝生に一人でいたら、
遠くにいる野犬の一団と目が合った。
その瞬間、野犬たちが「!(おっ)」となり、
私のほうも「!(やばいかも)」となった。
野犬たちが私をめがけて走り出し、
豆粒ほどだった姿がみるみる大きくなっていく。
とっさにくるりと向きを変えた私は、
頭上といっていいほどの高さの
社宅1階のベランダの柵をわしっとつかむと、
渾身の腕力と脚力でよじのぼった。
ほっと一息ついて、ベランダから野犬たちを
見下ろしたのを覚えている。間一髪だった。
鉄棒で「エビ上がり」ができるようになっていて、
つくづくよかったと思う。
<つづきます>