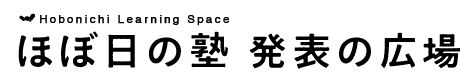父はその昔、とにかくひょうきんな少年だったという。
「学校をさぼって友達と喫茶店で漫画を読んでいた」
という父の高校生時代のエピソードを聞いたとき、
「なるほど僕は父のそういうテキトーな部分を
しっかりと受け継いでしまったのだな」
と、僕は半ば強引に納得することにした。
それは、自分自身のテキトーな性格を少しでも
正当化するためには、うってつけのエピソードだった。
そうはいっても、困ったときはなんやかんや
頼り甲斐がある。それが僕の父だ。
今でも、相談ごとがあるときは、躊躇なく連絡をするように
している。
「勝っておごらず、負けて憎まず」
というのが父の座右の銘であり、僕自身も大事にしている
言葉の一つだ。
そんな父の仕事場は、
機内食(飛行機で乗客に提供される食事)のメニュー開発を
中心事業とする会社だった
(つい最近、定年退職したばかり)。
父はその会社に転職するまで、
料理人をやっていた。
そして父の父、つまりは僕の祖父もまた料理人だった。
祖父は、名古屋に自分の店を持っていた時代も
あったそうで、実家には
亡くなった祖父が割烹着を着て、
真剣な眼差しで料亭の刺し場に立つ写真が飾られている。
加えてなんと、僕の曽祖父までも料理人だったという。
3人とも和食をつくる料理人、
いわゆる『板前』と呼ばれる職人だ。
そして、3代にわたる料理人の血筋を存分に引いたはずの
僕はというと、
ほとんどと言っていいほど料理をしない。
はっきり言って、料理することには大して興味がないし、
そもそも自分にはそのセンスがないことがわかっている。
「昔、料理をやらせてみようとしたけど、
全然興味を示さなかったし、
嫌がったのですぐに諦めた」と、父は以前、
僕に教えてくれた。今となっては、
「もっと父に料理を教わっておくべきだった」と
本気で後悔している。というのも、やっぱり
『料理ができる男』に対して少なからず憧れがあるからだ。
父は、週末で仕事が休みになると、よく家で晩ご飯をつくって
くれた。普通の炒め物や煮物というよりは、
やったら凝った創作料理みたいなのが多かった気がする。
そういえば、寿司を握ってくれたことも何度かあった。
釣りが好きだったので、自分で釣って来た鮎を塩焼きにして
食べさせてくれることもあった。

(父から送られてくる写真は
なぜかいつもピントが合っていない)
プロなんだから当たり前といえば当たり前だが、
父の料理も母の料理同様、めちゃくちゃおいしかった。
母のつくる料理と比べると、幾分『男の料理』という感じの
味付けだったが、僕にとっては、それがたまらなく好きな
味付けだったのだ。
父は僕が食べているのをじっと凝視しながら、
「どうだ。うまいだろう?」と、
いつも必ずそう言った。
僕は大抵の場合
「はいはい、おいしいおいしい」と、テキトーな返事を
していた。
すると父は屈託のない笑顔で
「そうだろう、そうだろう」と、
得意げに、嬉しそうに、そう言うのだ。
僕はそれに対して
「じろじろ見られると食べづらいから、やめてくれ」と
まるで反撃でもするかのように、いつも
つっけんどんな言葉を返した。
(つづきます)