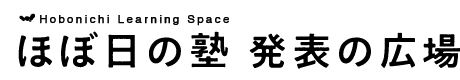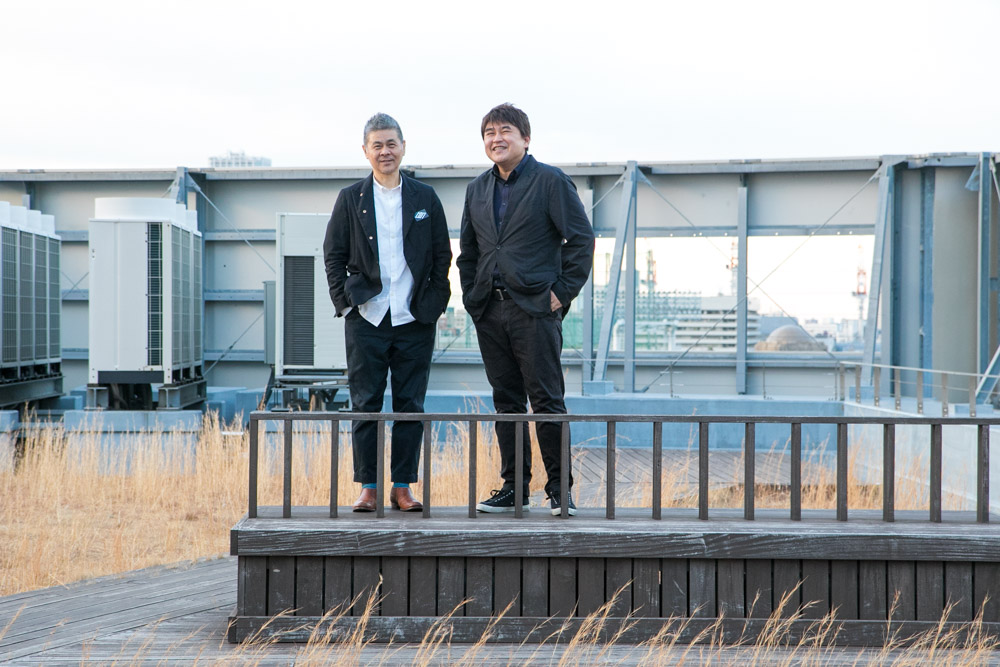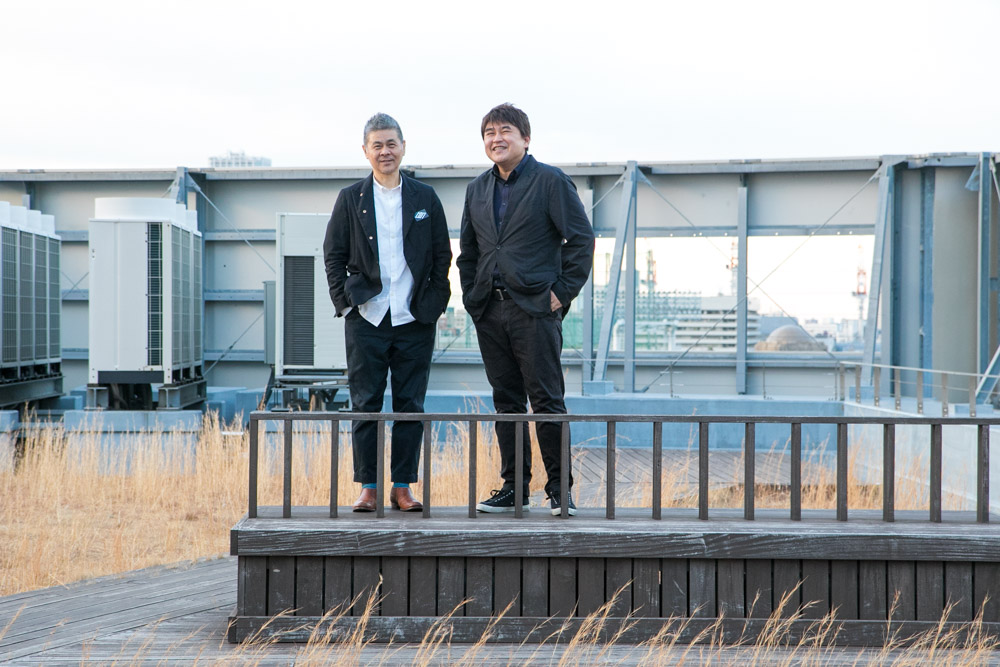
バスタブに水を張って待つ田中泰延×糸井重里書くふたりの「人生」対談
第2回 その場所で自由にみんな遊べ
- 糸井
-
自分は文字を書く人だとか、
考えたことを文字に直す人だっていう
認識そのものがなかった時代が、
20年以上あるっていう。
不思議ですよね。
「嫌いだ」とか「好きだ」とかは
思ってなかったんですか?
- 田中
-
読むのが好きで。
夏の皆さんとの「書くについての公開雑談。」でも、
「ひたすら読んでました」っていうのは言ったんですけど、
まさか自分がダラダラ何かを書くとは夢にも思わず。

- 糸井
-
今の言い方を、
自分がどういうふうに感じてるんだろうって、
頭の中で考えていたんですけど。
読み手として書いてるっていうタイプの人、
そういう表現を初めてしたんでわからないけど、
自分にもちょっとそういうところがあって。
コピーライターって、書いてる人っていうより、
読んでる人として書いてる気がするんですよ。
- 田中
-
はい、すごくわかります。
- 糸井
-
だから、視線は読者に向かってるんじゃなくて、
自分が読者で、自分が書いてくれるのを待ってるみたいな。
- 田中
-
おっしゃるとおり!
いや、それ、すごく、すっごくわかります。

- 糸井
-
これ、お互い初めて言い合った話だね。
- 田中
-
いや、そんな、ねぇ、糸井重里さんですよ。
- 一同
-
(笑)
- 糸井
-
いやいや。
- 田中
-
でも、本当にそうですね。
- 糸井
-
これを説明するの、むずかしいですねぇ。
- 田中
-
むずかしいですね。
でも、発信してるんじゃないんですよね。
- 糸井
-
受信してるんです。
で、自分に言うことがない人間は書かない
って思ってたら大間違いで。
読み手というか、「受け手であるということを、
思いっきりのびのびと、自由に味わいたい!」
って思って、「それを誰がやってくれるのかな」、
「俺だよ」っていう。
- 田中
-
そうなんです。
- 糸井
-
うわぁ、なんて言ったらいいんだろう、これ。
- 田中
-
なんでしょう。
- 糸井
-
今の言い方しかできないなぁ。
- 田中
-
そうですね。
映画を観るってことに関しても、
まずその映画自体を観ますね。
次に、今はいろんな人が、ネットでも雑誌でも
評論をするじゃないですか。
そうしたら、「何でこの中に、この見方はないのか?」。
それを探してあったら、
もう自分は書かなくていいんですけど、
「この見方、なんでないの?じゃあ、今夜、俺書くの?」
っていうことになるんですよね。
- 糸井
-
あぁ、俺、なんであんなにおもしろいかっていうことと、
書かないで済んでた時代のことが、今やっとわかった。
広告屋だったからだ。
- 田中
-
そうですね。
- 糸井
-
因果な商売だねぇ。
- 田中
-
そうなんです。広告屋はね、発信しないですもんね。
- 糸井
-
しない。
でも、受け手としては、感性が絶対にあるわけで。
発信するものだけが個性じゃないから、
「俺の受け取り方」も個性なんですよね。
それで、そこにピタッと来るものを探してるのに、
人がなかなか書いてくれないから、
「え、俺がやるの?」っていう。
それが仕事になってたんですよね。
- 田中
-
そうですね。
- 糸井
-
自分がやってることも今わかったわ。
- 田中
-
(笑)
- 糸井
-
僕ね、ものを書くのが嫌いなんですよ。
前から言ってますけど(笑)。
- 田中
-
僕もすっごい嫌(笑)。
古賀さんもすごい嫌って言ったけど、
みんな嫌なんですよ。本当に。
- 糸井
-
でも、「じゃあ、自分の考えってないの?」
っていう問いは、何十何年してきたと思うんですよ。
僕もそうですし、多分田中さんも、
「じゃあ、お前って、なんの考えもないのかよ」
っていうふうに誰かに突きつけられたら、
「そんな人間いないでしょう」っていう一言ですよね。
そこを探しているから、日々生きてるわけでね。
- 田中
-
そうですね。
あの、糸井さんがご存じかどうかわからないけれども、
糸井重里botっていうのがあるんですよ。
糸井さんの言葉を再読するちゃんとしたbotではなく、
糸井さんふうに物事に感心するっていう。
だから、いろんなことに関して、
「いいなぁ、僕はこれ、いいと思うなぁ」(笑)。
- 糸井
-
あぁ。
- 田中
-
つまり、糸井さんの、物事に感心するあの口調だけを
繰り返しているbotなんですよ(笑)。
それで、「僕はこれは好きだなぁ」。
- 糸井
-
僕はもうそればっかりですよ。
- 田中
-
ですよね。
だからそのbot、すごくよくできいて。
何に関しても、「僕はそれ、いいと思うなぁ」。
- 糸井
-
だいたいそうです。
- 田中
-
でもその時に、何か世の中に対して
伝えたいじゃないですか。
たとえば、この水でも、
「この水、このボトル、僕好きだなぁ」っていうのを、
相手にちょっとだけ伝えたいじゃないですか。
「僕は今、これを心地よく思ってます」って。

- 糸井
-
そうですね。
それは他のボトルを見た時には思わなかったんですよ。
そのボトル見た時に思ったから、これを選んだ。
また選んでいる側ですよ。
- 田中
-
そうですよね。
- 糸井
-
受け手ですよね。という日々ですよ。
なんだかこれ、コピーライターズクラブの
壇上でしゃべっているような(笑)。
- 田中
-
そうですね(笑)。
- 糸井
-
でも、コピーライターはこれ、わかってくれるかしら?
- 田中
-
多分この感覚、皆さんおわかりになるんじゃないですかね。
- 糸井
-
わかるんですかね。
- 田中
-
はい。
- 糸井
-
多分僕、このことをね、ずっと言いたかったんですよ。
で、自分がやっていることの
癖だとか形式だとかっていうのが、
飽きるっていうのもあるし、それから、
なかなかいいから応用しようっていうのもあるし、
そこをずっと探しているんだと思うんですね。
田中さんは、広告屋として、
そこで付けてしまった癖が20何年分あって。
- 田中
-
はい。
- 糸井
-
自分の名前で出していくっていう立場になって、
変わりますよね、自分。
- 田中
-
そうなんです。これがむずかしい。
今、「青年失業家」として岐路に立っているのは、
会社でコピーライターをやっていて、
そのついでに何かを書いてる人ではなくなりつつあるので、
じゃあ、どうしたらいいのかっていうことで、
すごい岐路に立っているんですね。

- 糸井
-
二つ方向があって、
書いたりすることで食っていけるようにする
っていうのが、いわゆるプロの発想。
それから、書いたりすることっていうのが、
食うことと関わりなく自由であることで書けるから、
そっちを目指すっていう方向。
二種類に分かれますよね。
- 田中
-
そうですね。
- 糸井
-
僕もきっと、それについては
ずっと考えてきたんだと思うんですね。
で、僕はアマチュアなんですよ。
つまり、書いて食おうと思った時に、
俺は、自分がいる立場が、
なんかこうつまんなくなるような気がしたんで。
いつまで経っても旦那芸でありたいっていうか、
「お前、ずるいよ、それは」っていう場所からいないと、
いい読み手の書き手にはなれないって思ったんで、
僕はそっちを選んだんですね。
田中さんは、まだ答えはないですよね。
- 田中
-
そうなんです。
- 糸井
-
どうなるんだろうねぇ。
- 田中
-
僕の「糸井重里論」っていうのは、
旦那芸として好きに書くために、
みんなが食べられる組織を作り、
それを回していき、物販もし、
自分のクライアントは自分っていう、
壮大な立場をつくるっていう。
- 糸井
-
そうですね。
- 田中
-
つくり切ったってことですよね。
- 糸井
-
『キャッチャーズ・イン・ザ・ライ』っていうので、
最初、ライ麦畑で捕まる話かと思ったら、
タイトルからして誤訳で。
「俺はキャッチャーだから、その場所で自由にみんな遊べ」
っていう話ですよね。
まさしく、僕が目指しているのは、
『キャッチャーズ・イン・ザ・ライ』で。
- 田中
-
見張り塔からずっとなんですね。
- 糸井
-
そうなんです。
それで、その場を育てたり、譲ったり、
そこで商売する人に屋台を貸したりみたいなことが
僕の仕事で。
その延長線上に何があるかって言うと、
僕は書かなくていいんですね。
本職は、管理人なんだと思うんですよ。
その意味では田中さんも、その素質もあると思うんです。
- 田中
-
なるほど。
- 糸井
-
僕は、人がなんと思っているかは知らないけど、
自分では、やりたいこととやりたくないことを、
燃えるゴミと燃えないゴミみたいに、本当に峻別して、
やりたくないことをどうやってやらないか
っていうことだけで生きてきた人間で。
「やりたいことだなぁ」とか、「やってもいいなぁ」
って思うことだけを選んできたら、こうなったんですよね。
で、多分、田中さんが僕を見てる目も、
そこのところをよく見てるわけだから。
- 田中
-
そうですね。
- 糸井
-
どっちに転んでも全然いいわけで。