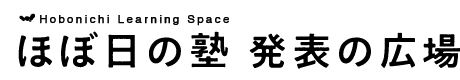- 糸井
- プロとして書くか、自由に書くか。ぼくも、きっとそれについてはずっと考えてきたんだと思うんです。で、ぼくはアマチュアなんですよ。つまり、「書くことで生計を立てようとしたら、俺はつまらなくなる」というような気がしたんです。
- 田中
- はい。
- 糸井
- いつまでたっても旦那芸でありたい。「お前、ずるいよ、それは」って言われるような場所にいて書くのではないと、「いい読み手の書き手」にはなれないって思ったので、ぼくはそっちを選んだんですね。田中さんは、まだその答えは出ていないんですよね。
- 田中
- そうですね。
- 糸井
- どうなるんだろうねえ。

- 糸井
- もうね、超アマチュア、っていう状態で一生が終われば、ぼくは満足なんですよ。
- 田中
- その「軽み」をどう維持するかっていうことについては、きっと、糸井さんの中ではずっと闘いだったんでしょうね。
- 糸井
- そうですね‥‥。でも同時にその軽さはコンプレックスでもあるんだけどね。「俺は、逃げちゃいけないと思って勝負してる人たちとは違う生き方をしてるな」って。
- 田中
- わかる。めっちゃわかる(笑)。

- 田中
- ぼく、まだものをちょっとでも書くようになってたった2年ですけど、書くことの落とし穴っていうのはすでに感じていて。それは、つまり、「俺はこう考える」っていうことを毎日毎日書いているうちに、だんだん独善的になっていく気がするんですね、やっぱり。
- 糸井
- うん。
- 田中
- ほかの書き手を見ていても、最初のころは人の揺れている部分をそのまま書いていて、いいな、と思っていたのが、書いているうちに、どちらかに振り切ってる感じの書き方になっていくことがある。人が書くって、そういうものなんだなと。
- 糸井
- なっていきますね。それって、「世界像を安定させたくなる」ということなんだと思うんですよね。
- 田中
- ああ、はい。
- 糸井
- でも、そうやって世界像を安定させると、夜中にものを書いている時の全能感っていうのが、昼間、ご飯を食べてるような日常にまで追っかけてくるんですね、たぶん。
- 田中
- そうですね。書くという行為が、そういうものであることを忘れるのは危ない。
- 糸井
- そういうところから、逃げたい。人間って、生まれた、娶った、耕した、死んだ‥‥というような、4つくらいしかないっていう生き方は、人によっては、つまらない悲しいことだと思うかもしれないけど、じつはこれ、やっぱり一番高貴な生き方じゃないかと思うんです。
- 田中
- ああ‥‥。
- 糸井
- 結局ぼくが行きつくのが「ご近所の人気者」っていうところで。中崎タツヤさんの『じみへん』という漫画に出てくることばなんですよね。
- 田中
- はいはい。
- 糸井
-
「よっ、○○さん、元気?」って言ってまわってるだけみたいな「ご近所の人気者」どまり。これがやりたいんだ、って思っていて。ぼくのことを生身の人間として把握してる範囲の人たちが、「今日も機嫌ようやっとるな。ええな」と言ってくれるような、お互い言い合うような。そういうのがいい。
そして、その「ご近所」のエリアが、本当の地理的なご近所と、気持ちのうえでのご近所と、両方あるのがいまなんでしょうね。
- 田中
- ああ、そうですね。ネットを介したり、印刷物を介したりしての「ご近所」もある。でもやっぱりその「ご近所感」には、フィジカルなことがすごい大事だという気がしますね。
- 糸井
- 大事ですね。
- 田中
- ぼくが今日の対談の1週間前に梅田ロフトの糸井さんの控室に5分だけでも訪ねていく、そして今日がある、だと、やっぱり全然違うんですよね。ちょっと顔見に行くとか、ちょっと話すとか。
- 糸井
- ああ、あの時も手みやげをどうもありがとう(笑)。
- 田中
- はい(笑)。
- 糸井
- アマチュアであることと「ご近所感」ってね、けっこう、隣り合わせなんですよ。
- 田中
- うん、うん。
- 糸井
- で、そこからずれるぶんだけ歪んでいるんじゃないかって。その人の世界像を他人に押しつけて平気でいられるような「偉い人」になっちゃうっていうのはね‥‥。
- 田中
- はい。
- 糸井
- 書き手っていうものに対して、うーん‥‥、ある種のカリスマ性を要求しますね、人って。
- 田中
- ああ、はい。
- 糸井
- そこからも自由になりたいな、と。でも「糸井さんは、本当にいろんなものから吹っ切れているようだけど、やっぱりちょっと作家を偉いと思ってる。それはものすごく惜しいことだと思う」というようなことをかつて言われたんですよ。ぼくがつい「拍手」してしまうというのが、作家に限ったことではなくて、絵を描く人や、映画作ってる人にも、全部そうなんですけど。でも、もっとしょうもないものへの拍手も同じぐらいしてるつもりなんだけどなあ‥‥。やっぱり表現者に対する拍手というのは、外からも見えやすいからかな。
- 田中
- ああ、だから、そこをバランス取るために、ぼくのような、このしょうもないことばかり言ってる人間に、夜中にツイッターでからむわけですか(笑)。
- 糸井
- からんでもだいたい「www」で返されてますけどね(笑)。
- 田中
- 「もう夜中の3時半だけど、またなんか言ってきたよ」って。
- 糸井
- へたすると、ひと寝入りしてからまた起きて、まだからんでたりするからね(笑)。

- 田中
- それはさておき、永遠に馬鹿馬鹿しいことをやるっていうのは、これは一種の体力ですよね。
- 糸井
- 体力ですね、そうですね。
- 田中
- でも、これをやらないところに陥った瞬間、偉そうな人になる。
- 糸井
- そうならないためのひとつが「ご近所の人気者」っていうあり方で。歪んでない人の視線で自分の歪みを見る、そういう目線を持つことが、「ご近所感」ということなんですよね。どうやってそういう部分を維持するか、どの部分について維持するか、ということについては‥‥ぼくに関しては、「ご近所感」をもっていた吉本隆明さんのような人たちを見ていたのが、とても大きいような気がしますね。
- 田中
- 吉本さんというと、あのお花見の話とか。午前中から、吉本さんがいろいろセッティングをしているという‥‥。
- 糸井
- そうそう。自転車で、ブルーシートを背中にしょって、1冊読む本を持って行って。夜、人が集まるまで本を読みながら場所取りを。うーん‥‥、すごいねぇ。
- 田中
- すごいですね(笑)。
- 糸井
- でも欠点は、鍋が上手じゃなくて。こう、鍋の具材を、火が点いてグツグツ言い出すと、全部いっぺんに入れちゃう。
- 田中
- いっぺんに。
- 糸井
- それで、「ちょっと、吉本さん、それはどうかと思いますよ」と。
- 田中
- (笑)。
- 糸井
- そうすると、「あぁ、そうか、そうか」って言うんですよ。すぐ謝っちゃうんです。
- 田中
- すぐ謝る(笑)。
- 糸井
- そう。
- 田中
- 「えらそくならない」っていうこと、これは大阪弁ですけど、偉そうにならないって、すごい大事だなって思いますね。「ご近所の人気者」というところでは、(笑福亭)鶴瓶さんとかもそうですよね。
- 糸井
- あれはもう鍛え抜かれた、えらそくならなさですね。
- 田中
- 矢沢永吉さんなんかも‥‥。
- 糸井
- 永ちゃんは、うん、すごい。本当に「ご近所の人気者」なんですよ。みんなで行くレストランの予約とかイベントの企画とか、なんでも自分でやっちゃう。なんか引っ越しする部屋を探しあぐねてる人の物件の世話までしてた。
- 田中
- 矢沢さんご本人が? それはすごい。
- 糸井
- そういうひとたちの影響を自分が受けてるというわけでもないんだけど、こういうあり方が可能なんだっていう、とてもいいモデルですよね。
- 田中
- いやあ‥‥すごいなあ。
- 糸井
- うん。あの、アマチュアだってことは、変形してないってことなんです。
- 田中
- 変形?
- 糸井
- つまり、「プロは変形している」。これは吉本隆明さんの受け売りで、吉本さんはマルクスの受け売りなんですけど。「自然に対して人間は働きかける。で、働きかけたぶんだけ自然は変わる、と同時に自分自身も変わる」という。
- 田中
- はい。
- 糸井
- 仕事、つまり、自然に対して何かをするっていうのは、相手が変わったぶんだけ自分も変わっているんだよ、ということですね。わかりやすいところで言うと、ずっと座ってろくろを回している職人さんがいたとしたら、座りダコができているし、指の形やらも変わっているかもしれないっていうふうなことですね。1日だけろくろを回す人にはそれはない。作用と反作用の関係で、なにかを変えたぶんだけ、自分も変わっている。
- 田中
- なるほど。
- 糸井
- だからプロというのは、さっきの、生まれた、娶った、耕した、死んだみたいな生き方からは離れてしまうという悲しみの中にいるわけで。アマチュアには戻れない。ぼくらの「ものすごく受け手でありたい」っていう気持ちも、ある意味行き過ぎていて、もうすでにそこが歪んでいるとも言える。
- 田中
- そうですよね。
- 糸井
-
どうしてもどこか歪んでしまうのだとしたら、じゃあ、どの部分で歪んでないものを維持していこうか、というところを考えることになる。
‥‥あの、うち、夫婦ともアマチュアなんですよ。ぼくの場合はそれで保ってる気がする。
- 田中
- ええ? 糸井さんの奥様は、ぼくなんかから見ると女優さんとしてプロ中のプロのような気がするんですけど。
- 糸井
- 違うんです。仕事中は「プロになるスイッチ」を入れて、その仕事が終わったら、アマチュアに戻るというタイプの人なんです。でも、スイッチを切り替えて、プロとアマチュアの感覚を両方を持つってことはなかなかしんどいんですよね。だから、アマチュアは体力がいるものなんです。
- 田中
- そうですよね。
- 糸井
- かみさんは、高い所が本当は苦手なんですけど、「仕事なら高い所でもやる?」って訊くと、「やる」って。
- 田中
- やるって、おっしゃるんですね(笑)。
- 糸井
- そう。もう間髪入れずに、「やる」。それが、仕事じゃない時には絶対しないっていうのと両立しているんですよ。
- 田中
- ははあ。
- 糸井
- いわゆる「プロ」になっちゃうと、「いまこれをやったら、プロだから次はこう」みたいなことを考えてしまうかもしれないけど、「アマチュア」はそういうものを飛び越える。「プロ」ということについては肯定的にも否定的にもいろいろな言い方ができるけど、‥‥いまのぼくは、「ただ、なんでもない人として生まれて死んだ」っていうのが人間として一番尊いんじゃないかという価値観が、強くなってきています。
- 田中
- なるほど。
- 糸井
- それで、田中さんはいまそのあたりをすごく考える時期で、人からも訊かれるでしょう? いわば、社会の中でどういう「機能」になっていくんだ、というようなことを。
- 田中
- ほんとうに、そうですね。いままで組織に所属していたことで担保されていたものがなくなったので、みんなが質問するし、ぼくもまあ時々、どうやって生きていこう? ということを考えるし‥‥。
- 糸井
- ぼくもそこは自分で探してきたところだから、‥‥いまは、こう、自転車に乗って、ランニングしてる人の横を走ってるみたいな、そんな感じで田中さんを見ていますよ。
- 田中
- ははは。伴走してる人。
- 糸井
- ときどき、「で、どうなの?」って(笑)。
- 田中
- 糸井さんが40代で広告の仕事に一区切りつけようと思った時、やっぱりそういうことに直面されましたか?
- 糸井
- それは、もう。いろいろ。「大冒険」です(笑)。でも、平気だったんですよ。その平気だった理由のひとつは、じぶんよりもっと「アマチュア」なままのかみさんがいてくれたことが大きいんじゃないかな。
(つづきます)