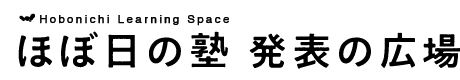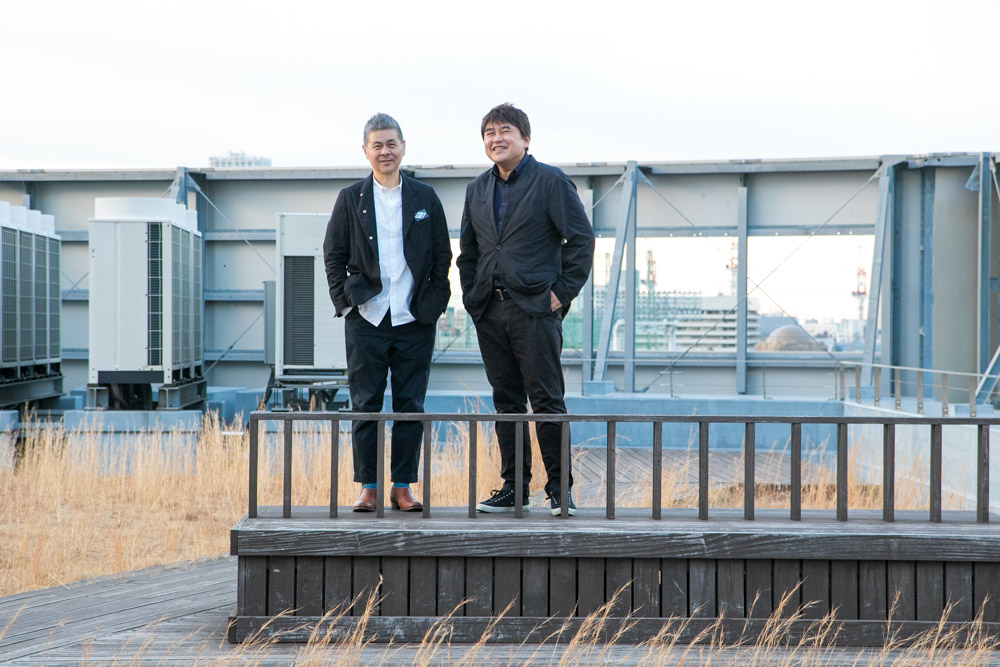- 糸井
-
僕ね、嫌いなんですよ、
ものを書くのが。
- 田中
- わかります。
- 糸井
- 前からそう言ってますけど(笑)。
- 田中
- 僕もすっごい嫌(笑)。
- 糸井
-
でも「自分ってないの?」という問いは
何十何年してきたと思うんですよ。
- 田中
- はい。
- 糸井
-
そこを探しているから、
日々生きてるわけでね。
自分への宿題にしているんですよ。
いずれわかったら、
またその話をします(笑)。
雑誌の連載ではできないけれど、
インターネットだから
いずれわかった時に
わかったように書けるんですよね。
- 田中
-
とりあえずその日は、
「これがいいなぁ」ということだけ
伝えることができますよね。
- 糸井
-
そうです。
やりかけなんですよ、
全部がね。
- 田中
- はい。
- 糸井
-
はぁ…。
このことをね、言いたかったんですよ、
僕、ずっとたぶん。
自分がやっていることの癖だとか形式だとかっていうのが、
まぁ飽きるっていうのもあるし、
なかなかいいから応用しようっていうのもあるし、
そこをずっと探しているんだと思うんですね。
田中さんも付けてしまった癖が20何年分あって
自分の名前で出していく
という立場になると、
変わりますよね。
- 田中
-
そうなんです。
これが難しい。
今、青年として、
「青年失業家」として(笑)、
会社でコピーライターをやっているついでに
何かを書いてる人では
なくなりつつあるので、
じゃあ、どうしたらいいのかということに、
すごい岐路に立っているんですね、今。
- 糸井
-
書いたりすることで
食っていけるようにするのが、
いわゆる「プロ」の発想。
そして食うことと関わりなく
自由であるから書ける。
そっちを目指す方向と、
2種類分かれますよね。

- 田中
- そうですね。
- 糸井
-
僕もそれについては
ずっと考えてきたんだと思うんですね。
僕はアマチュアなんですよ。
つまり、書いて食おうと思った時に、
自分がいる立場がつまんなくなる気がしたんで、
いつまで経っても
旦那芸でありたいというか…。
「お前、それはずるいよ」
という場所にいないと、
いい「読み手の書き手」になれない
と思ったんで、
僕はそっちを選んだんですね。
で、田中さんはまだ答えはないですよね。
- 田中
-
そうなんです。
僕の「糸井重里論」っていうのは、
好きに旦那芸として書くために
組織を作り、
みんなが食べられる組織を回していき、
物販もし、その立場を作るという壮大な…。
自分のクライアントは「自分」という立場を、
作り切ったということですよね。

- 糸井
-
そうですね…。
僕が目指しているのは、
「俺はキャッチャーだから、
その場所で自由にみんな遊べ」という
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』で。
- 田中
- 見張り塔からなんですね。
- 糸井
-
そうなんです。
その場を育てたり、譲ったり、
そこで商売する人に屋台を貸したり
みたいなことが僕の仕事で、
その延長線上に何があるかと言うと、
僕は書かなくていいんですね。
本職は「管理人」だと思うんですよ。
- 田中
- 管理人(笑)。
- 糸井
-
田中さんもその素質もあると思うんですよ。
僕はやりたいことと
やりたくないことを峻別して、
燃えるゴミと燃えないゴミみたいに(笑)。
やりたくないことをどうやってやらないか
ということで生きてきた人間で、
「やりたいことだなぁ」とか、
「やってもいいなぁ」と思うことだけを選んできたら、
こうなったんですよね。
超アマチュアっていうので一生が終われば、
僕はもう満足なんですよ(笑)。
- 田中
-
その軽ろみをね、どう維持するかという、
糸井さんはずっとその戦いだった
と思うんですよね。
- 糸井
-
そうですね。
同時にその軽さは
コンプレックスでもあって、
僕は「『逃げちゃいけない』と思って
勝負してる人たちとは
違う生き方をしてるな」って。
- 田中
- わかる、メッチャわかる(笑)。
- 糸井
-
(笑)
つまり僕は「受け手」として
書いてきた人間なんで、
「どうだ!」と言って人を斬っても
生き返って斬りつけてくる
かもしれないから、
もう1回刃を両手で持って
突き立てて、
心臓の所にとどめを刺して、
まだ心配だから踏みつけて、
「死んだかな」と確かめて、
心臓をえぐり出して、
ハァハァ言いながら「勝った」
と言うような人たちと
同じことをしてないんで。
生き返ってきたら
「そいつ偉いな」と思う
ところがあって(笑)。
- 田中
-
そうですね。
僕もものをちょっとでも書くようになって
たった2年ですけど、
書くことの落とし穴はすでに感じていて…。
つまり、「僕はこう考える」ということを重ねて
毎日毎日書いていくうちに、
やっぱりだんだん独善的になっていく。

- 糸井
- なっていきますね。
- 田中
-
そしてなった果ては、
人間は九割くらいは右か左に
寄ってしまうんですよね。
- 糸井
- うんうん。
- 田中
-
どんなにフレッシュな書き手が現れて、
すごい真ん中あたりで
心が揺れているのを、
みんな揺れてますから、
うまいことキャッチして
書いてくれたなっていう人も、
10年くらい放っておくと、
どっちか右か左に振り切ってる
ことがいっぱいあって。
- 糸井
-
世界像を安定させたくなるんだ
と思うんですよね。
- 田中
- はいはい。
- 糸井
-
世界像を安定させると
やっぱり、うーん…
夜中に手を動かしている時の「全能感」が、
起きてご飯食べている時まで
追いかけてくるんですね、たぶん。
- 田中
- なるほど。
- 糸井
-
僕はそこから逃げたいと思う。
…うーん…。
「生まれた」「めとった」「耕した」「死んだ」という、
4つくらいしか思い出がないというのは、
みんな悲しいことだと言うかもしれないけど、
僕は一番高貴な生き方だと思うんで。
- 田中
- なるほど。
- 糸井
-
そこからずれる分だけ歪んでいる。
なんか世界像を人にこう、
押し付けられるような
偉い人になっちゃうというのは、
拍手する時はいっぱいあるんだけど、
読み手として拍手はするんだけど、
人としてはつまんないかなっていうのが。
- 田中
-
書く行為自体が、
はみ出したり、怒ってたり、
ひがんでたりするということを
忘れる人が危ないですよね。
- 糸井
-
それ、書き手として生きてないのに、
そういうことを考えてる
「読み手」ですよね。
- 田中
-
そう、そう、そう(笑)
そうなんです。
- 糸井
- ややこしいよねぇ。

- 田中
-
僕はさっき言ったような、
世の中をひがむとか、
言いたいことがはみ出すとか、
政治的主張はないんですよ、
「読み手」だから。
常に「あ、これいいですね」
「あ、これ木ですか?」
「あぁ、木っちゅうのはですね」という、
ここから話がしたいんですよ、いつも。
- 一同
- (笑)
- 糸井
- お話がしたいんですね(笑)。
- 田中
- そうなんです。
- 糸井
-
うーん…
そのあたりはずっと考えてることですよね(笑)。
吉本ばななさんに、
「糸井さんは、本当にいろんなものから
吹っ切れているようだけど、
やっぱりちょっと作家を偉いと思ってる」。
- 田中
- って言うんだ、吉本さんは(笑)。
- 糸井
-
たぶん。
「で、それはすごく惜しいことだと思う」と
たしかポロッと言ったんだよね。
お父さんの吉本隆明さんも言ってたんですよ。
要するに、「思う必要がないのに」っていう…。
- 田中
- 本当そう思います、僕も。
- 糸井
-
僕もそう思うんですよ。
でも、しょうがないなぁ、
拍手に力がこもっちゃうなぁみたいな。
絵描きにも拍手するし、
映画作ってる人も全部するんだけど、
やっぱり表現者に対する拍手が
ちょっとでかすぎるかなみたいな。
- 田中
-
はぁ、はぁ。
なるほど。
- 糸井
-
もっとしょうもないものへの拍手
というのが同じ分量で
できてるはずなのに、
人に伝わるのはね、
やっぱり表現者に対する拍手だから、
そこはしょうがないのかなぁ。
そこで「自分の仕事やろう」って思うんですよね。
- 田中
-
だから僕のような、
しょうもない戯言言ってる人間にこう、
夜中に絡むわけですか(笑)。
- 糸井
- (笑)
- 田中
-
「もう3時半だけど、
またなんか言ってきたよ」って(笑)。
- 糸井
-
ひと寝入りしてから、
まだ絡んでたりするからね。
なんだろう…。
「これいいなぁ業」ですよね。
たぶん泰延さんも本当はそれですよね。
- 田中
- 「これいいなぁ」ですよ、本当に。
- 糸井
- ですよねぇ。
- 田中
-
永遠に馬鹿馬鹿しいことをやる
というのは、
一種の体力ですよね。
- 糸井
- 体力ですね。
- 田中
-
それをやらないところに陥った瞬間、
偉そうな人にやっぱりなるんで。
- 糸井
-
なるんですよねぇ。
で、「グルッと回って結論は?」ってなると、
「ご近所の人気者」っていうところへ行くんだよ。
- 田中
-
本当にそこですね(笑)。
「ご近所の人気者」。
(つづきます)