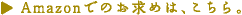- ──
- アクショーノフ先生が亡くなって、
このクリニックも
閉鎖することが、正式に決定したんですね。 - 山本
-
みんなで話し合いをして、
最終的には
ドクターの息子さんが結論を出したんだけど、
彼だって、つらかったと思いますよ。もう、60年ちかく続いてきたクリニックを
閉めるんだから。 - ──
- 息子さんは、お医者さんでは‥‥。
- 山本
-
ないんです。
代役を立てて続ける選択肢もあるだろうって
言うかもしれないけど、無理です。
みんな、ドクター・アクショーノフのことを
慕って来ていたわけだし、
あんな人は、もう、どこにもいないしね。 - ──
- 半世紀以上、ここで診察してきたってことは
親子でお世話になってた、なんて人も? - 山本
- 親子どころか、長いと4世代ぐらい診てた。
- ──
- すごい。
- 山本
- だから、ふつう医者は
患者さんのお葬式には行かないと思うんだけど、
ドクターの場合は患者っていうより、
「友だち」とか「親戚」に近いレベルに
なっちゃってる人もいたので。 - ──
- お葬式に出たりとかも?
- 山本
- しましたよ。私とふたりでね。
- ──
- 先生がいなくなって、ルミさんは今、
どういう光景を、思い出したりしますか? - 山本
-
そうですね‥‥ああ、そうそう。
ドクターって、
お酒やタバコは知らなかったんだけど、
とにかく甘いものが好きだったの。

- ──
- たとえば、どんな?
- 山本
- 砂糖のたっぷり入ったロシアのお菓子、
はちみつ、ケーキ、チョコレート‥‥。 - ──
- おお、筋金入りの甘党ですね。
- 山本
- そういう甘ぁい食べ物を
いつも自分の机の引き出しに隠してた。 - ──
- 隠してた? どうして?
- 山本
-
糖尿病で、注射まで打ってたから。
私がそばにいて目を光らせているときは、
食べられないんです。だから、
私が患者の血圧を測ってるときとかにね、
一瞬の隙をついて
こっそりパクッとか食べてんの(笑)。 - ──
- 子どもみたい‥‥(笑)。
- 山本
- そんな姿を、今ちょっと思い出しました。
- ──
- で、患者さんが部屋から出て行ったあと、
ルミさんに怒られる、
みたいなパターンですかね?(笑) - 山本
- そうそう(笑)。

- ──
- 最後の日々は、どんなふうでしたか。
- 山本
-
古い患者さんの中には
とくに、どこかが悪いわけじゃないけど、
ドクターに会いたかったのか、
お薬を取りに来たよーって言って来たり。するとドクターは「大丈夫?」とか言ってさ、
自分はベッドに寝たままで、
「ここは六本木だから寝ててもお金が稼げる」
とかって言っちゃってさ、
そのままの状態で患者と話して、握手して、
「じゃあ、
ルミちゃんから薬もらってね」って。 - ──
- それって‥‥すでに「診察」というか。
でも、それでも来るんですもんね、みなさん。 - 山本
-
うん、来たかったんでしょうね。
ただ、3年くらい前かな、
ドクター、軽い脳梗塞やってるんですけど
そのときから
患者には迷惑をかけられないって、
新規の患者さんを取ってなかったんです。だから、ここに来る人の数自体は
最後はもう、かなり少なかったんですけど。 - ──
- そうでしたか。
- 山本
-
そう‥‥最後まで、ドクターは最後の最後まで、
本当に一生懸命「医者」をやってました。ここ2~3年は、医療的なレベルで考えると、
もうこれ以上、
続けてはいけないって、ずっと思ってたけど。 - ──
- と言うと?
- 山本
- だって毎朝、自宅から車で来て、
自力では入口の階段を上がれないドクターを
みんなでこの部屋へ運んできて、
この椅子に座らせて、
患者の言ってることがよく聞こえないから
私が傍らに立って
「かくかくしかじか言ってますよ」って。 - ──
- そうでしたか。
- 山本
- それでもさ、本人やめるとも言わないし。
まわりも、やめろなんて言わないし。 - ──
- 患者さんだって、来るし。
- 山本
-
クリニック全体で、
ドクターは最後まで医者をやめないだろうから、
みんなでサポートしていこう、みたいな
「無言の決断」があったんです。だから毎朝、
みんなで、ドクターを抱えあげてでも
診察室に連れていったんです。

- ──
- ええ。
- 山本
-
それなのに、そんな状態なのに、
成田空港への往診を頼まれたら「行こう」って。
それも、一度じゃなく何度も行ったんです。ドクターにとっては
「仕事」って「つらくてキツいもの」じゃなく、
ピクニックみたいな感覚なんですよ。「ルミちゃんおやつ持った?」とかって言って。
- ──
- 肉体的には「つらくてキツい」んでしょうけど、
それ以上に「楽しいもの」だったんですね。 - 山本
-
ほら、人間、病気なんかに罹ったら、
ちょっとしたことで落ち込んだりするじゃない。私なんかもね、この間さ、
眼科で「老眼プラス1ですね」とか言われて、
「ついに来たか!」と。そういう、ちいさな落ち込みってありますよね。
- ──
- はい。
- 山本
-
最後のほうのドクターは、
どんどん、
いろんなことができなくなっていったけど、
でも、そんなことを
いちいち悔やんでなんかいなかった。僕にはできないって諦めるんじゃなくて
明るく、なんとかして、
「できるほう」へ持って行こうとしてた。

- ──
- そうですか。
- 山本
-
ドクターのそういうところは、
私もこれから一生、大事にしていきたいなと
思っています。諦めたときが、やめるとき。
諦めたときが、もう終わりのとき‥‥だから。 - ──
- 明るいっていうのは、まわりを助けますよね。
- 山本
-
そう! 亡くなる一週間前くらいなんかでも
「じゃあねドクター、チュッ♡」
とかってやると、
ドクターも「チュッ♡」って返してくれたの。あれで、こっちが救われたとこありますから。
- ──
- お会いしてみたかったです。
- 山本
-
それはね、ほんとに。
私たちとしては
100歳くらいまでがんばってほしかったけど。 - ──
- ルミさんは、アクショーノフ先生から
どういうことを学んだと思いますか? - 山本
- 「仕事って、こんなに楽しいものなんだ」
「はたらくって、
こんなにも素晴らしいことなんだ」
ってことかな。 - ──
- なるほど。
- 山本
- 90歳まで医者をやって、
もう最後の最後まで医者をやりきった人が、
「次、生まれ変わっても、
また医者になりたい」って言ってた(笑)。 - ──
- ルミさんも、楽しかったでしょうね。
アクショーノフ先生と一緒で。 - 山本
-
人って、人がよろこぶ顔を見たいんですよね。
それは、医療の場面でもおんなじことで、
「人のよろこぶ顔」を
看護師という仕事を通じて見ることができて、
そして、
それがこんなにも自分のよろこびにつながる。ドクターには
「仕事って、楽しくできるんだ」ってことを、
教えてもらった気がします。

- ──
-
ルミさん、ここへ来た当初は
英語もままならなかったと、聞きました。努力もご苦労も、あったと思うんですが。
- 山本
-
というより、そういう「わかんない人」を
よく採用したなって思いますよ。私、昔、新しいスタッフが来たときにね、
「あの人は
あれもできない、これもできない」って
思っちゃった時期があったんです。 - ──
- ええ。
- 山本
- でも、よくよく考えたら
英語すら、ろくにしゃべれなかった私を
自分の母校の
「慈恵医大」から来たってだけで採用して、
何にもできなくたって我慢しながら
のろのろ成長していく私を
見守ってくれてたんですよね、ドクターは。 - ──
- はい。
- 山本
-
当時、私を採用して
失敗だったって思わなかったのかなあって、
今になって。でも、「応えたい」と思ったんです、私も。
- ──
- ずっとお話をうかがってみて、
ルミさんだからつとまった「21年」でも
あるんだろうなと思いました。 - 山本
-
ドクターと出会えたことは、
私の人生のいちばんの宝物だと思ってます。
一生、忘れない。だって、凸凹コンビだったんですよ(笑)。
- ──
- 凸と凹の名コンビ、ですよね。
- 山本
- そうそう。ボケとツッコミの。
- ──
- その場合、当然「ツッコミの方」ですよね?
- 山本
- え、私? もちろんですよ!
ボケはとうぜんドクター、ですから(笑)。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アクショーノフ先生亡きあと、
日本で暮らす数多くの外国人が足を運んだ
インターナショナル・クリニックは
静かに、閉院しました。
9月、ある秋晴れの日曜日、
閉じたあとのクリニックを訪れると
壁にびっしり貼られた子どもたちの写真を
Tシャツ姿のルミさんが、
ご友人といっしょに、剥がしていました。
「この子は、注射が大きらいでね‥‥」と
ルミさんは、おどろくほど、
ひとりひとりの子のことを覚えていました。
ダンボール何箱にもなった写真は、
ずっとたいせつに、仕舞っておくそうです。
 遺影が飾られた、かつての待合室。
遺影が飾られた、かつての待合室。
 この部屋に敷かれているネパール製の絨毯は、
この部屋に敷かれているネパール製の絨毯は、
事業に失敗し、
ずっと治療代も払えなかった女性から
アクショーノフ先生が
お金の足しにと、買い取ったものだそうです。
なお、在りし日の
インターナショナル・クリニックのようすは
ルミさんが原案のコミックエッセイ
『患者さまは外国人』で読むことができます。
アクショーノフ先生の生い立ちや人柄、
ルミさんのもうひとつの顔である
「エスコート・ナース」という仕事について、
宗教や文化の違いからくる
日本人には信じられないような仰天話‥‥など
じつに、おもしろいです。
そしてなにより、アクショーノフ先生と
ルミさんはじめスタッフの
楽しく、賑やかだった日々が垣間見れるようで
いま読むと、ちょっとじんわりします。