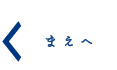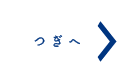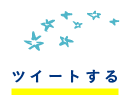ムーミンたちの住んでいる谷間は、
とてもきれいなところです。
そこには、小さな生きものたちが
たくさんしあわせに暮らしていて、
大きな木が青々としげっていました。
野原のまん中を川が流れ、
青いムーミンやしきのそばで、ぐるっとカーブしてから、
ほかの小さな生きものたちのいる土地へ、
流れていくのでした。
みんなは、この川がどこから流れてくるのだろうかと、
ふしぎに思っていました。
とてもきれいなところです。
そこには、小さな生きものたちが
たくさんしあわせに暮らしていて、
大きな木が青々としげっていました。
野原のまん中を川が流れ、
青いムーミンやしきのそばで、ぐるっとカーブしてから、
ほかの小さな生きものたちのいる土地へ、
流れていくのでした。
みんなは、この川がどこから流れてくるのだろうかと、
ふしぎに思っていました。
『ムーミン谷の彗星』
(トーベ・ヤンソン著 下村隆一訳)より
(トーベ・ヤンソン著 下村隆一訳)より

- 重松
- 『トーベ・ヤンソン ──仕事、愛、ムーミン』
でいくとちょうど真ん中あたりかな、
どんどんムーミンの存在が大きくなっていきますよね。
なにしろ、遠い極東の国で、
名前も変わり、色もついちゃって(笑)。
そうなると、当然、トーベの暮らしも変わっていきます。
「時間がない」っていうことと、
「自分はあくまでも芸術家である」
ということのジレンマを、
彼女は相当持っていたとわかる。
だから、あまり嬉しそうじゃないというか、
苦しそうですよね。
- 森下
- そうなんですよ。苦しそう。
自分はひたすらまっすぐに作っていきたかったのに、
と思いながら、
別のところからいろんな声が掛かってきて。
- 重松
- フィンランド的なサクセスストーリーというのかな、
アメリカンドリームみたいな、
フィンランディアドリームというかさ、
スオミドリームってのは、
どんなものなんだろう。
フィンランドの人たちにとって
いちばん幸せなことって、なんだろう。

- 森下
- わたし、トーベの弟さん
 ふたりと
ふたりと
一緒に島でお話しさせていただいたことがあったんですね。
そのときに弟さんふたりがはっきりわたしに言ったのは、
有名になってトーベが幸せだったことはひとつもないって。
有名になることは結局、幸せの条件ではないんですよね。
それで、何が幸せなのか。
周りのフィンランドの人たちを見ていると、
十分と思う額のお金を手にしたら、
それ以上を無理して稼ごうとしないんです。
彼らの小さい頃からの生き方は何かというと、
「自分で」という──、
重松さん、実は一緒に森を歩かれたときに
おっしゃってたんですけども、
森ってね、受け身ではなくて、
自分で見つけていくもの。
「だから、入る人によって違う。
見ているものが全然違うよね」
って重松さんおっしゃっていました。
それってわたしが20年ぐらいかけて
気づいたことなんですけど(笑)、
重松さん、一瞬でおわかりになっていた。
プロッレこと写真家のペール・ウロフ・ヤンソンと、
ラッセこと漫画家・小説家のラルス・ヤンソン。
--------
わたしは1997年の夏にラッセの暮らすブレッドシャール島を、プロッレと訪ねました。
ここはかつてトーベが暮らしていた島で、
小屋はトーベがちょうど50年前に
設計図を引かずに建てたものでした。
トーベが建てた小屋で弟ふたりが語ってくれた
姉トーベのことを伺ったんです。(森下)
- 重松
- そうだったかな(笑)。
- 森下
- 小さい頃から自分でものを見て、
自分で楽しいと思うものをずっと見つけながら
生きてきてる人たちなので、年と共に
どんどんどんどんそれが強くなっていくわけですよ。
「わたしの好きなもの」とか、
「わたしがこれを幸せだと思うこと」っていうものが
とてもはっきりしていて。

- 重松
- ぼくね、「ほぼ日」の
「フィンランドのおじさん」を見ていて、
趣味で線路と鉄道を買い取ったおじさんがいたじゃない。
- 森下
- あのおじさん!
キヒニオのエルッキさんですね。
- 重松
- あれって、線路端でマシュマロを焼くとかさ、
ウインナーを焼く程度のものなんだよね。
ビールも地ビールだよ。
で、多分、冬は寒いよ。
寒いんだけど、都会のヘルシンキに対抗して
自然暮らし、田舎暮らしをっていうんじゃなくて、
もう「まんま、それ」なんだもの(笑)。
こっちは仕事してるのに
あんなの平日の昼の11時から更新するんじゃねえよ!
って思ったりするくらいなんだよ(笑)。
日本というか中国でいう、
「足るを知る」っていう言葉。
あれをまさに実践しているという意識すらなく、
やっちゃってるんだろうな(笑)。
- 森下
- そうなんです、そうなんです。
みんなそうやりたいからといって生きてる。
これもやっぱり重松さんと一緒に
ラップランドに行ったときに、
タクシーの運転手さんが、
自宅にわたしたちを呼んでくれたんですけども、
そのときに見せたい「俺の楽しいもの」が
薪割りだったりとかして(笑)。
- 重松
- そう。そうなんだよ!
- 森下
- もうひたすら薪を割って
わたしたちに見せてくれるんですよ(笑)。
トーベも本当は、森が大好きで、
本当は住む島ももっと森がたくさんのところが
よかったと言ってるらしいんですけども、
そういうところにいる時間をたくさん持って、
孤独と自由を。
- 重松
- 『トーベ・ヤンソン』に載っている写真のなかで
ぼくのいちばん好きなのは、
戦争が終わったあとに、
トーベが島を買ったのかな、
自分の旗を、小屋のところに立てるんだ。
そこにはムーミンの絵が描いてあって。
その写真。カッコよかった。
島を持って、そこに自分の旗を掲げるって
最高にカッコいいことなんだろうな。
- 森下
- そうなんです。
- 重松
- でもさ、逆にその最高にカッコいい、
独立かもしれないし、自立かもしれないし、
まさに自由と孤独の完成形である離れ小島に、
逆にぼくたちが憧れちゃって、訪ねて行っちゃう(笑)。
孤独の完成形を壊してしまって、
トーベを苦しめちゃうこともあったんじゃないかな。

- 森下
- こういうムーミンのことで
仕事をさせていただくようになって、
トーベ・ヤンソンに手紙を書いた人たちというのに
何人かお目にかかることができたんですよ。
そしてトーベからお返事をもらったりしてるわけです。
そうするとね、みんな少なからず、
「わたしはトーベを苦しめたのかもしれない」
っていうちょっとした傷を負いながら、
みんなトーベのことを好きでい続ける。
やっぱりそうなんでしょうね。
- 重松
- 晩年の往復書簡に、架空の人として
“日本人のアツミタミコ”が出てくるでしょう 。
。
当時、日本からファンレターがたくさん来たんだろうね。
でも、最後、ここの境地に行かれちゃうと、
トーベもかわいそうだし、
好きだったみんなもかわいそうだなと。
1998年に出版された短編集『メッセージ』の中の
『往復書簡』に登場する日本人のファンの名前。
『往復書簡』はタミコから作家への8通の手紙というかたちで
構成された小説で、作家に対する憧憬がつのるにつれ、
作家はその思いを受け止めきれず後ずさりしてゆく。
- 森下
- そうなんですよね。
- 重松
- 『トーベ・ヤンソン』の副題もそうだよね。「仕事、愛、」。
「ムーミン」とついているのは日本語版だけだけれど。
ぼくね、さすがだなと思ったのはね、
戦争が終わったあとに、
「わたしが今とても欲しいものは小屋。
それに仕事、家、環境、愛する人との暮らし」。
「愛と仕事の融合にわたしは強く惹かれる」。
ところが、だんだん売れてきて、人気者になり、
だんだん悲しくなっていくんだ。
1955年には、
「一体いつから仕事は
わたしの敵になってしまったのだろう」って。
仕事って──ワーク、ジョブ、
いろんな言い方あるかもしれないんだけど、
フィンランドの人たちにとって「働く」って何なんだろう。
- 森下
- わたしは、トーベ・ヤンソンの「仕事」という言葉は
ふたつの意味を持っていると思います。
ひとつは生涯かけてずっと続ける作業。
芸術がそう。
トーベの両親も芸術は仕事であると考えていました。
つまり創作であり、じっさいトーベは生涯続けました。
でも、もうひとつはやっぱり、
どこか義務感のようなものがある
仕事がありますね。
ヴォッコ・エスコリン・ヌルメスニエミという
マリメッコで50年代から活躍した
デザイナーがいるんですけども、
彼女、現役で今でもやってらしてて、
その彼女が、フィンランドで初めて
デザイン賞を設けたときに、
彼女のところに打診があったんだそうです。
「こういう賞ができたんですけど、
あなたは誰を選びますか」って言われたんですって。
そのとき、いちばん最初に頭に浮かんだのが
トーベ・ヤンソンだった。
「彼女は生き方そのものがデザイナーだと思ったんです」
と。多分、フィンランド人のモノを作る人たちが
憧れる生き方というのは、
トーベ・ヤンソンのように、
本当に最後の死の直前まで筆を持ち続ける人、
なんだと思うんですよね。
そういう意味の「働く」というのはあると思うんです。
でも、一方で、社会で働く、
ちょっと義務があるところで言うと、
やっぱり人間は1年のうちに1か月長く休まないと
人間らしい暮らしはできないし、
効率のよい仕事をすることはできないんだよ、
と言っている部分というのもあって。
トーベの中ではそのふたつの「仕事」が
せめぎ合っていたような気がしましたね。

- 重松
- もうひとつね、家族を持つというのも、
本来であれば大きな仕事になりうるはずだった。
けれども結局、彼女は男性とは結婚しなかったし、
子どもも産まなかった。
マイノリティで言っちゃえばね、
スウェーデン語系とか女性であること以上に、
同性愛であるってことが少数派だったわけですよね。
この本でも、本人も少数派だったと言ってるんだけど、
北欧ってそういう面がすごく進んでる、
理解があると思いがちなんだけれど、
同性愛に対してはどうなんですか。
- 森下
- そうでもなかったんです。
わたしがフィンランドに行ったのは1994年ですが、
そのときから、けっこうゲイの友達が多かったんです。
けれども彼らが口揃えて言っていたのは、
とにかく家が借りられないんだと。
男同士で住むってわかると、
「おまえらはゲイなのか?」ってなったら、
もう大家さんが貸し渋るという。
1971年までは同性愛は犯罪とされていましたし。
- 重松
- それは何? 宗教的な、
キリスト教的にまずいってことなの?
それとも社会的?
- 森下
- 社会的に。
北欧というとフリーセックスのイメージが
すごく強いんですけど‥‥実はフィンランドって、
そこをちょっとちょっといつも避けてたんですって。
ただ、フィンランドの人って
極端にパーンと振り切れるので、
今はものすごい性に対してオープンです。
性の祭典みたいな「セキシビジョン」というのがあって、
おばちゃんたちが行って、男性器の飴ちゃんとか
ペロペロ舐めながら、「ああ、次何見に行く?」みたいな。
- 重松
- だってほら、夏至祭で見た
野外ロックフェスティバルのベーシストが、
スッポンポンだったよ。
脱いで見せるほどのモノじゃないなって思ったけど(笑)。
- 森下
- そうですよね(笑)。
94年といえば、当時、
ムーミンって言うとみんなが笑ったんですよ。
ちょっとバカにしたふうに。
「おまえ、日本からわざわざ来て、ムーミンかよ」
みたいな。

- 重松
- おお。
- 森下
- でも、いまやトーベ・ヤンソンは
2ユーロコインになったし、
国立美術館で特別展が開かれるまでになった。
「ついにやった」。
ここまで来たんだと思ったら、
わたし、けっこう悔し涙と嬉し涙で
この1年よく泣いてました(笑)。
パートナーのトゥーリッキ・ピエティラに
脚光があたりはじめたのもつい最近のことですし。
- 重松
- そうか、フィンランドでも
「再発見」されたんだね。
- 森下
- そうなんです、そうなんです。
いろんなところで何度も何度も泣きました。
ヤンソン家の人たちとも何度となく泣きながら、
「やっとここまで来たね」って。
彼らも嬉しいから、美術館に見に来てるんですよ。
わたしも十何回行ってるんですが、
行くたびに会うんですよね(笑)。

- 重松
- 郵便局のムーミンの切手なんかも最近の話なの?
- 森下
- 1990年代に入って、やっとです。
平成のアニメーションができてから。
ムーミンのブームは何度かあったらしいんですけど、
こんなふうにみんなが知って、
みんながトーベ・ヤンソンを尊敬してる、
みたいな感じになったのは、
本当につい最近と言ってもいいかもしれません。
- 重松
- 考えてみれば、
アラビアとムーミンがくっつくなんて、
すごいコンビなわけだよね。
- 森下
- そうですよね。これもコレクションとして
人が注目するようになったのは、
2006年になってからですって 。
。
それまでは誰もそんなに見向きもしてなかったもので。

フィンランドで放映される前だったんです。
でもそのときは話題になることはあまりなくって。
2006年からです、えらいことになったのは。(森下)
- 重松
- いやー、それにしても、
森下さんの訳した『トーベ・ヤンソン』で、
よりいっそうムーミンの存在が深みを持った気がする。
面白かった。本当に面白かった。
- 森下
- よかったです!


「あんた、ほんとにダンスがじょうずね。
これ、なんというダンスなの?」
──スノークのおじょうさん
「ぼくのダンスさ。ぼく、いま発明したんだ」
──ムーミントロール
これ、なんというダンスなの?」
──スノークのおじょうさん
「ぼくのダンスさ。ぼく、いま発明したんだ」
──ムーミントロール
『ムーミン谷の彗星』
(トーベ・ヤンソン著 下村隆一訳)より
(トーベ・ヤンソン著 下村隆一訳)より

(つづきます)
2015-03-12-THU