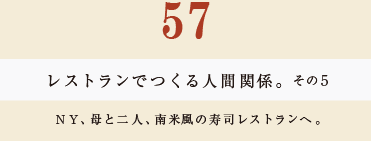お店に入ると、入り口のすぐ横に大きなバーがあって
おしゃれな人がエントランスホール周りにまで溢れてる。
その人ごみの向こう側にレストランがあるのだけれど、
その人の壁がササッと割れて、
ボクらは自然と奥へ奥へと、いざなわれていく。
目立つだけでなく、この店に
「ウェルカムされている」装い。
レストランとは、
「来てほしいお客様に対してやさしく明るい」
空間なのです。
とりあえず、見た目はウェルカムされたボクたち。
コンシエルジュ氏が言ってた通り、
大きな長いテーブルの真ん中の席に案内される。
両側にはスッカリくつろいで食事をたのしみはじめてる、
陽気なグループ客が一組づつ。
テーブル席は見事に満席。
いろんな人が集まっていて、けれどみんなお洒落で
しかもニコニコしながらお酒を飲んで食事をたのしむ。
その食事。
売り物は寿司、というコトではあるけれど
にぎり寿司のようなモノが出ているテーブルは
ひとつとしてなく、ほとんどがロール寿司。
それも海苔でまかれず裸のまんま。
ソースが上からかかったり、刻んだ野菜や
崩したトルティアチップのようなモノが散らかる
カラフルなお皿が並ぶ。
たしかに日本の頑固な寿司の職人だったら、
星一徹のごとき勢いで
お皿をヒックリ返したくなるであろう、
色とりどりの料理ばかりで、
なるほどこれが、南米風の寿司というコトなのでしょう。
マネジャーらしき人がやってきて、ボクらにたずねる。
「私たちのお店のことを、
どうやってお知りになりましたか?」って一言。
母は事情を説明します。
ホテルのコンシエルジュから
紹介された寿司屋にいったコト。
そこで不機嫌な寿司を食べて、不機嫌になったコト。
不機嫌な寿司の癖して、それは十分おいしくて、
それでますます不機嫌になってしまったコト。
なにより、私がそんなお店のコトを
好きなんじゃないかと
コンシエルジュが思ったコトを思うと
どうしようもないほど悔しくってしょうがなかったコト。
その不機嫌な寿司屋にココの話を聞いたの。
繁盛してるけど、
ニューヨークでしか通用しない店があるんだ‥‥、って。
でもそれってね、「ニューヨークにしかない、
だからニューヨークにきたら行かなきゃ損するお店」
だって、言ってるコトに他ならない。
それでワガママを言って予約をとってもらって、
それでこうしてやってきました。
来たら、なんてステキなコトでしょう。
日本でも食べるコトができないお寿司がこんなにもある。
しかもそれらがこんなにみんなに愛されている。
お寿司を生んだ日本人として、
こんなにうれしく誇らしいことってあるでしょうか?
と。
どんなレストランにおいても
「たのしんでやろう」
と思う前向きな気持ちがなくては、
たのしませてもらうコトはむつかしい。
母がマネジャーにした顛末に、
ボクらは一瞬にして
「たのしませてあげたい客」として受け入れられた。
ボクらを挟む2組の人たちからは握手とハグを求められ、
マネジャーは「当店でおすすめの寿司を
食べていただけますでしょうか?」
と張り切って、厨房の中に指示をだす。
お寿司はどれもエキゾチックな味がしました。
日本の寿司とはまるで違っていはしたけれど、
ハラペニョと一緒に食べるまぐろの甘くて鮮烈な味。
南米料理のセビーチェの
みずみずくて風味豊かなロール寿司とか、
パプリカをピュレ状にして
ハマチのタルタルをあえて軍艦巻きにしたのとか、
どれも風味豊かで食べ飽きない。
日本の寿司って、
醤油の味に甘えてしまっていたのかも‥‥、って。
そう思うほど、その寿司の味わいは多彩で鮮やか。
勧められて飲んだモヒートが、すすんですすんで、
グイグイたのしくなっていく。
ボクらがニューヨークにしかない
そうした寿司をどう感じるのかを
聞きたくてでしょう‥‥、
同じテーブルを囲む人たちばかりか、
いろんな人がやってくる。
そして、「結構、いけるよ」っていうと、
まるで自分が褒められたかのような
それはそれはうれしそうな顔をして、
自分のテーブルへ帰ってく。
街の料理をほめられるコト。
それは、そこに住んでいる人のコトも
褒めているコトになるに違いない。
|