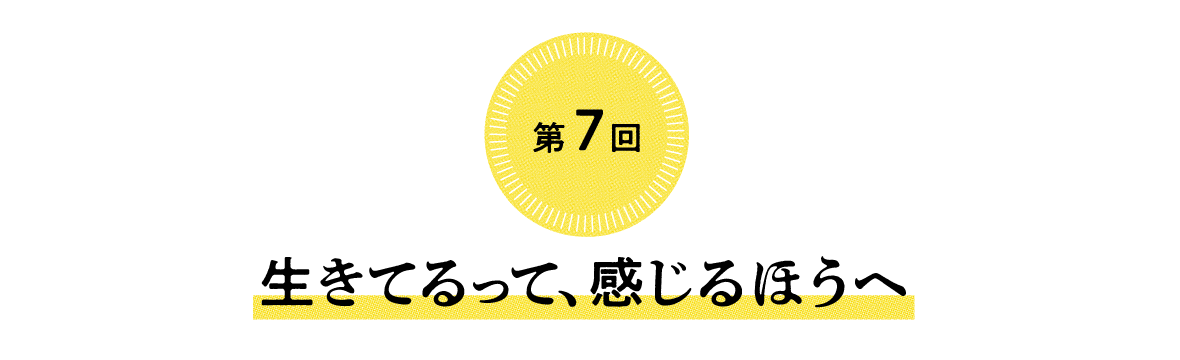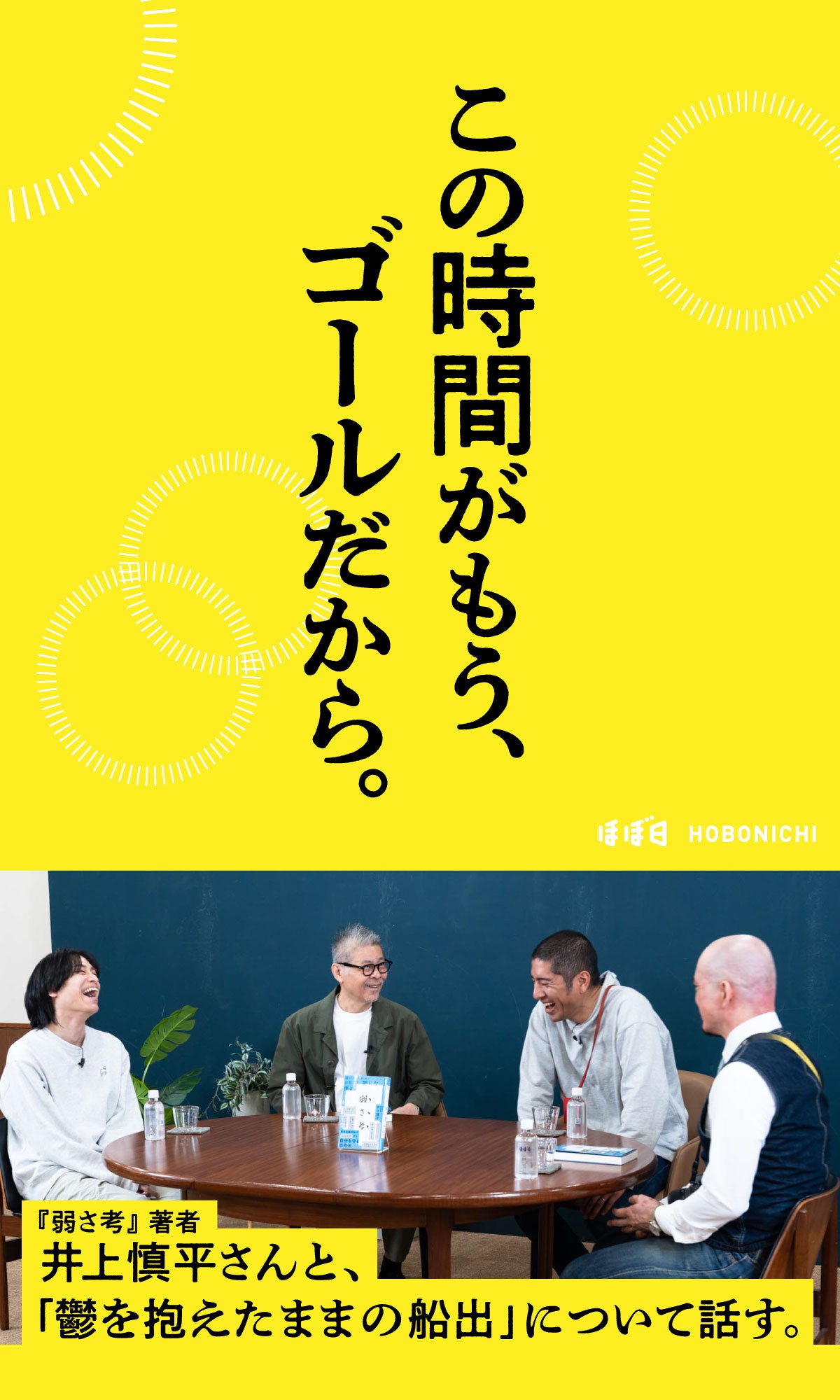
「ぼく、今日、めっちゃ幸せ。
だって、この時間がもう、ゴールだから」
対談の終わりに、井上慎平さんはそう言いました。
「NewsPicksパブリッシング」の編集長として
「強く、立派な人」であろうとするあまり、
ある日突然鬱を発症してしまった井上さん。
井上さんは、完治することのない症状を抱えながらも、
「もう一度社会に戻りたい」ともがく思いを
著書『弱さ考』にまとめました。
今回お会いすることになって、
糸井重里が決めたことはひとつだけ。
「井上さんが『ああ、居やすかった』と思える時間にする」。
全10回でお届けします。
井上慎平(いのうえ・しんぺい)
1988年生まれ。
ディスカヴァー・トゥエンティワン、
ダイヤモンド社を経て、
2019年、ソーシャル経済メディアNewsPicksにて
書籍レーベル「NewsPicksパブリッシング」を
立ち上げ創刊編集長を務めた。
代表的な担当書に中室牧子『学力の経済学』、
マシュー・サイド『失敗の科学』
(ともにディスカヴァー・トゥエンティワン)、
北野唯我『転職の思考法』(ダイヤモンド社)、
安宅和人『シン・ニホン』
(NewsPicksパブリッシング)
などがある。
2025年、
『強いビジネスパーソンを目指して
鬱になった僕の 弱さ考』(ダイヤモンド社)を出版。
株式会社問い読を共同創業。
- 井上
- ただ、まあ、逆を言えば、
起業しようというときにはまだ、儲かるかとか、目標だとか、
「未来に旗を立てそうになる自分」がいたんです(笑)。
- 糸井
- こんなになっても、まだ、旗を立てようとしていた!
- 井上
- どうしようもないやつですよね、本当。

- 糸井
- それはやっぱり、
「旗を立てることでいい点数をとってきた」
からなんでしょうね。
- サノ
- 「旗を立ててうまくいった」
という成功体験を積んでこられたという。
- 糸井
- そうそう。
ほぼ日はやっぱり、そういう体験がなかったんです。
旗を立てるってやり方でうまくいったことはなかったし、
むしろ「そういうやつらにはかなわない」
と思いながら生きてきた。
だからこそ、「ほぼ日のやり方は違うよ」
っていうふうになったんだと思っていて。 - 「旗を立てる」っていうのは、
現在地から目的地までを
「図で描く」ことじゃないですか。
そういうのは、ぼくはやっぱり不得意なんですよ。
「図で描く」んじゃなくて、
「景色で描く」みたいなことが、ぼくは好きなんです。
- 井上
- あああー。

- 糸井
- 「遠くのあそこに、島が見えるな。
でもそれ以外は、まだ何も見えない。
いまはあんまり考えようがないから、
とりあえずボートの上で、ちょっと釣りをしてみようか。
運がよければ、魚食えるし。
ああ、でも、そうだ、スコールが来たときのために、
一応水もためておこうか‥‥」
みたいに、景色を観ながら、
「さあ、どうするか」と考えている感覚なんです。
- 井上
- たしかにそれは、
「図で書く人」とは全然違う進み方になりますよね。
図だけ見てたら、
「向こうに雲が見えるから水ためよう」
とも思えないかもしれないし、
「船に穴が空いてるぞ」みたいなことも
なかなか気づけないかもしれない。 - あと、お聞きしてて思ったんですけど、
旗ってなんか、「目的地」であると同時に、
「俺はこういうことをやるんだ」って言って、
まわりから注目を集めるっていう意味の
旗もあると思うんですね。

- 糸井
- ああ、そうですね。
- 井上
- いまってやっぱり、
「お前の仕事はどう社会の役に立つんだ」みたいな、
「お前の旗はどんな旗なんだ」みたいな、
いわゆる社会的意義を
求められる部分もあるよなと思っていて。 - でも、もう、そういうことよりも、
それこそ、いまこの場でたとえるなら、
「この対談がコンテンツになって
世の中にどんな問いかけができるか」
みたいな社会的意義を考えるよりも、
「いまここにいる井上慎平、
糸井重里は、楽しくなれたのか」
っていう、そこが本当は、
めちゃくちゃ大切なんじゃないかと思うんです。
- 糸井
- ぼくも、そう思います。
- 井上
- あの、さっきちょうど、ほぼ日のオフィスに、
「今日も、きみの仕事が、世界を1ミリうれしくしたか?」
って書いてある掛け軸を見かけたんですけど、
あれもまさに「景色を楽しむ」っていうことだし。
- 糸井
- そうですね。
たとえば、サノくんはいまお子さんが生まれて、
「子どもの背丈が1ミリ伸びる」ということを
ものすごいことだと思えていると思うんだけど、
簡単に言ってしまえば、そういうことなんです。 - その1ミリに目が行ってるかどうかで、
「自分がここにいてもいい」という感覚が
すごく得られると思うんです。
その「1ミリ」が「1センチ」になったら、
もう、「おおー!」って自分に
拍手したくなるくらいすごいことで。
「俺、今日、なんか、1ミリぐらいは良くしたよ」
っていうのは、やっぱりうれしいじゃないですか。 - 「きょうはちょっと後退した」っていう日も、
もちろんある。でも、そういう日でさえも、
「目の前の1ミリ」のことを考えるっていうのはいいな、
と思って、あのことばを書いたんですよね。

- 井上
- いや、本当にそうですね。
「問い読」が社会の役に立つのかなんて
全然わかんないですけど、
1ミリでも目の前に手応えがあれば。 - こういうボートが何隻か走ったり、潰れたり、
それを見ていたべつのボートがまた走ったり、
そういうものにきっとあとから
なにか名前がつけられるだろうから、
このボート単体がどうなろうと、まずは漕ぎ出すだけっていう。
- 糸井
- その考え方はもう、まるで「生命史」みたいだね。
生命の歴史みたいですよ。
いつかは自分も
「そこらへんに転がる貝殻のひとつ」になっちゃうことを
わかりながら生きている貝‥‥みたいな感じでさ。
それは、ちょっと、カッコいいなあ。
- 井上
- カッコいいのかな、それは(笑)。
でも、まあ、いっぱい本を読んだら、
結果、ものすごく動物的になっちゃったっていう。
とにかく、「生きてるって感じがする」ほうを選びたかった。
- 糸井
- ああ、そのあたりのことは、
ぼくも本気で思ってることなんです。
やっぱり、どこかのところで、
「逃げてきた人たちの歴史」が、生命史なんですよね。

- 井上
- そうなんですよね。
- 糸井
- 哺乳類自体もともとは土の中で、
すごくちっちゃい動物として生きていたわけで、
もっと前から言えば、
「海の中から逃げて陸にあがった生き物」の末裔が、
ぼくらですから。
「強いもの」はやっぱり盛者必衰なわけで、
全部、「ボートを出して逃げ出した人たちの歴史」
なんですよ、いま続いてる生命って。 - 「このままじゃ食いっぱぐれちゃうし、
どうやって生きていこう」とか言って、
とにかく逃げたりして、何かにくっついたりして、
生きてきた。
「つよいもの」からは卑怯だとか汚いとか
言われるかもしれないけど、しょうがないんですよ、これは。
生きるためだから。
- 井上
- あと、「逃げる」みたいな話って、
「主戦場とされているところからの都落ち」
って意味で語られてることがほとんどなんですよね。 - なにか「王道」だとか、
「一般的」とか言われているものが前提にあって、
そこから「都落ち」することを、
逃げるって呼んでいたりして、
「逃げろだなんて無責任に
都落ちの後押しをしていいのか」とか、
「都落ちしても人間は生きていく価値がある」とか、
そういう話になってるけど、
そこでひとつ見落とされてるのは、
「都にいることがいつまでも安心とは限らない」
わけですよね。 - ぼくが会社をやめたことも、
たった3人で会社をつくったことも、
世間一般で言えば「都落ち」なのかもしれないけど、
いまこうして糸井さんとお話できているのも、
やっぱりその選択があったからで。
いまのぼくからすればもう、まったく、
「都だけがすべてじゃなかった」って言えるんです。

(明日につづきます)
2025-07-06-SUN
-
井上さんの著書
『強いビジネスパーソンを目指して
鬱になった僕の 弱さ考』
(ダイヤモンド社・2025)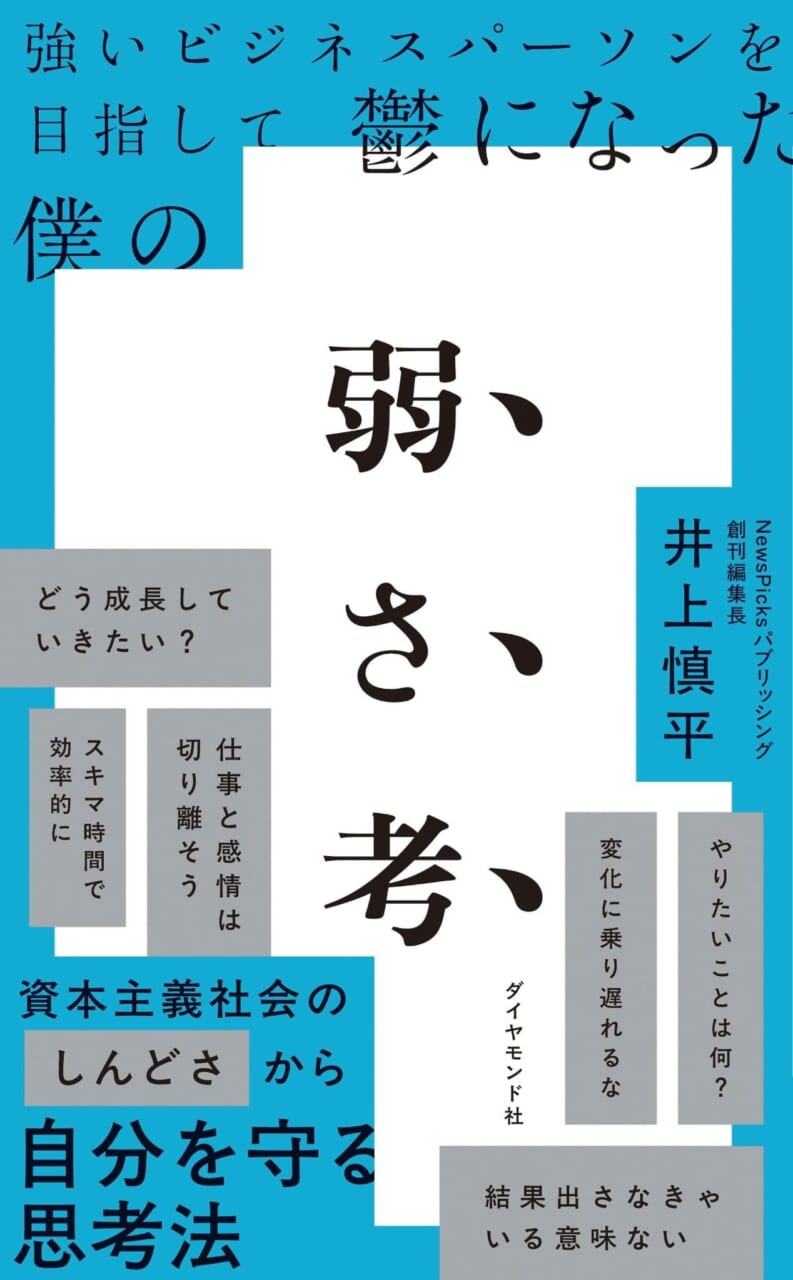
「強くて立派な人」を目指すなかで、
あるときふと、足が止まってしまった。
井上慎平さんがつづったこの本は、
「強がらざるを得ないで生きている人」であれば誰しも、
どこかに「自分」を見つけられる本だと思います。
「がんばれ」だけの本じゃない。
「寄り添う」だけでも終わらない。
強い誰かをまねて走りだすのではなく、
弱い自分と向き合って次の一歩を探していくような、
そういう「冒険書」を、井上さんは書きました。また、『弱さ考』の最後には、
井上さんが新たなに踏み出した
「次の一歩」が綴られています。
それが、「問いからはじめるアウトプット読書ゼミ」、
通称「問い読」です。
ふだん読まないような本を読んで、
ふだん出会えないような仲間と集まって、
「正解のない問い」について、みんなで対話する。
そんな、新しい学びの場。
「次回の募集」については、
ぜひこちらのサイトをどうぞ。