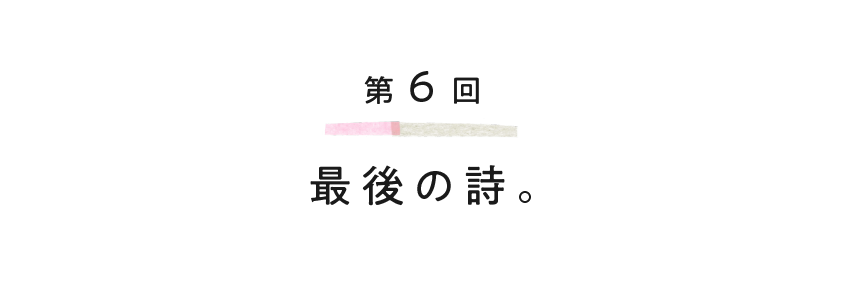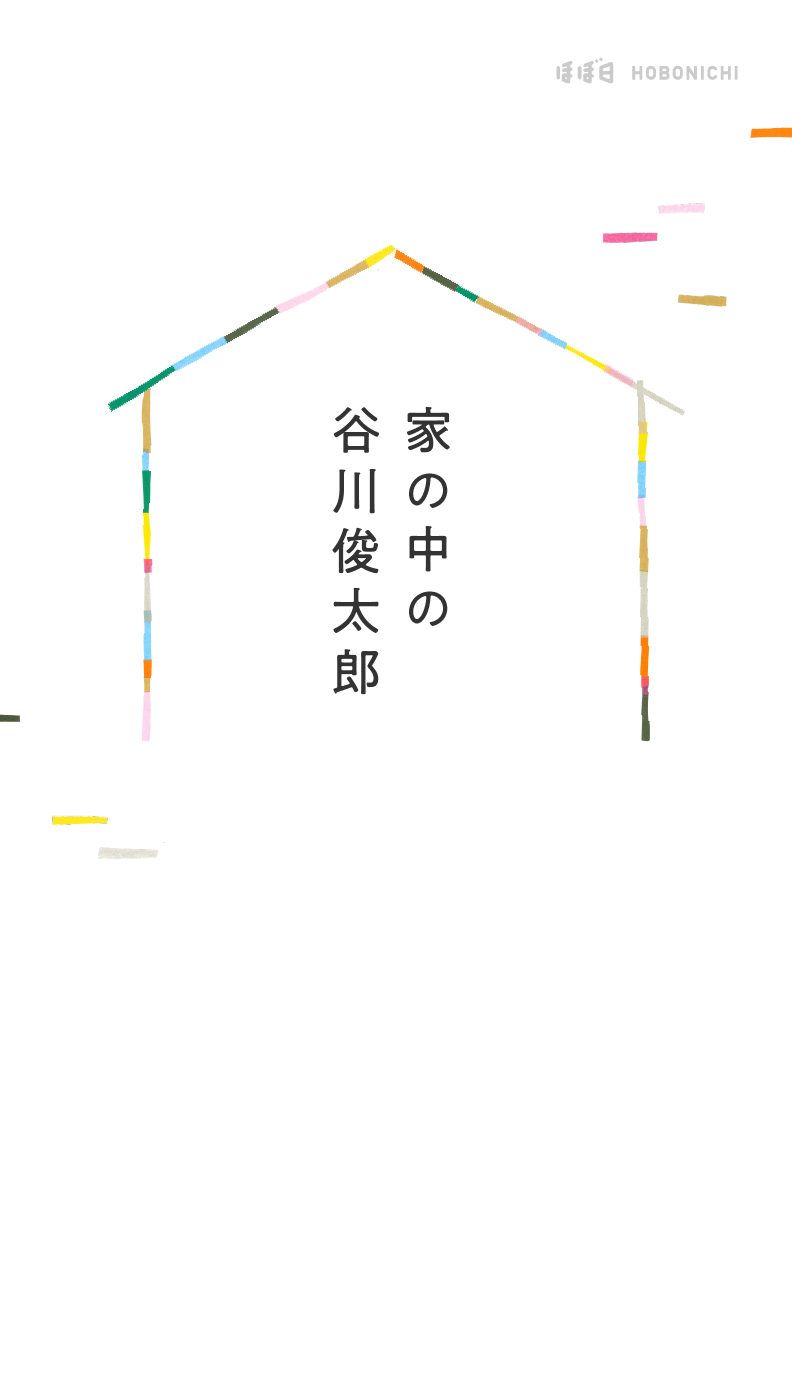
2024年11月13日、
93歳の誕生日を前にして詩人は空に旅立ちました。
私たちは谷川俊太郎さんの詩に、
本で、教科書で、歌で、アニメで、
これからもずっと会うことができます。
しかし、家の中にいる「谷川俊太郎」本人は、
いったいどんな人だったのでしょうか。
長男で音楽家の谷川賢作さん、
事務所でともに働いた編集者の川口恵子さんが、
屋根の下にいる詩人について、
糸井重里に話してくれました。
谷川 賢作(たにかわ けんさく)
音楽家、ピアニスト。
現代詩をうたうバンド「DiVa」、
ハーモニカ奏者続木力とのユニット
「パリャーソ」で活動中。
父であり詩人の谷川俊太郎との共作歌曲は、
「よしなしうた」をはじめとするソロ歌曲集、
合唱曲、校歌等など多数。
作曲、編曲家としては、映画「四十七人の刺客」、
NHK「その時歴史が動いた」のテーマ曲などを制作。
2025年6月に、谷川俊太郎さんの朗読と共演した
コンサートライブCD「聴くと聞こえる」が発売。
川口 恵子(かわぐち けいこ)
編集者。
美術館、出版社勤務を経て、
現在はフリーランスの編集者として活躍。
谷川俊太郎さんの『バウムクーヘン』をはじめ、
さまざまな書籍の編集を担当する。
谷川俊太郎事務所のスタッフとしても活動。
- 賢作
- 最晩年の谷川俊太郎について話しましょうか。
- 糸井
- 谷川さんの最晩年は誰も知らないんです。
人に会わなくなりましたからね。
- 川口
- そうなんです。
- 賢作
- 車椅子でボーッと庭を見ながらすごしているのを見て、
ぼくはずっとせつないと思ってた。
2021年に立教女学院小学校に
招かれて行ったときのことはよく覚えている。
- 川口
- あのあたりが、外の活動の最後でしたね。
- 賢作
- いまここに、ヘルパーさん方が書いてくださっていた
介護ノートというものがありまして。

- 糸井
- ああ、介護ノート、綴られてたんですね。
かわるがわる、シフトを組んだ当番制で
谷川さんを見守っておられたということなんですね。
- 賢作
- そうなんです。
2023年までは外出もありましたが、
去年(2024年)の1月の不調はかなりで、
新年早々寝込んでしまい。
- 川口
- おなかの調子が悪くなっちゃって。
- 賢作
- このまま寝たきりになってしまうのかな、と
心配になりました。
- 川口
- 私は、1月の初出勤の通勤途中で
賢作さんから「俊太郎が不調」という
メッセージを受け取りました。
- 糸井
- 「不調」という言い方なんですね。
- 賢作
- まずは
「起きたくない。今日はベッドで過ごす」
と言うのがひとつ。
そして、なにも食べられなくなる。
- 川口
- 俊太郎さんはずっと、食欲がすごくしっかりしてて、
ごはんはちゃんと食べてたんです。
おやつも食べて、
それがたのしみでもありましたから。
一時期は「1日1食にする」なんて
おっしゃってたこともあるんですが、
その頃はちゃんとヘルパーさんが作ってくださって、
きちんと食べてました。
それが「食べられない」という状況は、
けっこう大変だ、と私は受けとめました。
- 賢作
- その新年の不調時にチーフヘルパーさんと相談して、
不調から脱すると信じて
「朝6時半起床、夜9時就寝」
というリズムを作ると決めました。
そして起きているあいだは、必ず誰かがそばにいる。
体調が戻ると、最初はすごく不満そうでした。
ヘルパーさんに
「あなた、なんでここにいるの? 帰っていいよ」
なんて。
- 糸井
- なんかそんな気がします。
- 賢作
- それでヘルパーさんによっては、
いるんだかいないんだかわかんない感じで、
気配の消し方がうまい人がいました。
そのうち本人も慣れてきて。
- 糸井
- 介護ノートを見ると、
川口さんの「川」の字があったり、
ヘルパーさんのお名前があったり。
- 川口
- 俊太郎さんの中では、
「川口はヘルパーではない」
という意識がすごくはっきりありました。
- 賢作
- ものすごくあった。
- 糸井
- 「川」は違う。
- 川口
- 「川口さんは仕事の人です」
という意識がありました。
だから「ちょっとトイレ連れてって」とは
なかなか言ってくれませんでした。
最後までそうでした。
- 賢作
- トイレのときは、川口さんからぼくに
電話がかかってくるんです。
「俊太郎さん、トイレでーす」って言われて、
ぼくが隣の自分の家から走っていく。

- 糸井
- それが去年の1月で、
亡くなられたのが11月で。
1月の段階では、お話はできてたんですよね。
- 賢作
- はい。でもしゃべり方も
だんだん弱々しくなっていったなあ。
「このままだと入院もあり得るかな?」と思って訊くと、
「それは困る!」とすぐにかえってきて。
- 糸井
- 困るって?
- 川口
- できれば最後まで自分のおうちで過ごしたい、
と思ってらっしゃったし、
ご家族もそうしたいというお気持ちでした。
「じゃあ、どうしたらそれができるかな?」
という感じでみんなで考えました。
「お金はあるんだから使いましょう!」
「俊太郎さん、自分で全部
使い切ったほうがいいですよ」
という話になり。
- 糸井
- うん、いやほんとに、それはそうですね。
- 川口
- ご本人は笑ってましたけど、
でも、そう考えて、シフトをしっかり組みました。
- 賢作
- 彼は最後まで、自分の意思表示はしっかりしていました。
規則正しい毎日ものぞんでいた気がする。
6時半にチーフヘルパーさんが来て、
少し遅れて私が行き、
「おはよう、いい朝だよ~」とか声かけて、
まずそのときの返事でその日の調子がわかります。 - 父が寝ていたのは電動ベッドなんですけど、
ちょっと不調っぽい日でもそれをグィーンと起こして、
車椅子に移ってもらって、リビングルームまで行く。
「まずは起きてベッドから出てもらうこと」が
毎朝のひとつの大事なミッションになっていました。
川口さんが来てくれる日だとすると
「今日は川口さんが来るから仕事の日だね!」
とかなんとか言いながら移動しました。
- 糸井
- 川口さんは、毎日来るわけじゃないんですね。
- 川口
- 毎日ではありません。週3、4とか。
俊太郎さんの調子と、仕事に合わせて
変えてました。
- 糸井
- でも、その頃はまだ、
仕事はどんどん入ってきてましたよね。
詩も書いてたじゃないですか。
- 川口
- でも少なくはしてて、断ってるほうが多かったです。
朝日新聞の連載は、ご本人も
最後まで「やめる」とおっしゃらなかったので、
ずっと書いていました。
最後に「感謝」という詩が載って、
それは亡くなったあとに掲載されたんですが、
あの詩が最後のストック、最後のひとつだったんです。
これはいよいよ俊太郎さんに、
原稿の催促をするという仕事を、
私は新しくやることになるかもしれない、
と思っていましたが、
それをやらせてくれないまま、亡くなりました。

(明日につづきます)
2025-08-17-SUN