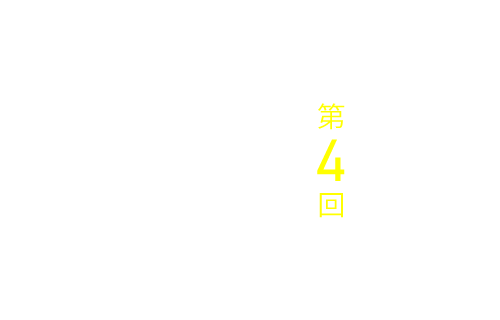フランスで実際に起こった
「嬰児殺し」事件の裁判の様子を描く
『サントメール ある被告』。
被告らの発言記録を
そのままセリフに採用した法廷劇で、
ヴェネツィア国際映画祭では
銀獅子賞と新人監督賞を獲得しました。
この1年、同作といっしょに
世界を旅してきた
アリス・ディオップ監督が
最後の最後、日本にも来てくれたので、
短い時間でしたが、お話を伺いました。
その創作論、物語の根底にあるもの。
担当は「ほぼ日」奥野です。
アリス・ディオップ
1979 年生まれ。ソルボンヌ大学で歴史と視覚社会学を学んだのち、ドキュメンタリー映画作家としてキャリアをスタート。2016 年『Vers la Tendresse』がフランスのセザール賞最優秀短編映画賞。2021 年の長編ドキュメンタリー『私たち』は、ベルリン国際映画祭最優秀ドキュメンタリー賞とエンカウンターズ部門最優秀作品賞を受賞。本作『サントメール ある被告』が長編劇映画デビュー作となり、2022 年ヴェネチア国際映画祭で銀獅子賞(審査員大賞)と新人監督賞、セザール賞最優秀新人監督賞を受賞。本年度アカデミー賞®国際長編映画部門のフランス代表にも選出された。
- ──
- 監督が、映画『サントメール』で
伝えたかったのは、母性の問題。
- アリス
- 嬰児殺しという
三面記事的な興味に訴えるかたちで
アプローチしてしまうと、
俗な好奇心を掻き立てるだけの、
単なる法廷劇に終わってしまいます。 - そうではなく、
裁判の場面を主体にしてはいるけれど、
ひとりの女性が、
「嬰児殺し」をするに至った‥‥
そうせざるを得なかった事情だとか、
人間の精神状態を、
観る人に追体験してほしかったんです。
- ──
- なるほど。
- アリス
- 彼女の話から、観客のみなさん自身が
「母性」というものについて、
何かを考えるきっかけになったら、
うれしいなと、わたしは思っています。

- ──
- ぼくは2回、映画を拝見したんですが、
2回めで、
傍聴席の女性たちが泣く理由が、
何となくわかったような気がしました。
- アリス
- ええ、傍聴席の女性だけではありません。
この映画の上映会は、
全世界で100回くらいやっていますが、
劇中の傍聴席の女性だけでなく、
観客のなかでも、
本当にたくさんの女性が涙を流すんです。
とくに、あの最終弁論の場面。 - 他方で、泣いていない人もいるんですね。
比較的、冷静に観ている人もいる。
つまり、この作品は、
きわめて個人的な映画体験になっている、
そんなふうに感じます。
- ──
- なるほど。
- アリス
- おそらく、批評家のような分析的視点で、
「頭」で観た場合には、
感情は揺さぶられにくいんだけれども、
たとえば、ご自身の母子問題など、
個人的な体験や記憶のせいで、
あの場面に埋没して觀ることになると、
まるで自分も
傍聴席に座っている気持ちになって、
涙が出てきてしまうのかもしれないです。 - 1年くらい上映会で世界を回ってみて、
そういう結論に、たどりついたんですね。
泣いている理由は何なのか、
奥野さんはどんなふうに思ったんですか。
- ──
- 自分は、母性とは何かについて、
自分の言葉で言えそうにはないんですが、
まさに個人的経験から、
母性というものについては、
何でしょう、
「かなわないなあ」
というようなイメージを抱いてはいます。
- アリス
- どういう意味ですか。
- ──
- まさしくその最終弁論の場面で、
子を宿しているときに、
子どもの細胞が母の体にも混じり合って、
ともすれば長い間、
母の体の内にとどまり続ける‥‥という、
キマイラ細胞の話が出てきますね。 - 自分の妻が子どもを妊娠したときに、
産婦人科で、エコーの画像を見たんです。
そのときの画像って、
ぼくには、
そこまで人間のかたちには見えなくて、
これが生命の兆しなのか‥‥と、
まさしく頭で理解しただけだったんです。
- アリス
- はい。
- ──
- でも、その同じ画像を見て、
妻は「かわいい」って言ったんですよね。 - この状態で「かわいい」と思える人には
ちょっとかなわないというか、
合っているのか間違ってるのかは
わかんないけど、
これが母性なのかとそのとき思いました。
- アリス
- なるほど。
- ──
- 今回の映画は、実際の裁判のやりとりを、
そのままセリフにしているそうですが、
あのキマイラ細胞の部分は、
脚本で付け足したと、うかがっています。 - つまり、アリス監督や脚本家の方など
創り手の側の
「伝えたかったこと」が凝縮した、
緊張感の高い場面ですが、
その場面と個人的な記憶がつながって、
傍聴席の女性や、
実際の観客が泣いているという理由が、
わかったような気がしたんです。
- アリス
- ありがとうございます。
個人的な経験を、共有してくださって。 - わたしも「母親になる」って何なのか、
母性とは何か‥‥については、
よく考えています。
言い換えると、女性というのは、
「いつ」母親になるんだろう‥‥って。
- ──
- いつ。
- アリス
- わたし自身が、
「母親になったんだ」って感じたのは、
妊娠4ヶ月か5ヶ月くらいで、
お腹の赤ちゃんが
「はじめて、動いたとき」なんですね。 - あのときに、わたしは、
「ああ、わたしは母親なんだな」って
心から感じることができた。
でも、この映画の主人公であり、
被告のロランス・コリーは、
まだ母親になっていないのではないか。
- ──
- ああ‥‥。
- アリス
- つまり「嬰児殺し」は、彼女にとって、
遅れてやってきた
中絶みたいなことだったのではないか。
そんなふうに、わたしには思えました。 - 何が言いたいかと言うと、つまり、
母性というものは、
どんな女性でも、
妊娠したらすぐに持てるものではない。
人によって、女性によって、
それぞれに違うものだということです。
- ──
- なるほど。
- アリス
- 母性は、いつの時点で感じるべきとか、
そういうものではないんです。
きわめて複雑な感覚だと思っています。
- ──
- その監督の「母性」に関するお考えは、
映画を撮る前と後で、変わりましたか。
- アリス
- ひとつの「発見」がありました。
- わたしには長年、母との関係において、
しっくりこない感情があったんです。
この映画を撮ったことで
その傷ともいうべきものが修復され、
沈静化された気がしました。
母親が早くに亡くなったことを
ゆるすことができたし、
すべての母親に対するゆるしの感情が、
わたしの中に芽生えました。
- ──
- おお‥‥映画を撮ったことで。
- アリス
- 母が、わたしを残して、
早くにこの世を去ってしまったという、
そのことさえ許すことができた。 - 同時に、まだ誰にも見せていなかった
この作品を、
わたしの15歳の息子に見せたとき、
彼がどう思うか、
わたしは非常に「怖かった」んですね。
- ──
- ああ、こんどは「母」として。
- アリス
- でも、作品を観終えたあと、
息子が素晴らしいことを言ってくれた。 - 「ママ、いまぼくはこの映画のことを
すべてはわからないけれど、
いつかわかるときが来ると思う」って。
- ──
- すばらしいですね。
- アリス
- それは、衝撃的にうれしい言葉でした。
- 彼は、おそらく本能的に、
この映画が
自分にも向けて語りかけていることを
感じ取ってくれたんだと思います。
だから、いつか、
彼にとって必要なときに見返して、
理解してくれるような気がしています。
 © SRAB FILMS – ARTE FRANCE CINÉMA – 2022
© SRAB FILMS – ARTE FRANCE CINÉMA – 2022
(つづきます)
撮影:福冨ちはる
2023-08-05-SAT
-

数々のドキュメンタリーを撮ってきた
アリス・ディオップ監督による
初のフィクションが
『サントメール ある被告』です。
実際に起きた「嬰児殺し」、
その裁判の傍聴に通い詰めた監督が、
裁判記録を台詞に採用するなどして
話題となりました。
監督は、この映画をたずさえて1年、
世界中をまわってきたそうです。
法廷劇の形式をとっていますが、
監督が伝えたかったテーマは
「母性」や「母と子の関係」とのこと。
静かに、力強く訴えかけてくる作品。
ヴェネツィア映画祭で銀獅子賞を受賞。
劇場情報などは公式サイトで。
-
《2015年公開のコンテンツです》