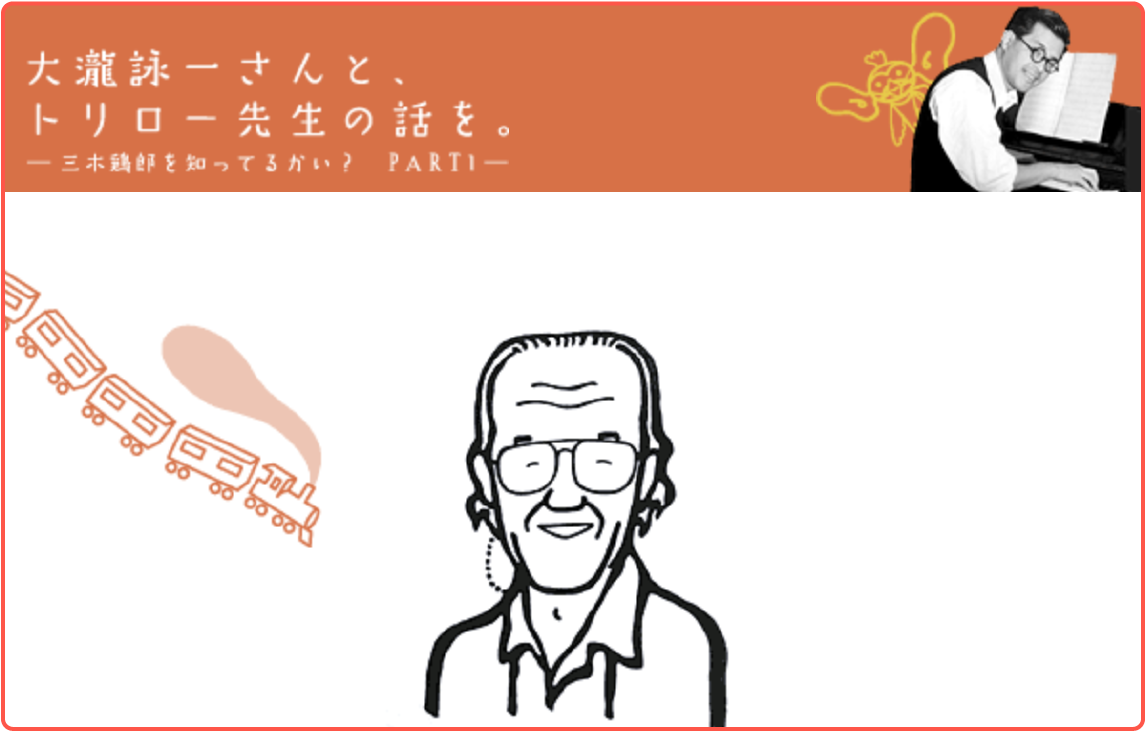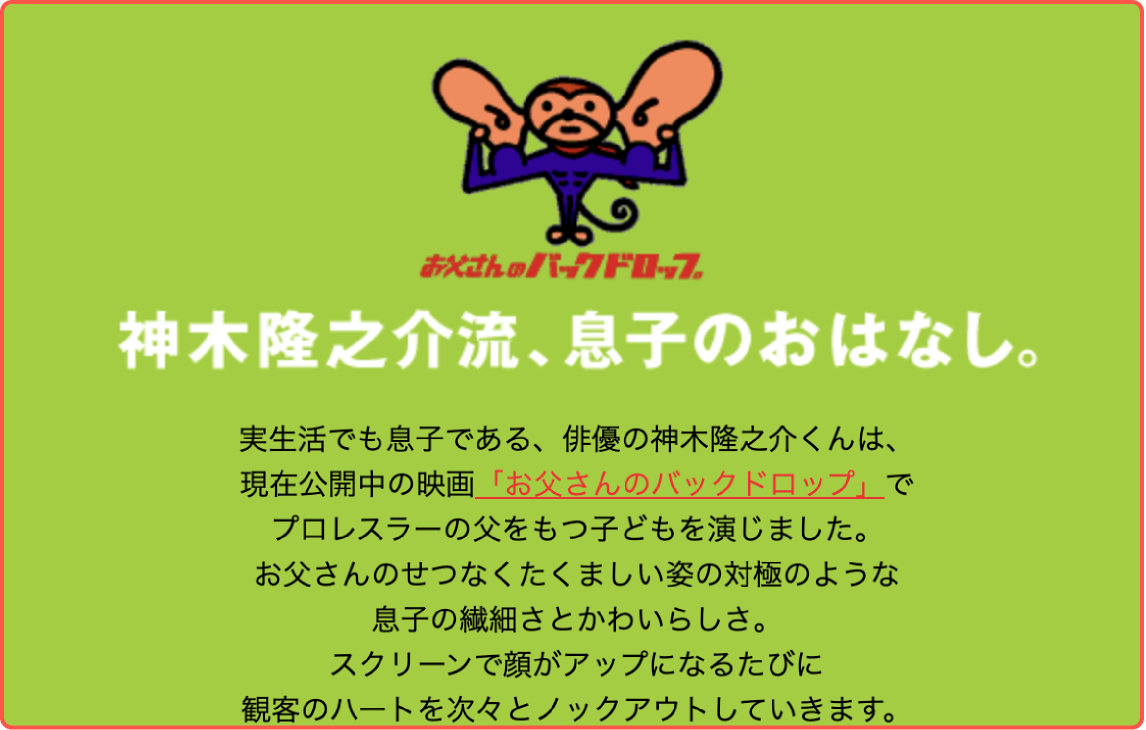ほぼ日の20年以上蓄積された読み物のなかから、
いろんな人にいろんな切り口で
「音楽のプレイリスト」をつくるみたいに、
おすすめのコンテンツを選んでしまう企画です。
去年の年末にはじめてやってみたところ、
たいへん好評だったので、今年もいろんな人に
お願いしてつくってもらいましたよー。
12人の方がつくった「ほぼ日のプレイリスト」、
年末年始にのんびりおたのしみくださいー。
背のびするコンテンツ。
山邊 恵介(やまべ けいすけ)
靴磨き職人の仕事をしていた山邊くん。
その後、筑波大学に進学、現在大学院生。
目下、修士論文を鋭意執筆中。
最近、ちょっとワインに詳しくなった24歳。(編集部記)
縁あって18歳からほぼ日とお仕事をしております。
当時、ほぼ日の乗組員のみなさんは、
「ほぼ日は大人向けだから、若い読者は珍しい」と
まさに珍しいものを見るように仰いました。
そのときは「はあ、そうですか」と聞いていましたが、
「大人向け」を田舎の10代が一生懸命読んでいた
揺るがせない事実について、改めて考えてみました。
私はおそらく「背のびをしていた」のだと思います。
コンテンツの内容が、知らないことだらけだったり
よくわからなかったり。それは普通のことでした。
わからない、わかりたい、わからない。
そんな背のびの繰り返しが私にとってのほぼ日です。
いつかはわかりますように!と焦がれる、
もしくは、なにくそ!と勉強のタネにもなる、
息ながく読めるでありましょうコンテンツを、
選びました。
年の初めは背のびの運動から!
背のびをする、とひと口に言っても、
それは様々ありますが、
10代が読んで「これは、なに?」
と思ったコンテンツから。
教養とはなんだろうか、
プロフェッショナルとはどんなものだろうかと
糸井さんと吉本さんの対話は
行きつ戻りつ回を重ねていきます。
その応答の様子を画面越しに見ていると、
時々ふたりのやりとりに
ついていけない瞬間がやってきます。
激しく話の内容が飛躍しているわけでも、
難解な概念がくるくると
操作されるわけでもないのに、わからない。
それこそ最初に読んだ中学生の時には
ほとんどわかりませんでした。
唯一、わかったのは第7回「モーターボート」。
この回は前半のテーマから後半のテーマへと
切り替わる幕間のような役割を果たしていて、
中学生の私はその幕間のひと芝居だけを
「へえ、そうなんだ」と思いながら
読むことができました。
その後、靴磨き屋として働き出してから、
前半に登場する「専門の人間」の話は
よくわかるようになってきました。
とくに、
自分の専門としていることに
自分は影響されていないと
思っているかもしれないけど、それは大嘘です。
という一文は、高校をやめて働き出したものの、
ろくろく仕事もできない当時の私にとって
大問題であった「それでお前は何者なんだ?」を
考える上でとても大きな発言でした。
元から備わっていた才能が開花したにせよ、
後から学習して構築されたにせよ、
人は自分がやっていることから
逃れることはできないんだ、ということ。
学校をやめて仕事をはじめたことで
自分のなけなしのアイデンティティが
ぼろぼろになっていく、
その不安の源をぴたりと言い当てられて、
少し楽になった記憶があります。
いま、大学院で勉強をしている身として
面白いのは第8回〜第9回です。
そこで話されていることがらは
「吉本さんが大切にしてきたもの」ではありますが、
聞き手である糸井さんの予想、
ひいては読者の予想とも大きく異なる回答が
吉本さんから出てきます。
そして、こちらの予想についても、
それはこういうことですよ、と続けられる。
この辺りの話は、
世の中のことを考えようとしている身として、
大変ハッとする部分ですし、
前半の教養についての対話を思い出しながら読むと、
今度はそちらの話もよくわかるようになってくる
仕掛けになっていると思います。
まだまだわからないのは対談終盤の老いに関する話で、
こればかりはやっぱり全く
見当がつかないと言いますか、
覚えておくことぐらいしか
今はできないと思っております。
靴磨きの仕事をしていると、
よく「手仕事ですね」と、
声をかけていただくことがあります。
確かに道具といえば
ブラシや靴墨や布くらいで、
あとはほとんど手をうごかして、
なんとかしているので、
手でする仕事といえばそうなのか、
と思います。
でも、なんだかしっくりこない。
手仕事と言われるとなんだか
こそばゆい気持ちになります。
そんな大したもんではないんですよ、
と言いたくなる。
謙虚なのか、謙遜なのか
はっきりはしませんが、
手をつかって仕事をすることについて、
仕事をはじめてもうすぐ10年に
なるけれどよくわかっていません。
そんな中で折にふれて
読み返すコンテンツが
辰巳芳子先生のインタビューです。
日々、行っている仕事だとか
業務であるとかを、
このくらいでいいかな、
と手を抜くつもりはなくても
加減してしまうことは
往々にして起きることだと思います。
自分の可能性を試す時間であるはずの
学生だって手抜きをすることは多いです。
それは、本当にまずいことなのですが。
どうして、まずいのか。
それがこのコンテンツには書かれています。
自分が生まれるより前のことに、
つよい関心を持ってきました。
ほぼ日を一生懸命読んでいたことも
結局はその関心に突き動かされての
行動だったといえますが、
そのおかげでにわかに詳しくなったり、
なんだかよくわからないんだけど
覚えてしまった笑い話みたいなものが
それなりに私の中に貯まっています。
この対談は、45歳で没した漫画家
上村一夫さんの回顧展に合わせて、
漫画家の若年の友人であった糸井さんと
漫画家の娘である上村汀さんとのあいだで
行われたものです。
朝5時ごろ家に帰り、昼まで眠り、
そこから事務所で仕事をして夕方には飲み始め、
そして明け方に家へ帰る「規則正しい」生活を
送っていた上村一夫さんには
学校に通っている娘との時間は多くなかったといいます。
そんな汀さんに、糸井さんが
「お父さんは」「上村さんは」と、
往時の記憶をふんだんに語っている、そういう対談です。
どこか、法要の席上で故人の友人が思い出話をし、
家族が「へえ!」と聞いている、
そんな風景に似ているかもしれません。
その思い出話の中で出てくるのは
不可解な「くるぶし」談義であったり、
汀さんに「バカな大人」と笑われる
「マツタケ退治」の顛末であったりするわけですが、
一つひとつの語り口が
すごくたのしそうだということで一貫しています。
私は上村一夫という人とその作品を
この対談ではじめて知りました。
その後、近所の古本屋で『同棲時代』の文庫版を
揃で手に入れたり、
人から譲られた古書の山に
『関東平野』が混じっていたりと、
何かしら機会があって
私の本棚にちょっとした上村一夫コーナーができています。
ただ、糸井さんをして「老人のさらに先」と言われる
上村一夫さんの老成ぶりと、
取り扱う主題の多くが
男女のどうこうであることから、
この対談にしても、
上村作品そのものにしても、
共感しながら読むという経験は私には少ないですが、
それゆえ、くり返し読んでいつか、
ああ、あそこで言ってたのはこういうことか、と
わかるのかなと思ったりしています。
それが単に楽しみなだけではなく、
けっこう恐ろしくもあるのですが。
4
歌う歌。
前川さんがしきりに、
「糸井さん、なんのお仕事を?」とたずね、
会場(天幕がかかりソファが置かれ、
ミラーボールが吊されている)に
集まっているほぼ日の乗組員たちへ
「みなさん、仕事といっても、なにを?」と
首をかしげるところから対談ははじまります。
それだけでもう面白いわけですが、
何が仕事になってるのかよくわからず、
何をしているのかよくわからないんだけど、
どうにもなんだかあつまって、
全体にざわざわと笑っているような、
童話に出てくる小人の集団みたいな会社
としてのほぼ日の存在が
ひとつここで記録されていると
読むことができるでしょう。
前川さんが
「蛾だった人が、ポカポカ陽気で出てきて、
うれしそうに花にとまってるのかな?」
と例えておられるのも大変よくわかります。
ただ、前川さんはこの会場全体を大いに気に入って、
ソファの背もたれに肘かけちゃったりして、
スナックの奥の席ばりにお使いになっています。
そういう場所の雰囲気だけでも、
読み手が笑う気持ちになるような
そういうコンテンツの一つの代表だと私は考えています。
対談の実の内容では、
前川さんが歌いながら
ステージを降りて客席を握手して回ることについて、
最初は「いやだな」という意識で
客席に行きました。
「オレはまだ下には降りたくないんだ」
「歌で感動させたいんだけど、
感動させられない自分がいるから、
ちょっと降りてみるんだ」
と、自分を変える決心で
客席に降りたこと、
それで歌を歌う自分と
それを聴く人たちのことが
わかってきたというあたりの話を、
つまり歌い手という仕事について
前川さんが考えてきたことを、
折々に話される歌嫌い話のB面として
読むこともできます。
それに引きつづいて、
糸井さんも
「もうふたまわりぐらいバカになって」
自分を変えようと思っている、と
話されていて、
読み手の素朴な感想では、
あ、糸井さんや前川さんでもそうなのか、
と安心すると同時に背筋が伸びていきます。
5
大瀧詠一さんと、トリロー先生の話を。
細野さん・慶一さんと、
トリロー先生の話を。
昭和という時間に音楽、
芸能の水脈を作り出した、
三木鶏郎なる大人物について、
PART1では大瀧詠一さんと糸井さん、
PART2では細野晴臣さんと鈴木慶一さんが、
驚きながら知っていくコンテンツです。
戦前から戦後にかけての
芸能談義として読むならば、
こちらが知らない名前や楽曲、
番組がとめどなく登場してきて、
それだけで息もつけないほどですが、
あえてそれらを「ついで」として
読んでみることで、
なんの前情報もなく「三木鶏郎」を
知ることができるのではないかと思います。
私にとって、このコンテンツ最大の魅力は、
例えば大瀧詠一と糸井重里が、
昭和23年生まれの同い年として
キャーキャー言いながら、
当時の状況や三木鶏郎門下の様子を
話している空気そのものなんです。
大瀧さんは
「うっかり見てたんだよ」「当てずっぽうだよ」と
はぐらかしながら、
あらゆる面白そうなことについての
生きた知識を出し、
それに対して糸井さんが、
「へー!」と大いに喜びながらも、
三木鶏郎の仕事と自分たちの仕事の轍が
交差する様子を捉えていきます。
なにせ水源池のような三木鶏郎作品を
相手にしているので、
おのずと糸井さん、大瀧さん、ご両人が
どうやってその人になっていったのか、
という話も語られます。
PART2の細野さんと鈴木さんは
鶏郎事務所のアーカイブを眺め、聴きながら、
三木鶏郎の耳を再現する仕事をしています。
ビリッと痺れるのは、
細野さんが三木鶏郎事務所の
「門を叩くべきだったな」と言い、
鈴木さんが「86年から90年くらいまでは暇だったのにな。
失敗したなぁ!」と惜しんでおられることです。
その様子を見るだけでも、
すげえ人がいたんだな、
と肌で感じられるだろうと思います。
あとはコツコツ調べたり、思い出したりしていけばいい。
ずーっと、
年長の方のコンテンツが
続いてきましたが、
ここで急に若返ります。
神木隆之介さん、当時11歳。
李闘士男監督『お父さんのバックドロップ』の
公開に合わせて行われたインタビューです。
すでに少なくないドラマや映画でのキャリアを
重ねていた神木さんが、
キラキラと輝いた表情で
お父さんのことや、
笑いすぎて電車を降りちゃったことや、
芝居のことを答えていく。
それを読むことが
いったい、どうして
背のびすることになるのか。
たしかに、知らないことや
未経験の出来事について、
つま先を立てて覗いてみようと
思うことはあるでしょう。
でも、なにかに憧れて、
ああ、いいな、そうなりたいな、と考える、
それも背のびであるはずです。
このコンテンツでは、
11歳の神木さんの
その幼気なさとピッタリと
くっついた素直さが
全編を貫いています。
それを、徐々に人が大人になるにつれて、
つまり成長の名の下に失っていくものだと、
子ども特有のものだと言うのはたやすい。
でも子どもだとか大人だとか歳だとかを
一度忘れてしまって、
人間として向かい合うとき、
答えられるものについては即答する直截さに、
いや、かっこいい、と思わずにいられません。
自分がまだ持っていないものにばかり
手を伸ばすのではなく、
すでに失くしたことにして
放ったらかしにしているものの輝きを
このコンテンツは見せてくれていると思います。
その素直さにこそ、私は背のびしたいと思うのです。
玄人ぶりたい、というときがあります。
その気持ちの内訳はおそらく、
目の前にあるものが、
どうやって、できているのかを
瞬間的に見抜きたいというものです。
ただ、その気持ちが大きくなりすぎると、
実際その料理が美味しかったのか、
そうでなかったのか、
映画が面白かったのかどうなのか、
忘れてしまうことが多くなってきます。
客観性に乗っ取られて、
主観がぺちゃんこになってしまう。
そういうときに読み返すのが、
画家・山口晃さんの語る技術論です。
私がこのコンテンツの中で、
息が浅くなるような衝撃を受けた発言は、
「人間の目には現実が10割、見えています」。
人間の目には現実が10割、見えている。
しかし、それを絵画であれ、
言語であれを通して
伝達あるいは再現しようとするならば、
そこに距離が生まれてしまう。
しかもその距離に気が付かずに
当の絵画を見た人には、
ほほお、あの作家にはこういうふうに
見えてるのか、と思われてしまう。
そうすると作家の現実と作品と
観客の現実とのそれぞれの間で、
距離は二重に発生していくことになる。
普段、なんの気なしに美術館や街角で
作品を見たりしているときに、
そんなやっかいなことが起きていることに、
私は驚きました。
そしてそれは、
こうして文章を書いている時も、
あるいは読んでいる時も、
絶え間なく生じているはずなんです。
自分が考えていることと、
自分が手持ちの技術で
成立させようとしていることの
ズレに敏感になりつつ、
読者はまったく違うものを
読んでいるかもしれないという想定をする面白さ。
技術の話は細部にわたるからこそ
読む楽しみが格別ではありますが、
そこからさらに表現全般へとジャンプすることが
当然のように起こるわけで、
その圧倒的な跳躍に、呆然としつつ憧れています。
8
黄昏
いよいよ、最後のコンテンツです。
ここまで読んでくださって本当にありがとうございます。
私がいちばん最初に買った
ほぼ日の本は『黄昏』でした。
中学3年生の一年間、
朝の読書の時間に
繰り返し読みました。
例のごとく、
そこで展開されている話の
意味するところは
全然分かりませんでしたが、
会ったことのないおじさんが二人、
楽しそうにゲラゲラ話をしているのが、
おかしくて、おかげで何度も読みました。
ところどころ、暗記もしています。
このコンテンツは、
書籍化された『黄昏』には
収録されていない、
赤瀬川原平さんと
南伸坊さんと糸井さんの
鼎談形式の散歩話です。
こればっかりは説明がきかないので、
どうぞ、慌ただしい年末に、
ひと息お茶でも入れて
うっすら笑いながら読んでみてください。
よくわかんない、
今の自分には理解できないものを、
できれば丸ごと引き受けられるような、
でっかい駐車場みたいな場所を
私は自分の中にしつらえたいと思っています。
背のびを繰り返すうち、
背が高くなることを切に願いまして、
来年もほぼ日を読んでいきましょう。
いやー、どうもお疲れ様でした!
2021-12-25-SAT
-
イラスト&タイトル:あーちん
あーちん
2002年生まれ。9歳のとき、お母さんのすすめで
「ほぼ日マンガ大賞2012」にエントリーし、
約1000通の応募のなかから見事入選。
小学生漫画家として、『くまお』の連載をスタート。
初の単行本『くまお はじまりの本』を出版。
2年半の連載の後、小学校卒業をきっかけに、
『くまお』は246回で終了。
続く、中学時代は、好きなたべものを描く
『たべびと』を連載。
終了までに144品のたべものを描きあげた。
現在、日本の北のほうで、大学生活エンジョイ中の19歳。