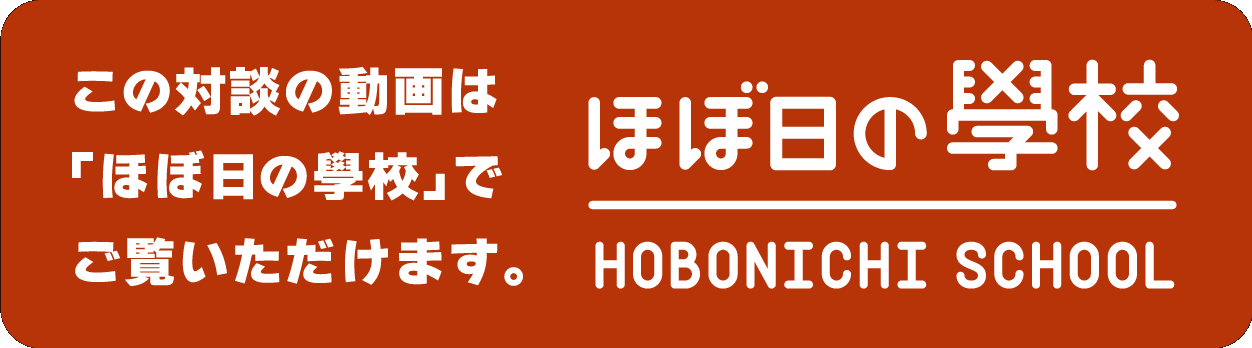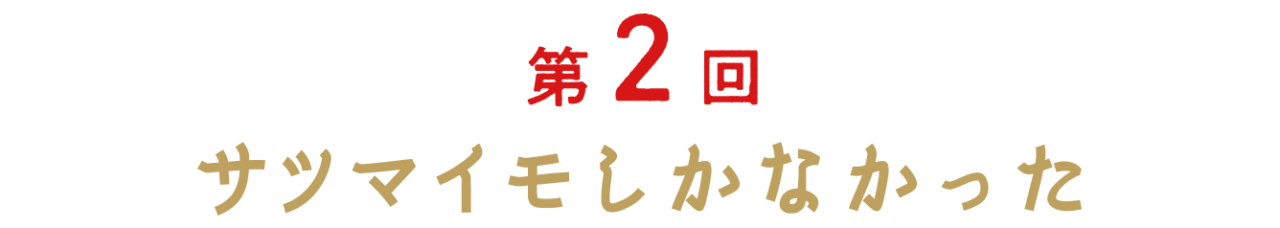新潟県長岡市に本社をかまえ、
「黒豆せんべい」や「大袖振豆もち」など、
おいしいヒット商品を生み出してきた岩塚製菓。
ほぼ日社内にもファンが多く、
もちろん糸井重里もそのひとりです。
そんな人気者の岩塚製菓ですが、
「おせんべいがおいしい」以外、
じつはあまり知られていなかったりします。
この会社がどんな想いから生まれ、
どんな困難や失敗を乗り越えてきたのか。
まだ稲穂が青々としていた7月下旬、
糸井は岩塚製菓の本社をおとずれ、
槇春夫会長からいろいろなお話をうかがいました。
キーワードは、ズバリ「米と縁」です。
紆余曲折、ドラマチックなエピソードの数々、
たっぷりとおたのしみください。
槇春夫(まき はるお)
岩塚製菓株式会社
代表取締役会長CEO
1951年 岩塚製菓の創業者の一人。
槇計作の三男として新潟県長岡市に生まれる。
1974年 富山大学卒業後、ダイエーに勤務。
1976年に岩塚製菓株式会社に入社。
以降、数々の要職を歴任し、
1998年に代表取締役社長に就任。
2023年より現職。
2021年旭日小綬章を受章。

- 槇
- 1929年頃ですけど、
世界史的に見ると世界恐慌の時期に、
日本中も大不況に陥って、
新潟県にも凄まじい荒廃が襲いました。
- 糸井
- 自分たちの食べものもないくらいですよね。
- 槇
- このへんもかなり大変だったようで、
当時は娘がどこかに売られていったとか、
なんかそういう時代があったそうで。
- 糸井
- はぁー。
- 槇
- そういう歴史がある村で、
なんとか種だけでも植えられないかと。
つまり、この零細の地である岩塚で、
なにか産業を起こせないかってことですよね。
それで平石さんやうちの親父が、
出稼ぎにいかなくても
暮らしていける地域にするんだと。

- 糸井
- この村の苦しい状況を変えようと。
- 槇
- それはもう大変な苦労があったんだと思います。
- 糸井
- ぼくの知り合いに
ネパールの人がいるんですけど、
ネパールって山の上にある土地なので、
他の国と貿易ができなくて、
貧困問題もすごく残っているそうで。
- 槇
- あー、そうですよね。
- 糸井
- だけど、このままじゃダメだってことで、
いまの状況をどうしたら変えられるか考えて、
その彼は「教育」しかないと。
それでいまもネパールの山奥に
学校をつくる活動をつづけているんです。
- 槇
- 素晴らしいですね。
- 糸井
- 教育からはじまるという発想は、
立派な話にも聞こえちゃうんですけど、
でも、その場しのぎのことをしていては、
結局、なにも変えられないままで。
- 槇
- いまの話は長岡の「米百俵」物語と同じですね。
- 糸井
- あ、そうですね(笑)。
- 槇
- 戊辰戦争で長岡藩が焼け野原になったとき、
支藩の三根山藩から、
それこそお米を百俵いただいたと。
そのとき家老の小林虎三郎が、
「これは絶対、食べちゃいかん」と。
それを文武両道に必要な資金にしようと。
- 糸井
- ええ、ええ。
- 槇
- それを聞いた若い武士は、
自分の子どもが飢えているのに、
なんで米を配らないのかと。
それで刀を抜いて襲い掛かるという、
そういう場面もありますけど(笑)。
- 糸井
- (笑)
- 槇
- 一時的に配って食べてしまえば、
それで終わりだったけれども、
それを元手に学校をつくったという話は、
もうほんとにそれと同じことですね。
- 糸井
- そういう文化風土が、
この土地にはあるんですかね(笑)。
- 槇
- 脈々と伝わっているんでしょうかね。
その時々で必死になんとかしようと、
考えながら、やりながらだとは思いますけど。
- 糸井
- 大変なことですね、それは。

- 槇
- ほんとにそう思います。
親父たちが最初にはじめたのは
サツマイモを使った「イモ飴」の製造ですけど、
それもたまたまといいますか、
偶然あの山の上がサツマイモ畑だったからで。
- 糸井
- いいなぁ、いちいち(笑)。
- 槇
- 結局、このへんは土地が痩せていて、
蕎麦とかサツマイモくらいしかできなかったんです。
- 糸井
- それしか採れないと。
- 槇
- あるものといえば、それくらいしかない。
それで手っ取り早いところで、
イモ飴の産業を起こしたわけです。
- 糸井
- 最低限、いまあるものでやろうと。
- 槇
- 手に入るものだけで、
なんとかしようとしたんでしょうね。
- 糸井
- 我慢するのを超えちゃったところに、
次の芽があったってことですね。
- 槇
- そうかもしれませんね。
- 糸井
- そういう歴史を知らずに地図だけを見たら、
「あのへんは米どころだから米菓が有名なんだ」
とか思っちゃいますよね。
- 槇
- 「当然じゃないの?」みたいな(笑)。
そう思っちゃうんですけど、
ほんとうはそうじゃないんです。
- 糸井
- いまは米も余るほどあるわけだけど、
そういう新潟という土地でも、
米がなくて苦しんでいるときがあって。
- 槇
- はい。
- 糸井
- で、イモのまま売っても二束三文だから、
手間をかけてイモ飴にして売ってみようと。
つまり、そうしたというのは、
商品化したかったんでしょうね、きっと。
- 槇
- そういうことですね。
- 糸井
- イモ飴ってジュースにするんですよね。
それを搾って、煮詰めて、飴にする。
その手間がお金になるわけで。
- 槇
- それでもギリギリだったと思いますけど。
- 糸井
- そういうことを無理をしてでも
はじめなきゃならなかった理由は、
それまでに相当な苦労があったからで。
- 槇
- 想像を絶する苦労だったと思います。
自分なんかはよく覚えていませんけど。
- 糸井
- お父さんの時代ですよね。
- 槇
- 親父の時代なんですけど、
ただ、親父にすれば、
そのまた親がえらかったと(笑)。

- 糸井
- 米百俵からつづくわけだ(笑)。
- 槇
- お金を持ち出しても、
見て見ぬふりしたりとか(笑)。
まあ、いろいろ大変なことはあったようで。
- 糸井
- そういう教えを近くにいた子どもが、
見たり聞いたりしていたんですかね。
- 槇
- どうなんでしょうね。
ただ、なんでもそうかもしれませんけど、
やっぱり結果だけ見ても
よくわからなくなるんですけど、
そこに至る過程を見ていくと、
そうなっていった理由というのが、
またよくわかるといいますか。
- 糸井
- そういうことですよね。
イモ飴からはじまったというのも、
つまり、藁をもすがるの「藁」を探して、
その藁で草履を編んだみたいな。
- 槇
- はい、もうほんとに。
- 糸井
- そういうスタートだったわけですね。
この会社のはじまりは。
(つづきます)
2023-11-14-TUE