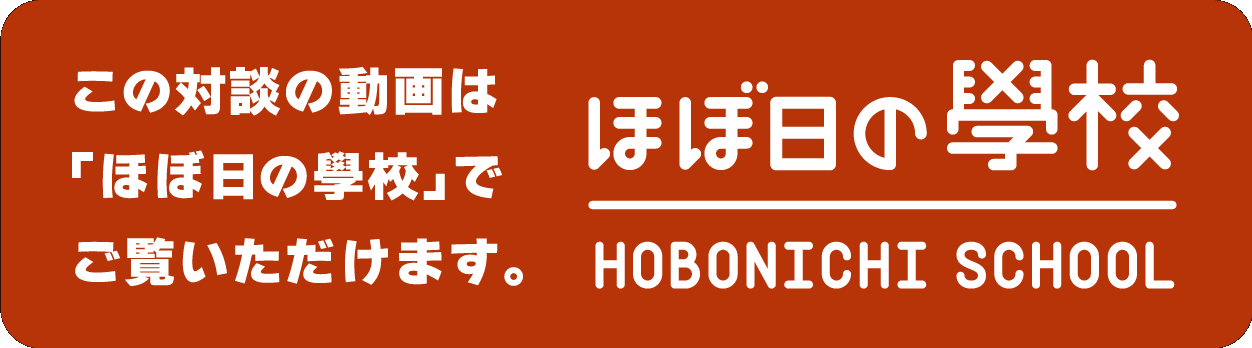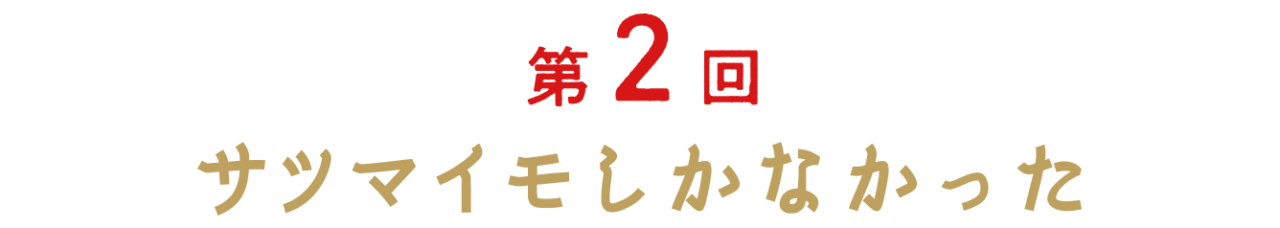新潟県長岡市に本社をかまえ、
「黒豆せんべい」や「大袖振豆もち」など、
おいしいヒット商品を生み出してきた岩塚製菓。
ほぼ日社内にもファンが多く、
もちろん糸井重里もそのひとりです。
そんな人気者の岩塚製菓ですが、
「おせんべいがおいしい」以外、
じつはあまり知られていなかったりします。
この会社がどんな想いから生まれ、
どんな困難や失敗を乗り越えてきたのか。
まだ稲穂が青々としていた7月下旬、
糸井は岩塚製菓の本社をおとずれ、
槇春夫会長からいろいろなお話をうかがいました。
キーワードは、ズバリ「米と縁」です。
紆余曲折、ドラマチックなエピソードの数々、
たっぷりとおたのしみください。
槇春夫(まき はるお)
岩塚製菓株式会社
代表取締役会長CEO
1951年 岩塚製菓の創業者の一人。
槇計作の三男として新潟県長岡市に生まれる。
1974年 富山大学卒業後、ダイエーに勤務。
1976年に岩塚製菓株式会社に入社。
以降、数々の要職を歴任し、
1998年に代表取締役社長に就任。
2023年より現職。
2021年旭日小綬章を受章。

- 糸井
- 岩塚さんの話、
ちょこちょこ聞いていると、
すごい会社があるもんだなと(笑)。
- 槇
- いやいやいや(笑)。
- 糸井
- 岩塚さんとのご縁の話からすると、
お仕事で映画のナレーションをしたんですけど、
そういう録音スタジオって、
よくテーブルの上にお菓子が置いてあるんです。
そこで何気なく食べたのが「大袖振豆もち」で。
- 槇
- はいはい、うちの商品で。
なんと光栄な。
- 糸井
- 名前も知らないまま1枚食べて、
まわりの人と話しをしながら
無意識で2枚めを口に入れていたんです。
その途中で「俺、これ好きかも!」って(笑)。
- 槇
- わっはっはっは!
- 糸井
- その話をあとで人にすると、
みんな「あれ、おいしいよね」って言うんです。
それでさらに好奇心が湧きまして、
調べられる程度の検索をすると、
この会社がどうやって生まれたとか、
世界の人とどうつながっているとか、
いまもまた次のレベルに行こうとしていて。
- 槇
- ええ、ええ。
- 糸井
- だけど、もともとは風光明媚な
大きな産業があるわけじゃない場所から
スタートした会社なわけで。

- 槇
- まあ、なにもないところです(笑)。
- 糸井
- そんな場所で生まれた会社が、
いまみたいな規模へ広がっていく話は、
誰が聞いてもおもしろいと思うんです。
それでいつか新潟に行って
工場見学もしてみたいと思っていたら、
こうやって実現したという(笑)。
- 槇
- 糸井さんのような有名な方で、
いまのような
「食べておいしかったから」という理由で、
ここまでお出でになられたのは、
おそらく初めてじゃないでしょうかね。
- 糸井
- そうですか(笑)。
- 槇
- バイヤーさんとか、団体の見学会とか、
そういうのはありますけれども。
- 糸井
- ぼくはここに来るあいだに、
岩塚さんのことが書かれた本まで読みまして。
きょうのアンチョコですけど(笑)。
- 槇
- ああ、お読みいただいたんですね。
- 糸井
- これを読むとまた全然イメージがちがいました。
岩塚製菓という会社は、
槇さんと平石さんがはじめた会社ですよね。
- 槇
- そうです。
父の槇計作と平石金次郎の2人が創業者です。
- 糸井
- だけど、会社の名前は「岩塚製菓」。
- 槇
- 岩塚というのは、
このへんの土地の名前で。
つまり、地名なんですね。
- 糸井
- 本の中にもありましたが、
「岩塚を良くしようと思ってはじめた会社だから」と。
その話がぼくは大好きで(笑)。
- 槇
- ほんとうにそうなんです。
窓の向こうにお稲荷さんが見えますけど、
その下にJR信越本線が通っていて、
そこに「越後岩塚駅」という駅があります。
いま「岩塚」という名前が残っているとしたら、
そこくらいじゃないでしょうかね。
- 糸井
- もう「岩塚」という地名はないんですね。
- 槇
- もうないんですね。
じつはこの本社がある場所も、
もともとは岩塚小学校があった場所。
私の母校ですけど(笑)。

- 糸井
- あ、ここで(笑)。
- 槇
- そうなんです(笑)。
岩塚村という村だったので、
その名前が付いた小学校で。
- 糸井
- 当時、このへんで大きい建物というと、
お稲荷さんと小学校くらいですよね。
- 槇
- あとは岩塚農協とかですかね。
- 糸井
- つまり、産業は「農業」ということですよね。
- 槇
- 農業なんです。
うちも農家でしたし、
ここからちょうど家が見えますけど、
対岸にある小っちゃな村にいくと、
私の「槇」という名前も
「平石」という名前もゴロゴロいます。
- 糸井
- そうですか。
それにしてもいい景色ですね、ここは。
まさに「うさぎ追いし、かの山」のような。

- 槇
- まあ、夏の時期はそうなんですけど、
これ、冬になるともう雪が2メートル以上‥‥。
- 糸井
- そうか。一面、雪に。
- 槇
- 冬になると2、3メートルは積もります。
そういう地域なんですね。
- 糸井
- 当時だと半分の季節が仕事にならないですね。
- 槇
- もう雪で仕事になりません。
なので男は出稼ぎに行くしかない。
農家といってもみんな五反百姓で、
要するに小規模農家。
それだけでは食べていけないんです。
- 糸井
- 出稼ぎしないとやっていけない。
- 槇
- そういう農家ばっかりでしたね。
私の小学校時代、
1クラスに45人くらいいましたけど、
冬休みが近づいてきますと、
自分の顔をクレヨンで描きなさいと
先生に言われるんです。
出稼ぎで家にいないお父さんのために。
- 糸井
- つまり、お父さんに送るために。
- 槇
- そうなんです。
送らずに持って帰るのは
同居している人だけでしたけど、
それもクラスで3人ぐらいでした。
あとはみんな出稼ぎですね。
工事現場や風呂屋、豆腐屋、大工さんとか。
- 糸井
- 石焼きいも屋さんもそうですよね。
- 槇
- ああ、そうですね。
ほとんどが豪雪地帯からの出稼ぎの人だと。
- 糸井
- ここにいる人たちは、
そういう暮らしが当たり前だったんですね。
- 槇
- 当たり前でした。
家を守っているのはおふくろ一人。
屋根の雪下ろしも年に7、8回やるわけですけど、
それも全部女性の仕事でした。
主婦が屋根に上がって雪下ろしをやるんです。
- 糸井
- 男の仕事じゃないと。
- 槇
- 冬に男がいませんので、出稼ぎで。
- 糸井
- そういうことですね。
- 槇
- 当時は消雪パイプや除雪車もありませんから、
道に積もった雪が溶けないんです。
だから毎朝、子どもたちが歩く道を
女性たちが早起きしてつくらないといけない。
- 糸井
- それを毎日、お母さんたちが。

- 槇
- だいたいおふくろの仕事でしたね。
もうそうするしかないというか。
諦めもあったでしょうけど。
- 糸井
- その生活をずっと繰り返してきた歴史があって、
でも、そんな村で産業を起こせたら、
男たちが出稼ぎにいかなくていいわけですよね。
- 槇
- ええ、ええ、まさに。
- 糸井
- そうやって立ち上がったのが、
槇さんのお父さんと平石さんのおふたり。
- 槇
- そうなんです。
(つづきます)
2023-11-13-MON