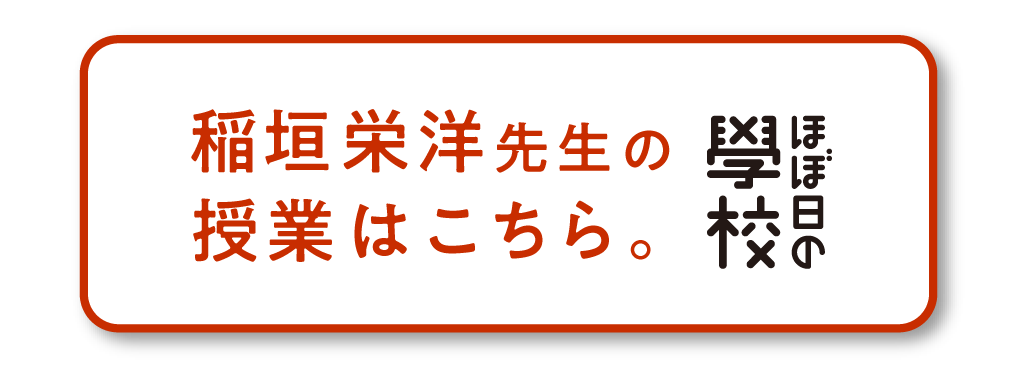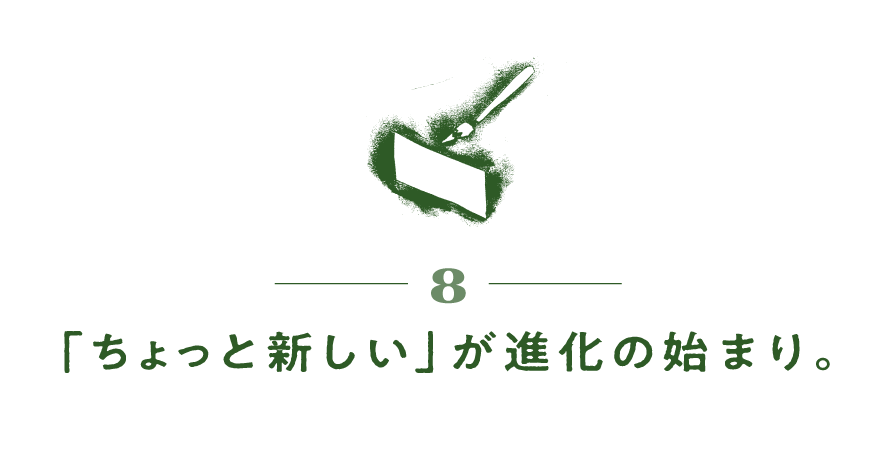あけましておめでとうございます。
とつぜんですが今年、ほぼ日は雑草に学びます。
農学博士(雑草生態学)の稲垣栄洋先生の
「ほぼ日の學校」でのお話や著書をきっかけに、
急速に雑草に興味が湧いてきた
糸井重里と、ほぼ日のメンバーたち。
さらにいろいろなお話を聞けたらと、
先日みんなで、先生が普段から研究をすすめる
静岡大学の藤枝フィールドに行ってきました。
そのとき教えてもらった、たのしくて、
元気のもらえる生物のお話の数々を、
新春第1弾の読みものとしてご紹介します。
雑草のように、戦略的にクレバーに、
やさしく、つよく、おもしろく。
さぁ、新年のほぼ日、はじまります。

稲垣栄洋(いながき・ひでひろ)
1968年、静岡県静岡市生まれ。
静岡大学大学院教授。農学博士。
専門は雑草生態学。
自称、みちくさ研究家。
岡山大学大学院農学研究科修了後、
農林水産省、
静岡県農林技術研究所などを経て
現在、静岡大学大学院教授。
『身近な雑草の愉快な生きかた』
『都会の雑草、発見と楽しみ方』
『身近な野菜のなるほど観察録』
『身近な虫たちの華麗な生きかた』
『生き物の死にざま』
『生き物が大人になるまで』
『手を眺めると、生命の不思議が見えてくる』
『敗者の生命史38億年』
など、その著書は50冊以上。
- 糸井
- 先生は『古池に飛びこんだのはなにガエル?』
という本も出されていて、
俳句や短歌にも興味がおありなんですよね。
- 稲垣
- そうですね。
俳句や短歌は生き物のことを詠んでることが
けっこう多くて、見ていくと
「昔の人、よく観察してるなあ」とか思うんです。

- 糸井
- ご自分でおやりになることもあるという。
- 稲垣
- そこは恥ずかしいんですけど(笑)。
- 糸井
- はじめたきっかけもあるんですか?
- 稲垣
- 10年ぐらい前、中学校の同窓会に行ったとき、
中学校のときの先生から
「お前、短歌やれ」って言われたんです。
そこで
「とりあえず10首作ってこい」と
宿題を出されまして、持っていったのが最初ですね。
- 糸井
- すごい先生ですね(笑)。
- 稲垣
- そうなんですよ。
卒業してもう何10年も経ってるんですけど。 - まぁ、なかなか難しくて、
そんなに作れてるわけじゃないんですけど。
- 糸井
- やろうとすると、難しいですよね。
- 稲垣
- ただ、俳句や短歌って
研究と似ているところがあるんですよ。 - 俳句や短歌って新しい目のつけ所とかが必要ですけど、
発想がぶっ飛びすぎてると、
相手に理解してもらえないんです。
逆にあんまり人と同じだと
「当たり前だよね」とか言われるんで、
人よりちょっと違う、新しいこととかが求められるんです。 - 研究も同じで、ちょっと新しいとか
みんなが気づかなかったところをやる。
それが俳句と研究ってすごく似てて。
- 糸井
- ああー。
- 稲垣
- ついでに言うと、生き物の進化というのも、
普通より飛びすぎちゃうとだめで、
「ちょっと違う」「ちょっと新しい」
みたいなのがはじまりだったりするんですよ。
そのあたりはすごく共通点を感じますね。
- 糸井
- 俳句や短歌って、ひとりで詠んでると思っても、
実は絶対に相手がいて。

- 稲垣
- あ、そうですね。
その「伝える」が難しいんですよ。
- 糸井
- 若いときには、
「読み手や受け手のことを考えずに
自分を表現しろ!」みたいな芸術論の影響を受けて、
そっちが純粋かのように思ったりもしますけど、
それって、ありえないんですよ。
- 稲垣
- 相手が受けてくれてはじめて、
発信になりますからね。
- 糸井
- あと、先人たちの見事な俳句や短歌でも、
実はフィクションが混じるものがやまほどあって。
- 稲垣
- そうですね。昔の人の俳句を読んでも、
「これ、事実とちょっと違うから
頭の中で作ったんじゃないの?」
とか考えるのも楽しかったり。 - まあでも文学なので、
フィクションがあってもいいと思います。
「ほんとはこうだったけど、
こうしたほうが文学的にいいよね」
という判断もあって、
それがまた表現を豊かにしてくれますし。
- 糸井
- ぼくも全くそう思うんです。
- 前は自分もどこか、
「俳句や短歌は、自分が
思ったことだけを書くものだ」
と思い込んでて、
「いまは何も思わなかったから」とかで
おしまいにしちゃうところがあったんです。 - でも、たとえばロケットの絵を描くにしても、
大抵はそんなによく見てもないし、
実はフィクションですよね。
だけど、それで描かれたロケットの絵も
それはそれでいいじゃないですか。 - 「そっか、俳句や短歌も同じようなことを
やってるんだな」って、
最近ぼくも思うようになったんです。
- 稲垣
- 糸井さんも俳句や短歌を作られるんですか?
- 糸井
- 今年、夏井いつき先生にお会いしたことを
きっかけに、俳句をはじめたんです。 - だけどやっぱり本当に難しくて、
作るのはほとんどできてないんです(笑)。
ただ、俳句論を読むのが
めちゃくちゃにおもしろくて。
- 稲垣
- わかります。
人の作品を見るの、私もすごい好きなんですよ。 - 将棋で「見る将」ってあるじゃないですか。
自分は将棋を指さないけど見るのが大好きという。
私もそういう感じがあって、
自分ではなかなか作れてないですけど、
人の俳句とか短歌とかを見るのは
すごい好きなんですね。
- 糸井
- そう。おもしろいですよね。
- ただ、ぼくもそういう感じなんですけど、
「やっぱりそれじゃいけないんじゃないか」
みたいに、勝手に思ってて。 - だから先日、夏井先生にもう怒られようと思って
「俳句やりますって宣言しましたけど、
実はちっとも作らずに、そういう本ばかり
読んでるんです」って告白したら、
「いいんです」って言われたんですよ。 - 「それはそれで俳句をやってるということです」
みたいに言ってもらって、
「あ、よかった」と思って。
- 稲垣
- なるほど、なるほど。
- 糸井
- なんだかそのときに
「作らないとだめ」という自分の発想も、
近代の教育のなかで学んだ
思い込みだったかもしれないなと思ったんです。 - 自分みたいな人間にも、
自分で自分を閉じ込めてる枠が
いっぱいあるんだなって思いましたね。

- 稲垣
- やっぱり学校って、特に「揃える」場所なので、
そこで学んだ私たちって、
「揃えなきゃ」という発想が
けっこう考え方の前提にあるんですよね。
- 糸井
- そうなんですよ。
- 稲垣
- 農業もまさにそうですけど、
管理する人からすると
「揃える」ってすごく大事なんですよね。 - だからそういうときに揃えられる側が、
揃えられながらも
「ほんとは違うんだけどね」ということを、
同時に思っていく必要が、おそらくあるというか。 - 若い人たちにも、そこは伝えたいんですよね。
「成績としてはこうだけど、
それは私の先生という視点での評価であって、
あなたの評価じゃないからね」って、
最初からみんな知っておくといいんじゃないかなって。
- 糸井
- やっぱりその「これは枠だよ」を
言いながらやるのがポイントかもしれないですね。 - お互いに枠であることをわかりながら、
「それはそれとして、ぶつかろう」っていう。
もしかしたらいま、そういうやり方が、
いちばんおもしろいような気もしますね。 - 枠は枠として学んで、
自由にやることは自由にやることとして
楽しんで、という。 - 同時にぼくらのまわりには、
雑草みたいな先生が、いつもいるわけですから。
- 稲垣
- そうですね(笑)。
雑草を見ていると、どれが普通かわからなくなって、
「あ、なんでもありなんだ」ということに
思いを馳せることができますから。
 岩の隙間で咲くスミレのなかま。
岩の隙間で咲くスミレのなかま。
雑草コラム08
ナンバーワンか、オンリーワンか。
(「ほぼ日の學校」稲垣先生の授業より)
「ナンバーワンとオンリーワンの
どちらがいいか?」みたいな話って
あるじゃないですか。
「オンリーワンでいいんだ」とか、
「いや甘い。世の中は競争社会だから
やっぱりナンバーワンじゃなきゃ」とか、
2つの考え方がある。
生物の世界って、もう答えが出てまして。
生物の世界では基本的に、
ナンバーワンじゃないと生き残れないんですよ。
人間の世界ならナンバーツーでも銀メダルだし、
業界3位ってけっこうなものですけど、
生物の世界はナンバーワン以外はダメ。
とにかく、1番になって勝たないといけないんです。
でもそう言われると、最終的に
1種類しか生き残れない気がしますよね。
なのに自然界には、たくさんの生き物がいるわけです。
理由は何かというと、ナンバーワンになる方法が
たくさんあるからなんです。
すべての生物がどこかの部分でナンバーワンで、
自分が勝てる場所をかならず持っている。
多様性ある世界が実現してるのは、
勝ち方が多様だからなんですよね。
で、それぞれの生物が、自分がナンバーワンに
なれるところにひとつひとつ入っていく。
そういうナンバーワンになれる条件のことを
生物学の世界では「ニッチ」と言うんですね。
「ニッチ」って、ビジネスの世界などでは
「隙間」みたいな意味ですけど、
生物学用語では
「その生物がナンバーワンになれる居場所」を
指す言葉なんです。
「ナンバーワンになれる場所」って、
生物ごとに固有なんです。
つまり、それってオンリーワンなんですね。
だから「ニッチ」というのは、
それぞれの生物がナンバーワンになれる、
オンリーワンな場所のこと。
そんなふうにすべての生物が、
絶対に負けない、自分の得意なところで生きてる。
そういうのが生物の世界なんですね。
人間の世界にしても、
ナンバーワンになる方法はたくさんあって、
みんなが自分の得意を活かして
ナンバーワンになれる「ニッチ」の場所って、
それぞれきっとあると思うんです。
だからたとえば学校の成績が悪かったとしても、
自分が勝てるものさしを見つければいいんですよ。
もちろん簡単なことではないですけど、
自分の得意が発揮できる
「ここならが勝てる」というものさしを
探し続けて、そこにピッタリはまる努力をする。
生物の世界も、それをやって成功した
生物だけが生き残ってますから。
だから、そういう
「ニッチ」の場所を探していく。
人間もそういうことが重要なのかな、
なんて思ったりしています。
(つづきます)
2025-01-09-THU