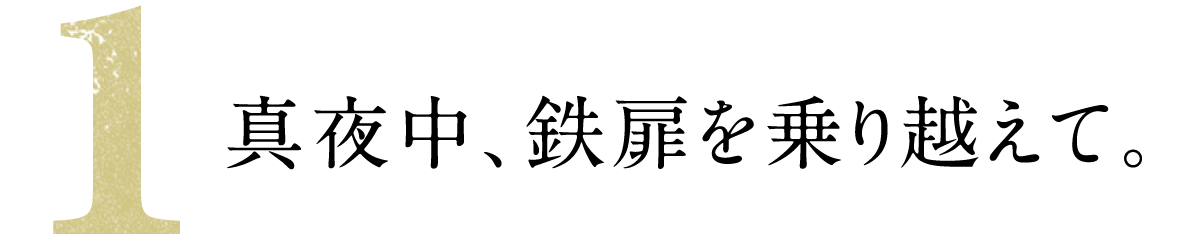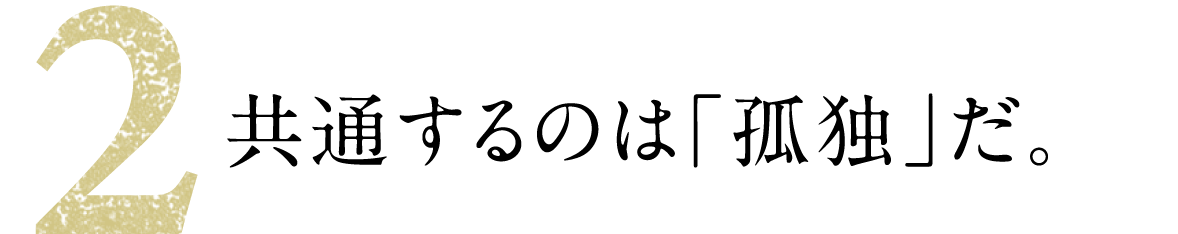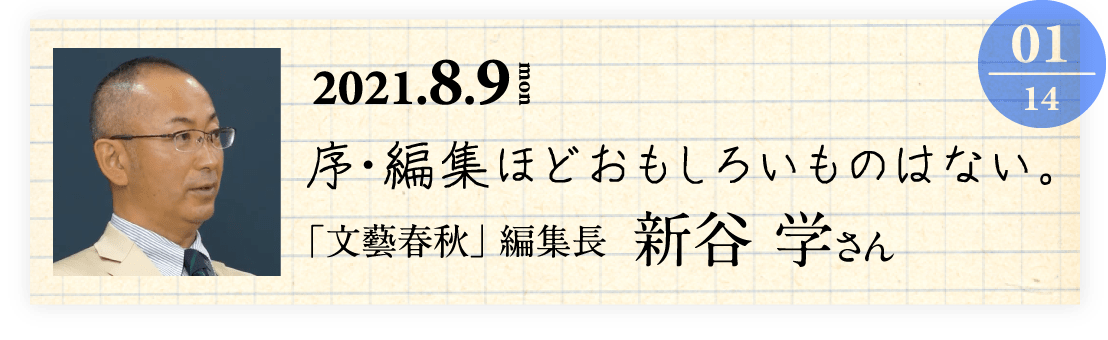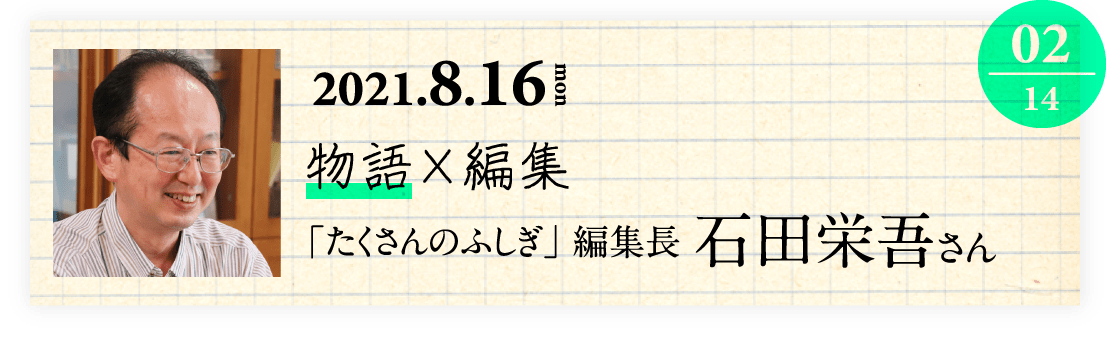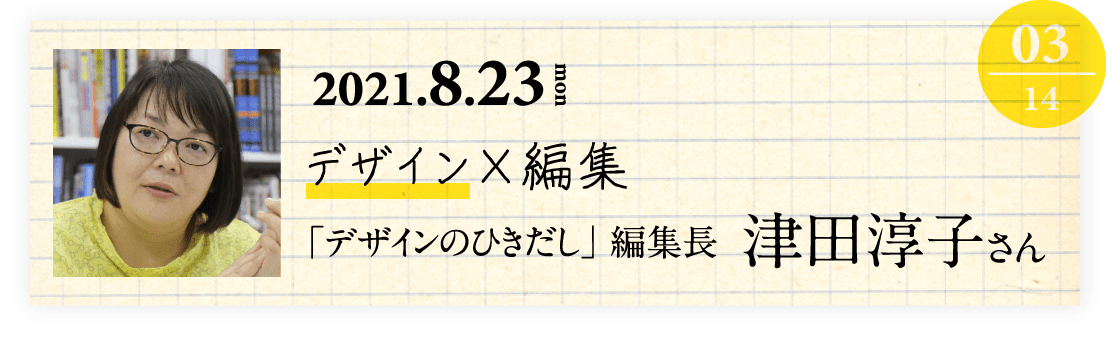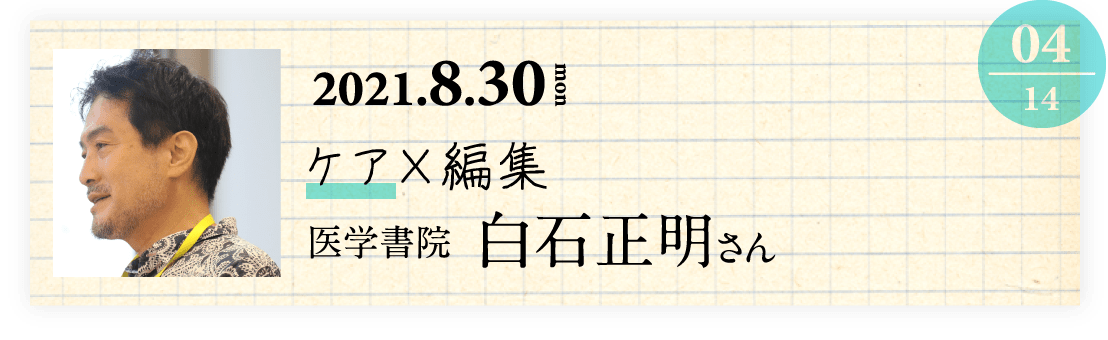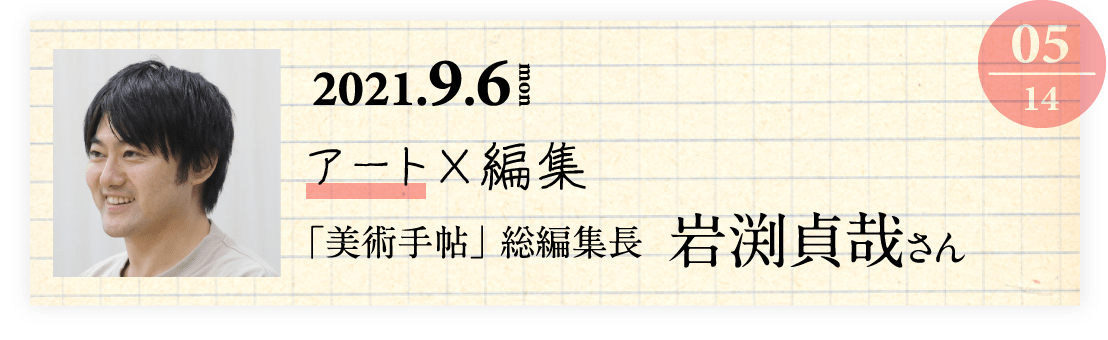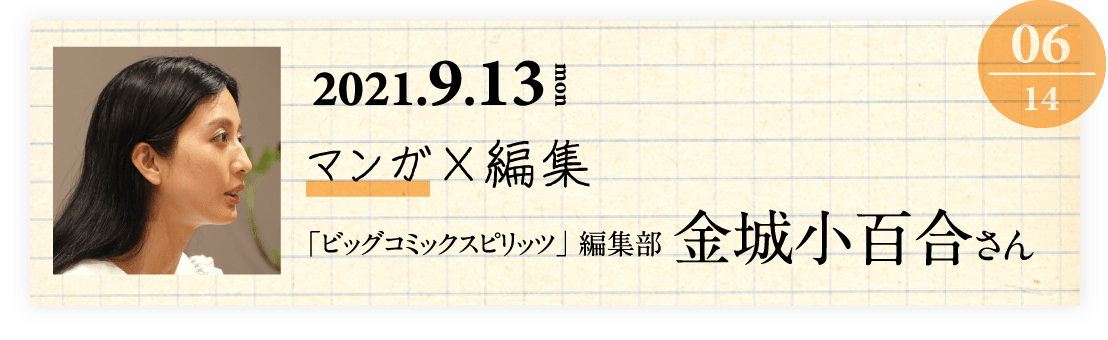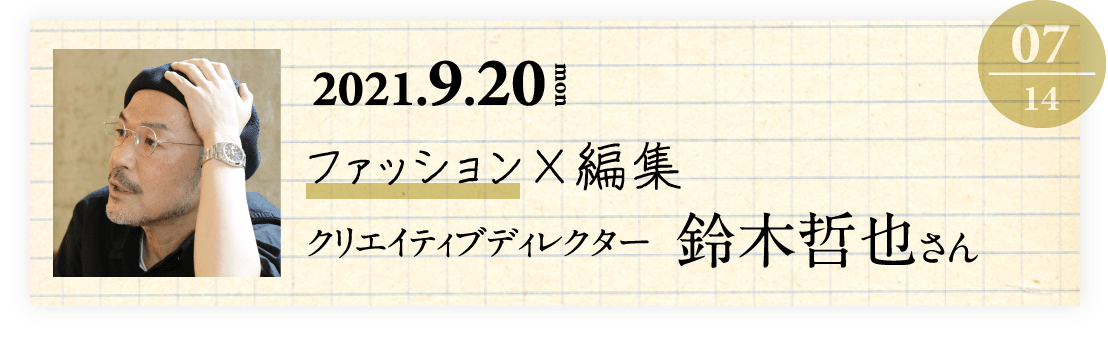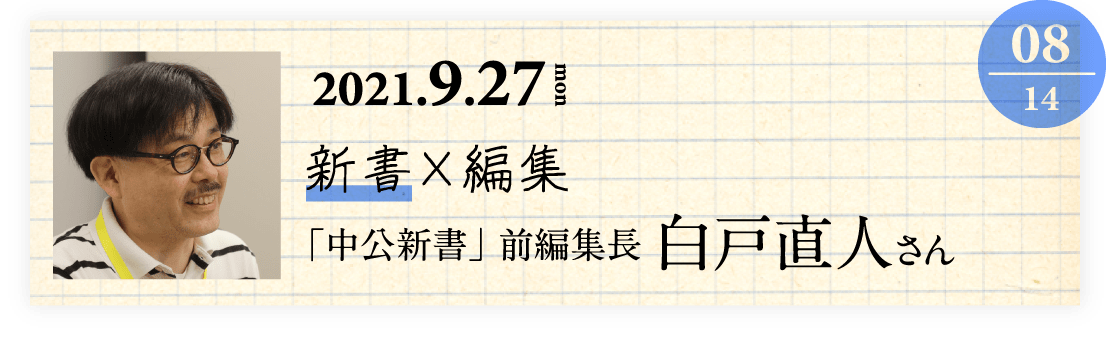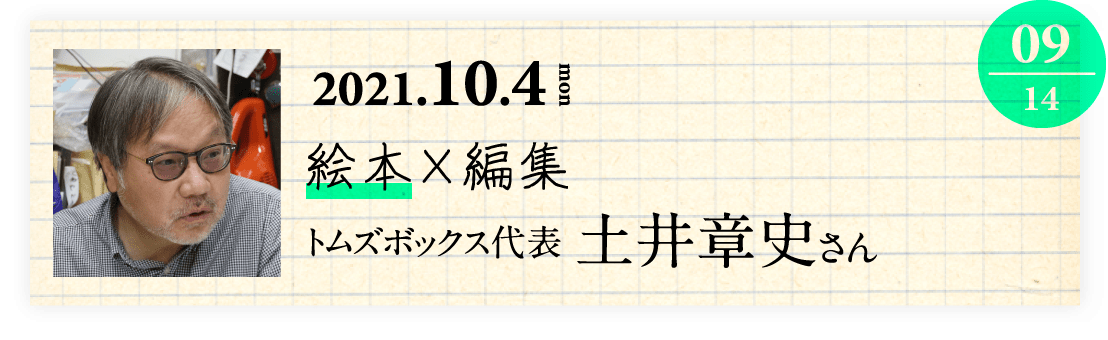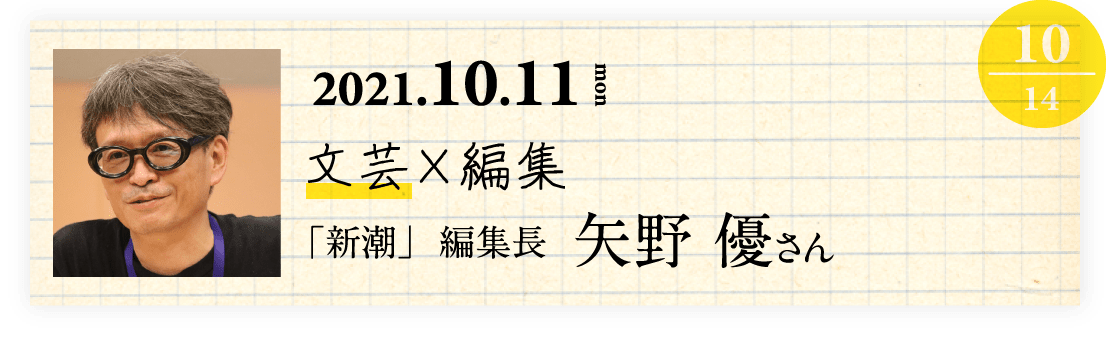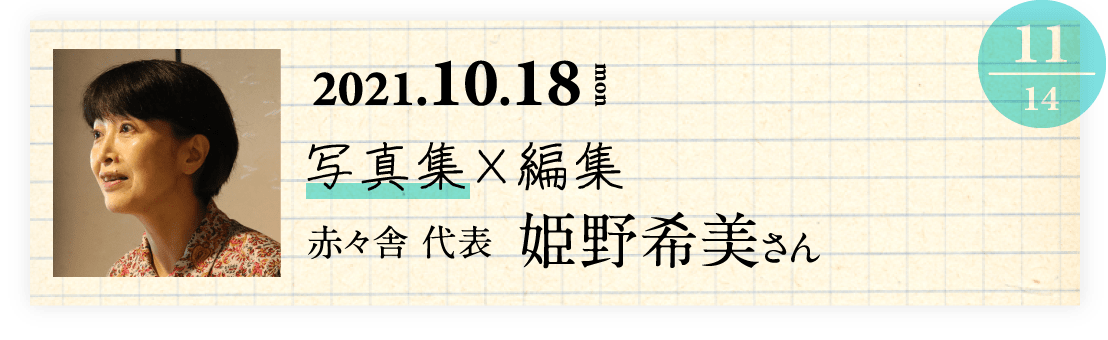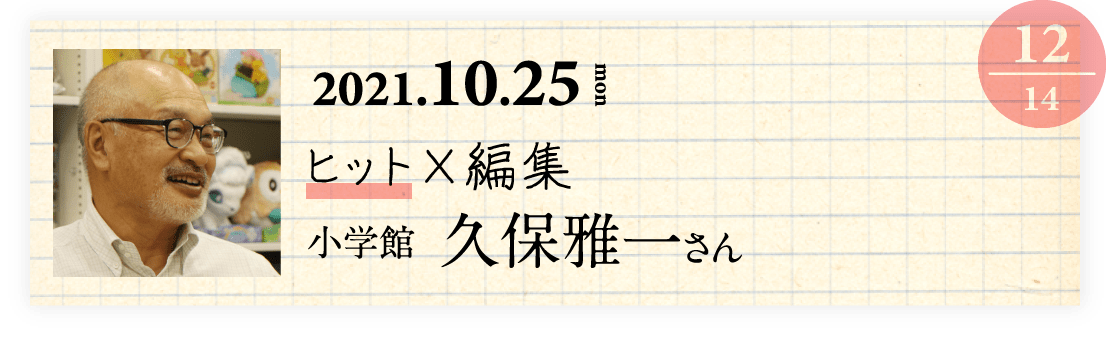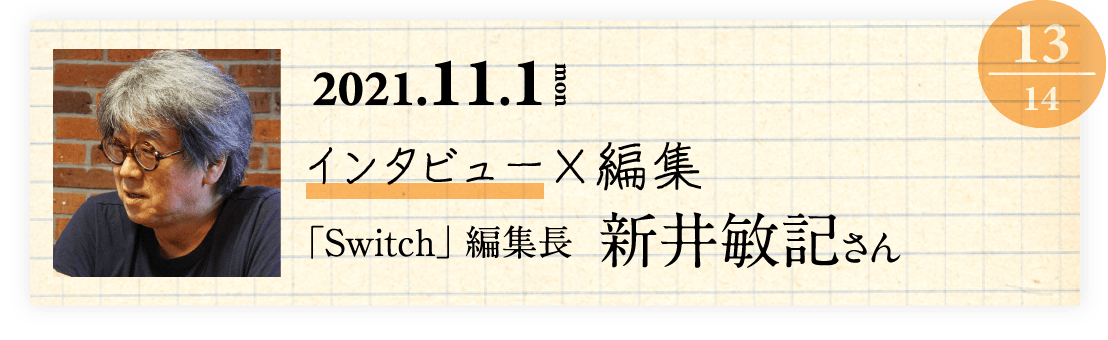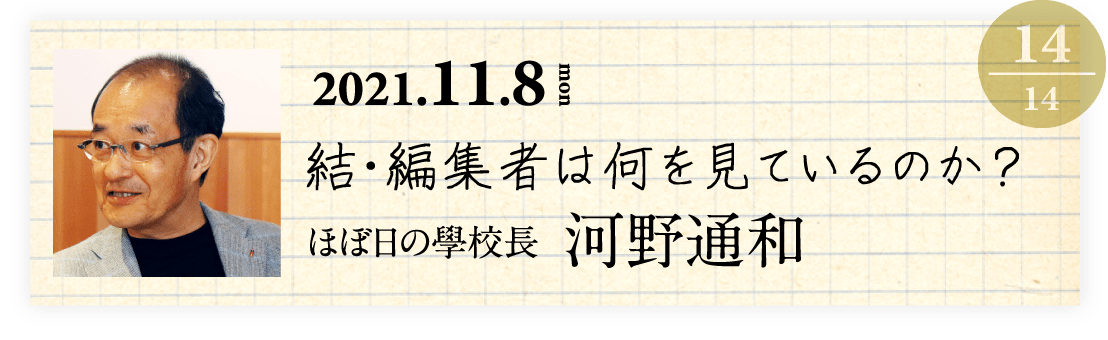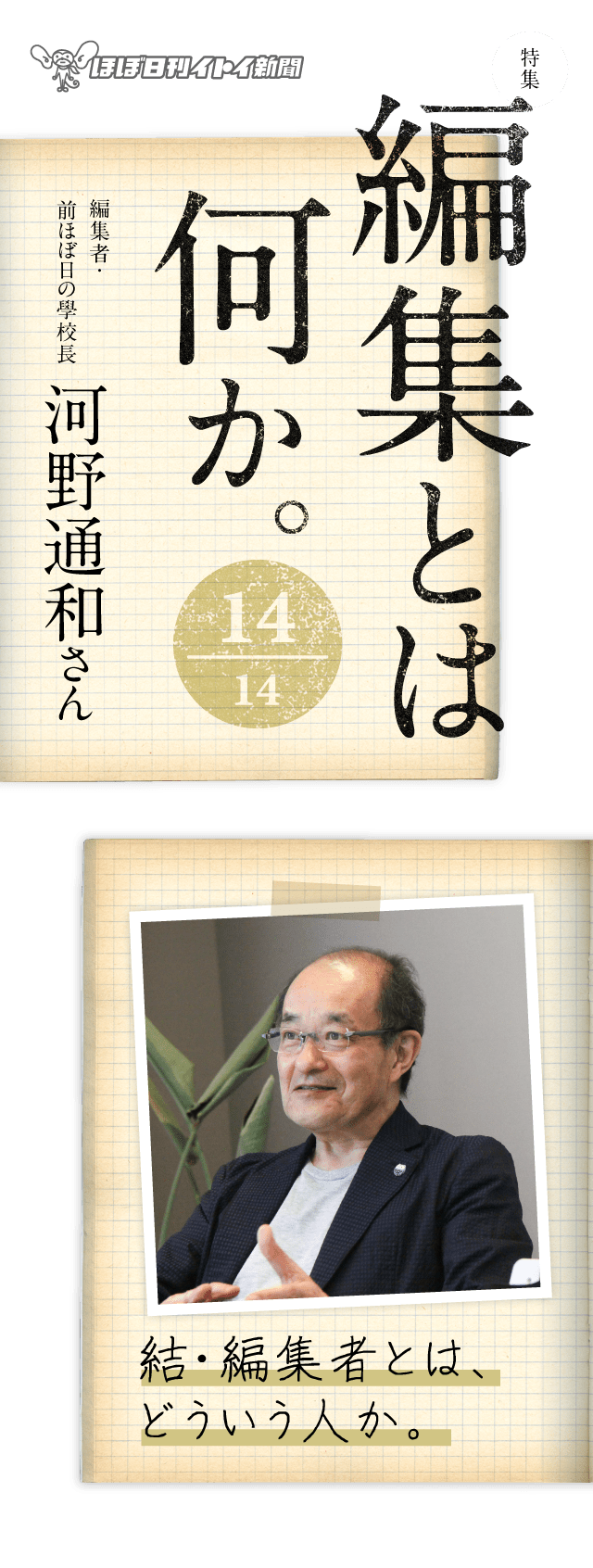
特集「編集とは何か。」最後はこの人、
前ほぼ日の學校長である河野通和さんです。
野坂昭如さんはじめ
一癖も二癖もある大作家たちとの交流、
編集者としての河野さんをつくったという
ふたりの先輩のこと。
そしていま、あらためて
「編集者とは、どういう人か?」について、
言葉にしていただきました。
とても身近だけど、
いちばん遠くに感じる編集者の、編集論。
担当は「ほぼ日」奥野です。
河野通和(こうのみちかず)
1953年、岡山市生まれ。東京大学文学部ロシア語ロシア文学科卒業。1978年、中央公論社(現・中央公論新社)入社。「婦人公論」「中央公論」編集長を歴任。2008年6月、同社を退社。株式会社日本ビジネスプレス特別編集顧問を経て、2010年6月、新潮社に入社。季刊誌「考える人」編集長。2017年3月、同社を退社。同年4月、ほぼ日に入社。「ほぼ日の学校(學校)長」を務め、このほど10月末日をもって退社。著書に『言葉はこうして生き残った』(ミシマ社)、『「考える人」は本を読む』(角川新書)がある。
- ──
- これまで、13人の編集者のみなさんに
お話をうかがってきて、
どのかたも本当に
個性的で、おもしろくて、才能があって、
心から感服したんですが。
- 河野
- そうですねえ。
- ──
- ぼくの思い描いている「ザ・編集者」を
ひとりだけ挙げるとすれば、
まさしく目の前の河野通和さんなんです。
- 河野
- えっ、そうなんですか。
- ──
- 博学で、いろんな人とお知り合いで、
おもしろい本をたくさん知っていて、
ぼくの好きな「雑誌」出身で、
文章を書いても、すばらしいという。 - なかでも自分にまったくないものとして
いわゆる「編集者」の仕事で
思い浮かべやすい、
作家の担当編集も多くなさっていますし。
- 河野
- いわゆる文芸編集者ではないんですが、
わりに多くの作家を担当しました。 - 作家という人種に、興味がありました。
- ──
- 自分が唯一担当させていただいた作家は、
亡くなられた百瀬博教さんなんですが、
ただ、そのときは
純粋な文章の企画ではなく、
ポラロイドの写真日記の連載だったので。
- 河野
- これまたユニークだなあ(笑)。
逆に、その話を聞きたいくらい。
- ──
- 毎月『PRIDE』の格闘家などと撮った
写真を受け取りに行っていたので、
いただいた原稿を、
その場で、
その作家の前で読む‥‥という経験は、
まったくないんです。 - これまで河野さんは、たとえば、
どんな作家さんを担当されてきましたか。
- 河野
- そうですね、いろんな人がいましたけど、
ぼくは、なぜだか
悪筆の作家の担当になることが多かった。 - たとえば水上勉さんや黒岩重吾さんは、
とにかく、肉筆の原稿が「読めない」。

- ──
- 石原慎太郎さんの字なんかも有名ですが、
そうなんですか‥‥読めないレベル。
- 河野
- 当時は、肉筆原稿が届いて、赤入れして、
印刷所にそれを届けて、
そこでオペレーターさんが打つんですよ。 - 原稿のままだと、オペレーターさんが読めない。
そこで、黒岩さんの原稿の場合は、
ぼくが別に清書したものを用意し、
水上さんの場合は、
肉筆の脇に添え書きをして届ける。
そうでないと、入稿できなかった。
- ──
- それほどまでに。
- 河野
- 黒岩さんは、
締め切りどおりに原稿をくださる方で、
清書して入稿する時間もとれたので、
よかったんですが‥‥
水上さんは、いつもギリギリなんです。 - 『良寛』という連載小説では、
禅の世界の話が延々と綴られていて、
昔の偉い禅僧の言葉が引用されていたり、
字が読めないうえに、
書かれている内容も難しくてわからない。
- ──
- 手強い!
- 河野
- そう、だからせめて、
何という文献から引用なさっているのか、
教えてもらえたら助かるんだけど、
「まあ、そういうことはな、
うーん、
そのうちおまえにも教えないといかんが」
とかむにゃむにゃおっしゃって、
なかなか教えてくれない。ネタ本だから。
- ──
- 想像を絶する世界です(笑)。
- 河野
- だから、毎回、ギリギリまで
解読したり調べたりで、
非常に苦労した思い出があります(笑)。 - 作品を味読するより何より、
滑り込みで、
印刷所に入れられるか入れられないかが、
最大の問題だったんです。
- ──
- でも毎回、なんとか解読して、入稿して。
- 河野
- 水上さんは原稿を渡してくださるときに、
怖い決まり文句があるんですよ‥‥。
- ──
- 怖い。
- 河野
- 「これで渡すけど、
ゲラになったら締めるから」
って、いつもおっしゃるんですよね。 - この「締めるから」っていうところが
怖いんだよ(笑)。
ゲラで手を入れるという意味ですから。
- ──
- つまり、また、難読の修正が‥‥。
- 河野
- しかも、今度はゲラの狭いスペースに、
細かく書き込まれてくるわけです。 - 基本、原稿はその場で読むので、
対面していただいた場合はすぐに尋ねます。
でも、
預けてある原稿を受け取ったりするときは、
わからないから電話をするんですが、
当時は携帯なんてないし、
真夜中じゃご自宅に電話できないから、
入稿ギリギリの翌朝に電話すると、
すでに水上さんは、
旅行に出かけてしまって不在‥‥とか。
- ──
- 原稿も終わったしということで(笑)。
- 河野
- 印刷所から、旅先に電話したりしてね。
- 出張校正室に電話機が一台しかなくて、
しかもオペレーターが帰った夕方以降は、
市内通話しかできない電話だから、
十円玉をごっそりポケットに入れて、
旅先の水上さんに赤電話をかけに行って。
死にそうでした(笑)。
- ──
- 死‥‥河野さんがおっしゃるんだから、
相当ですね(笑)。 - そんなに大変だったら、
連載が落ちちゃったことなんかも‥‥。
- 河野
- 幸い、それだけは免れました。
- ──
- おお、なんとかしてたんですか。
- 河野
- 野坂昭如さんの担当をやってたときは、
毎回40枚の原稿をいただいてましてね。 - 野坂さんから
それだけの枚数の原稿を取ろうなんて、
至難の業だぞ、いい度胸だって、
他社のベテラン編集者に脅されたんです。
だからよけいに、
絶対に落としてなるものか、と思って。
- ──
- 野坂昭如さん‥‥また手強そう。
- 河野
- のちに新潮社でたいへんお世話になる
先輩編集者が、
『小説新潮』で「野坂番」だったとき、
創刊500号の記念号で
野坂さんに短編を依頼しました。 - そのときの編集長が渾身の力をこめて、
編集部が総力をあげてつくった号でした。
結局、野坂さんの原稿は、落ちたんです。
- ──
- わあ。
- 河野
- 野坂番だったその先輩は、
深夜、名古屋までタクシーを飛ばして
野坂さんに迫ったんだけど、
タイトルと
最初の1ページの原稿が入っただけ。 - 編集長は怒り心頭に発し、
野坂さんの「読者へ」というお詫び原稿を
そのまま掲載して、
天下にその事実をさらしたんですよ。
- ──
- えっと、つまり‥‥。
- 河野
- 書かれるはずだった短編のタイトルと、
書きだしの1ページ。 - あとは、
野坂さんのお詫びの手書き原稿がそのまま、
予定のページ数を埋めていくというね。

- ──
- ひゃあ‥‥現代アートみたいな。
- 河野
- 業界が騒然となりました。
- 豪華執筆陣の作品がズラリと並ぶ中で、
異彩を放つこと!
読者としては、
たまらなくおもしろかったんですが、
いつわが身に
同じような悲劇が起こらないとも限らない。
矢野優さんの第3回に、
このエピソードが紹介されてますね。
- ──
- あ、悔しがった編集長さんが、
ナイフでソファをグサグサ刺した‥‥! - あの話につながるんですか。
- 河野
- 中上(健次)さんなんかも、
広告のチラシの裏に書いてきたりとか。 - まあ、いろいろありますよ。
- ──
- 中上さんといえば、
ちびた煙草をくわえて、
新宿の「ブラジル館」という喫茶店で
執筆しているモノクロ写真が、
なぜか印象に残っているんですけれど、
チラシの裏‥‥ですか。
- 河野
- ふつうは原稿用紙に400字のところ、
1枚の紙に2000字くらい
ギューッと詰めて書いてあったとかね、 - そういう「伝説」というかな、
編集者の
泣くに泣けない話なら山のようにあります。
- ──
- 泣くに泣けない(笑)。
- ぼくが出版社に入った時点で、
すでにDTP化がはじまっていたので、
ほとんど経験がないのですが、
各版元の編集者が、
原稿を持って
校了ギリギリの印刷所に詰めるのとか、
想像するだに大変だったろうな‥‥と。
- 河野
- そのころは、校了間際の雑誌は、
出張校正と言って、
印刷所内の小部屋に出向いて作業しました。
そこで、各社の人間が顔を合わせるんです。 - たとえば大日本印刷には、
ぼくのいた『中央公論』の部屋の他に
『文學界』『海燕』『文藝』
『朝日ジャーナル』『アサヒ芸能』‥‥
と、出張校正室が並んでいたんですね。
各雑誌が、同じ場所で、
最後の追い込みをかけていたんです。
- ──
- 大変さを知らない身には、
すっごくおもしろそうです、その場所。
- 河野
- 赤電話の前には中上番、野坂番‥‥と、
あ、今月もどうも、みたいな感じで、
十円玉を握りしめた編集者が集まってくる。
- ──
- 「いつもの人たち」が。
- 河野
- 印刷所に1台だけあったファックスが
ジジーィッと鳴ったら、
みんな「誰の原稿だ、俺の原稿か」と
色めき立つんだけど、
書かれた文字を見れば一目瞭然だから、
「あ、違った。山田詠美さんだ」
とか言って、ため息をつくという(笑)。
- ──
- 仲よくなりそうですよね。
そんな経験を共有したら。
へんな時間帯でしょうし。
- 河野
- うん、他社の編集者と
赤電話仲間やファックス仲間になって、
こんど飲もうかって話にもなる。 - 戦友だよね。
原稿をもらうときも、各社の編集者が
ご自宅の応接間なんかで待つわけです。
たとえば、井上ひさしさんの場合は、
これが『小説現代』ね、
これが『婦人公論』ね‥‥って、
ちょっとずつ渡されていくわけ(笑)。
- ──
- ひなにご飯をやる親鳥のような(笑)。
- それってつまり、井上ひさしさんは、
こっち書いてできたところまで渡して、
次に、
こっち書いてできたところまで渡して、
というふうにしていたんですか?
- 河野
- すごい才能だよね。
- いまは、パソコンで書いて送信だから
その部分は不可視になってる。
執筆現場に編集者がいるわけじゃない、
原稿を送受信するのもインターネット。
- ──
- ええ。
- 河野
- でも、かつては、そこがすべて、
リアルな場所で行われていたんですよ。
ぜんぶが「見える」わけ。 - A社の担当者はこいつかっていうのも
見えるし、
B社の編集者の
追い込まれ具合も手にとるように‥‥。
- ──
- 作家の先生のお宅には、
編集者を待たせる部屋のような場所が、
あったってことですか。
- 河野
- そうですね、待ち部屋。
- ただ、野坂さんの場合は、
仕事関係を
ご自宅の中に持ち込まない主義なので、
すべてが「玄関先」でした。
だから、ぼくは、
夜中にその門を何度も乗り越えています。
- ──
- はい、噂では(笑)。
- 河野
- 真夜中に、門を乗り越えて庭先にまわって
雨戸をトントンて叩くんです。
「野坂さーん」って呼びかけながら(笑)。
- ──
- それで、出てこられるんですか?
- 河野
- 出てこられたためしはないです(笑)。
- ──
- でも、一応やるんですね(笑)。
- 河野
- これ、ご近所の方に
通報されたらアウトだと思いながらね。 - 杉並の住宅街の坂を上がっていって、
立派な門がまえの家の鉄扉を、
夜中に男が乗り越えていくわけだから。
ぼくは、野坂番になってすぐ、
下宿を
野坂さんのうちの近くに移したんです。
みんなに、そうしたほうがいいって。
- ──
- 真夜中に高い門を乗り越えて
雨戸を叩くこともあるから、と(笑)。
- 河野
- そう(笑)。あるとき野坂さんが
週刊誌のコラムに書いていたんですが、
最近、
中央公論社に入った若い編集者が、
月半ばになると、ニコニコしながら
自分のところに足しげく通ってくると。
- ──
- ニコニコしながら‥‥足しげく‥‥
途中で
閉ざされた鉄扉を乗り越えて(笑)。
- 河野
- まあ、愛想はいいほうだとは思うけど、
ニコニコとは‥‥(笑)。 - でも、野坂さんって、
本当に、人徳のある方だったんですよ。
だって、
そういう大変な思いをした挙げ句、
やっと原稿を受け取るわけですよ。
ふつうは腹も立つでしょうに、
「今月も、ありがとうございました!」
という晴れやかな気持ちになるんです。
- ──
- そうなんですね(笑)。
- 河野
- とにかく、いろいろ大変だったけれど、
今月もぶじにゴールしましたね、
という深い感慨を、毎回抱くんですよ。 - またひどい目にあわせやがってだとか、
そんふうにはぜんぜん思わず、
すごく、いい気持ちになるんです。
- ──
- なんででしょうね(笑)。
- それが「人徳」というものなのかなあ。
作家という人たちの魅力というか。
- 河野
- 根本のところでの、
野坂さんの品のよさ‥‥というのかな。 - 原稿を終えたよろこびを、
ともにわかち合える感じがするんです。
- ──
- 一緒に険しい山を登りきった仲間意識、
みたいな感じですか。
- 河野
- そうそう。
- 「来月はもっと早めに仕上げますから」
とか、ボソボソおっしゃる。
「一気呵成にやりますから」とか。
その約束が守られたことって、
まあ‥‥ついぞなかったんですが(笑)。
- ──
- ええ(笑)。
- 河野
- そういうところも、好きだったんです。

(つづきます)
2021-11-08-MON
-
河野通和さんから、読者のみなさんへ。

「10月末日をもって、ほぼ日を退社しました。
このシリーズの企画が立ち上がった春先には、
まだ退社の考えもさらさらなく、
インタビューを受けたのが、
退社を決めたひと月後。
内々の決定事項だったので、
記事をまとめる担当者の奥野さんに
その事実を伝えたのが、10月に入ってから。
そして結局、
記事の公開が退社後ということになりました。
目下、新潮社時代以来の大荷物
(本と資料の山ですが)を詰めた段ボール箱が、
まとめて運び込まれた一室を
バリケードのように占拠しています。
これを一つ一つ開梱しながら、
「この先」のことを
ぼんやり考えている状況です。」
(河野さん)写真は「ほぼ日」最後の日、
イベント「フェニックスブックス」終了後の
打上げのようす。
河野さん、これから、何をはじめるのかなあ。
ワクワクしつつ続報を待ちたいと思います!
河野さん、これまで
「ほぼ日」にたくさん刺激を与えてくださり、
ありがとうございました。
-
「編集とは何か。」もくじ