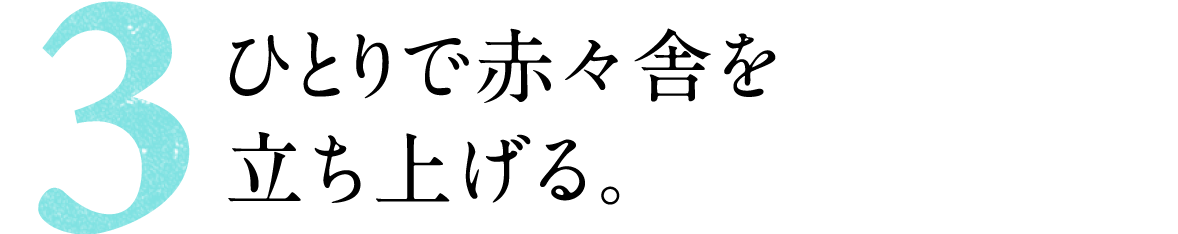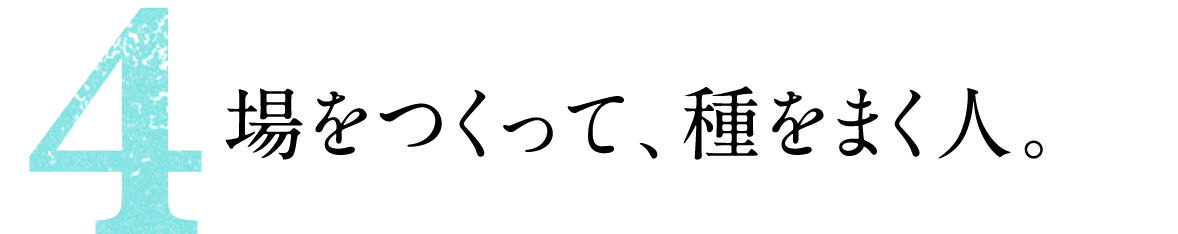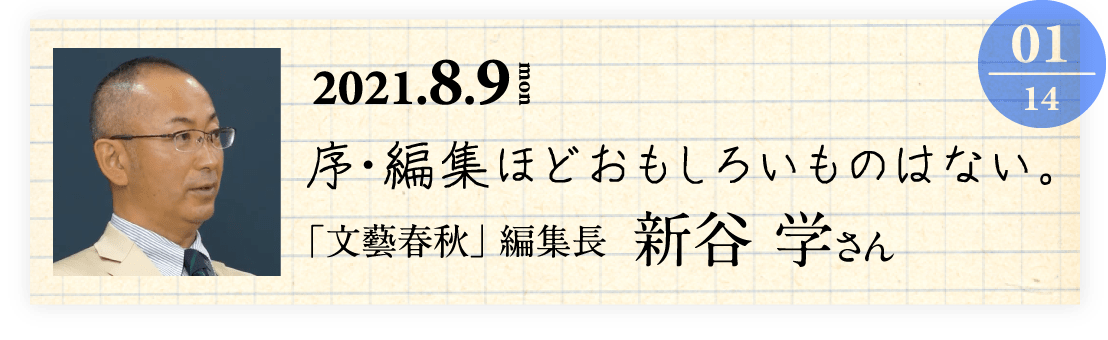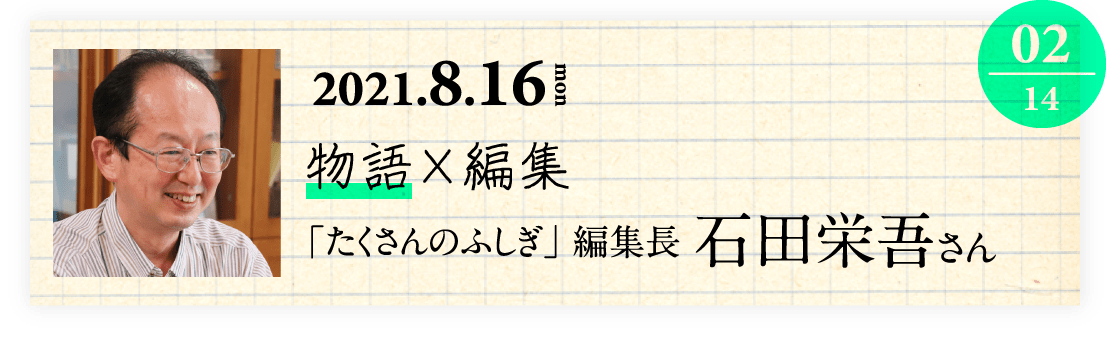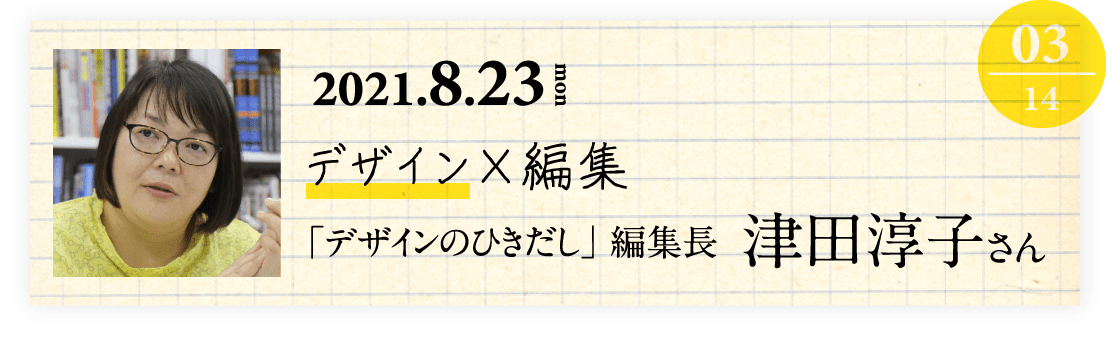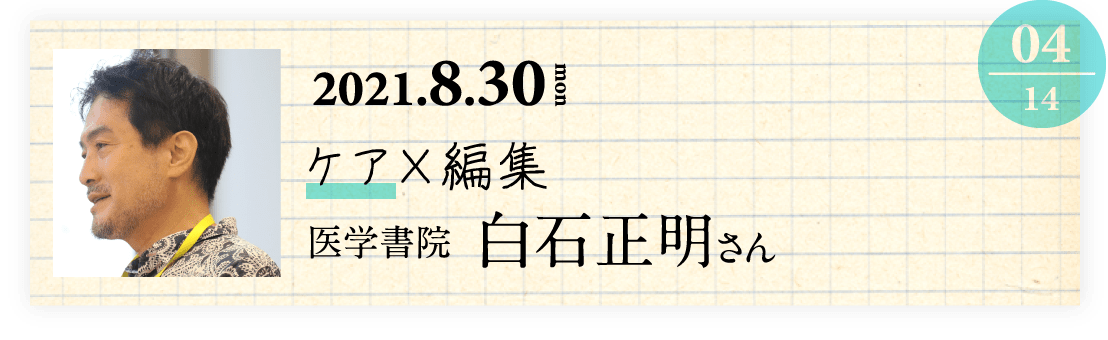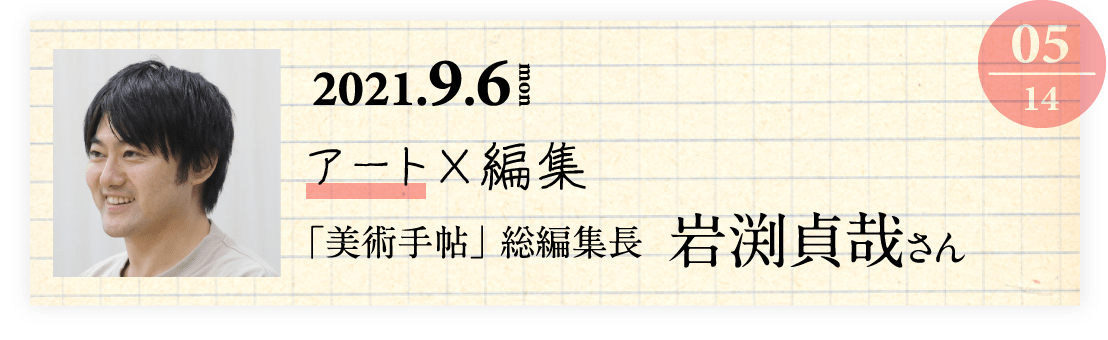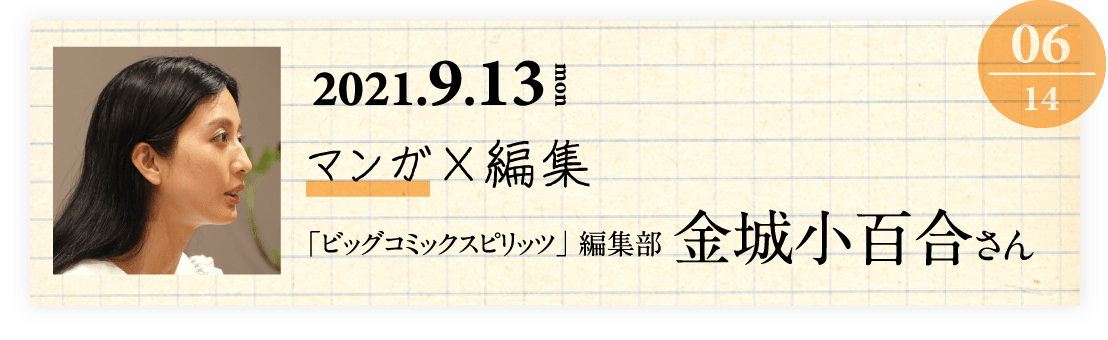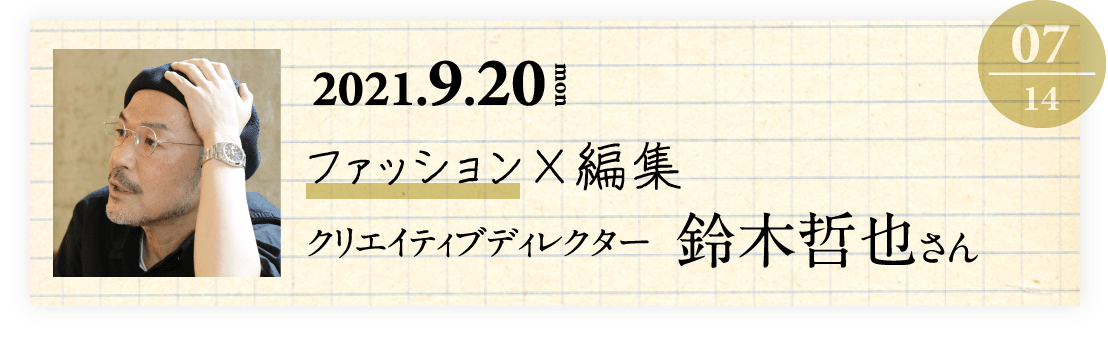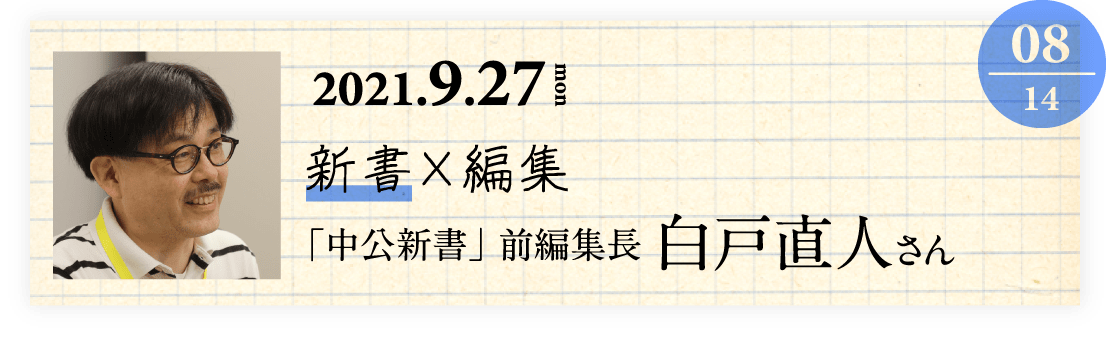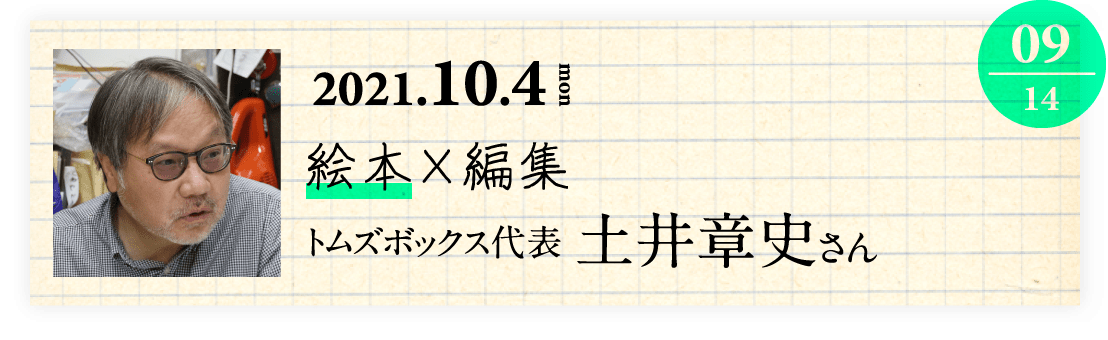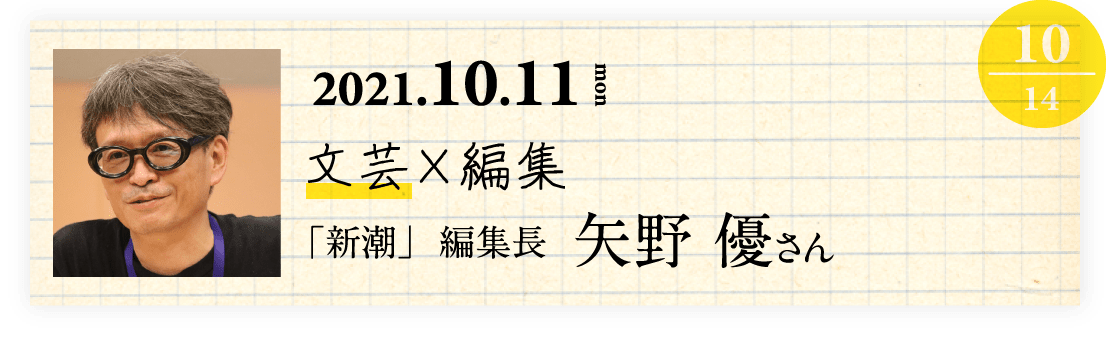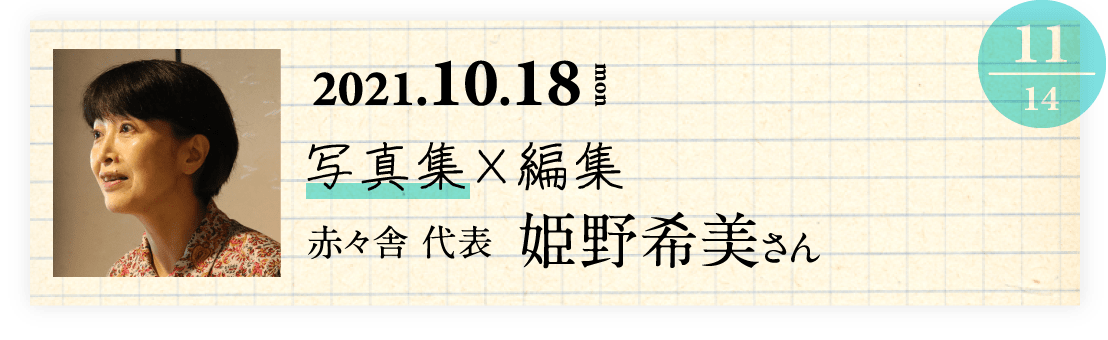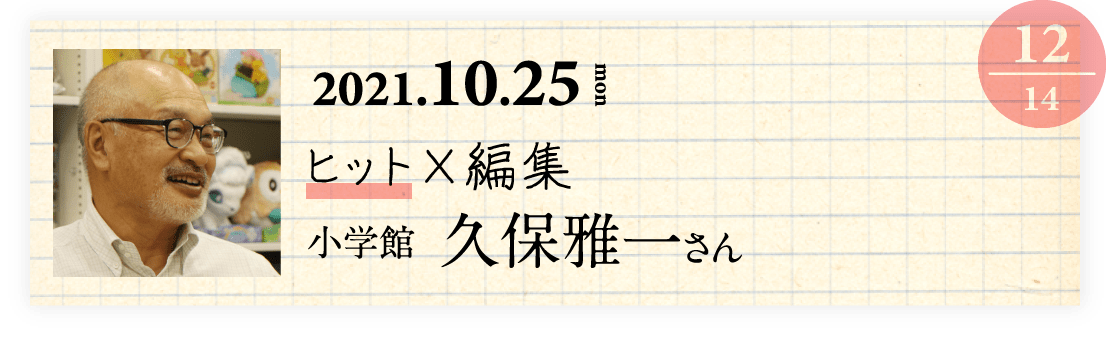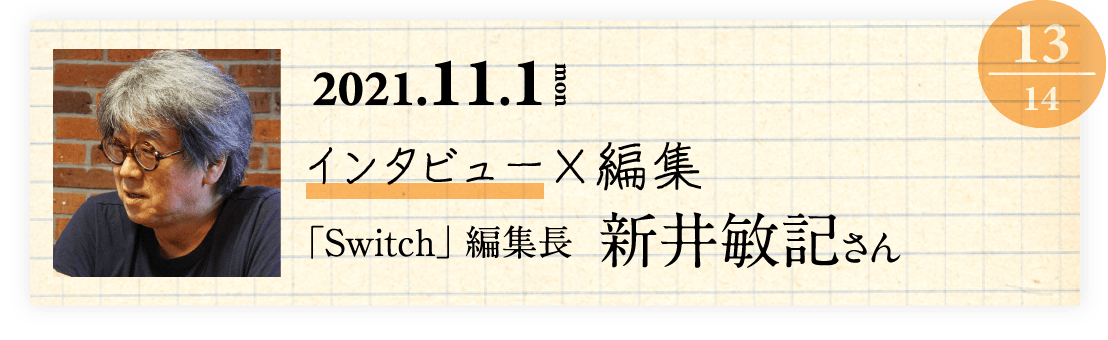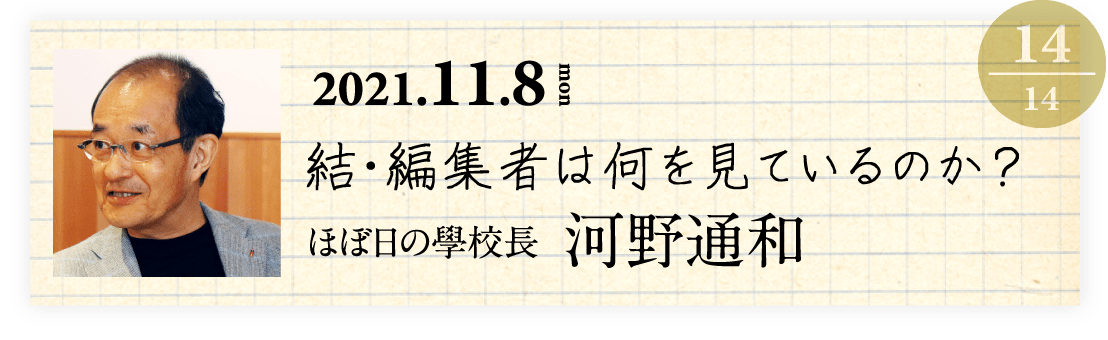これまで、木村伊兵衛写真賞の受賞作を
たくさん手がけてきた
出版社・赤々舎の代表、姫野希美さん。
編集者と言われることに、
「ずっと、抵抗があった」そうなんです。
和歌の研究を志していた学生時代、
旅先の「上海の人の顔」に衝撃を受け、
ここに住みたいと思い、
現地で不動産屋をつくってしまったこと。
出版社でアルバイトをはじめ、
いきなり舟越桂さんの作品集を企画して、
1年かけてつくったこと。
写真との出会いから、赤々舎の設立。
じつにおもしろい半生をうかがいました。
担当は「ほぼ日」奥野です。
姫野希美(ひめの・きみ)
大分県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。2006 年に赤々舎を設立。写真集、美術書を中心に200冊余りの書籍を刊行。第33回木村伊兵衛写真賞の志賀理江子『CANARY』、岡田敦『I am』、第34回同賞の 浅田政志『浅田家』、第35回同賞の高木こずえ『MID』『GROUND』、第38回同賞の百々新『対岸』、第40回同賞の石川竜一『絶景のポリフォニー』『okinawan portraits 2010-2012』、第43 回同賞の藤岡亜弥『川はゆく』などがある。
- ──
- 姫野さんは、その後、青幻舎を辞めて、
赤々舎を立ち上げるわけですが、
そのきっかけって、何だったんですか。
- 姫野
- 衝動的にです。上海行きも衝動ですが、
あんまり深く考えずに‥‥。 - 青幻舎で「写真」に出会ったんですね。
90年代の半ばですが、
佐内正史さんや、大橋仁さんの写真に。
そしてショックを受けました。
それまで触れたことのない表現だった。
- ──
- 佐内さんの『生きている』とかですか。
- 姫野
- そうです。青幻舎からお出しになった。
- 写真は言語ではないけれど、
でも、あの作品は
ひとつの「新しい言葉」のようにして、
若い人たちに受け入れられて、
とても大きな流れをつくりましたよね。
- ──
- 衝撃とかショックというのは、
具体的に言うと、どういう感情ですか。
- 姫野
- 怖さ、ですね。

- ──
- 怖さ。
- 姫野
- 写真家って怖かったんです、やっぱり。
上海の人たちにも共通するような。 - 何かをすごく考えているんだけど、
その思考が、宙に浮いていないんです。
「生きること」と「考えること」とが、
ぴったり貼りついているというか。
- ──
- そういう感覚。
- 姫野
- 生きること、考えること、撮ること。
- それらをぜんぶ、
ぴったりくっつけながら歩いている。
そういう存在って、怖いものですよ。
- ──
- 佐内さんの『生きている』って、
写ってるものって、
ガードレールとか青空とかですよね。
- 姫野
- そういう写真のどこが怖いんだって
思うかもしれないけど、怖いです。 - 極限まで研ぎ澄まされた‥‥
「そこに自分が生きている」ことの、
照り返しみたいな写真で。
- ──
- そういう表現、はじめてだった?
- 姫野
- はい。ブレッソンだとかアジェだとか、
古典的な写真は見ていたんですが、
佐内さんや大橋仁さんには
安心できないもの‥‥
つまり、
とても安全なところにはいられないぞ、
みたいな感じを受けました。 - 何だろう‥‥「浸食」っていうか‥‥。
- ──
- わかります。そういう感じは、
自分は、志賀理江子さんに感じました。 - 写真の雰囲気はぜんぜんちがいますが。
- 姫野
- わかりますでしょう?
いままでの自分が
なくなるような感覚があったんです。
一回ぜんぶ、死んじゃうような感じ。 - 出会おうとして出会ったんじゃなく、
そんな気ないのに出会っちゃった。
本当に、
上海と似た出会い方だったんですよ。
で、そこから、
写真への傾斜がはじまったわけです。
- ──
- なるほど。
- 姫野
- そのころには、
短歌をつくることもやめていました。
ちょっと、ダメだなと。 - とてもじゃないけど、
自分で何かをつくるのは無理だなと。
- ──
- 佐内さんや大橋さんの写真に触れて。
- 姫野
- はい、脅かされながら‥‥
自分をわーっと揺さぶられるような、
自分の足場がなくなるような、
そういう体験が積み重なっていった。 - で、そうなってくると、
そういう本がつくりたいわけですが、
写真集って、
当時からなかなか採算が合わなくて。
- ──
- めちゃくちゃ売れるわけでもないし。
- 姫野
- もう青幻舎も大きくなってきていて
スタッフも増えていて‥‥
わたしは、写真集以外の本を、
つくらなきゃならなかったんですね。 - 編集者は、わたしひとりだったので。
- ──
- ああ、そうか。
- 姫野
- それなのに、自分の気持ちとしては
写真集をつくりたい、
いまを生きているような作家と、
いっしょに本をつくりたい‥‥って。 - 会社を支えるための本と、
自分のつくりたい本とのバランスが、
取りにくくなってきたんです。
それで、後先顧みずに
わがままを言って、辞めたんですね。
- ──
- なるほど。
- 姫野
- 何のアテもなかったけど、
ちいさい所帯で自分ひとりでやれば、
採算が取りにくい分野でも、
やっていけるんじゃないかと思って。
- ──
- 当時、おいくつだったんですか。
- 姫野
- 39でした。
- いよいよ人生も半分だなってときに、
塀にひょいっとのぼって、
向こう側を見てみたら、
舟越さんの『水のゆくえ』のような、
自分の何かを
丸ごと注ぎ込めるような本って、
そう何冊もできないな‥‥
ということも、わかったんですよね。
- ──
- ええ。
- 姫野
- 残された時間、限られた機会の中で、
わたしは、ああいう本を
あと何冊つくれるんだろう‥‥って。 - それで、辞めようと思ったんです。
- ──
- そうやって立ち上げたのが、赤々舎。
- 姫野
- はい。
- ──
- それから、何年ですか。
- 姫野
- 16年目です。
- ──
- 写真集だけじゃなくて、もう、
いろんなジャンルの本を出してますよね。
- 姫野
- はい。写真集の出版社と思われることも
けっこう多いんですけど、
写真集に特化しようと思ってたわけでも
ないんですよね。
- ──
- 独立のきっかけではあったけど。
- 姫野
- 文学もやりたい。和歌の研究書もやりたい。
- でも、赤々舎をはじめてすぐの時期、
新人の写真家から、
企画を持ち込まれることが多かったんです。
で、そうやってつくった写真集が、
木村伊兵衛写真賞を受賞したりもして。
それで、まわりから、
写真集の出版社だと思われるようになって。
- ──
- はい。ぼくも、そういうイメージでしたし。
- 木村伊兵衛写真賞の受賞作を
たくさんつくっている出版社さんだ‥‥と。
志賀理江子さんの本も、初期ですよね。
- 姫野
- ええ、はじめての受賞が2冊同時で、
そのうちの1冊が
志賀理江子さんの『CANARY』でしたね。 - もう一冊が、岡田敦さんの『I am』。

- ──
- おお、岡田さんの作品も赤々舎でしたか。
- 姫野
- その翌年が浅田政志さんの『浅田家』で、
そのまた翌年が
高木こずえさんの『MID』『GROUND』。
- ──
- つまり3年連続、木村伊兵衛写真賞受賞。
- 姫野
- そうなんです。
- ──
- 何か大きく変わりましたか。会社として。
- 姫野
- 写真家がいただく賞ですから、
それは、とてもよろこばしいことですし、
本が知られる契機にはなります。 - でも‥‥だからといって、
そのことがすごく大きいかっていうと、
わたしの中ではそうでもなくて。
- ──
- あ、そうなんですか。あまり変わらない。
- 心をかたむけてつくった本が、
どういうふうに
世間に受け入れられていくかってことは、
気にならないですか?
- 姫野
- あんまり気にならないんです、たぶん。
- ──
- どうしてですか。
- 姫野
- わからないものに、惹かれるんですよね。
- わたしが、ある作家や作品に
自分の心をかたむけていける理由って、
たぶん、
わからない部分がたくさんあるからです。
- ──
- その作家さんや、作品に。
- 姫野
- 自分自身を本や写真集で表現したいとは
まったく思わないんだけど、
自分自身がググーッと入っていくとき、
自分の関わった痕跡というものが、
否応なく、にじむだろうと思うんですね。
- ──
- 本や作品集、写真集に。
- 姫野
- でも、そういう、かすかな痕跡を含めて、
世間に幅広く受け入れてもらいたい‥‥
読者に受け入れられなきゃいけないとは
思ったことがないです。 - わたしが「これは、すごい!」と思った、
良し悪しの判断もできなくなるくらいに
強く惹かれて、
巻き込まれてしまったものに、
自分の存在を懸けることができたわけで。
- ──
- ええ。
- 姫野
- それだけでよくて、それを送り出せて、
まず満足している。 - 世の中に
どのように受け取られてもいいんです。
- ──
- 昔から、そういう思いですか。
- 姫野
- そうですね、たぶん‥‥。
- ただ多くの人に受け入れられなくても、
そこにおろした「錘(おもり)」
のようなものは、
かならず伝わるだろうと信じています。

- ──
- 錘。
- 姫野
- 編集者としての自分は、
できるだけ透明な「穴」のような存在で
いたいと思っているんです。 - そのほうが、できあがる本が、
どうやら強さを持つらしいということに、
気がついたんです。
- ──
- 穴、ですか。
- 姫野さん‥‥というか、赤々舎さんでは、
まだ評価の定まってない
新人作家の
初の写真集をつくることが多いですよね。
- 姫野
- ええ。
- ──
- 持ち込みもけっこうあると思いますが、
出すものと出さないもの、
そこには、何かの基準があるんですか。
- 姫野
- まず、見たことのないものだと思った。
- しかも、それが
その人からしか生まれない、と思った。
- ──
- おお。
- 姫野
- そして、「謎」がある、
わからないことにみちみちている‥‥。 - とかでしょうか。
つまり、どこかの誰かに似ているとか、
このあたりに位置づけられるとか、
そう思えないものに惹かれてきました。
- ──
- 謎で、未見で、分類不能で。
- 姫野
- わたしの知識不足で
知らないこともたくさんありますけど、
でも、少なくとも自分にとっては
見たことがなく、
しかも、その人からしか
生まれようのない表現だなという感触。 - 感触‥‥でいいんです。
たった1枚でもそういう感触があれば。
- ──
- たくさんは、なくていい。
- 姫野
- はい。いいです、持ち込みのときには。
- 浅田(政志)さんくらいですもん。
80枚とかの写真を撮り終わっていて、
それを本にすればよかった写真家って。
- ──
- なるほど。
- 姫野
- だいたい完成形には遠い状態ですから。
じゃあ、やってみようかと決めてから、
撮った写真を1枚ずつ見ながら、
ああだこうだと話して、
また、次の写真を撮りにいくんですね。 - その繰り返しだから時間がかかります。
- ──
- 新しい作家の写真集って、
どういうところが、おもしろいですか。
- 姫野
- はじめての作家とは、
「一緒に見出していく」ことができる。 - それが「どのようなものであるか」は、
まだ、おそらく作家本人も、
よくわかってなかったりするんですね。
- ──
- ええ。
- 姫野
- なので、作品の束からセレクトしたり、
新しく撮ったり、
ステートメントを練ったりしながら‥‥
たがいに、見出していくんです。
- ──
- それが、どのようなものであるか‥‥を。
- 姫野
- その作業が、わたしはすごく楽しいです。
- 売れるものをつくる商才はないですけど、
かたちのないところから、
作家と1冊の本をつくりあげていくこと。
- ──
- はい。
- 姫野
- そこに、わたしの「楽しみ」があります。
- そうしているとき、わたしは、
いちばんイキイキしているって思います。
(つづきます)
2021-10-20-WED
-
写真家・石川竜一さんの最新作
『いのちのうちがわ』

木村伊兵衛写真賞受賞作家の石川竜一さんが、
2015年から山へ入り撮影してきた、
さまざまな「いのち」の「うちがわ」の写真。
作品は本として綴じられてはおらず、
1枚1枚のプリントを束ねた
ポートフォリオブックの体裁をとっています。
限定700部。
作家によるサインとエディションナンバー入り。
定価14300円(税込)。その美しさは完璧なように思え、
頭で考えても理解できない感覚や感情は
ここからきているのだと感じた。
個々の存在とその意思を超えて形作られたその様は、
生い茂る木々や岩石と重なっても見えた。
自然のうちがわに触れ、
その圧倒的な力を思い知らされたとき、
物事の区別は緩やかなグラデーションで繋がって、
自分自身もその循環のなかにいるのだと感じた。
石川竜一『いのちのうちがわ』あとがきよりお問い合わせは、赤々舎のHPから。
-
「編集とは何か。」もくじ