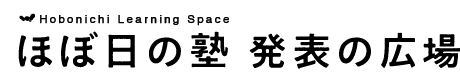「たぶん、この子はすぐ辞めるんじゃないかって
みんな思ってたよ(笑)」
当時のチームメイトに後々そう言われた。
そりゃそうだ。
高校1年生当時の僕はめがねで、
ものすごく自信なさげで、
おまけに人とまともに喋れなかったのだから。
最初のころは、「もっと喋ったほうがいいよ!」とよく助言された。
でも、嫌な気はしなかった。
バスケ部の中に中学までの僕を知っている人は居なかったから、
生き直しの場としては持ってこいだったのだ。
予想していた以上に、コートの上は戦場だった。
初心者は僕ひとり。
他はみんな、ミニバスや中学からのバスケ経験者。
なんなら同期7人のうち3人は、
中学時代に全国大会を経験したエリートだった。
初心者の僕には、スタメン争いに参戦する余地なんてない。
むしろ他のメンバーとは違う種類の戦いをしなければならなかった。
自分との戦い。今までの弱かった自分を打ち破ること、
そして人と喋れるようになることだ。
というと聞こえはいいのだが…、
実際にはとてつもなく泥臭く、
絵的にもかっこ悪いことこの上ない奮闘の日々だった。
まず、基礎体力・筋肉がなさすぎて練習についていけない。
疲れると吐き気に襲われる。
ボールもまともにキャッチできず、何回も顔面で受けた。
めがね、何回直しに行ったかな…?
生まれてはじめて肉体的にも精神的にも追い込まれて、
「人生にこんなつらいことがあったのか…」と打ちひしがれた。
そんな僕に先生が課したたった一つのことは、
「上手くできなくてもいいから、とにかく声を出せ」だった。
声を出す。
中学生までの僕を苦しめてきたその難題は、
バスケを通して強制的に解決していった。
練習が苦しくても逃げなかったのは、
ここで逃げてしまったら前の自分に戻ってしまう、
というのが一番の恐怖だったからだ。
はじめてだらけの感情
バスケ部は、僕がはじめて本格的に経験した社会だった。
言葉を取り戻し始めた僕は、
一歩ずつ一歩ずつ、仲間たちと距離を縮めていく。
自分の気持ちを話すこと。
相談したり、されたりすること。
励ましあうこと。
それこそ、憧れていた他愛もない話もようやくできた。
相手がちゃんと自分のことを大事に
思ってくれていると感じられる、あたたかな気配。
言葉を話せるというだけで、
こんなにも世界が変わるのか。
こんなにも、心の交流ができるのか。
すべてが新鮮だった。
色んな感情を知っていく過程は、
まるで数色しか色のなかったパレットが、
だんだんカラフルになっていくような感覚だった。
当時の僕は他の子たちよりも、
人生経験がひと回りもふた回りも遅れていたと思う。
だからこそ、全身でひとつひとつの感情を受け止めた。
僕は常に一番下手でボロボロだったけど、
誰も僕を見捨てることはしなかった。
レイアップシュートを覚えたとき、
はじめて公式戦でシュートを決めた日、
仲間や先生たちはそれを自分のことのように喜んでくれた。
「この人たちに恩返しがしたい」
引退するその日までの間に、
試合に出させてもらえるチャンスがあるならば、
その時は一本でも多くシュートを決めて来る。
言葉でじゃなく、自分のプレーしている姿で感謝を伝えるのだ、と心に誓った。
それからはそのささやかな夢に向かって、
個人練習に明け暮れるようになった。
人に何か「伝えたい」とこんなに強く思ったのは、
これが初めてだった。
(つづきます)