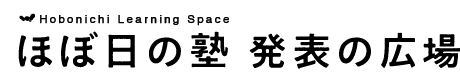- ぼく
-
それじゃそろそろ、『MOTHER2』をしましょうかね!
赤色に光ってるボタンを押してもらえますか?
- お母さん
- はい、はい。

- ぼく
- さて、今日はどこまで進むかなあ~。

- お母さん
- …うわ、これ、1994年のゲームだってさ。
- ぼく
- ははは。ぼく、1歳だ。

- お母さん
- ああ、やったなあ。ここ、ここ、行ったねえ。ほんとに変わってないんだね。
- ぼく
-
当時とまったく同じだよ。
…でもあれだね、全然コントローラーを手に取ろうとしないね(笑)。
- お母さん
- だって、昔のと違うから! 使い方わかんない。
- ぼく
- とりあえず、Aを押しましょう。今も昔も、Aを押しておけばたいてい大丈夫です。

- ぼく
- さ、出たよ。この野球帽が、主人公。あとは、リボンが似合う女の子、メガネをかけたおともだち、柔道着を着た王子さま。旅する4人の少年少女に、好きに名前をつけてください。
- お母さん
-
私ねえ、じつはもう昨日から考えてたの。
昔はさ、お兄ちゃんがこれに、家族4人の名前をつけたでしょ。つばさ(兄)、るみ(お母さん)、ともき(ぼく)、こうじ(お父さん)。
やっぱり、『MOTHER2』はこの4人だなと思うの。離婚してしまった今でも、白い柔道着を着た人は、お父さんです。
- ぼく
- そっか。ぼくが小学校5年生のときだから…離婚して10年以上経つけど、それでも。
- お母さん
-
うん。私にとってはもう、決まってるの。この4人じゃなきゃ、このゲームじゃないの。
…でも、いいのかしら、これ(笑)。今の旦那さんの前でやるのはなんとなく気まずいよね(笑)。結局、また夜中だよ、これやるの!
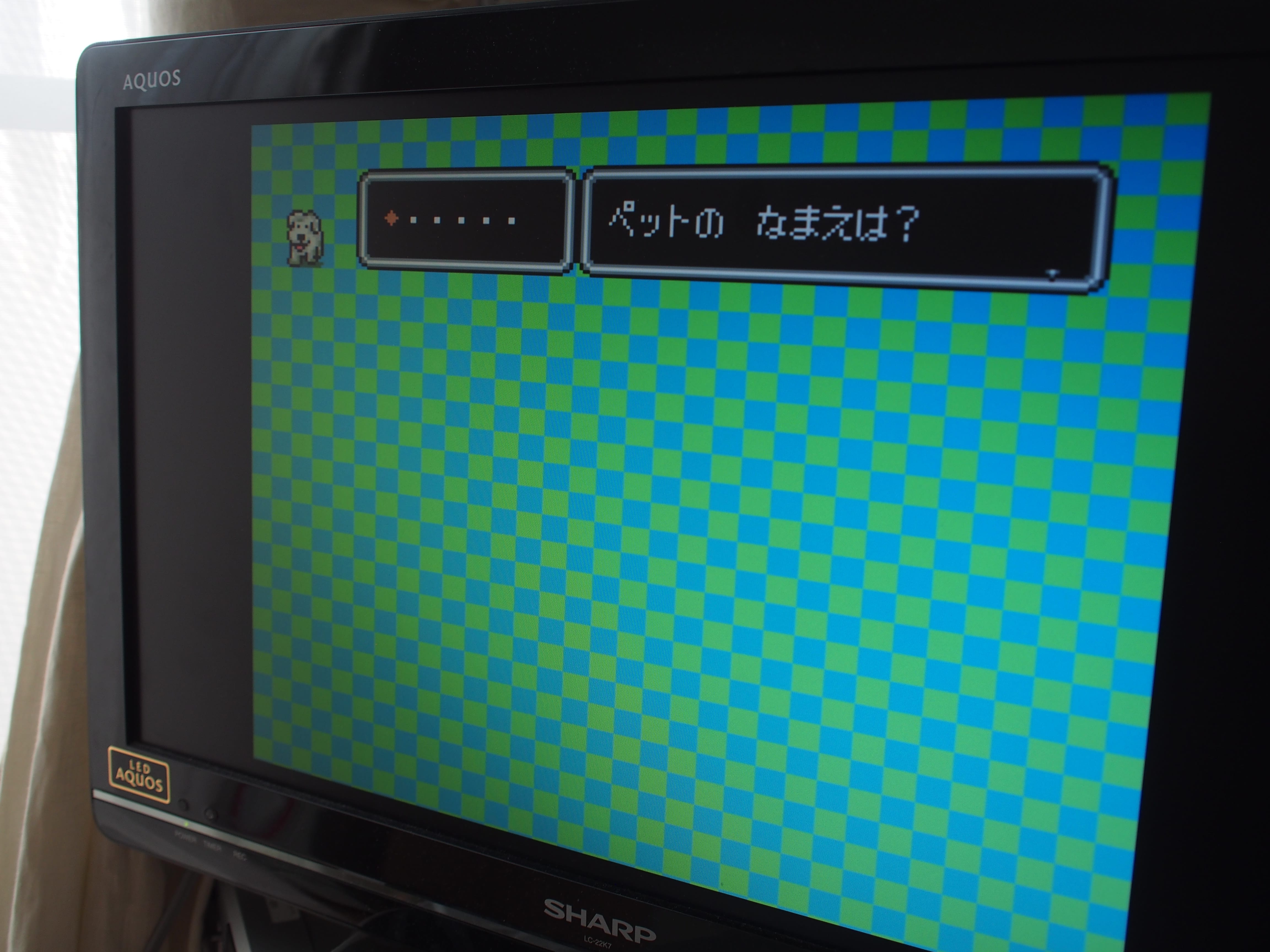
- お母さん
-
あら、わんちゃんなんていたっけ。
でも、やっぱりノエルだよね。あのときはまだいなかったし、今ももういないけど。
- ぼく
- うん、ぼくもそうすると思う。家族だもんね。
- お母さん
- ノエルも今、膝のうえに乗ってたらよかったね。
- ぼく
- うん。
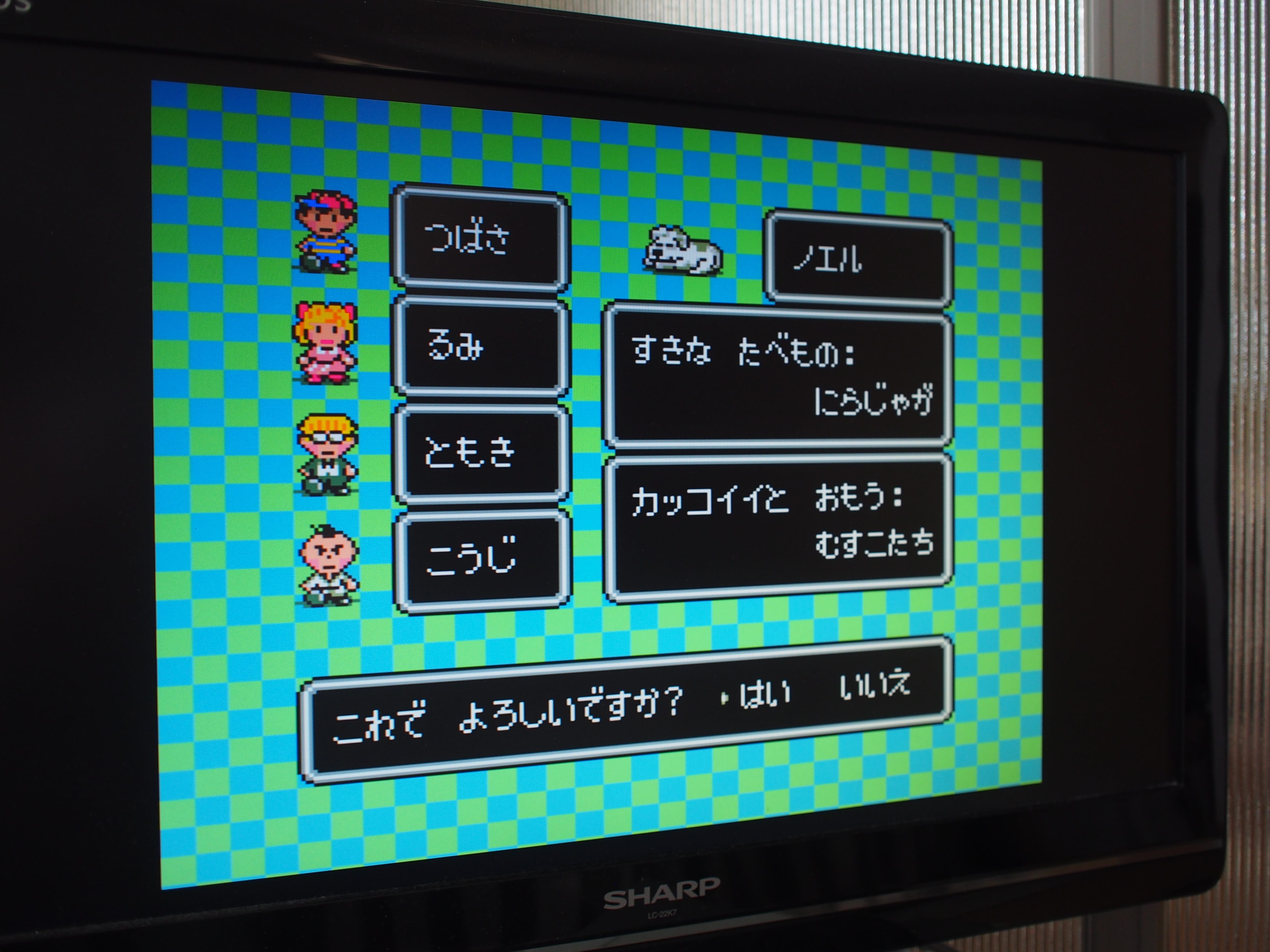
- ぼく
- やっぱ、この4人だよね。
- お母さん
- うん。これが私の『MOTHER2』の、当たり前。

- お母さん
- ああ、懐かしいなあ。これ、199X年が舞台なんだね。糸井さん、どうして20XX年とかにしなかったんだろう。(『MOTHER2』は、ほぼ日の社長・糸井重里さんが作っています)
- ぼく
- たしかに。すごく近い未来だね。

- ぼく
- さて、ゲームのはじまりは主人公の家から。町に隕石が落ちてきたようです。家を出て、ようすを見に行きましょう。

- お母さん
- そうそう、急に夜の町に放り出されるんだよね。怖かったよ、昔も。


- ぼく
- 全員に話しかけていくのね(笑)。真面目だ。
- お母さん
-
なんか話しかけちゃうね(笑)。
昔こんなにしたかは覚えてないけど、今の私はしてしまうね。昔より面倒くさい人になってるかもしれない。

- お母さん
-
ああ、お隣さんだ。ずいぶん立派な、アーリーアメリカンな家だね。
でも、隕石落ちたばっかりだし、今は入りづらいなあ…。

- お母さん
- あら、ダメだ、この先に隕石があるのに、進めない。いったん警察に任せて、お家に帰ればいいんだっけ?
- ぼく
- ふっふっふ、どうでしたかね?
- お母さん
- あっ、ママ。家の前で待ってるじゃん。心配になって、出てきちゃったんだ(笑)。帰ろう、帰ろう。
- ぼく
- よかったよかった、無事到着。

- お母さん
- あっ、おうちの電話が鳴ったよ。出ればいいの?
- ぼく
- パパからだね。あのさ、このゲームって、こうやってお父さんが電話でしか登場しないじゃん?
- お母さん
- たしかに、一緒に暮らしてないよね。
- ぼく
- これって、ゲームを作った糸井さん自身が一度離婚をしていて、子どもと離れて暮らしていたから、このゲームもパパは電話だけなんだって。「離れてるお父さんに愛されてる」という、世界でたったひとりのお子さんに対するメッセージだったみたい。
- お母さん
-
そうなんだ。でもたしかに、家族を思わせるね、このゲームはね。
…「パパだってヒーロー! …のちちおやになれるならわるいきはしないぞ」だって(笑)。このパパ、すっごくうちのお父さんっぽくない? 言いそうだもん。
- ぼく
- それはね、わかります(笑)。「わかいときのくろうはかってでもしろ」も、ぼくが新卒入社した会社を辞めるか悩んでたとき、同じようなことを言われたな。
- お母さん
- でも、こうやって、子どもがいて、パパとママがいる、そういう家族が懐かしいなとは……ちょっと、思うよ…。

そう口にすると母は、コントローラーを机に置きました。