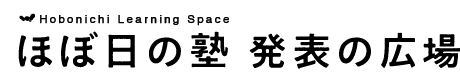しかし、人生とは面白いもので、私は再び横浜に住むことになった。
結婚したのだ。
何者でもなかった私は、妻という肩書きを手に入れた。
その肩書きに安心したのか、小説を書かなくなった。
詳細は割愛するが、数年後、私は離婚する。
カフェは、離婚の話し合いの場にもなったりした。
ある日、私たちはカフェで待ち合わせた。
パリに本店があるそのカフェは、
平和な日曜日の午後そのもので、
若いカップルや家族連れ、老夫婦がお茶をしていた。
青白い顔をした私は、そこに入った瞬間、
異世界にいるような気分になった。
やり直そう、やっぱり無理だ、いやでも・・・。
行ったり来たりする話し合いを重ねる中で、
このときの私は、なんとか元に戻れないかと思っていた。
そこで作戦を立てた。
クッキーを焼いたのだ。
それを5枚ほど、小さく包んで、彼に渡そうとした。
彼は甘いものより、お煎餅が好きだけど、
私のクッキーをみんなに自慢してたじゃない。
僕の奥さんは料理上手なんだぞって。
あの頃を思い出せば、もしかして。
そんな思いは、それはきれいに打ち砕かれた。
少し遅れて着いたカフェに、彼はすでにいた。
テーブルの上には、コーヒーと食べかけのクッキーがあった。
いつも甘いものなんて頼まないのに、
しかもよりによってクッキーって・・・
私は紅茶だけ頼んだ。
なんだかこの時の私には、コーヒーは強すぎて、飲める気がしなかった。
店員さんにケーキセットを勧められたが、薄く笑って断った。
なんの話をしたのかよく覚えていないけど、
とにかく二人の距離は1ミリも縮まらなかった。
私がそれでもと、すごすごとバックから取り出したクッキーを、
彼は「・・・もう食べたから」と受け取らなかった。
しばらくして離婚届を出した後、
携帯電話の家族割だかの解約手続きをするために、
私は再び彼と顔を合わせた。
かっこ悪い自分を封印し、完璧に吹っ切れている人として、
私はその場を乗りきれたと思う。
その後、チェーンのカフェに入った。
私の人生で、あれが彼に会う最後だっただろう、
と思いながら、私はカフェラテと何か甘いもの頼んだ。
早めの午後だったと思う。
初めて入った横浜駅東口のその店舗は、
パソコンに打ち込む人や、ミーティングをするビジネスマンがいた。
子連れのママの笑い声と、ときおき混じる怒鳴り声が、
ざわめきの中で際立っていた。
授業をサボったらしい制服の高校生は、
スマホで動画をつまらなそうに見ていた。
私はカフェがあってよかった、と思った。
まっすぐ家に帰れるほど、心は軽くなかった。
ねっとりとした薄暗いものは、短時間なら押し込めていられるけれど、
気を緩めればすぐに心を支配する。
いろんな人が、いろんなことを勝手にやっていた。
それが、心地よかった。
私は、よくがんばったと自分をほめたり、
突然あふれてくる涙をそれとなく拭いたりしながら、
カフェラテを飲んだ。
そこは、私の居場所だった。
その他の人と同じように、私は勝手に、自分のことをやっていた。
妻という肩書きを返却し、私はまた何者でもない人になった。
ちょっと悔しいのだが、存外にダメージは大きかった。
日本にいるのが辛かったので、私は、日本から脱げ出した。
ここでなければどこでもよかったが、
そうだ、私は甘いものが好きで、お菓子づくりも好きだったと、
財産分与で得たお金(リアルだ・・・)で、
パティシエの勉強をしようとパリに向かった。
友達の友達家族(つまり初めて会った)の
アパートメントに転がり込んだ。
間借りした4畳ほどの子供部屋が、新しい私の居場所だった。
英語の通じないベトナム人の奥さんと、
私を「タター(おばちゃん)」と言えず
「カカー(う○ち)」と呼ぶ3歳児(もしかしてわざとだったのか?)と、
無職の陽気なアルジェリア系のフランス人との生活が始まった。
しばらくしてある問題に気づいた。
パティシエになるべくパリに来たのだが、
あんなに好きだったスイーツを、
あまり美味しく感じられなくなってしまったのだ。
気が弱くなっていたついでに、胃腸も弱くなっていたらしい。
私はバターの重さに耐えられない体になっていた。
それでも、3ヶ月間、語学学校に通いながら、
カフェやパティスリーで、一生懸命甘いものを食べた。
しかし、体は正直だ。
やっぱり、食べたくない。
これを仕事にできるのだろうか?
私は、違う道を探すことにした。
自立しなければと見つけた仕事は、
インドネシアのジャカルタにあった。
日本人ゲストの対応をするホテリエになるのだ。
新しい土地、新しい仲間。
英語には全然自信がないけど、
働いていればきっとできるようになる。
同じ部署には日本人が3人いると聞いていた。
きっと助け合いながらがんばれる!とジャカルタに着いたその日、
私の採用を決めた、営業部の日本人の女は言った。
「この部署、あなただけになるから」と。
色々割愛するが、ブラック企業再びである。
ホテルの一室に住む私は、24時間、いつでも呼び出しがかかる。
全てはホテルの監視カメラが見ている。
3人分の仕事を1人でこなさなければならず、
毎晩2時まで仕事をし、朝8時には次の勤務が始まる。
休みの日だって、日本人ゲストからの問い合わせがあれば、
朝5時でも部屋に電話が回される。
「トイレどこですか?」と叩き起こされても、
優しく答えなければならない。
月給は500$だった。
一年後、私はジャカルタのホテルを辞めた。
結局、私はまだ何者にもなれていなかった。
英語は前よりも話せるようになったけど、
ビジネスで通用するほどでもない。
日本に帰って、一人で生きていく自信がまだ持てなかった。
もう少し、何者かになる道を探しつづけたかった。
そこで私はカナダのモントリオールに向かった。
一度ワーキングホリデーで滞在し、とにかく楽ちんだなぁと感じた土地だ。
他人に関心がなく、人種差別も少なく、好き勝手に生きている人が多い。
フランス語圏だからフランス人の移民が多く、
おしゃれなカフェもたくさんあった。
現地の友人に相談すると、来なよ!と言ってくれた。
何者かになるべく、私は友人の影響で写真を始めた。
いっぱしにカフェでパソコンを広げ、
Photoshopをいじっている自分が、なんだかかっこいいと思った。
大学生の頃憧れていた、カフェの人たちに近づけているような気がした。
私はずっと居場所を探していたのかもしれない。
自分を受け入れてくれる場所を。
外国は、そもそも永住権がなければ、永遠の居場所にはならない。
ただ少しのあいだ、滞在させてもらっているだけだ。
それが心地よく、それが心細かった。
カフェは、そんな私のほっとできる場所だった。
フランスでも、インドネシアでも、カナダでも、
国は違えど、コーヒーはコーヒーだったし、甘いものは甘いものだった。
椅子とテーブルがあり、飲み物と食べ物がある。
スタッフがいてお客さんがいる。
私は、私の居場所を、お金を出して買えた。
どんな国でもそこには私の居場所があった。
それがカフェだった。
だからかもしれない。
この放浪期には、海外ならではの景色をたくさん見たのに、
妙に思い出されるのは、その土地土地のカフェでの記憶だったりする。
あの窓から見た景色。
アメリカーノから立ちのぼる湯気。
クロワッサンのバターの香り。
BGMのように流れていく外国語の会話。
孤独と安心。
食べて、飲んで、自分にエネルギーが入ってくる。
体が生きているという感覚。
「人類は進化しているか、退化しているか?」
大学生のときに、元夫の友人にそう聞かれ、
私は「進化も退化もしてない。人類なんて、変わらない」と答えた。
だけど、今は思う。
貨幣を発明して、そのお金で居場所を買える分だけは、
人類は進化したかもしれない。
(逆に、ダメになっている部分もあるから、
答えはあの頃と変わらないのかもしれないけれど。
それはまた考えてみようと思う。)
自分の居場所を持てることは、心を健全に保ってくれる。
昔、貨幣のない時代の人は、
一人ぼっちがつらい時、どうしていたのだろう。
家族や、社会の中にいるのがつらい時、どうしていたのだろう。
私は帰国した。
そろそろ離婚の傷も癒えた。東京に行ってもきっと大丈夫。
とにかく行けば、なんとかなる。仕事だって見つかるはず。
あれから3年、そうやって生きてきた。
家賃を安く抑えられるからと、東京のシェアハウスを探し始めた。
そんなころだった。
松本の知人から、知り合いのカフェを手伝ってくれないか、と言われた。
東京に行くまで、1、2ヶ月でよければ、と言った私は、
その後3年間、そのカフェと、系列店のイタリアンレストランで、
奴隷のように働くことになる。
ブラック企業最強編、松本暗黒時代が始まるのだった。
ここで働いている間に、
今度は精神的に「死ぬ・・・」と思ったが、大丈夫、こうして生きている。
詳細は割愛するが、いろいろなものを犠牲にした代わりに、
お菓子づくりと料理の腕は、格段に上がった。
そうして私は、東京に行くことになる。
カフェで働くのだ。