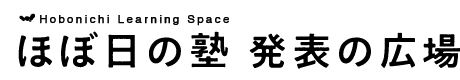- 糸井
-
これから会社ではなく
自分が名前で出していく立場になって、
変わりますよね、自分。

- 田中
-
そうなんです。これがむずかしい。
今、青年として、青年失業家として岐路に立っていて。
会社でコピーライターをやっている、
そのついでに何かを書いてる人ではないので
じゃあ、どうしたらいいのかっていうことに
岐路に立っているんですね。
- 糸井
-
2つ方向があって
書いたりすることで食っていけるようにする
いわゆるプロの発想と、
書いたりすることが、食うことと関わりなく
自由であることを目指す方向と、
2種類分かれますよね。
- 田中
- そうですね。
- 糸井
-
僕もきっとそれについては
ずっと考えてきたんだと思うんですね。
それで、僕はアマチュアなんですよ。
書いて食おうと思った時に、自分のいる立場が、
つまんなくなるような気がしたんで、
いつまで経っても旦那芸でありたい。
「お前、ずるいよ、それは」っていう場所からいないと
良い読み手の書き手にはなれないって思ったんで、
僕はそっちを選んだんですね。
田中さんはまだ答えはないですよね。
- 田中
- そうなんです。
- 糸井
- どうなるんだろうねぇ。
- 田中
-
僕の「糸井重里論」っていうのは
そういう好きに、好きに、旦那芸として書くために
みんなが食べられる組織を作って、回して、物販もして
それで、その立場を作っている。
壮大な、自分のクライアントは自分っていう立場を。
- 糸井
- そうですね。
- 田中
- 作り切ったってことですよね。
- 糸井
-
『キャッチャーズ・イン・ザ・ライ』っていうのは
最初、ライ麦畑で捕まる話かと思ったら、
タイトルからして間違った誤訳で。
本当は、
「俺はキャッチャーだから、その場所で自由にみんな遊べ」
っていう話ですよね。
まさしく僕が目指しているのは
『キャッチャーズ・イン・ザ・ライ』で。
- 田中
- 見張り塔からずっと。

- 糸井
-
そうなんです。それで、その場を育てたり、譲ったり、
そこで商売する人に屋台を貸したり
みたいなことが僕の仕事で、
その延長線上に何があるかって言うと
僕は書かなくていいんですね。
本職は、管理人なんです。
その意味では、田中さんもその素質もあると思うんですよ。
- 田中
- なるほど。
- 糸井
-
僕は人がなんと思っているかは知らないけど
自分では、やりたいことと
やりたくないことを峻別していて。
燃えるゴミと燃えないゴミみたいに。
それで、「やりたいことだなぁ」とか、
「やってもいいなぁ」って思うことだけを選んできたら、
こうなったんですよね。
田中さんは、たぶん、
僕を見てる目もそこのところよく見てる。
- 田中
- そうですね。

- 糸井
-
僕が大変だったのは、書き手っていうものに対して、
人はある種のカリスマ性を要求しますね。
- 田中
- はい。
- 糸井
-
僕は、そんなのどうでもいいのだけど。
人は書くっていうことは、士農工商みたいな順列で
なんだろう、トランプ大統領よりも
ボブ・ディランが偉いみたいな。
- 田中
- わかります。
- 糸井
-
その目をどうしても向けるんで、
その順列からも自由でありたいなぁっていう。
だから、超アマチュアっていうので一生が終われば
僕はもう満足なんですよ。
- 田中
-
その軽ろみをね、どう維持するか、
糸井さんはずっとその戦いだったと思うんですよね。
- 糸井
-
そうですね。
同時に、その軽さはコンプレックスでもあって、
「俺は、逃げちゃいけないと思って勝負してる人たちとは
違う生き方をしてるな」って。
- 田中
- わかる、メッチャわかる。
- 糸井
-
俺は受け手として書いてきた人間なんで
たとえば、「どうだ!」って言って人を斬って、
まだ生き返って斬りつけてくるかもしれないから、
心臓の所にとどめを刺して、
「死んだかな」っていうのを確かめて、
ハァハァ言いながら、「勝った」って言うような人たちと
同じことを俺はしてないから。
生き返ってきたら、「そいつ偉いな」
って思うみたいなところがあって(笑)。
- 田中
-
そうですね。
まだものをね、ちょっとでも書くようになって
たった2年ですけど、書くことの落とし穴は
すでに感じていて。
それはつまり、僕はこう考えるっていうことを重ねて
毎日毎日書いていくうちに、だんだん独善的になっていく。
- 糸井
- なっていきますね。
- 田中
-
はい。そして、なった果ては、
人間は、九割くらいは右か左に寄ってしまうんですよね。
これが、どんなにフレッシュな書き手も、
すごい真ん中あたりで心が揺れていて、
その揺れているのを
うまいことキャッチして書いているなっていう人も、
10年くらい放っておくと
どっちか右か左に振り切ってることがいっぱいあって。
- 糸井
-
世界像を安定させたくなるんだと思うんですよね。
で、世界像を人に押し付けられるような偉い人になると、
読み手として拍手はする時はいっぱいあるんだけど、
人としてはつまんないかなって。
- 田中
-
恐ろしいですね、それは。
僕は別にさっき言ったような、
世の中をひがむとか、言いたいことがはみ出すとか、
何か政治的主張があるとかはないんですよ。
読み手だから。
よく言われるのは、何か映画評とか書いてたら、
「じゃあ、田中さん、そろそろ小説書きましょうよ」。
- 糸井
- 言いますよね、必ず言いますよね。
- 田中
-
まぁそれは読みたいっていうのもあるだろうし、
あと、商売になるって思っている人もいる。
だけど、やっぱり別にないんですよ。
そんな、心の中に「これが言いたくて俺は文章を書く」
っていうのはなくて。

常に、
「あ、これいいですね」
「あ、これ木ですか?」
「あぁ、木っちゅうのはですね」
っていう、ここから話しがしたいんですよ、いつも。
- 一同
- (笑)
- 糸井
- お話しがしたいんですね(笑)。
- 田中
- そうなんです。