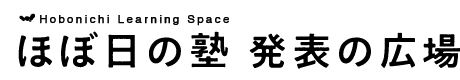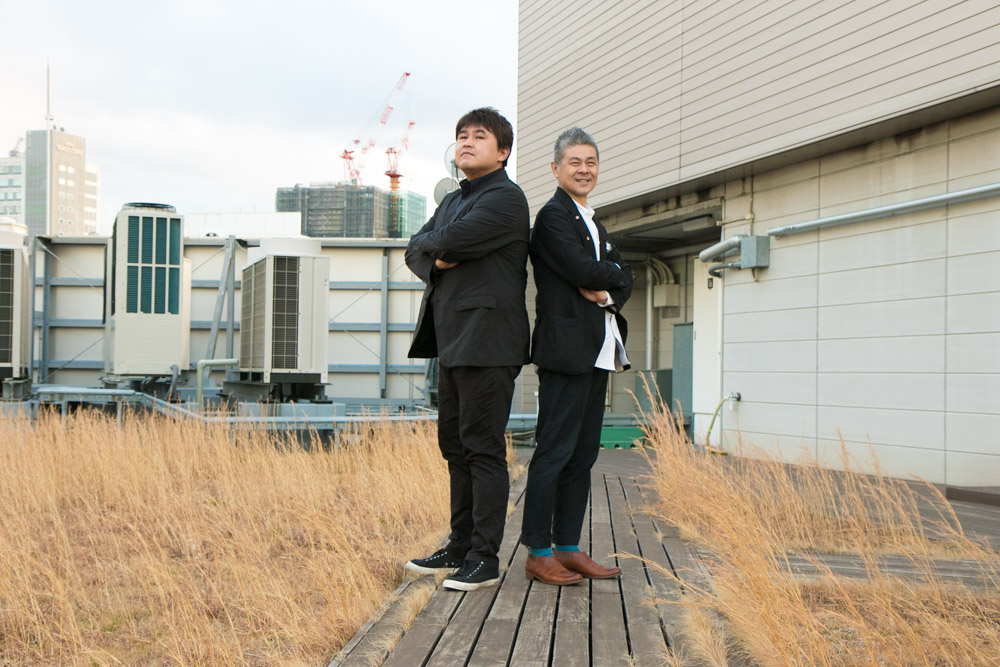- 糸井
- 最初の映画評はなんだったんですか?
- 田中
- 『フォックスキャッチャー』っていう映画で。オリンピックのコーチが、選手を自分の所で育ててるんだけど、男性間の愛憎の乱れみたいになってしまうっていう実話なんですけど、それについての映画で、アカデミー賞候補とかなってたんですけど、それを観て、それも2、3行書くつもりだったんですよ。そうしたら、その時初めて、勝手に無駄話が止まらないっていう経験をしたんですよね。
- 糸井
- あぁ。
- 田中
- キーボードに向かって、「俺は何をやっているんだ、眠いのに」っていう。
- 糸井
- うれしさ?
- 田中
-
「これを明日ネットで流せば、絶対笑う人がいるだろう」とかっていう想像すると、ちょっと取り付かれたようになったんですよね。

- 糸井
- 一種、大道芸人の喜びみたいな感じですね。
- 田中
- そうですね。
- 糸井
- 雑誌のメディアだったら、そんな急に7,000字って、まずはないですよね。頼んだほうも頼んだほうだし、メディアもインターネットだったし、本当にそこの幸運はすごいですねぇ。
- 田中
- その後、雑誌に頼まれて寄稿っていうのもあったんですけど、雑誌は、それに対して僕に直接、「おもしろかった」とか、「読んだよ」とかないので、いくら印刷されて、本屋に置いてあっても、なんかピンと来ないんですよね。
- 糸井
- インターネットネイティブの発想ですね。
- 田中
- 反応がないというのが。
- 糸井
- 若くないのに(笑)。
- 田中
- 45にして(笑)。
- 糸井
- でも、その逆転は、25の人とかが感じてることですよね。すごいことですね。酸いも甘いも、40いくつだから、一応知らないわけじゃないのに。
- 田中
- すごいシャイな少年みたいに、ネットの世界に入った感じですね。
- 糸井
- すると、コピーライターズクラブのちょっとした文章って、あれは何回書いてますかね。
- 田中
- 2015年と2016年に、10回書いてますね。
- 糸井
- それしかまず出てくるものはなかったわけだ。
- 田中
- はい。あれだけがはけ口だったんですけど(笑)、しかも反応がないんで、ツイッターとかみたいに。
- 糸井
- あれ反応ないと思いますね。なんていうんだろう、あれは、嫌々やる仕事ですよね。
- 田中
- はい、回ってくるので。
- 糸井
- それを田中さんは嫌々ふうに書いてるけど、全然嫌じゃなかったんですか?
- 田中
- もう初めてのことなんで、「あ、なんか自由に文字書いて、必ず明日には誰かが見るんだ」と思うと、うれしくなったんですよね。
- 糸井
-
新鮮ですねぇ。あぁ、それはうれしいなぁ。

- 田中
- 糸井さんはそれをずっと毎日やってらっしゃるわけでしょう?休まずに。
- 糸井
- うーん‥‥、でも、「大変ですね」って言われても、「いや、うん、みんな大変なんじゃない?」って(笑)。
- 田中
- 「みんな大変だろう」って(笑)。
- 糸井
- あえて言えば、休まないって決めたことだけがコツなんで、あとは、なんでもないことですよね。仕事だからね、おにぎり屋さんはおにぎり握ってるしね。
- 田中
- なるほど。
- 糸井
- たぶん田中さんは今そうだと思うんですよね。
- 田中
- 大してね、食えないんですよ。これが。でも、この間の塩野さんとの対談でもそうだったんですけど、これからの時代、コンテンツ、文章っていうのをお金を出して読もうっていう人がもうどんどん減るから、今ぼくが得てる、あれで全然儲かってないし、何を書いても生活の足しにはならないので。
- 糸井
- ならない。
- 田中
- 前は大きい会社の社員で、夜中に仕事終わった後書いてましたけど、今はそれを書いても生活の足しにならないから、じゃあ、どうするんだ?っていうフェイズには入っています。
- 糸井
- 27歳の人と今話してますね。
- 田中
- すごい、若者の悩み相談(笑)。
- 糸井
-
27歳の子が独立したっていうことで、「それは誰かに相談したの?すでに。奥さんはなんて言ってるの?」

- 田中
-
そんな感じですね(笑)。
ただ、ぼくの中では相変わらず、未だに、何かを書いたらお金ではなく、「おもしろい」とか、「全部読んだよ」とか、「この結論は納得した」とかっていうその声が報酬になってますね。
- 糸井
- 自分が、文字を書く人だとか、考えたことを文字に直す人だっていう認識そのものがなかった時代が20年以上あるっていう、不思議ですよね。「嫌いだ」とか「好きだ」とかは思ってなかったんですか?
- 田中
- 読むのが好きで。
- 糸井
- あぁ。
- 田中
- 「ひたすら読んでました」っていうのはあったんですけど、それで自分が何かを書くとは夢にも思わず。
- 糸井
- コピーライターって、書いてる人っていうより、読み手として書いている気がするんですよ。
- 田中
- はい、すごくわかります。
- 糸井
- だから視線は読者に向かってるんじゃなくて、自分が読者で、自分が書いてくれるのを待ってる、みたいな。
- 田中
- おっしゃるとおり、いや、それすっごくわかります。
- 糸井
- 「受け手であるっていうことを、思い切り伸び伸びと自由にこう、味わいたい!」って思って、「それを誰がやってくれるのかな」、「俺だよ」っていう。
- 田中
- 映画を観ても、その映画自体を観ますね。次にいろんな人が今ネットでも雑誌でも評論をするじゃないですか。そうしたら、「何でこの中に、この見方はないのか?」。で、それを探してあったら、もう書かなくていいんですけど、「この見方、なんでないの?じゃあ、今夜俺書くの?」っていうことになるんですよね。
- 糸井
- あぁ、書かないで済んでた時代のことがなんであんなにおもしろいかっていうと、広告屋だったからだ。
- 田中
- 広告屋はね、発信しないですもんね。
- 糸井
- でも、受け手としては感性が絶対にあるわけで、
- 田中
- はい。
- 糸井
- 受け取り方っていうのは、発信しなくても個性なんですよね。で、そこでピタッと来るものを探してたら、誰もなかなか書いてくれないから、「え、俺がやるの?」っていう、それが仕事になってたんですよね。
- 田中
- そうですね。
- 糸井
-
自分がやってることも今わかったわ。

- 田中
- (笑)
- 糸井
- ぼくね、嫌いなんですよ、ものを書くのが。
- 田中
- わかります。
- 糸井
- 前からそう言ってますけど(笑)。
- 田中
- みんな嫌なんですよ、本当に。
- 糸井
- たぶんぼくもそうですし、田中さんも、「お前って、じゃあ、何も考えもないのかよ」っていうふうに誰かに突きつけられたら、「そんな人間いないでしょう」っていう一言ですよね。そこを探しているから、日々生きてるわけで。
- 田中
- ツイッターで、糸井さん風に物事に感心する、糸井重里botっていうのがあるんですよ。そのbot、すごいよくできてて、何に関しても、「それいいと思うなぁ」なんです。
- 糸井
- ぼくはもう、だいたいそればっかりですよ。
- 田中
-
その時に何か世の中に対して、たとえばこの水でも、「このボトル、好きだなぁ」っていうのをちょっとだけ伝えたいじゃないですか、相手に、「ぼくはこれを心地よく思ってます」って。

- 糸井
- そうですね。そのボトル見た時に思ったから、これを選んだ。他のボトル見た時には思わなかったんです。でも、それも受け手ですよね。
- 田中
- ですよね。
- 糸井
-
受け手ですよね。という日々ですよ。
なんでいいかっていうのは、ぼく自分に宿題にしているんですよっていう。これは雑誌の連載ではできないんですよ。インターネットだから、いずれわかった時にわかったように書けるんですよね。
- 田中
- でもその日は、とりあえず「これがいいなぁ」ってことはまず伝えることができますよね。それは、「前もちょっと話したけど、何がいいかわかった」っていう話がまたできるんですね。
- 糸井
- 田中さんがやっているのもだいたいパターンはそれですよね。
(つづきます)