ほぼ日の学校長だよりNo.137
一生忘れることのできない弔辞
「今日のダーリン」の呼びかけで、「この人がしてくれた、こんな話」という投稿を募りました。8月19日、糸井さんの文章が公開された直後から、次々にメールが寄せられ、きょうまでに200通以上の「こんな話」が届いています。
近く、ほぼ日のウェブサイトでも紹介したいと思います。
糸井さんも書いていたように、小学校の時のおばちゃん先生、冗談ばかり言っていた高校の先生、両親や祖父母、友人、上司、あるいは有名な誰かの講演、ラジオやテレビで聞いたこと‥‥。私自身を振り返っても、いまだに耳に残っている話がたくさんあります。
<人が声を出して語りかけてくれることは、
人の耳からこころに伝わってきます。
もちろん、書いたことばを読むことも、
人の目からこころに伝わってきますが、
どういう理由でか、声から耳へのことばのほうが、
印象深く覚えていたりもする。>(糸井重里「今日のダーリン」、2020年8月19日)
そんなことを考えていたら、たまたま開いた新聞で、小泉武夫さん(作家・発酵学者)の記事を目にしました。小さい頃、お父さんに聞かせられた話の思い出です(朝日新聞夕刊「一語一会」、2020年9月3日)。
「いいか、お前ら。日本人になりきれよ」
食事時に言われたとか。小泉さんの生家は、江戸時代から続いている福島県の造り酒屋です。お父さんは日中戦争から復員しました。「戦争末期には中越国境地帯で現地の人々に稲作を教え、畦道(あぜみち)に大豆を植え、飯と味噌汁の旨(うま)さを伝えてきた」と、鮮やかな描写で話してくれたとあります。
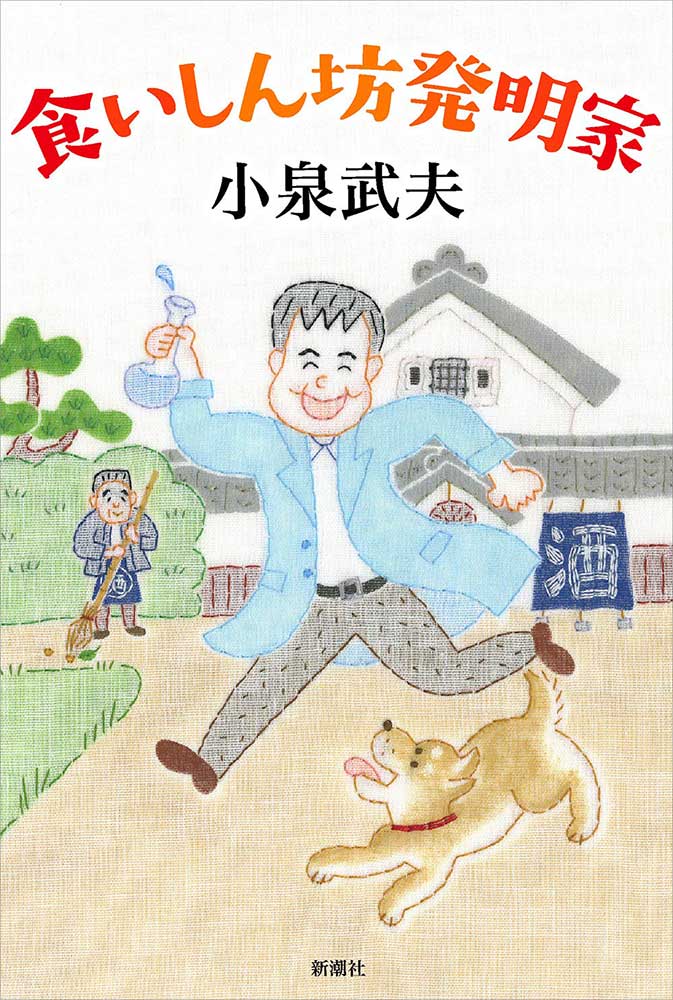
<剣術や昔々の英雄譚を語る時もあったが、心に残ったのは日本の「食」が戦地で人々をつないだこの話だ。だから「日本人になりきる」とは何か、正直よくわからなかったが、「和食しか食わぬこと」と幼心に解釈し、以来、実践することにした。>
おかげで、小泉さんはその後大学で発酵学を専攻し、いまではその道の権威として、また発酵食品の伝道師として多忙な毎日を送っています。
<来し方を振り返るたび、和食を貫く道へと背を押した父に感謝する。「日本人になりきれ」には別の意味もあったかもしれぬが、今となっては構わない。「和食を食べる」と誓ったことが、研究の上でも人生においても、己の礎となっているからだ。>

父親の言葉が、まさに「学びの原点」になったのです。さて、これほどの「一語一会」がわが来(こ)し方にあったかというと、むしろ脳裏に浮かんでくるのは、酒場などで聞いた、あの人、この人の、実に雑多な“名言(迷言)”です。
アホになれんやつがほんまのアホや。
男は愛嬌、可愛気(かわいげ)よ。
明けない夜はない、やまない雨もない。
人生には3つの坂がある。上り坂、下り坂、そして「まさか」の坂がある。
左遷されたとか、降格されたとか、不遇な時に何をやったかで、その後の人生が決まってくる。
誰かが止めてくれなければ、そのうちオレは自分の好奇心に殺されると思う。
青年、また飲もう!
どの場面も、語ってくれた人の表情、語り口、聞いている自分の姿、心境、お店の雰囲気などが、いまでもリアルによみがえります。場面がくっきり目に浮かびます。
酒席では、時事ネタ、スポーツ、懐メロ、ミステリー、映画、演劇など、にぎやかな話題が飛び交います。深夜のバーのカウンターでは、本にまつわるよもやま話や、作家のとっておきのゴシップが、最高のおつまみ、いえ、ご馳走です。
映画のセリフからも、さまざまな人生模様を教えられました。ある人がお気に入りだったのは、
<人生に必要なものは、勇気と想像力、‥‥そして少しばかりのお金。>
チャップリン晩年の名作「ライムライト」(1952年)のセリフです。病気で踊れなくなり、絶望のあまり自殺しようとした若いバレリーナを、売れなくなった落ち目の喜劇役者(チャップリン)がなぐさめ、励まします。「そう、人生はすばらしい。人生を恐れてはいけない」――その後に、先ほどのセリフが続きます。

Cap : 『ライムライト』
価格 Blu-ray¥3,500+税
発売元・販売元 株式会社KADOKAWA
酔ってご機嫌になると、このセリフが口にのぼり、そのあたりから徐々に持論の「プロデューサー論」が、熱をこめて語られます。当時、御茶ノ水にあったカザルスホールの総合プロデューサーを務めていた萩元晴彦さん。

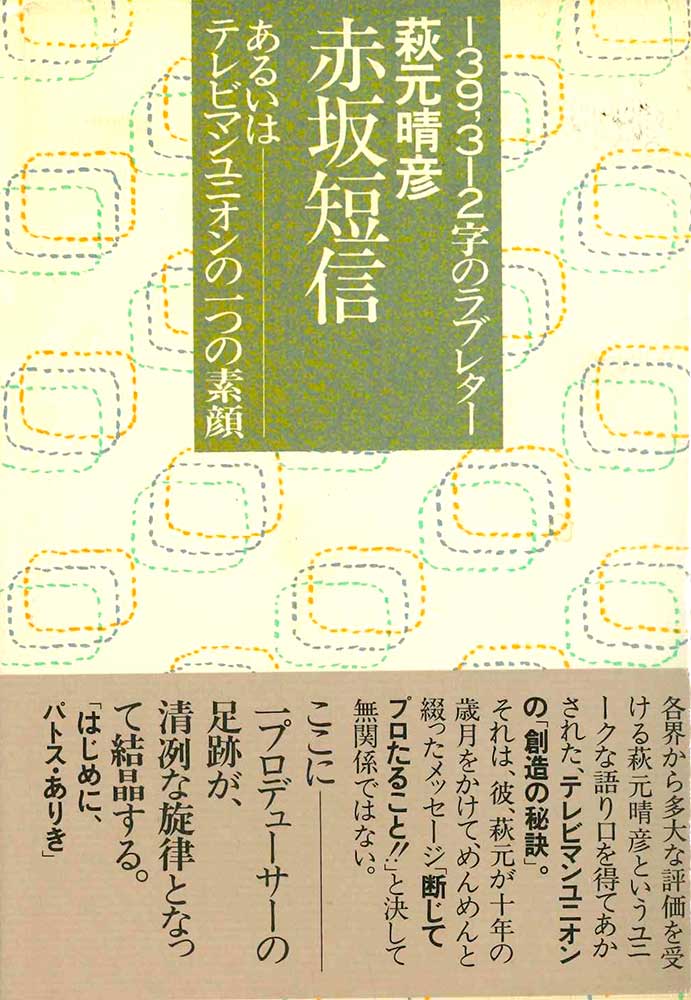
1970年に、テレビ番組制作会社のテレビマンユニオンを設立し、「遠くへ行きたい」「オーケストラがやって来た」など、数々の名番組を手がけるとともに、音楽プロデューサーとして、サントリーホール開館(1986年)の時の企画制作や、カザルスホール(1987年オープン。チェロの世界的名演奏家パブロ・カザルスの名前を冠した、日本初の室内楽専用ホール)のプロデュースにあたります。

『オーケストラがやって来た』DVD-BOX
価格:15,200円(税抜)
発売元:テレビマンユニオン
販売元:TCエンタテインメント
© テレビマンユニオン
<熱狂する。
熱狂できぬ者はプロデューサーたり得ない。
けれども、人間は命じられて熱狂するだろうか。
それは「血」である。
熱狂する「血」が流れていない者はプロデューサーになるべきではない。
あらゆる新しいこと、美しいこと、素晴らしいことは一人の人間の熱狂から始まる。>
<夢見る。
「プロデューサーに必要なものぜんぶ取り上げる。ただしひとつだけ残してやろう」と神さまが言ったとする。
私ならば躊躇なく「夢見ること」と答えよう。
プロデューサーは夢見る。>(萩元晴彦「ホルショフスキーへの旅――プロデューサーは何をするか」より、「婦人公論」1994年9月号~95年9月号連載)
病に倒れ、2001年に亡くなるまで、しばしば夜の席にお供しました。「銀座は夜の学校」と称していました。
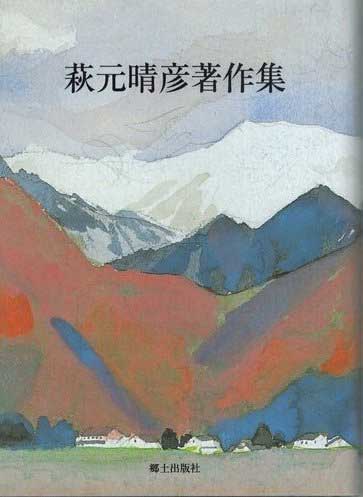
葬儀はカザルスホールで行われ、谷川俊太郎さんが詩を朗読し、今井信子・堀米ゆず子さんらの弦楽演奏や、小澤征爾・井上道義さん指揮による新日本フィルハーモニー交響楽団の演奏が献じられました。
葬儀といえば、「決して一生忘れることはないだろう」と思った弔辞があります。2003年12月6日、しんしんと冷え込む雨の青山葬儀場でした。
イラク復興支援のために現地に赴き、銃撃を受けて非業の死を遂げた2人の日本人外交官、奥克彦さん(45歳)と井ノ上正盛さん(30歳)の葬儀です(現地のイラク人運転手も犠牲になりました)。
辛口時評が売りものだったコラム「紳士と淑女」(雑誌「諸君!」連載)が、「なぜ、こんなにいいヤツがイラクに行って死なねばならないのか」と嘆き、「この世にまだこんなに感動に値することがあったのかと思うほど感動した」と記した葬儀です。
<二人はイラクの未来を信じ日本人の可能性を信じて、現地で積極的に働いていた。恐れも気負いも、シニシズムのカケラもなかった。奥が七十一回も外務省HPに送り続けた「イラク便り」。
「俺は危険がないなんて一言も言っていない。危険を回避するために可能な限りのことをする。ただ、リスクがあってもやらなければならないこともある」と言ったという。かつてエジプトで大ヒットしたアラビア語の「おしん」を、イラクに持っていったのも彼だった。>(「紳士と淑女」、「諸君!」2004年2月号、文藝春秋)

2人の遺影の前で弔辞を読んだ小泉純一郎首相は、途中で言葉に詰まり、語ろうとして言葉になりませんでした。一国の総理が絶句し、しばしの沈黙に耐えている姿には、さすがに胸を衝かれました。
最後にマイクの前に立ったのは、奥克彦さんの小・中・高校の先輩で、同じ伊丹高校ラグビー部で“花園”をめざした阪本真一さんという人でした。震える声で彼が語り始めた瞬間に、思いが参列者に伝わります。
「奥よ。
聞こえるか。どうしてるねん、そんなところで横になって。まだ、ハーフタイムじゃないか。ほら、立ち上がって、後半もいっしょに戦わないとあかんやろう」
兵庫県大会の準決勝、左ラインアウトからのロングスロー、阪本のパスを奥が取ってつないで、トライ! 「おぼえているよな。僕は昨日も今日も夢にみた。おまえは輝いていたぞ。でも、僕は、これからは誰にパスをすればいいんだ」
そして、呼びかけ続けます。「奥よ。おまえは決して逃げなかったなぁ」「奥よ。おまえは本当のリーダーだった」「なぁ、奥よ。人はどこから来て、どこにいくのだろう。人は何をするために生まれてきたのだろうなぁ」
「ことし、八月末、おまえが、「‥‥したがって、僕の結論はダイ・ハードです」と書いてきた時、僕は「人生、一度や二度は命を張る心算でやらざるを得ないこともあり、貴兄がいま、根性をいれてタックルをする決意で踏みとどまろうとすることを、何よりも誇りに思います。(略)」と答えた。おまえは覚悟を決めた、と感じ、僕も覚悟したのだ。
でもなぁ、奥よ。僕の返事はそれで良かったんだろうか。昔読んだ与謝野晶子の歌が耳を離れない」
“君、死にたまふことなかれ”の例の歌です。そしてもう一度問いかけます。
「人は何をするために生まれてきたんだろう。
奥よ。
ようやく分かったよ。
おまえはこの仕事をするために、きっと選ばれて生まれてきたんだ。そうに違いない。死に様で、生き様を示すよう、天に呼ばれたんだろう」
この人の声涙ともに下る弔辞を聞きながら、ほんとうに胸を打たれました。「紳士と淑女」が「この世にまだこんなに感動に値することがあったのかと思うほど感動した」というのは、立ち合った約3500人の参列者すべてだったと思います。

それから7年後、「ラグビー 男たちの肖像」(「週刊現代」連載・第67回)で、スポーツライターの藤島大さんは、奥さんについて回想します。
<36年前、異色のフルバックが花園の全国大会に出現した。兵庫県立伊丹高校2年、奥克彦である。手足が外国人のように長い。色白で細身で天然の茶髪。風貌のみならず、ストライドの広いラン、懐の深さを利したパス、よく飛ぶキックは独特で県の選抜にも入った。
早稲田へ進み、ラグビー部の門を叩く。身長181cmは当時としては大型だ。鍛えられた。レギュラーの座はすぐそこにありそうだった。それなのに2年の夏合宿の途中、退部を申し出た。「外交官試験」が理由である。根底には、青春のまっとうな悩み、すなわち「ラグビーばかりでよいのか」が横たわっていたはずだ。>
個人的に、私も多少の付き合いがありました。奥さんが外務省に入り、オックスフォード大留学を終えて間もない頃に、共通の友人を通じて知り合い、交流を持つようになりました。共通の友人は、1998年に45歳の若さで亡くなりますが、その「追悼文集」に並んで文章を寄せました。
イラクでの活躍ぶりは、もっぱら外務省の先輩である岡本行夫さん(外交評論家)から聞いていました。その岡本さんに私がインタビューした「湾岸戦争のような禍根を残さないために」(「中央公論」2003年11月号)を、奥さんは先の阪本真一さんに「読んでほしい」と死の直前にメールしていたそうです。数年後に知った事実です。
岡本行夫さんは、2006年に記しています。
<奥克彦大使と井ノ上正盛書記官がイラクのティクリット近辺で襲撃され非業の死に遭ってから、三年近い歳月が流れた。奥たちが文字通り血と汗を注ぎ込んだイラクでは、今も戦闘とテロが続いている。彼らが思い描いた復興の道は、まだ遠い。(略)
時は人間の記憶を薄れさせる。しかし、逆に記憶を鮮明にすることもある。人間の強い思いが却って浮き彫りにされ、心の中に一層強く刻みつけられる。奥に関する思いは、僕の中で弱まることはない。彼を知る多くの人間にとっても同じだろう。>(『砂漠の戦争――イラクを駆け抜けた友、奥克彦へ』文春文庫)

奥さんを襲った事件のことは、社会的な記憶としては次第に薄らいでいるかもしれませんが、「ラグビーを通した日英交流を」というその遺志を引き継いで、両国の関係者らによる「奥記念杯(Oku Memorial Trophy)」追悼試合が、死の翌年(2004年)から毎年、英国で行われています。奥さんの念願だったラグビー・ワールドカップの日本開催も、昨年、みごとに実現しました。
「making a difference(行動し変化をもたらす)」(奥記念杯プログラムより)の人として、いまだに日英のラガーたちから慕われています。
「この人がしてくれた、こんな話」のことを書き始めたら、酒場での昔の会話に思いがおよび、映画のセリフから萩元晴彦さんを思い出し、そして阪本さんの弔事、奥さんのことがどうしても書きたくなって、自分でも思いもかけない原稿になりました。
“随想”とはこのことかと思いつつ、ここにもコロナウイルス禍の影を感じないわけにはいきません。
2020年9月10日
ほぼ日の学校長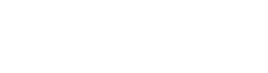
*4月24日、岡本行夫さんが新型コロナウイルスによる肺炎のために亡くなりました。茫然とした思いが、いまだに消えそうもありません。
*ほぼ日の学校オンライン・クラスに万葉集講座・第9回の後に行われた
<補講>、「梯久美子さんが語る、
島尾敏雄とミホ、戦時下の愛と歌」を公開しました。

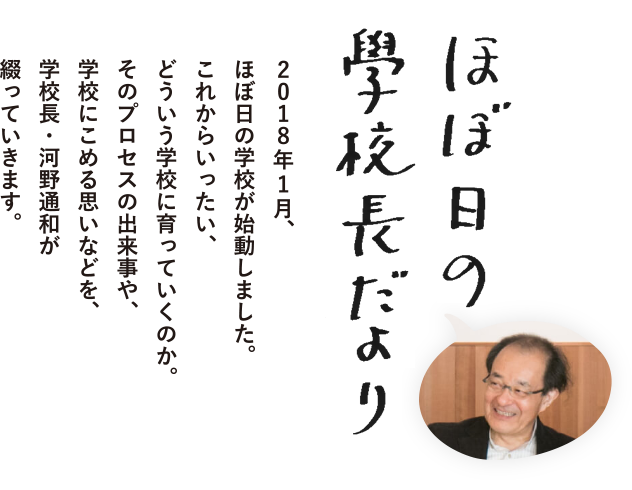
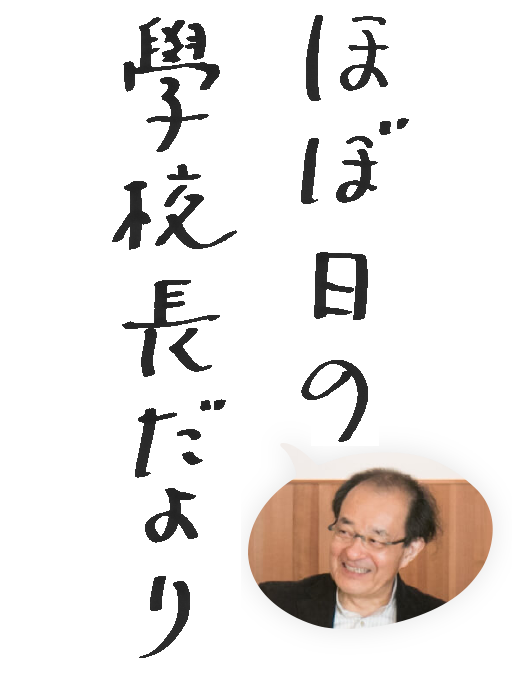
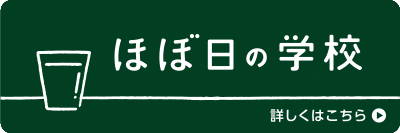

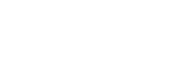

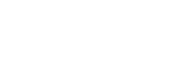




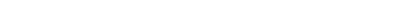
メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。