ほぼ日の学校長だよりNo.102
ゴッホの感動(その2)
原田マハさんの『たゆたえども沈まず』(幻冬舎)をおもしろく読みました。「ゴッホの壮絶な人生を描いたアート小説の最高峰!」と帯に謳われています。

1886年2月、32歳のゴッホは突然パリにやってきます。画廊勤めをしている弟のテオを頼って、何の前触れもなく――。テオはその日の朝、兄がパリに着いたと知らせる短い走り書きの手紙を受け取ります。
<一気にパリまで来てしまった。どうか怒らないでくれ。
いまからルーブルへ行ってくる。「方形の間(サル・カレ)」に来てくれるかい。待っているよ。
君と話がしたい。きっとすべてがうまくいくはずだ――。 フィンセント>(前掲書)
テオにとってはまったくの不意打ちでした。しかし兄は、「ずいぶんと考えたし、こうすることで時間の節約になると思っている」と言うのでした。
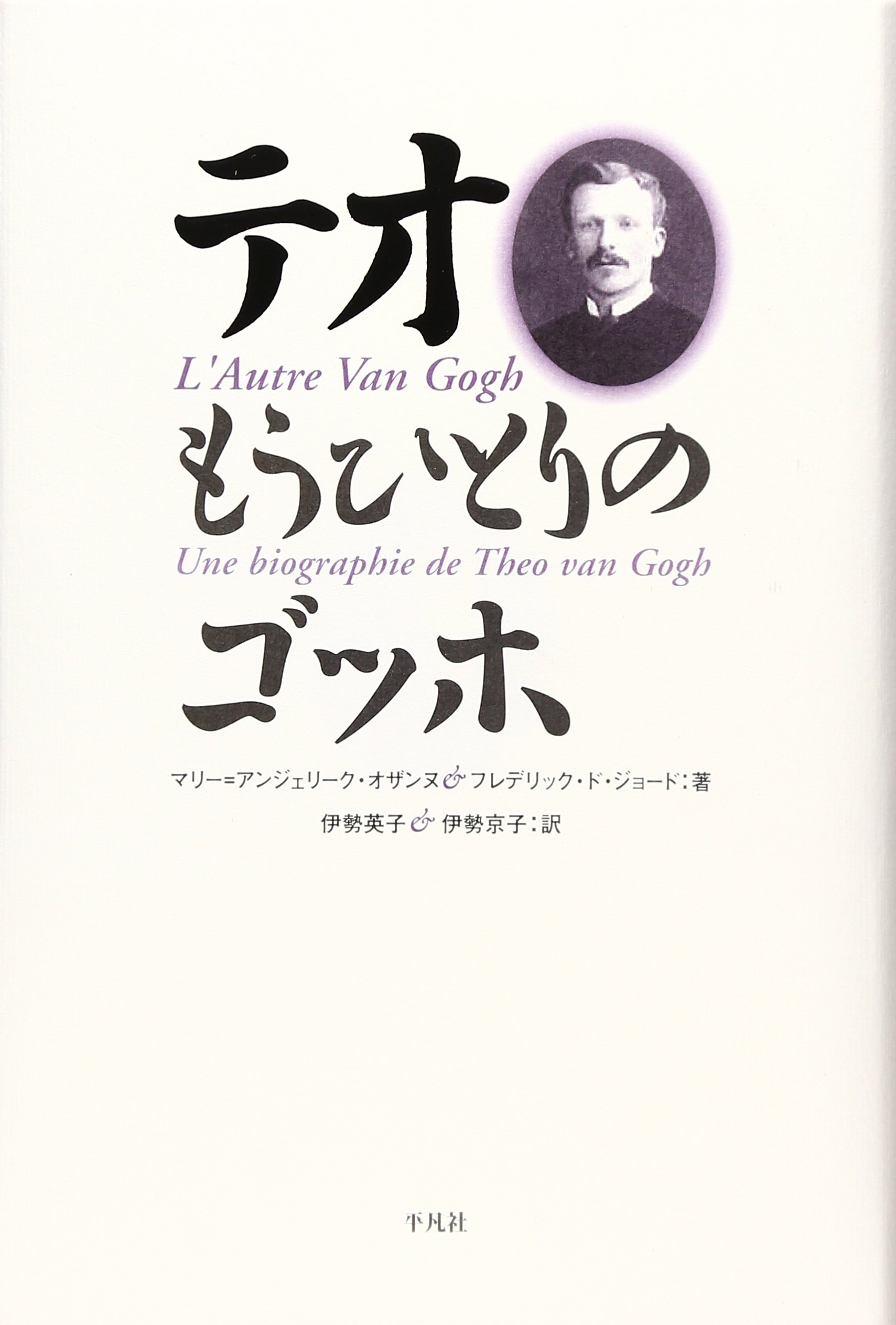
このパリ転居を機に、ゴッホの画風は一変します。テオの協力を得て印象派の画家たちと出会い、彼らの明るい色彩や斬新なタッチに衝撃を受けます。
自由な感性に基づき、新しい視覚を信じる印象派画家たちとの交流が、彼の作品を劇的に変えます。「彼の天才は、直ちにこれに応じた」と小林秀雄が評する通りです。
<先ず何を置いても、全く謙遜に、無私に驚嘆する事。そういう身の処し方が、ゴッホの様な絶えず成長を止(や)めぬ強い個性には、結局己れを失わぬ最上の道だったのである。>(『ゴッホの手紙』小林秀雄全作品20、新潮社)
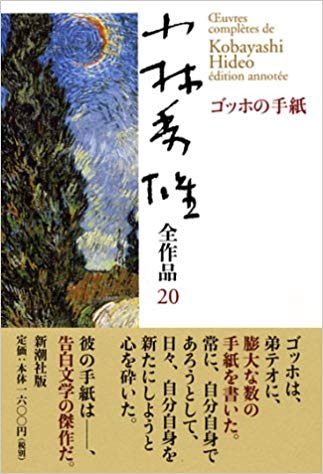
もう一つは、日本美術の影響です。ゴッホに「花魁(おいらん)」(1887年)という作品がありますが、溪斎英泉(けいさいえいせん)の浮世絵「雲龍打掛(うんりゅううちかけ)の花魁」を模写しつつ、独自の新しいスタイルを模索したものです。
<中央に花魁の絵が色鮮やかに描かれています。さらに模写だけでなく、オリジナルで竹林や睡蓮の池、鶴など、日本のイメージを集めて描いています。当時としてはアバンギャルド、コラージュ的で、まさに現代アート。無謀なことをやってのけている感じが伝わってきます。色もビビッドで、ゴッホが心から楽しんで描いたことが想像できる一点です。>(原田マハ『ゴッホのあしあと――日本に憧れ続けた画家の生涯』、幻冬舎新書)

何を見てこれを描いたのか? おそらくオリジナルの版画ではなく、「パリ・イリュストレ」誌の日本特集号(1886年5月号)の表紙に使われた英泉の「雲龍打掛の花魁」を模写したのではないか、と推測されます。
そこで原田さんは、「パリ・イリュストレ」誌に日本美術の紹介記事を書いている林忠正という日本人美術商に着目します。
パリで「ジャポニスム(日本趣味)」と呼ばれる日本ブームが巻き起こったのは、19世紀後半のパリ万博がきっかけでした。パリでは頻繁に万博が開かれ、1855年、67年、78年、89年、1900年、1937年と続きました。その間、日本では1867年に大政奉還があり、68年に明治政府が樹立します。まさに激動の67年に、日本はパリ万博に初参加します。
<万博は、世界各国の産業の見本市です。各国が「我が国のイチオシはこれだ!」という産業や物産を展示し、世界へアピールしました。ところが日本は鎖国をしていたので、海外にアピールすべき産業が何もありませんでした。何を見せたらよいか。そこで考えたのが美術工芸品でした。日本はこの美術工芸品を引っ提げて、一八六七年のパリ万博に初登場しました。一八七八年のパリ万博で二度目の登場をしたときも、やはり美術工芸品がメインでした。>(同前)
これを機に、19世紀末から20世紀初頭にかけて、西洋社会に「ジャポニスム」の一大ブームが起こります。フランスでは、浮世絵を中心に日本の美術品の熱狂的な収集が始まります。新しい表現を求める画家たちは、熱心に浮世絵の技法――斬新な構図、独特の遠近法、鮮やかな色、描線――などを研究します。マネ、モネ、ドガ、シスレー、ロートレック、そしてゴッホなどです。

オーヴェールの麦畑(撮影・今村正治、以下同)
そのブームの一翼を担ったのが、先の林忠正です。3回目のパリ万博に通訳として参加し、そのままパリに定住し、浮世絵などの日本美術を扱うビジネスを始めます。
<日本からたくさんの美術品を仕入れてヨーロッパで売り、多くの芸術家やコレクターたちと交流し、一時代を築いた人物です。孤軍奮闘して日本美術の正当な価値を西洋社会に認めさせた人物として、研究者のあいだでは「ジャポニスムの陰の立役者」とも称されています。>(同前)

「烏の群れ飛ぶ麦畑」の場所
質の高い日本美術を取り扱う本格的な美術商で、しかも純然たる日本人。完璧なフランス語を使い、機知に富んだ会話で人を魅了し、優雅な物腰、人あしらいの巧みさを備えています。もちろん日本美術に関する豊かな知識は言うまでもありません。
しかし、これだけの成功を収めた人物であるにもかかわらず、なぜか歴史の闇に葬られ、いまではすっかり忘れられた存在です。パリから帰国した後、「日本の大切な美術品を海外に流出させた」というので“国賊”呼ばわりされ、52歳で失意のうちに亡くなります。
とはいえ、何をおいても、林はゴッホ兄弟と同じ時期にパリにいたのです!
そして、弟のテオは同じ美術業界で働いていたのです!
林忠正とゴッホ兄弟の間に「交流があった」という文献は、いまのところ見つかっていません。面識があったという証拠も何一つありません。しかしながら、彼らに「交流があったかもしれない」という可能性は否定できません!
原田マハさんの『たゆたえども沈まず』は、まさにその点に着想を得て書かれた作品です。「交流があったかもしれない」――そこに創作の可能性を見出し、林忠正と彼の部下である加納重吉という架空の人物を配することで、日本人美術商とゴッホ兄弟の類まれな物語を紡ぎ出します。
そして、「互いを自分の半身であると感じる双子のような不思議な結びつき」――4歳違いの「分かちがたい魂」であるゴッホ兄弟の愛と苦悩のドラマを浮かび上がらせます。
諸説あるようですが、生前にゴッホの売れた絵は「赤い葡萄畑」(1888年)の1枚だけだったと言われます。描いた絵を、ゴッホはすべて弟のテオに送りました。「売ってほしい」「売ってくれ」と。
テオは自分の「専属画商」であるべきだ。弟が売るべきなのは、フランス芸術アカデミーに所属する大家や印象派画家たちの絵ではなく、自分の絵だ、とゴッホはかたく信じていました。しかし、ゴッホの作品はただの1枚も売れません。
<フィンセント・ファン・ゴッホという画家を、この世でもっとも理解しているのはテオである。フィンセントの画家としての力量を推し量り、将来性を信じ、経済的にも精神的にも、全力で支えている。(略)
フィンセント・ファン・ゴッホ。――ぞっとするほど、すごい画家だ。
けれど――。
彼のすごさを、どうやって世の中に認めさせたらいいのか。テオの苦悩を重吉は共有していた。
自分だとて、フィンセントが比類ない画家だとわかっている。しかし、それを世の中に認めさせる方法を知らないし、そんな力量もない。
それができるのは、冷徹に社会を俯瞰し、鋭く市場を見極め、新しい芸術を果敢に押し出す勇気を持った人物。
それは、いったい誰か。
――林忠正こそが、その人ではないだろうか?>
このように4人は交錯していきます。史実と想像が溶け合った原田ワールドの醍醐味です。
2年間のパリ生活に見切りをつけ、その後、アルル、サン=レミ、オーヴェール=シュル=オワーズに移り住むゴッホ。その間に、画家ゴーギャンとの共同生活、わずか2ヵ月での訣別、「耳切り事件」、精神病の発作、などが相次いで起こります。

ゴッホが下宿していたレストランのラヴー亭(オーヴェール)
そして人生最後の2ヵ月をオーヴェールの地で過ごし、1890年7月29日、37年の短い生涯とわずか10年間の画業を、自らの手で絶ちます。
自殺者だったため、教会での葬儀はかなわず、弔鐘も鳴らされませんでした。棺桶を運ぶ馬車すら教会は貸し出すことを渋ります。結局、告別式は宗教的な儀式もなく、ゴッホが下宿していたラヴー食堂の2階で行うことになり、棺を墓地へ移送するのは隣村の村役場の馬車を借りました。
テオはパリからオーヴェールに駆けつけ、その葬儀の一切をひとりで仕切ります。テオの妻ヨハンナ(通称ヨー)は、幼子を連れて、折悪しくオランダの実家に帰省している時でした。
小説では、その場に重吉が駆けつけ、テオを見守ります。晩秋に、日本からパリに戻ってきた林は、すぐさま重吉とともにオーヴェールに赴き、ゴッホの墓参をします。
<葬儀のときに弔鐘が鳴らなかったと聞かされて、憤った彼は、正午ぴったりに墓の前に到着すると、昼を報せる教会の鐘が鳴り響く中で、深く頭を垂れた。鐘が鳴り終わっても、なかなか頭を上げなかった。フィンセントの魂と会話しているのだ――と重吉は察した。>

作品にも描かれたオーヴェールの教会
ゴッホの生涯はよく知られるところですが、そこに林忠正、そして加納重吉を寄り添わせることで、作者は自らの思いを重ねます。「日本とゴッホは相思相愛」というそのメッセージを、物語の通奏低音として響かせます。
元来、病弱だったテオは、兄の死をきっかけに健康を害し、ゴッホの後を追うようにわずか半年後の1891年1月、ユトレヒト(オランダ)の精神科病院で亡くなります。33歳。
亡くなってユトレヒトに埋葬されたテオでしたが、やがて妻のヨーが、オーヴェールにあるゴッホの墓の隣に、テオの墓も移します。こうしてゴッホ兄弟の墓は、2つ並ぶことになりました。

蔦に覆われたゴッホ兄弟の墓(オーヴェール)
テオの妻ヨーの功績は多大です。彼女はゴッホとテオが亡くなった後、オランダのラーレンという町で下宿屋をしながら一人息子を育て、2人の遺産を管理します。次第に名声が高まるゴッホの回顧展に作品を貸し出し、かたわらゴッホの膨大な量の書簡を整理し、没後24年の1914年に最初の書簡全集を刊行します。
岩波文庫で3冊、またゴッホ研究者の二見史郎、圀府寺司両氏による『ファン・ゴッホの手紙』(ゴッホの没後100年を記念して刊行された新たな書簡全集の選集、みすず書房)などの翻訳を、いま私たちは手にすることができます。
ヨーの四半世紀にわたる、気の遠くなるような編集作業のたまものです。ゴッホ兄弟への深い愛情と理解、尊敬の念がなければ到底不可能な事業であったことは言うまでもありません。
「ゴッホの手紙は告白文学の最高傑作だ」(小林秀雄)とまで評される彼の文章に触れることができるのも、またテオとゴッホが並んで眠るオーヴェールの墓に、世界中からのファンが足を運ぶことができるのも、すべてヨーの偉大な功績です。
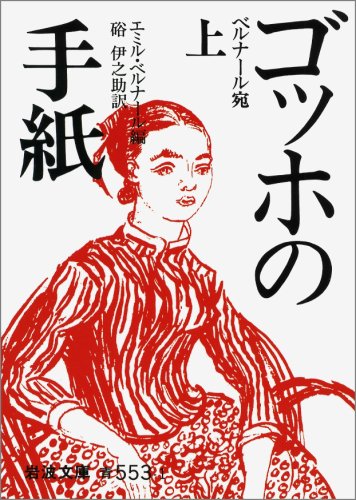
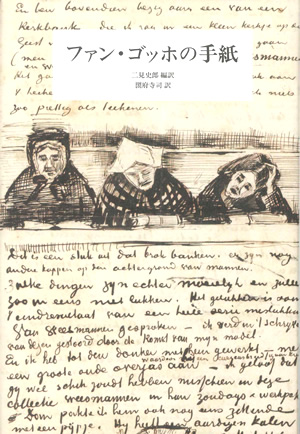
最後にこの小説のタイトルについてですが、「たゆたえども沈まず」とは、花の都パリ市の紋章にラテン語で記されたことばです。「揺れはしても、決して沈まない」という意――。

なぜこのタイトルがつけられたのか? それは作品をお読みいただくのが一番です。このことばに作者のさまざまなイメージが重ねられ、情感がこめられます。そして4人のドラマを見守るように、いつも背後に流れていたのがセーヌ川です。
2019年10月31日
ほぼ日の学校長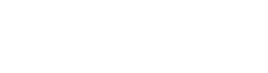
*11月30日(土)に、江戸東京博物館にてほぼ日の学校のイベント「浮世絵ひらがなトーク」を開催します!河野学校長とお話ししてくださるのは美術ライターの橋本麻里さんです。ゴッホも魅了した日本の浮世絵について、ゆっくり目を向けてみませんか? 併せて、予告コンテツもぜひ読んでみてください。

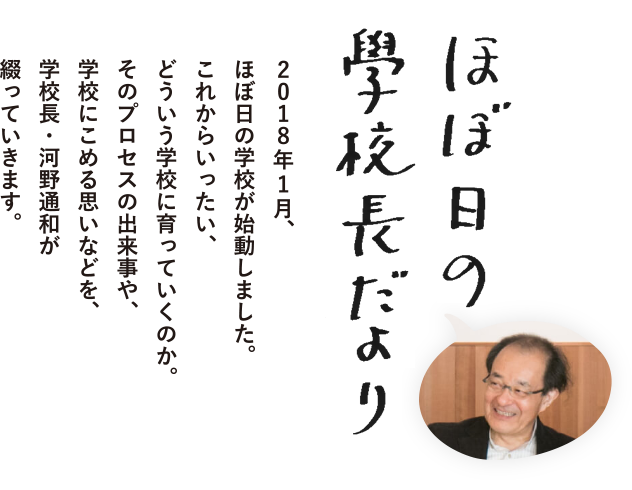
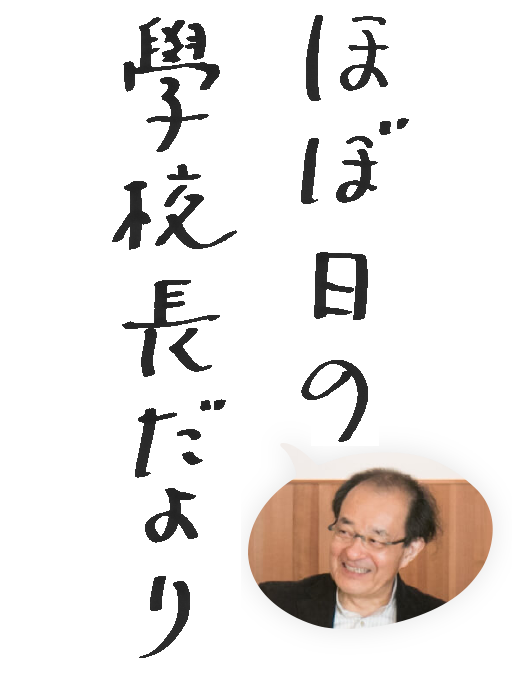
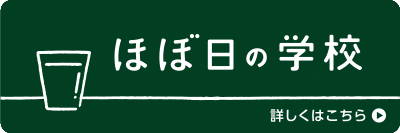

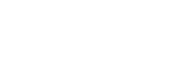

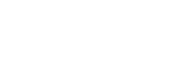




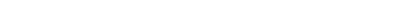
メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。