ほぼ日の学校長だよりNo.103
岩谷時子という人生
1953年生まれの私の世代だと、作詞家・岩谷時子の名前を知らない人は、まずいません。国民的大ヒット曲となった加山雄三の「君といつまでも」をはじめ、作曲・弾厚作(加山の作曲家としてのペンネーム)、作詞・岩谷時子の名コンビは、「夜空の星」「お嫁においで」「旅人よ」「ぼくの妹に」「海 その愛」など、数々の名曲を生み出しました。

1960年代以降の流行歌でいえば、ザ・ピーナッツ「恋のバカンス」「ウナ・セラ・ディ東京」、岸洋子「夜明けのうた」、ピンキーとキラーズ「恋の季節」、園まり「逢いたくて逢いたくて」、佐良直美「いいじゃないの幸せならば」、郷ひろみ「男の子女の子」などが、次々に思い浮かびます。

「愛の讃歌」「サン・トワ・マミー」「ろくでなし」など、昭和の大スター越路吹雪(こしじふぶき)の歌ったシャンソンの訳詞は、すべて岩谷時子が手がけたものです。人気テレビドラマ「これが青春だ」「サインはV」「アテンションプリーズ」の主題歌もそうだと聞くと、「うそっ!」と思わず言いたくなります‥‥。
ただ、名前はいつの間にか覚えたものの、どういう人なのかはまったく知らないままでした。雑誌編集者になってほどなく、1980年11月7日に、越路吹雪さんが56歳で亡くなります。その時初めて、越路さんの生涯にわたるマネージャーが、岩谷さんだったと教えられます。
やがて、劇団四季の「ジーザス・クライスト=スーパースター」や「ウェストサイド物語」、あるいは東宝の「レ・ミゼラブル」「ミス・サイゴン」などの上演訳詞を、岩谷さんが書いていることを知ります。彼女に関する情報も、少しずつ耳に届くようになりました。
彼女を語る人は、決まってその人柄を讃えました。控えめで、清楚で、気どらなくて、ざっくばらん。いつも穏やかな笑みを絶やさない、まるで“聖女”のようだ、と。
それでいながら、言うべきことはきちんと言う。外柔内剛で、芯は強い。仕事は誠実で完璧。彼女に頼んだら、あとは“大船に乗った気”で安心して任せられる、と。
岩谷さんの書く詞には、ドキリとさせられるフレーズや情景が出てきます。その頃の歌謡曲ではあり得ない発想、センス、意表をついた語彙や比喩が衝撃的でした。「恋のバカンス」や「恋の季節」など、“女”の視点で書かれたおしゃれで、品よく、都会的な恋――。


初めて「ウナ・セラ・ディ東京」(1964年)を聞いた小学生時代、「街はいつでも 後ろ姿の 幸せばかり」――このフレーズが、なぜか好きで好きでたまりませんでした。

岩谷さんのエピソードは聞けば聞くほど、むしろ神秘性が増すようで、どういう人であるかが気になりました。けれども、謎は謎のまま、ついにお会いする機会はなく、2013年10月25日、97歳の天寿をまっとうし、天国へと旅立たれます。
前置きがすっかり長くなりましたが、こうした積年の思いを一気に満足させてくれる渾身の評伝にめぐりあいました。村岡恵理さんの『ラストダンスは私に――岩谷時子物語』(光文社)です。

著者の村岡恵理さんは、NHK連続テレビ小説「花子とアン」の原案である『アンのゆりかご――村岡花子の生涯』(新潮文庫)の著者です。この村岡さんと岩谷さんという組合せを見た瞬間、ベスト・マッチングではないか、という期待が高まりました。

まさにそういう本でした。いまの若い読者が岩谷時子の名前をどれほど知っているかはわかりません。現に、この本を読むように勧めた30代後半の男性は、岩谷さんを知りませんでした。本の帯に「作詞家として大衆を魅了し、影の人として友を支えた人生。彼女はまさに“利他の心”の表現者であった」という言葉を寄せた竹内まりやさんのほうに反応していました。
著者の村岡恵理さんは1967年生まれなので、「君といつまでも」など岩谷さんのヒット曲をオンタイムで聞いた世代ではありません。ただ、「母や母の親友が越路吹雪さんの大ファンで、私自身も子どもの頃から日生の名作劇場や宝塚歌劇、東宝や四季のミュージカルに親しんでいましたので、岩谷時子さんのお名前は大変よく耳目にしていました」(あとがき)と述べています。

近すぎず遠すぎず。この絶妙な距離感が作品にとっては幸いでした。“聖女”のようだったという岩谷さんの人柄の魅力、ピュアなたたずまいを伝えるとともに、彼女の著書や、若き日の日記などを手がかりに、その穏やかな笑顔の奥に秘められた強い意志、働く女性としての苦悩や葛藤、プロフェッショナルとしての情熱や矜持、あるいは焦燥感や孤独など、これまで見えてこなかった岩谷時子像を鮮やかに浮かび上がらせています。
さまざまな意味でパイオニアであった彼女の人生がどのように“豊か”なものであったかが、具体的な手触りとして伝わってきます。
全篇、興味深いエピソードが満載されています。どれにしようかと迷うのですが、やはり8歳年下の越路吹雪さんとの40年来の友情は格別です。
リサイタルの本番を直前に控えた越路さんの横顔は、よく知られるところです。それが、岩谷さんとの会話を通して描かれます。
<「お客さんは入ってる?」
「満席よ」
「本当?」
「本当よ」
「みんな本当にあたしの歌を聴きに来ているの?」
「今日、あなたの他に歌う人いる?」
「そりゃそうだけど‥‥」
「あなたは全てやり尽くしたんだから、
あとは楽しめばいいわ」
「無理よ。楽しむなんて‥‥。息がつまりそう」
越路の指先が細かく震えていた。百選練磨のはずなのに舞台に慣れることを知らない稀少な神経の持ち主である。時子は越路の背後に回り、力が抜けるよう両手でゆっくり肩を撫でた。>
そうして「おまじない」をかけ、歌い手をステージへと送り出します。スポットライトを浴びたその瞬間から、越路さんがみるみる観客を惹き付け、劇場の空間をわがものとしていきます。それを、舞台袖で身を震わせ、ぞくぞくしながら見守っているのが常だったといいます。

1953年、「本場のシャンソンを自分の目と耳で確かめたい」と、パリに旅立つ越路さんに、岩谷さんは1冊のノートを手渡します。エディット・ピアフを生で聞いた感激が、その日記帳に綴られます。
<4月23日
夜、ピアフを見る。オーケストラの良さ、彼女の歌うときのゼスチャア、アレンジの素晴らしさに、私は悲しむ。(略)
私もパリで生活し、キャバレエで歌っていたら、何かをつかむことができるだろうか。まだ何もつかむことができず、ただ疲れている自分を感じる>
<5月7日
ピアフを二度聞く。
語ることなし。小林さんも感激していられた。
私は悲しい。夜、ひとりで泣く。
悲しい、淋しい、私には何もない、何もない。私は負けた。
泣く、初めてパリで>
小林さんは、批評家の小林秀雄です。親友の今日出海(こんひでみ)さんと2人でヨーロッパを旅行中でした。ちなみに、『ボクの音楽武者修行』(新潮文庫)の小澤征爾さんも、この時パリで小林さんと歓談のひと時を過ごしています。

後年、大スターになった越路吹雪について、岩谷さんはこう語っています。
<越路は18年前に初めてのパリで小林秀雄と今日出海に連れられ、生のピアフを聴いて、打ちのめされた。だからこそ、どんなに賞讃されても決して驕らない今の彼女がある。>
とはいえ、マネージャーとタレントの関係は、いつも晴天とは限りません。友情に亀裂が生じかねない危機もありました。越路の夫で作曲家の内藤法美(つねみ)とは、越路をはさんで、つねに確執がありました。

東宝演劇部の総帥である菊田一夫、劇団四季の浅利慶太らとも、厳しい駆け引きや、軋轢が絶えません。その板挟みのストレスに耐えながら、実力者たちを相手に、ちゃんと筋を通していく岩谷さんの姿が見事です。
越路の人間的な弱さ、浪費癖などに苛立つ様子も描かれます。2人の間に想像以上の、激しい言葉の応酬があったことにも驚かされます。「越路さんとの友情も、時には火花を散らし、本音でぶつかりあったからこそ、より深まったのではないでしょうか」と、著者は記します。
1951年、宝塚歌劇団を退団し、東宝に移籍する越路に同行して、12年間勤めた宝塚出版部から東宝文芸部に異動し、岩谷さんは越路の正式なマネージャーになります。次の転機は1963年に訪れます。作詞家として多忙な日々を送り始めたこの年に、東宝を退社し、47歳でフリーの道を選びます。
「今後、越路のマネージャーは社命ではなく、友情で続けていく」
こう宣言して、生業はあくまで作詞であり、マネージャー業で稼ぐつもりはない、と言い切ります。そして実際、以後は無償のマネージャーに徹するのです。
<「勝手かもしれないけれど、私たちは共存共栄で行きたいの。(略)対等だからこそ、言えること、できることもあると思うのよ」
「わかったわ。つまり、時子さん、あたしにいばりたいんでしょう。お金もらったらいばれなくなると思ってるんでしょ」
「そうよ」
顔を見合わせてお互い吹き出した。付き人やファンの延長のようなマネージャーならいくらでもいようが、本当に親身に、時には苦言を呈し、時には共に戦う、信頼のおける助っ人は、時子をおいて他にはいないということを、越路自身が誰よりも一番よくわかっていた。>
<マネージャーはタレントを本当に愛し、苦楽を共にする覚悟がなければやってはいけない、できない仕事だった。>

本気で人を愛し、才能を愛することの厳しさ、人に尽くすことの孤独を、これほどわきまえ貫いた人だとは、この本を読むまで想像もしませんでした。本書の最大のオマージュは、岩谷さんのこの生き方に捧げられています。


彼女の訳詞について「名人芸」と早くから評価したのは、永六輔さんでした。「越路吹雪のシャンソンがいかに美しい日本語か」と言い、「言葉が譜面の上で正しく生きている」と評しました。劇団四季の浅利慶太氏も「言葉が端的に洗われていて素晴らしい。岩谷さんの仕事は俺の感覚に合う」と言って、彼女の訳業を頼みにしました。
岩谷さんは19歳で神戸女学院を卒業後、23歳で宝塚歌劇団出版部に就職するまでの4年間、病身の父親を抱えながら、「歌劇に慰められ、宝塚文芸図書館に通い、ひたすら本を読み、投稿を続け」ます。「この時期に、後に詩人としての才能をいかんなく発揮する、言葉の宝石が豊かに蓄えられたのだと思います」(あとがき)と、著者は述べます。

その岩谷さんならでは、という逸話を最後に紹介しておきます。1987年4月、ミュージカル「レ・ミゼラブル」の日本上演が決定されます。その訳詞を岩谷さんが担当するのですが、オリジナルスタッフの音楽監督(クロード=ミッシェル・シェーンベルク)からは「言葉を乗せすぎて、メロディラインが台無しになっている。原則としてひとつの音符にひとつの言葉だ」と言って、徹底的なやり直しを命じられます。

ところが、稽古に入ると、今度は演出家(ジョン・ケアード)から「言葉を削りすぎているため迫力に欠ける」と厳しい指摘を受けます。「ビクトル・ユゴーの思想は君に捨てられた言葉の中にある」と、歌詞の書き込まれた楽譜が放り投げられます。
<負けるものか――。ビクトル・ユゴーの思想と、一音符一シラブルの法則のはざまで、連日手直しは続いた。ジョン・ケアードとシェーンベルクの間でも火花が散り、時子を加えた三人、通訳も数えると四人で徹底的に話し合い、いくつかの歌詞の字余りが認められた。舞台に懸ける情熱は、言語や文化の違いを越えていた。>
なんとも凄まじい現場です。それに「負けるものか」と食らいついていくのが、71歳の岩谷さんです。これも、素晴らしいのひと言です。
そして本書は、この「レ・ミゼラブル」の公演が初日を迎える直前で、物語の幕を下ろします。
そこで、ここまで読んでくださった皆さんに、最後にひとつお尋ねです。この場面を皆さんはどう読むのでしょう? 亡くなるひと月ほど前の越路吹雪さんの胸のうち、です。
<ある日、時子は越路に手招きで呼ばれた。腰でも痛くなったのかとベッドの近くに寄ると、突然、彼女がゲンコツで時子の頭を殴った。病人にこんな力があるのかと思うほどの強さだった。何も言わずにじっと見つめられ、咄嗟に返す言葉もなく、鈍痛の響く頭の中で、時子は自分に向けられた怒りの意味をその後ずっと考えた。
それからは坂道を転がって下りていくように容態は悪化した。>

本の中に直接の答えや解釈が述べられているわけではありません。私も読後、「ずっと考えている」さなかです。「読書会」というのは、こういう時にやればいいのでしょうね。
2019年11月7日
ほぼ日の学校長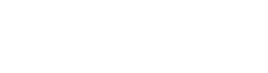
*都合により、来週は休みます。次回の配信は11月21日の予定です。
*ほぼ日の学校オンライン・クラスに万葉集講座第6回授業が公開されました。俵万智さんによる、歌にあわられた「万葉びとの恋」について。

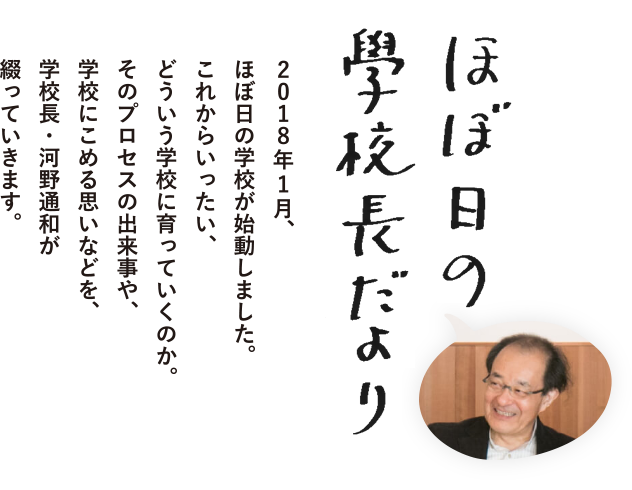
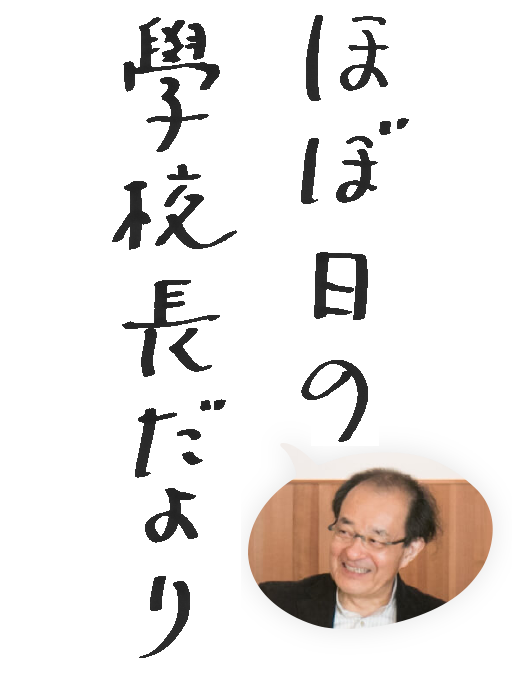
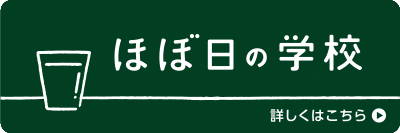

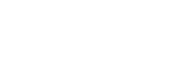

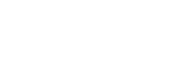




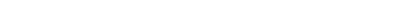
メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。