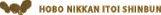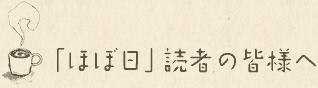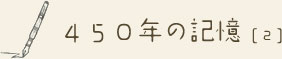山本彩香さんは、1935年に東京で生まれた。
沖縄出身の母親と本土の父親が結婚し、
その4番目の子どもだった。
当時、沖縄の人は本土で差別されていたという。
一家は貧困の中で長女と次女が相次いで病気でなくなり、
彩香さんは2歳で母親の姉のところに養子に出される。
その女性が彩香さんの育ての親となり、
後の彼女の人生を決定づける影響を与えることになる。
女性の名は、カマト、
那覇にあった花街『辻』の遊郭で
芸妓(沖縄では尾類<じゅりぬくゎ>と呼ばれる)
をしていた。
当時の『辻』は琉球文化の担い手の
役割も果たしていたという。
芸妓たちは踊りや音楽、さらに琉球料理の腕も磨いた。
「母(カマト)は音楽や踊りの才能はなかったんだけど、
その分、料理はすごくできたの」
と彩香さんは言う。
その母親の手料理を食べて彼女は育った。
その料理が首里城のもてなしの伝統を
受け継ぐものだった。
1941年の真珠湾攻撃で、
日本とアメリカの戦争が始まった。
翌年、7歳だった彩香さんは、
母親に連れられて那覇から沖縄北部にある
今帰仁(なきじん)に疎開する。
母のこの早い判断が
2人の命を救ったと言えるのかもしれない。
1945年には米軍が上陸、
那覇など南部に暮らしていた住民は
さらに南に追い詰められ、
多くの人が命を失ったからだ。
このとき、もし自分が沖縄の住民だったと想像すると、
あまりの悲惨さ、ひどさに言葉を失ってしまう。
日本は当時すでに戦争を継続する力は残っていなかった。
制空権も制海権も失い、鉄鋼の生産力も激減していた。
米軍が沖縄に上陸するのを食い止められるなど、
日本政府も思っていなかった。
政府内は陸軍の強硬姿勢と国体護持にこだわるあまり、
降伏を受け入れることができず、
いたずらに時間ばかりが過ぎていた。
予想される本土決戦までなんとか時間かせぎをするのが
沖縄に課せられた役割だった。
つまり見殺しにされたと言ってもいい。
しかしそんなことは住民に知らされるわけもなく、
少年まで鉄血勤皇隊といういさましい部隊に組み込まれ、
少女たちは『ひめゆり隊』で知られるように
野戦病院などに動員された。
さらにどれだけ追いつめられても、
米軍に投降することは許されなかった。
『生きて虜囚の辱めを受けず』
という教えばかりではない。
そこには住民たちへの不信、
そのうしろには差別意識とでもいうべきものが
横たわっていると考えるほかはない。
住民は沖縄の言葉を使うことが禁止され、
方言をしゃべるとスパイとみなされた。
沖縄の住民はすぐに米軍の協力者になるのではないか、
という疑心暗鬼が垣間見えるのだ。
このため住民たちは、
持たされた手りゅう弾で自決したり、
家族で殺しあう集団自決も相次いだ。
さらに、追いつめられた住民たちは
最南端の喜屋武岬(きゃんみさき)や
摩文仁の丘(まぶにのおか)の絶壁から
次々と身を投げた。
今こうした絶壁に立つと、
真っ青な美しい海が広がるばかりだ。
だが当時この場所に立った住民にとっては、
北からは陸路で米軍がすぐそばまで迫り、
南の海上には数えきれないほどの
アメリカの艦船がひしめきあっていたのだ。
投降さえ許されていれば、
そして日本軍が南部の住民を道連れにするような
持久戦に持ち込まなければ、
多くの住民の命が救われたに違いない。
沖縄戦での一般住民の死者は、9万4千人にのぼった。
話を戻そう。
彩香さんが疎開した北部に、
米軍がこなかったわけではない。
しかし南部の壮絶さに比べると、まだましだった。
米軍の砲撃があるたび、彩香さんは墓の中に隠れた。
沖縄の墓は本土より数倍大きく、
まるで小さな家のような造りになっているため、
子どもが隠れるには格好の場所だった。
終戦になると、住民たちは
破壊されずに残った民家にあつめられた。
彩香さんは他の子どもたちと一緒に地面に座って、
アルファベットと賛美歌を
アメリカ兵から教えてもらった。
アメリカの支配下に置かれて、
彼女が最も驚いたのは豚だった。
それまで沖縄には黒い豚しかいなかったのに、
白い豚が入ってくるようになった。
アメリカ人が来ると、豚まで白くなってしまうんだ、
と子供心に思ったのを、彩香さんは覚えている。
学校に通うようになると、
彼女は思ってもいなかった環境におかれることになる。
遊郭で働いていた女性の子ども、遊女の子だと指差され、
いじめにあいつづけたのだ。
「一番つらかったのは学校に行くことだった。
なんで自分は悪いこともしていないのに、
皆につまはじきにされなくてはならないの、
と思っていた。
登校拒否になったりしたのを見かねて、
先生がいじめをしないよう
生徒たちを叱ってくれたけど、
それでも誰も一緒に帰ってはくれなかった。
学校が終わると毎日、
がじゅまろの木の下にひとりで座った。
みなが帰ったのを見計らって、ひとりで帰るの。
4キロの農道を歩くんだけど、
まだあちこちに戦争で亡くなった人の
頭蓋骨が転がっていたから、怖くてね。
人は無視されるのが一番つらいということが
あの時わかった」
中学を卒業すると、彩香さんは10年ぶりに那覇に戻る。
幾つかの仕事をしたあと、結婚して出産、
しかしわずか2年で離婚する。
その後料亭で働きながら琉球舞踊の稽古に励み、
26歳にして琉球舞踊の新人賞をとるまでに上達した。
それがきっかけとなり、
那覇の高級ホテル『東急ホテル』の
芸能部の係長として採用される。
客の中にはアメリカのお役人や
軍の関係者もたくさんいた。
ベトナム戦争に向かう兵士は、明日をも知れぬ命の中で、
あり金を気前よく使ったという。
アメリカの雑誌である
『エスクァイア』1965年8月号。
思い出話をしている時、彩香さんが引っ張り出してきた。
薄いビニールに覆われた大きな雑誌だった。
開いてみると特集記事が目に入った。
第二次大戦中の戦地の写真と、
同じ場所が1965年にどんな佇まいになっているかを
撮影したものを並べた特集だ。
最初は、攻撃されている1941年の真珠湾、
そしてその見開きページには1965年の
のどかな真珠湾の風景の写真が掲載されていた。
さらに幾つかの戦地、
その後の同じ場所の写真が並べられていたが、
特集の最後を飾ったのが沖縄だった。
那覇の教会前で市街戦が繰り広げられている
写真の見開きには、
同じ教会をバックに米兵の将校と着物姿の日本人女性が
身を寄せ合っている写真が載せられていた。
「この着物の女性、私なの」
彩香さんが照れくさそうに指差す。
驚いている私をよそに、彼女はなつかしそうに続けた。
「東急ホテルで踊っていた女性の中から、
カメラマンが私を指名して、
モデルになってくれないかって言ってきたのよ。
それでこの写真が撮られたの。
将校は当時24歳の本当の米兵だった」
彼女が30歳の時だった。大勢の踊り手の中から、
カメラマンの目に止まるほど彩香さんは輝いていたのだ。
その翌年に彼女は琉球舞踊を極めたいという思いから、
ホテルでの勤めを辞める。
昼は舞踊に集中し、
夜は初めて開いた小さな料理店を切り盛りする。
2足のわらじを履く生活の中で、
彼女は踊りの最高の賞を獲得する。
一時は大勢の弟子を持つまでになり、
彩香さんの名前は
琉球舞踊の世界で広く知られるようになった。
その頃、沖縄は日本復帰を果たす。
戦後アメリカの支配下に置かれた日本は、
1951年のサンフランシスコ講和条約で
独立を果たした。
しかしその条件は、沖縄、奄美、
小笠原を切り離すことだった。
「沖縄戦で日本人になろうとして死んでいった。
だがサンフランシスコ講和条約で、
沖縄はやはり日本とは別なんだという気持ちになった」
と沖縄の作家、大城立裕さんは語っている。
そしてようやく72年の日本に復帰するが、
それまで沖縄は日本の新憲法の権利を
享受することもできず、
アメリカの核基地となることを余儀なくされる。
もう少し長いスパンで見てみると、
沖縄はこれでもかというほど
歴史に翻弄され続けていることがわかる。
琉球王朝は中国との関係を続けながらも、
1609年に薩摩藩に組み込まれる。
薩摩藩が明治維新で大きな力を発揮できた陰に、
琉球の存在があった。
貧乏だった薩摩藩は、
琉球と奄美のサトウキビからつくる黒糖を独占することで
財政を潤し、軍艦を購入する資金などにあてた。
つまり明治維新は琉球と奄美の犠牲の上に、
成し遂げられたともいえるのだ。
ところが明治維新後は廃藩置県で強制的に沖縄県にされ、
450年続いた王朝は崩壊、
琉球の伝統文化は否定されて本土化されていった。
その果てが、多くの住民が道連れにされた沖縄戦、
そして戦後『アメリカ世(アメリカユー)』に
なったかと思うと、
本土復帰で今度は『大和世(ヤマトゥユー)』に戻る。
しかも米軍基地は残ったままだ。
「何度も往復ビンタをされているようなものよ」
あきれたように彩香さんはつぶやいた。
たび重なる“往復ビンタ”で風前の灯になっているのが、
琉球文化、とくに琉球料理だった。
彩香さんは50歳を機に、琉球舞踊の世界を引退し、
料理家として生きることを決意する。
彩香さんの突然の引退を、
周囲は驚きをもって受け止めたという。
「踊りは技術で客を錯覚させることができる。
踊りは自分をごまかせないけど、客はごまかせる。
でも料理は自分も客もごまかせない。
私は2足のわらじをはいて、
最後に難しいほうをとったの」
『穂ばな』という店を経て、64歳の時、
現在の『琉球料理乃山本彩香』を開いた。
それから10年、全国から客が集まり、
沖縄ブームも後押しして雑誌やテレビにも取り上げられ、
琉球料理という存在も
間違いなく以前より知られてきていた。
その間には、伝統の味を伝えてくれた養母のカマトさんが
97歳でこの世を去った。
彩香さんが最初に出した料理店『歩』から数えると、
はや40年以上が過ぎていた。
今年6月に地元の新聞に、ひとつの広告が掲載される。
「『歩』、『穂ばな』そして『琉球料理乃山本彩香』と
四十数年の長い歳月に亘り
多くの皆様方にご愛顧を賜りました弊店は
今年8月を以ちまして、
その長い歴史に幕を降ろすことになりました。
これまで長年に亘って、
皆様方から賜りましたご厚情に
心より感謝申し上げここにお知らせ方々、
御礼のご挨拶を申し上げます。
平成二十一年六月吉日 山本彩香」
彩香さんの店に食べに行った翌日の昼、
一緒に沖縄そば屋に行った。
彼女はオバマ大統領の顔が
大きくデザインされたTシャツに
ジーンズ生地のスカートをはき、
イギリスのコンパクトカーとして人気のあった
ミニを自ら運転した。
74歳になっても好奇心が衰える気配はない。
去年私が沖縄に行ったときのことだ。
彼女が大好きなチェ・ゲバラのTシャツを、
私がたまたま持ってきていると知ったときの、
うらやましがりようといったらなかった。
そこまで欲しいのであれば
プレゼントしようと思ったものの、
あいにく着古して穴のあいたような代物だった。
そんなこと彼女はまったく意に介さなかった。
おそるおそる手渡すと、
彩香さんはゲバラの顔を眺めて
うっとりした表情を浮かべた。
「いい男ねえ」
そばを食べて店に戻ると、
建築家と店の内装の打ち合わせが待っていた。
新しく生まれかわる店内には、
沖縄の土産になる陶芸品も並べ、
豆腐ようも販売する予定だ。
「私も74歳になったし、このくらいの歳になれば、
茶器セットとかを山本彩香厳選と銘打って
販売しても叱られないんじゃないかな」
店は夜の営業をやめて昼間だけにし、
これまでと違って一品料理だけになる。
ゴーヤジュースやマンゴジュースなど
沖縄ならでは飲み物もそろえて、
喫茶店としても利用できるようにするという。
もちろん酒呑みのために、泡盛もある。
「こんな店をやりたかったっていうような店にしたいの。
昼の営業にするのは、長く続けるためよ」
こう彼女は繰り返したあと言った。
「きちんと料理が作れるのは、
あと10年だと思っているから」
「あと10年ですか」
「そうあと10年‥‥」
「10年で一番何をしたいですか」
彼女はしばらく考えて口を開いた。
「琉球料理は中国の影響が7割、日本の影響が3割、
とうがらしの使い方なんかは朝鮮から伝わっている。
この独特の料理を受け継いでこれまで作ってきて、
大勢の人が支持してくれた。
だから、お客さんにこれだよねと言われている料理を
少しでも伝えていきたい」
琉球舞踊は感情をあくまで内に秘め、
体を動かす表現は最小限にするという。
強い抑制が生み出す気品は、
料理にもつながっているのかもしれない。
「琉球の料理は、かつおだしだけで
あえて昆布を使わないの。
いいかつお節、塩、しょうゆ、
この3つがあれば基本的な味付けはできる」
料理だけではない。
彩香さんは“言葉”も残していきたいという。
「沖縄料理の炒め物は、『ちゃんぷるー』
という言い方がよく使われるけど、
もともとこの言葉を使うのは豆腐が入る場合だけなの。
出汁を入れて麩(ふ)などを煮ふくめるのは
『いりちー』、
そうめんは『たしやー』、
こんなふうに本当は言葉が違うのよ」
沖縄料理の店に入ると、『ソーメンちゃんぷる』
というメニューを見かけることがあるが、
『ソーメンたしやー』が本当なのだという。
「これらを区別せずに『ちゃんぷるー』と
呼ぶようになったのは、戦後になってからよ。
先人たちが大事にしてきた言葉が
失われていくのはさびしいじゃない」
450年続いた琉球の記憶を未来に引き継ぐ。
彩香さんの決意を込めた新しい店は、
10月後半にスタートする。
「メニューには、『どぅるわかしー』はありますか?」
と私が心配そうに訊ねると、
彩香さんはあきれたような表情でうなずいた。
「大丈夫、安心して」
沖縄の言葉で、
食いしん坊のことを『がちまやー』と呼ぶという。
彼女の新しい店には
“餌づけ”された『がちまやー』たちが
再び集まるに違いない。
もちろん私もそのひとりだ。
(終わり)
山本彩香さんの物語の決定版は
雑誌「coyote」(スイッチ・パブリッシング)
のNO21からNO30までに
10回にわたって連載されています。
タイトルは「とーあんしゃさ」
作家の駒沢敏器さんが書かれています。
|