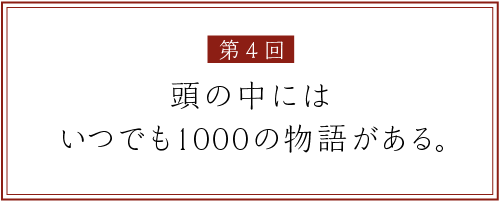
- ──
- 監督は、就職先として
どうしてNHKを選んだんですか?
- 佐々木
- 本当は、商社に行きたかったんだ。
- ──
- あ、そうなんですか。
- 佐々木
- でも、就職試験で「全滅」しちゃって。

- ──
- え、そうなんですか?
- 佐々木
- 英語が好きで真剣に勉強していたから
海外で活躍するような仕事に
就きたかったんだけど、
うちは、はやいうちに父親が死んで
「片親」だったから。
- ──
- ええ。
- 佐々木
- いや、当時は、両親がそろってないと
入れない業界ってあったんです。
今じゃ、考えられないだろうけど。
- ──
- それは‥‥聞いたことないです。
- 佐々木
- 商社・銀行・デパート関係‥‥
お客さん相手の商売は、まずダメだった。
でも、新聞社やら雑誌社、テレビ局とか
マスコミには、そういう差別はなかった。
- ──
- それで、NHKに入局されたんですね。
じゃあ、テレビドラマをつくるなんて、
学生時代には
思ってもいなかったってことですか?
- 佐々木
- うん。ただ、中学から高校にかけて
毎日のように映画館へ通いつめていたほどの
映画少年だったんで、
好きな分野だったことは、たしかだけど。
- ──
- 最新作の『ミンヨン 倍音の法則』って
観ている側としては
映画のストーリーを追いかけるというよりも
大写しにされるミンヨンの姿が印象的で、
すごく念入りに
主人公を描写しているなあと感じました。
- 佐々木
- 結局、ずいぶん長いことやってきて思うのは
僕は、登場人物の姿を通じて
自分を表現したかったんだなということでね。
- ──
- 自分自身を表現する?
- 佐々木
- そう、何て言うのかな、
僕自身は画面に出るなんてできませんよね。
みっともなくてさ。
だから登場人物に、託してる。
監督が主演を兼ねてる作品もありますけど、
心底すごいって思えるのは、
そうだな‥‥オーソン・ウェルズくらいで。
- ──
- 『第三の男』の。
- 佐々木
- そう、あの人が最低予算でつくった映画で、
ほら、ええと‥‥『市民ケーン』とか。
- ──
- 新聞王のお話ですね。
- 佐々木
- あれは、じつにみごとな作品だった。
圧倒的で、巨大な人物を描いているんだけど
彼自身、実際に「巨きな人」じゃないですか。
- ──
- たしか処女作で、公開当時は
20代半ばとか、かなり若かったはずですけど
そんな印象はぜんぜんないですね。
- 佐々木
- 絶対2枚目なんか演じられない男ですよ。
そこで「新聞王」に扮するわけだけれど、
そいつは世の中を知りつくし、
右から左へ活字を売って大成功している、
大金持ちですよね。
- ──
- ええ。
- 佐々木
- そんな「巨大な新聞王」が
最期、これで命もおしまいだってときに
「薔薇のつぼみ」って、つぶやく。
- ──
- 「Rose Bud」と。
- 佐々木
- そう、新聞王ケーンは
幼いころ、もらいっ子に出されるんだよね。
で、金持ちに拾われていくんだけど
大好きな母親と
幸福に暮らしていたときに乗ってたソリに
「薔薇のつぼみ」が描いてあったんだ。
- ──
- はい。
- 佐々木
- そのことを思いながら、死んでいく。
市井の人たちから見れば
怪物みたいな、あれだけ巨大な人間でも、
それを根っこで支えていたのは
「薔薇のつぼみ」という
ほんの小さな存在なんだって「真実」を
みごとに描いてるんですよ。

- ──
- なるほど‥‥。
- 佐々木
- まあ、僕の勝手な解釈だけどさ。
- ──
- でも、自分の頭で考えるのが
「観る側のおもしろさ」ですものね。
今のお話を聞いて
もう一回、観なおしたくなりました。
- 佐々木
- 観てください。で、なんの話だっけ?
- ──
- はい(笑)、自分を表現したい、と。
- 佐々木
- そうそう、うん。表現したいんですよ。
他の人にはあまり聞いたことないけど、
ものをつくってる人なら
多かれ少なかれ、同じじゃないかなあ。
- ──
- そういうものですか。
- 佐々木
- でも、ほとんどの作家っていうのはさ、
クリント・イーストウッドみたいに
2枚目なんか演じられないんであって。
- ──
- ええ。
- 佐々木
- ましてや
女性になんか、なれるはずもない。
だから僕らは、登場人物に託して、
自分のことを描くんです。
- ──
- そういえば、今回の映画のなかで
行商の桃売りの桃を買って食べた男性が
血を吐いて死ぬシーンがありましたけど
それって、たしか、
監督の身に起きた実話を元にしていると‥‥。
- 佐々木
- そう、僕の父親の佐々木修一郎って人は
早稲田を出て、
毎日新聞の記者をやってたんです。
戦時中に、軍は腐っているとか言って
辞表をたたきつけた男なんだけど、
そんなだったから、
特高警察に目をつけられてたみたいで。
- ──
- ええ。
- 佐々木
- 家の前に、そういう人がよく立ってた。
- ──
- へえ‥‥。
- 佐々木
- で、あるときに、その父が
僕を江の島へ遊びに連れて行ってくれて、
天丼を食べさせてくれたんです。
すごくおいしかったのを、今も覚えてる。
- ──
- 『ミンヨン』にも、海岸で
少年が天丼を食べる場面が出てきますね。
巨大なエビ天の載った、立派な天丼を。
- 佐々木
- うん。で、翌朝、おやじと汽車に乗って
故郷の宮城に向かったんだけど
どこかの駅で
桃売りから買った桃を口に入れた途端に、
おやじが血を吐いて倒れたんです。
そしたら、すぐさま、近くにいた水兵が
おやじを窓から外に出した。
で、そこにはなぜか担架が置かれていた。
- ──
- えっと、つまり‥‥。
- 佐々木
- 幼いながら、明らかにおかしいと思った。
本当のところは知る由もないけど
あのころ不審死ってけっこうあったしね。
- ──
- そんな、ものすごい体験を
まるまる描いていたんですか、あの場面。
- 佐々木
- うん。
- ──
- そういう、戦争や敗戦の体験というのは
監督の作品に、影響していますか?
- 佐々木
- どうだろう、自分ではよくわからない。
今回の作品では、戦中戦後の浮浪児を
現代の東京の街の中に走らせたりとかは
やってますけどね。
- ──
- あ、あの靴磨きの少年ですね。
- 佐々木
- 戦争当時から終戦後にかけてのころには、
ああやって、
両腕に時計をいっぱい嵌めてる子どもが、
たくさんいたんですよ。
時計のことを「ケイチャン」って言って。
- ──
- ケイチャン。時計のケイ、ですか?
- 佐々木
- そう、彼らは、電車や道ばたで
ばっと袖をまくって、ケイチャンを売る。
ひとつ「50円」とかで。
- ──
- 安い‥‥んでしょうね。
- 佐々木
- 泣き売(ばい)ってのも、いたなあ。
- ──
- 泣き売?
- 佐々木
- 万年筆を分解した部品なんかを並べて
泣きながら、売るんだよ。
「勤め先の会社が潰れたんです」
とか、
「火事で家が焼けちゃって」
とか、おんおん泣きながら
「みなさん、どうか買ってください。
この万年筆、誓って本物ですから」
とかって言って。
- ──
- それ‥‥買うんですか?
- 佐々木
- けっこう買ってたよ。適当な値段だから。
ただし、ぜんぶ偽物なんだけど(笑)。
- ──
- やっぱり(笑)。ちなみに
終戦のとき、監督は何歳だったんですか?
- 佐々木
- 僕、終戦、9つです。小学校4年生。
だから、毎日毎日、
いま言ったような光景ばっかり見てた。
浮浪者もそこら中にいて、
もう、みんな煙草パカパカ吸ってたな。
- ──
- なるほど。
- 佐々木
- 今にして思えばおもしろいんだけど
実際は食うにもたいへんな時代だったから
そういう体験が
作品に、どこかで影響はしているかもね。
直接的に描いたことは、ないけど。
- ──
- 監督にとって「心を動かす演技」って
どういう演技ですか?
- 佐々木
- やっぱり「つくらない演技」だよね。
悲しくて悲しくてしょうがないってときに
絶対に悲しい顔をしないような、さ。

- ──
- それって、ふつうの人は
必ずしも、そうじゃないってことですか?
- 佐々木
- うん。だって、電車に乗ってる人でも
いろんな運命を背負っているわけだけどさ、
悲しくったって、
みんな、そんなの隠して座席に座ってるよ。
- ──
- たしかに。
- 佐々木
- そういう姿がきれいなんだと思う、僕は。
つくった姿は、みにくいと思う。
感情をつくってね、表情をつくってね、
声色をつくってね、
「ほうら悲しいでしょ?」とか、最低だよ。
- ──
- ひとつ、佐々木監督に
どうしても聞きたかったことがあるんです。
- 佐々木
- 何ですか。
- ──
- いま、世の中には、たくさんの「物語」が
ありますよね。
洞窟壁画の時代からはじまって
今後も、人は、
たくさんの物語をつくりだすと思うんです。
- 佐々木
- でしょうね。
- ──
- カラハリ砂漠に住む「サン族」の会話を
分析したら
昼の会話のうち「物語」が占める割合は
全体の6%にすぎなかったのに
夜には、お金とか狩りの話は数%に減り、
8割が「物語」になったそうです。
つまり、そういった
焚き火の近くで交わされる「物語」が
人類の文化の形成に
役立っただろうって話なんですが、
そのあたり、
どうして人は物語を必要とするのかを‥‥。
- 佐々木
- 必要とする? 人が、物語を?
- ──
- はい。
- 佐々木
- 知らない。考えたこともない、そんなこと。
- ──
- でも、監督ご自身は、これまで
多くの「物語」をつくってきましたよね?
- 佐々木
- だってそれは、僕の頭のなかには
いつでも1000くらいの物語が、あるから。
- ──
- そんなに。
- 佐々木
- で、そのなかのどれかひとつが、
中尾幸世に出会ったり
ミンヨンに出会ったりすると
実際の作品となってかたちを結ぶんです。
- ──
- そういうものですか。
- 佐々木
- うん。だから「物語」っていうのは、
僕にとっては、
「誰かが必要としているもの」というより
「つねに、あるもの」なんだよね。
- ──
- あるから、かたちにしたくなる?
- 佐々木
- そう。
だから、いつも「次は」って、思ってるよ。
- ──
- いまでも?
- 佐々木
- もちろん。
「次は、どうしてやろう」って。

<終わります>
2014-11-11-TUE
