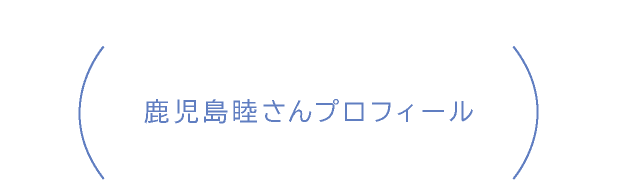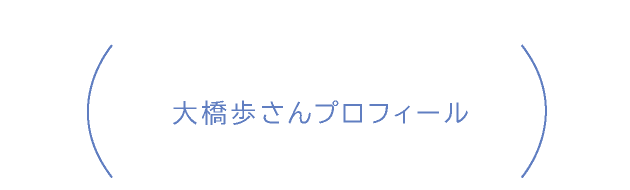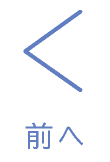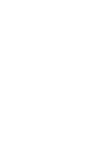2018年春の「やさしいタオル」で
いっしょに「ほぼ日」に登場した、
イラストレーターの大橋歩さんと陶芸作家の鹿児島睦さん。
「いちどもお会いしたことがない」
というふたりを引き合わせたくて、こんな機会をつくりました。
大先輩を前に最初は緊張していた鹿児島さんでしたが、
「おんなじだ!」「ぜんぜんちがう‥‥」という発見が、
どんどん距離をちぢめてゆきました。
雑談めいたぶぶんも含めて、そのようすを
全6回でおとどけします。
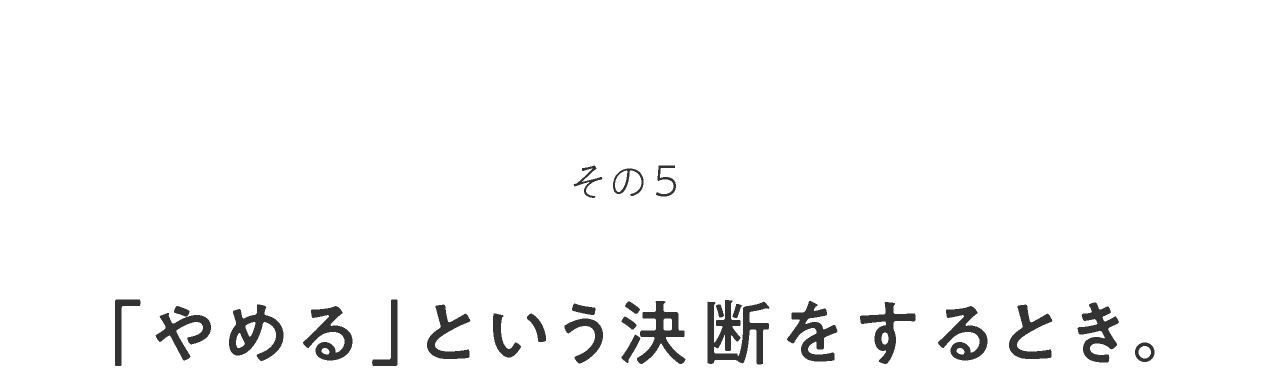
- ──
- つくられてきた雑誌『大人のおしゃれ』を
終刊にすると決めたと、
大橋さんはすごく明るくおっしゃったんです。
「終わりなのよ!」って。
そして「次は何をするんだろう、わたし。
ワクワクしちゃう」っておっしゃって。
もうほんとうにびっくりしました。
- 鹿児島
- すごい‥‥。
- 大橋
- 飽きたんじゃないんですよ、
あるとき、うまくいかなくなるんです。
それを「自分がうまくいかない」と思うかどうかは
わたしの問題だと思うんです。
人によって違うと思いますけれど、
わたしの場合は、そう。
例えばAさんがすごく素敵だから、
ちょっとお話を伺いたいなと思っても、
わたしがどこかで
「引いて」しまっていたりすると、
うまくいかないものですよね。
それは「わたし」の問題です。
そういうことが重なったりしたとき、
フッと、もうこれをやめていい時期なんだ、
と思うんです。 -
それでやめる。
やめれば、次に新しいこと、
やりたいことが出てくるかもしれない。
だからOK! って思えちゃうんですね。
周りは「そんなこと言って、どうするの?」
っていうことにはなるんですけどね(笑)。
鹿児島さんは、会社をお辞めになられたときは、
陶芸をおやりになりたいと思ってのことでした?

- 鹿児島
- いえ‥‥会社自体はものすごく楽しかったんです。
天職だと思っていたほどでした。
ずっとこのまま会社員を続けたら
楽しいだろうなとずっと思っていました。
でも、その当時ぼくは35ぐらいだったんですが、
25、6歳くらいのときから、
かっこいい先輩たちが口をそろえて
「お前は35からだな」って言っていたんですね。
お会いするタイミングとか
シチュエーションとかバラバラなんですけど、
何故か25、6のぼくに向かって、みんなが
「35からでいいから、
何でも今のうちやっとけよ」
って言ってくれていたんです。
そんなことがありつつ、
実際に35ぐらいになってみたら、
ぼくは会社員で、じゅうぶん下も育ってきて、
ぼくがこのままいたら、
後輩たちが上に行けなくなると思いました。
そのときですね、
「そろそろ辞めてもいいのかな」
と考えたのは。
「このままではうまくいかなくなるかもしれない」
とか、
「ここにいなくてもいいかな」
という思いでした。

- 大橋
- うわぁ。
- 鹿児島
- つまり、陶芸をやりたいという情熱が
あったというわけではないんですよ。
もちろん、年をとったら、
こういうふうに、物を作る仕事を
したいなとは思っていたんですけれども。
- 大橋
- そうなんですか!
- ──
- 先輩が35だぞって言ってくれたのが
引っかかってもいたんでしょうけれど、
「時期」って来るものなのかもしれないですね、
そういうふうに、自然に。
- 鹿児島
- どうなんでしょうね。
あと、すごい馬鹿だと思われるんですけれども、
『ノストラダムスの大予言』ってご存知ですか。
- 大橋
- はい、ありましたね。
- 鹿児島
- 1999年に地球が滅亡するという。
あれをぼく、本当に信じていて(笑)。
あれを小さい頃にテレビで見て真に受けて、
ああ、もう自分って
32、3ぐらいまでしか生きられないんだ、
と思っていたんです。
だから1999年以降の人生設計が
まったくなかったんです(笑)。
- 大橋
- ほんとですか!
- 鹿児島
- はい。アホなんです。
だから、逆に言うと、ぼくは、
たとえば会社員をやりながら、
面白そうなことを30代の頭までに
結構やってきたんです。
毎週金曜日の晩だけ開ける
バーの運営をさせてもらったりしていました。
それは福岡の第一線で活躍される素敵な方たちが
情報交換をするサロンがない、
場所を提供するから‥‥と、
素晴らしい実業家の方から声をかけていただきました。
ぼくも忙しいから
金曜日の晩だけだったらやれますって言って、
ほんとに金曜日の夜だけ、やっていたんです。
確か26から33ぐらいまで。
- 大橋
- 面白そう、そういうの。
- 鹿児島
- そこに福岡の社長さんたちが集まってくださって。
世界中を飛び回ってるような方たちなので、
「俺、こないだパリでこんな話聞いたんだよ」
「イギリスでこんなふうに日本のこと
言われてるんだけど、知ってるか」
とかって面白い話をどんどんしてくださる。
そうしてる間に、福岡の学生たちが
そのおじさんたちの話を聞きにやって来て、
グラスワインを舐めながら、
ずっと聞いてるんですよ。
「今週も勉強になりました」って。
でもいちばん勉強したのはぼくなんです。
そこでも「35から」って言われました。
老舗の4代目から、進学もせずたたき上げの社長さん達から
「35までは、何でも来るもの拒まずで
仕事しなさい」って。
‥‥恵まれていますよね。
- 大橋
- そうですよね、すごい!
わたしの最初の『平凡パンチ』の表紙も、
大人が「何だ、こんな絵?」っていう時代に、
わたしを引っ張り上げてくださった
大人の方がいた。
ほんとのイラストレーターたちの方は
「何だ、あれ?」っていうふうに
思ってたと思うんですね。

- ──
- そんなことは‥‥。
- 大橋
- だって、そりゃそうですよ。
稚拙で、「誰がこれクレヨンで描いたの?」って。
- 鹿児島
- でもそれまでになかった仕事ですよね。
パイオニアじゃないですか。
- 大橋
- あんなお絵描きに使うようなものを
雑誌の表紙に使うプロの人たちは
それまでいなかったわけですものね。
つまり、だからわたしは
そこいら辺がすごくよかったなと
思っているんです。
- 鹿児島
- ぼくも、10年先、20年先に
こうなんなくっちゃ!
というお手本がまわりにいたことが、
有難かったなと思ってます。
そして今どうかというと、
中学生ぐらいのときから
引っ越しのバイトを始めて、
いろんな仕事をやってきたので、
今も「その中のひとつ」という意識があります。
そんなに違う仕事をやっているわけじゃない。
そうそう、今でも
内定を頂いてるところが何社かあって!
陶芸やめたら、いつでもうちの会社に来いって。
- 大橋
- それはすごい。
- 鹿児島
- この先陶芸の仕事ができなくなることだって
あると思うんです。
ぼくの祖父は博多人形を作っていましたが、
60幾つかのときに辞めています。
「博多人形の顔が描けなくなった」と思った瞬間に、
手は震えてもないし、綺麗な線が描けてるのに、
「引退ばい」って辞めた人なんですよ。
その後、祖父はいろんな面白いことをやって、
周りを困惑と失笑の渦に巻き込むんですけれども、
ぼくもわりとそんな感じで、
もし陶芸ができなくなっても、
なにか面白いことをするんだと思います。

- 大橋
- うんうん。
- 鹿児島
- オールマイティです、
と言ってるわけじゃないですよ!
そんなにこだわってはないんです。
いっぱいある仕事の1個だなと思っている。
奥さんには「就職して」と今でも言われます。
- 大橋
- でも作品を拝見するとね、
そういうふうには見えないですよね(笑)。
- 鹿児島
- だいたいぼくが弱音を吐くとそう言われます。
もうほんとに進まないよとか、
ほんとつらいとかって言っちゃうと。
- ──
- なるほど。じゃあもしかして大橋さんみたいに、
突然フリ幅としてこれをやりたいと、
人がアートと呼ぶような仕事に進む可能性も
ないわけじゃないですね。
突然大きな絵が描きたいとか思うかもしれないし。
- 鹿児島
- あるかもしれません。
- ──
- わかんないですよね。
- 鹿児島
- あるいは突然「角打ち*の店をやりたい」
って言うかも。
*角打ち(かくうち)は、北九州発祥の飲酒のしくみで、酒販店がその場でお客さんに飲ませる形式。
- ──
- 面白いなあ。
(つづきます)
©HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN