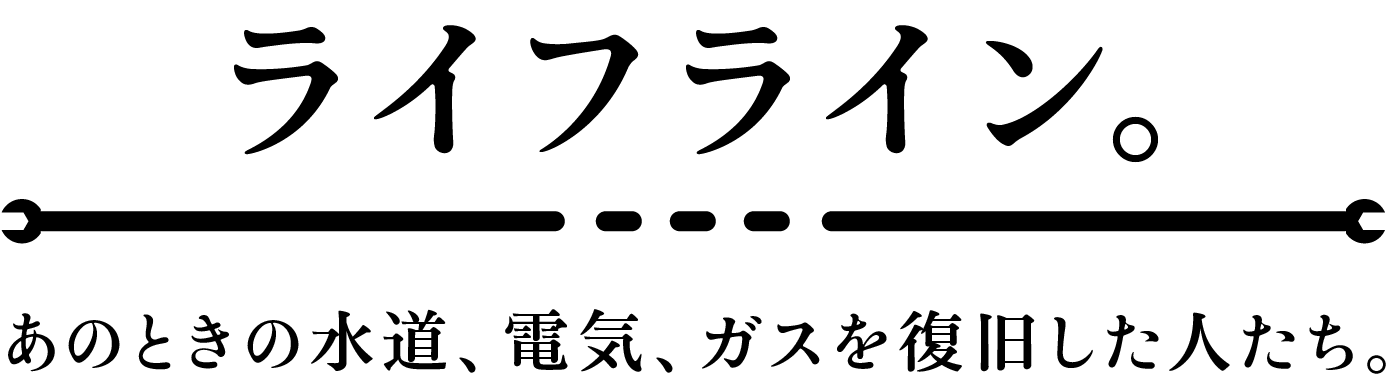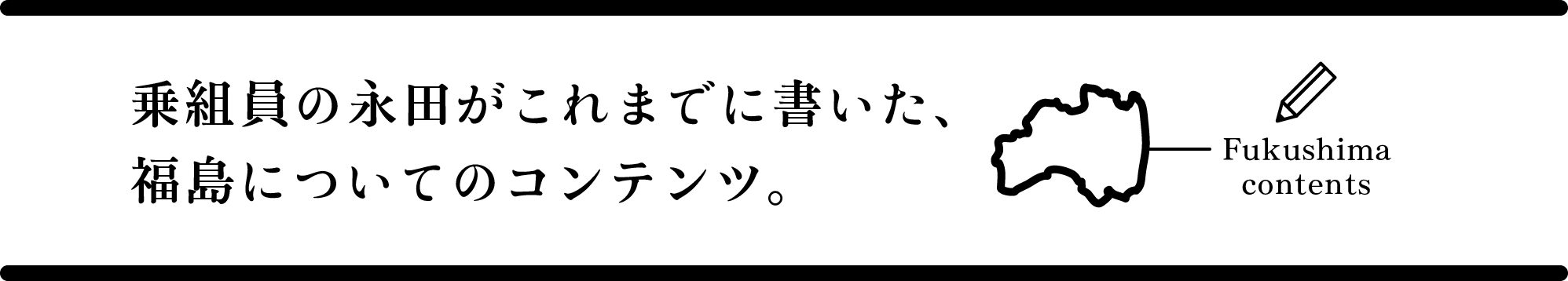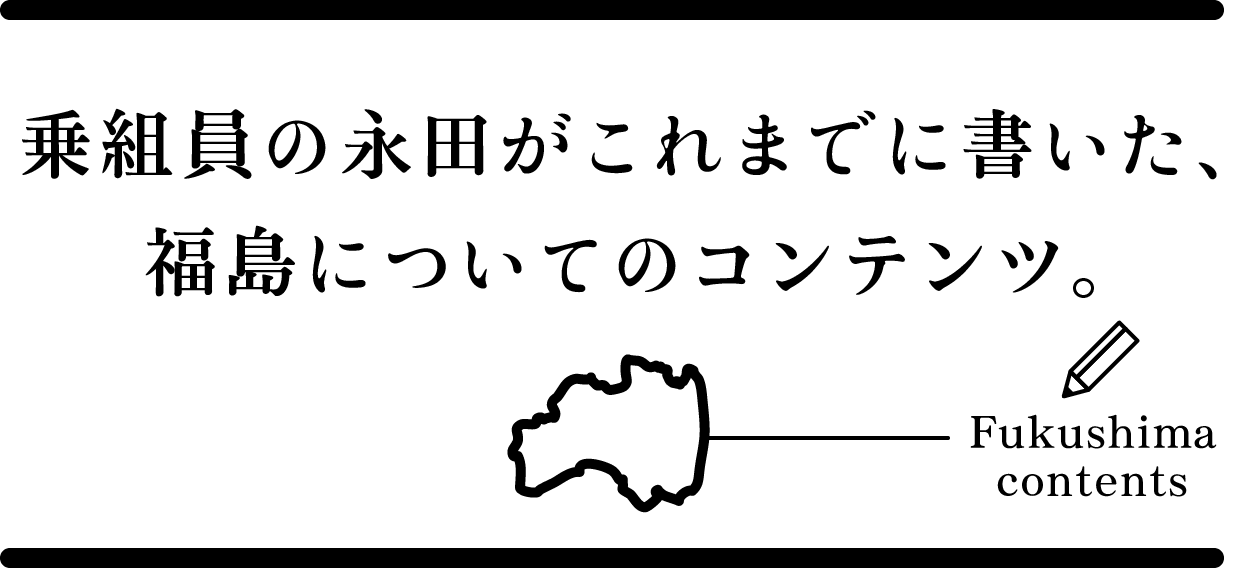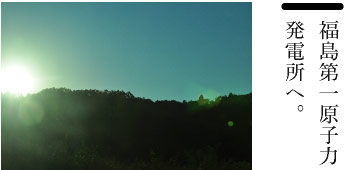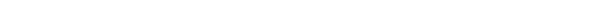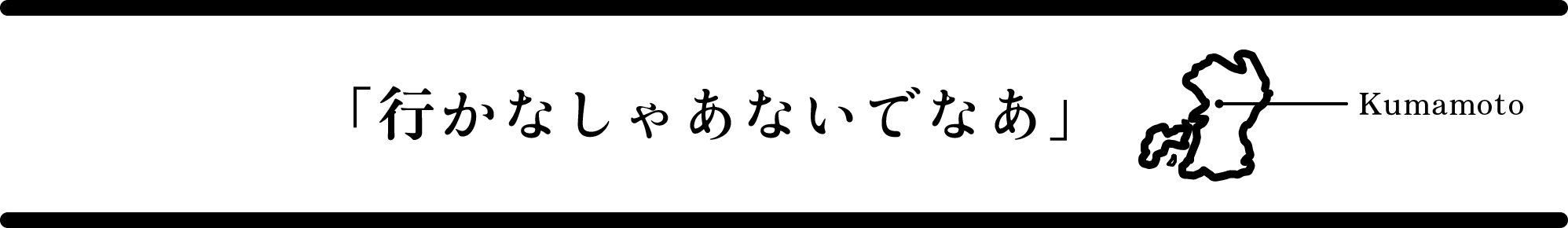
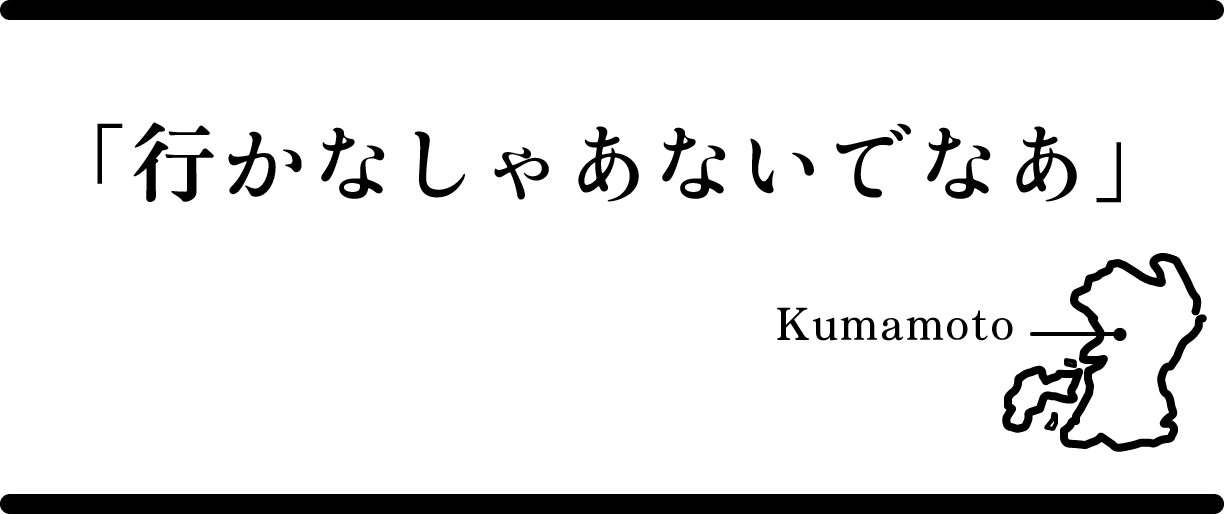
昨年の4月、熊本で大きな地震が起きたとき、
読者の方からメールがあって、
それがとても印象深かった。
どちらかといえば日常的な、
軽い感じで書かれたメールだった。
「昨晩、ガス会社に勤める兄から
『熊本行くことになるかもしれん』
と、電話がありました。
ガス会社に勤める兄は、
震災があると家と被災地を何度も往復し、
一ヶ月以上帰ってこないこともありました。
『地震起きたら、うちら行かなしゃあないでなあ』
と言って、ひたすら
直して直して直しまくってくるそうです。
直してるほうのおっちゃんが倒れることもあるけど、
文句言われても、誰かとけんかになっても、
とにかく直すだけだからと。
しゃあないわなあ、と言います。」
当たり前だけれど、ふだん意識していないこと。
直ったものは、誰かが直したから、直ったのだ。
たとえば、いま、被災地にいくと、
かつてあった瓦礫はほとんどなくなっている。
それは、誰かが撤去したから、なくなっているのだ。

福島県新地町釣師地区
東日本大震災で道路が崩れたとき、
大規模な停電が起こったとき、
あちこちの水道管から水が吹き出したとき、
ガスや電話や高速が止まってしまったとき、
やがてぼくらはニュースかなんかで
「復旧までは時間がかかる見通し」とか、
「現在は復旧しています」とか耳にするけれど、
復旧したものは、誰かが復旧させたのだ。
街は、自然に、自動的に、直ったりはしない。
「行かなしゃあないでなあ」と言って現場へ行く人がいて、
直して直して直しまくってくれるから、
被災地は復旧するのだ。
広くとらえるなら、
そういう人たちがいるから、
私たちの暮らしはいまも続いているといえる。

福島県相馬市古磯部地区
2011年3月11日から6年が経って、
そういう、当たり前に現場で動いている人たちのことを
あらためて、知りたくなった。
ライフラインをひとつひとつつないできた、
その人たちの咄嗟の判断と、手の動きを。
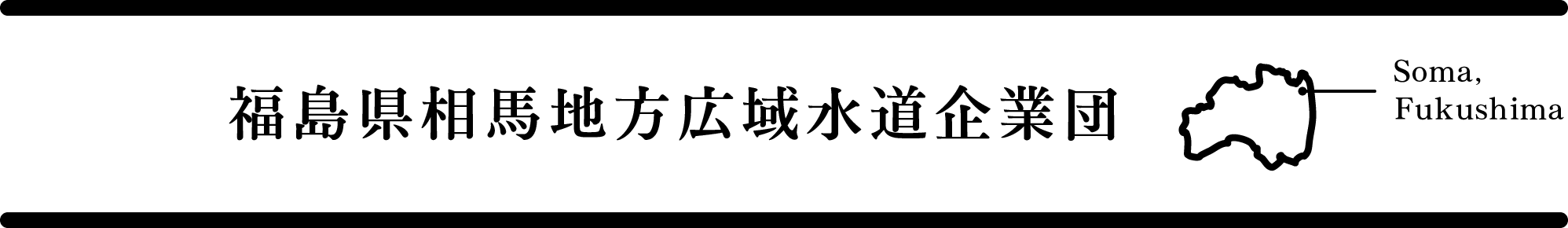
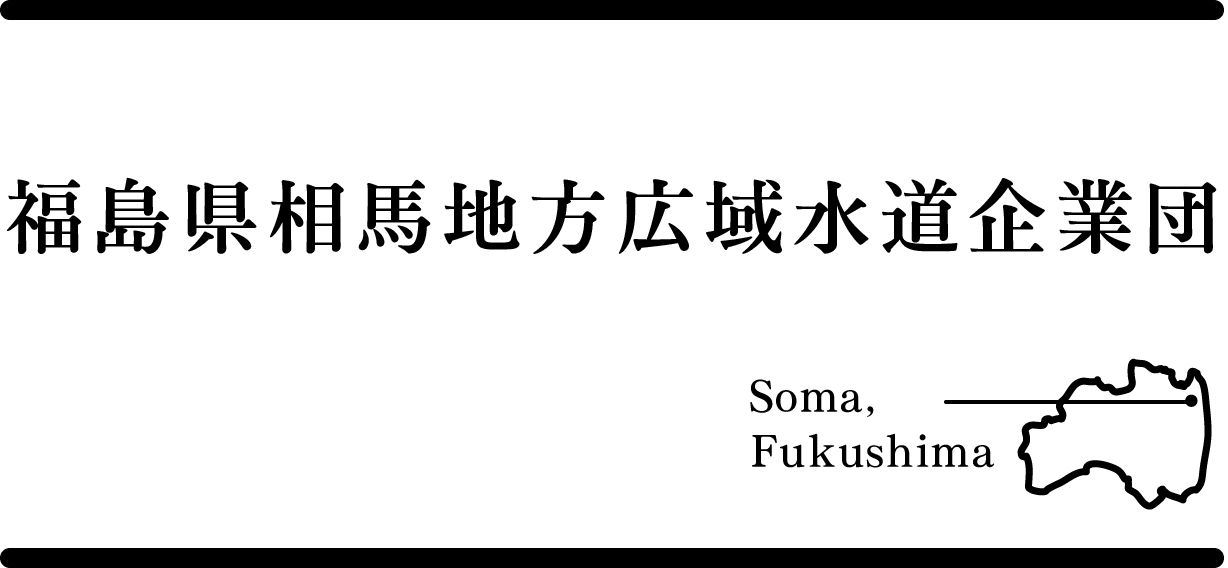

向かって右から、齊藤喜則さん、荒 嘉久さん、渡部明彦さん。
2011年3月11日14時46分、
東日本を大きな地震が襲った。
福島県浜通りの震度は6強。
相馬市は最大9メートルを超える津波に襲われた。
今回取材させていただいた
「相馬地方広域水道企業団」は
それまで20940戸の住宅に給水をしていたが、
震災によって約7割の14156戸が断水した。
と、数字だけを連ねると現実味がないが、
震度6強の地震が起こって、
しょっちゅう余震も起こっているなかで、
9メートルの津波が街を襲って、
管轄している地域の7割の家庭が断水してしまったら、
いったい、どこから、なにを、どうすればいいんだろう?
その瞬間から復旧に向けて動くことになった、
齊藤喜則さん、荒嘉久さん、渡部明彦さんにうかがった。


- 齊藤
- 「当時、職員が22名いたんですけど、
地震が起きたとき、この建物にいたのは
全職員の半数程度でした。
そのうちあちこちから無線が入ってきたので、
まずは事務所に一度集まれ、と言って」
- 荒
- 「ぼくは外にいたんですけど、
もう、道路のあちこちから水が吹き出していて、
ああ、これはたいへんだな、と思いながら
とりあえず事務所に帰ってきました」

福島県南相馬市鹿島区北海老
- 渡部
- 「ふつうの地震ならそのままパトロールして
被害状況を確認するんですけど、
あまりにも大きかったので事務所に無線を入れたら
まずは1回帰ってこい、と。
で、みんなでばらばらと集合したんですが、
事務所には入れなかったんですよね」
- 齊藤
- 「建物がものすごく揺れてましたから。
結果的には崩れはしなかったんですけど、
やっぱり、中にいたくないわけですよ。
事務所も停電してますし、
机の上の書類なども散乱している状況でしたから、
駐車場内の倉庫にストーブを置いて
事務所代わりにしました
災害が起こったときの対策やマニュアルはあった。
しかし、なにしろ、規模が大きすぎた。
一旦、みんなで事務所に集まって
どこから手をつけたのですか、と聞くと
「6号線ですね」という答えが返ってきた。
国道6号線は福島県の浜通りを
海に沿って南北に走っている道路である。

福島県相馬市尾浜海水浴場(下方をはしる大きな道が6号線)
- 齊藤
- 「津波は6号線までしか来てない、
という情報が入ってきたんです。
一部、越えてるところもあったんですが、
まあ、6号線は通れるようだと。
じゃあそこを目安にしようということで、
6号より下流はぜんぶ止めて、
そこから作業がはじまった」
- 荒
- 「まずは、どこまでが通れるのか、
行けるのはどこかっていう判断ですよね」
- 渡部
- 「集まって、各班に人を振り分けて、
あとは破裂、漏水しているところのピックアップ。
そのくらいしか当日はできなかった」

- 齊藤
- 「この建物の前の道も半分崩れてて、
メインの水道管が外れちゃったんですね。
で、それを止めて‥‥
あれは自動で止まったのかな?」
- 渡部
- 「そこは手動で止めた。
破裂してて止まんないからって」
- 荒
- 「なにしろ、
やれることからしか手がつけられなくて。
何日くらいでどこまでやったか、
ちょっと感覚がないんですよね。
ないというか何も考えられないというか。
あまりにも勝手が違うので。
たとえば、瓦礫でバルブの位置さえ
わかんなかったりするんですよ」
- 齊藤
- 「最初のうちはそうだったね。
海のほうに行くと漁船が道路を塞ぎ、
車や網があちこちに流れ着いてて作業ができない。
電柱なんかもそのへんに転がってるし。
ある一箇所のバルブが見つかれば
なんとかなったりするんですけど、
そこにたどり着けなかったり。
なにしろ、目標物がなんにもないわけさ」

福島県新地町釣師地区漁港付近
- 荒
- 「うん(笑)。
すげえなこれ、って、他人事みたいに。
そんな感じで10日間くらいは
まったく休みなくやってましたかね。
最初に風呂入ったのが
震災から2週間後くらいだったのを憶えてます」
- 渡部
- 「俺もずっと作業してて、
1週間後くらいにはじめて
津波の被害を実感したんですよ。
ずっと事務所を中心に作業してましたから、
そこまで行くこともできなくて」
当時の22名の職員のうち、
7名の方のご自宅が津波の被害を受けている。
荒さんのご自宅も、波をかぶった。
自分の家、自分の家族の心配と、
職務である水道の復旧作業。
葛藤は、当然、あるに決まっている。
- 荒
- 「とりあえず、メールで家族の
安否の確認だけはしたんです。
親父だけ連絡が取れなかったんですが、
ひとまず探すのは家族に任せました。
こっちはこっちでやることがたくさんあるので。
自分の家が流された場所に行ったのが、
震災から2週間後くらいですかね。
そのへんはよく憶えてないですね。
なにが起こったのかなって、他人事みたいな感じで。
ただ、もう、目の前にあることをやろう、みたいな。
目の前のことに集中してたほうが、
らくというと変ですけど‥‥」

福島県相馬市尾浜海水浴場
- 齊藤
- 「ひとつひとつの作業そのものは冷静に、
順調にできていたと思います。
もう、ほんとうに、一個一個、水を出してみて、
漏れていれば直してっていうことを、
順番にやっていくしかないですから。
出して出なければ直して、
つぎ、またつぎ、またつぎっていう、
その連続が2ヵ月くらい続いたかな」
- 渡部
- 「エリア内の通水自体は1ヵ月くらいで完了したんです。
そのあとは、個別の対応に移っていくんですが、
一軒一軒の対応になりますから、
そっちのほうがけっこう時間がかかるんです」
- 荒
- 「どうしても出せないところがあったりするんです。
高台に1軒だけ残った家があって、
まわりは流されてしまっているんですけど、
やっぱりご家族の方はそこに住みたいですから、
なんとかして出さなきゃない。
県境に1軒だけ残った家は、
隣の県から水をもらうように手配したり」
- 渡部
- 「あとは、原発の事故が起こってから、
物流が止まって物資がなくなったんですよ。
給水車も来ない、ガソリンもない、
資材を頼んだけどちっとも届かないから、
宮城県まで直接取りに行きました」
- 齊藤
- 「あとは、作業員さんたちのなかにも
避難する方がいらっしゃって、
いつものチームが成り立たなくなってしまったので、
混合チームをつくったりしましたね。
所属する会社が違う作業員の方たちで
ひとつのパーティーをつくって」

福島県相馬市柏崎大正堀
- 渡部
- 「社長が避難しちゃったから仕事が回らない、
っていう作業員の人たちを振り分けて、
3社くらいの合同班をつくったり。
ふだんはそういうことは、まずないです」
大きな震災が起きたときなどは、
非常時ならではの結束が生まれると聞く。
実際、ぼくが取材したいくつかの現場でも、
日常の垣根を超えた関係が生まれ、
たくさんの人がなんの見返りもなく
献身的に活動するということがしばしばあったようだ。
相馬市の水道を復旧する現場でも
そういうことがあったんでしょうかと訊くと、
現場を守り続けたみなさんは
ちょっと照れたように笑いながら、
「まあ、やるしかなかったから」と言った。
- 齊藤
- 「逆にいうとね、一人ではなにもできない。
グループじゃないとなにもできないですから。
やっぱり、目の前にやることがいっぱいあるから」
- 荒
- 「気持ちが妙に事務的になっていったのを憶えてますね。
これができたからこれ、そのつぎはこれ、って。
慌てず、騒がず、というか。
最初のうちは目的もわかりやすく決められましたから。
まず病院までライフラインを復旧しよう、とか」
- 渡部
- 「あと、まあ、こんなこと言ったらなんだけど、
最初のうちは電話が通じなかったから、
広範囲の復旧を計画通り進められた、
というのもありますね。
通信網が復旧してくると、
じゃんじゃん電話が鳴りはじめましたから」
- 荒
- 「まあ、そういうリクエストが来はじめるというのが、
日常が戻ってきた証拠ですから、
いいことといえばいいことなんですけどね(笑)」

少し、ことばに注意しながら、質問してみた。
その作業は、もちろん、途方に暮れるほど
たいへんなことだとは思うのですが、
やりがいもあった、
という部分もあったのでしょうか、と。
- 渡部
- 「ありますよ、やっぱり。
ありがとうって、言われますし、
いやぁ助かったって声も聞こえてくるし」
- 齊藤
- 「やっぱり、ないとどうにもならないですからね。
津波のあとで家を片づけるにしても、水は必要です。
- 荒
- 「最初はやっぱりありがとうってすごく言われましたね。
で、まあ、どんどん復旧した範囲が広がっていくと、
電気は来てるのに水道はまだか、とか(笑)」

話すとき、それぞれの方の口調に、
生々しいものを語る苦さのようなものはもうない。
つらさ、悔しさがまったくなくなったわけではなく、
そういうものは記憶の別のところにしっかりと残っている。
それはそれとして、
当時のことをひとつの大きな仕事として
現場の人たちが語れるようになったというのが、
震災から6年、という時間の長さなのだろう。
- 齊藤
- 「まあ、振り返ってみると、
大きな震災には遭いましたけど
幸い、職員たちには命があった。
家が流されたり壊れたりということはあったけど
命があって、作業をすることができた。
それがいちばんじゃないですかね」
- 荒
- 「みんな一生懸命にやってましたね。
だから、人ってすごいなあ、って思いました。
いろんな意味で、仲間も含めて、
店を開けてる人も、自衛隊の人も、
ガソリンを持ってきてくれる人も、
ボランティアの人たちも、すごいと思った」

- 渡部
- 「当時のことを思い出すと、
水道一筋でやってきた人たちが集まって
きちんと機能したというか、
ライフラインを止めて直したり、つなげたり、
現場のみんなの日頃の経験を活かして
できたというのは、よかったんじゃないかな。
いまって、スマホにしてもパソコンにしても、
電気やバッテリーがないと
なんにも動かない時代じゃないですか。
でも、携帯電話が通じなくても無線でやり取りして、
電子機器がなくても、日頃から現場に作業してきた
みんなの経験によってスムーズに復旧できた。
それは、なんか、よかったですねぇ」
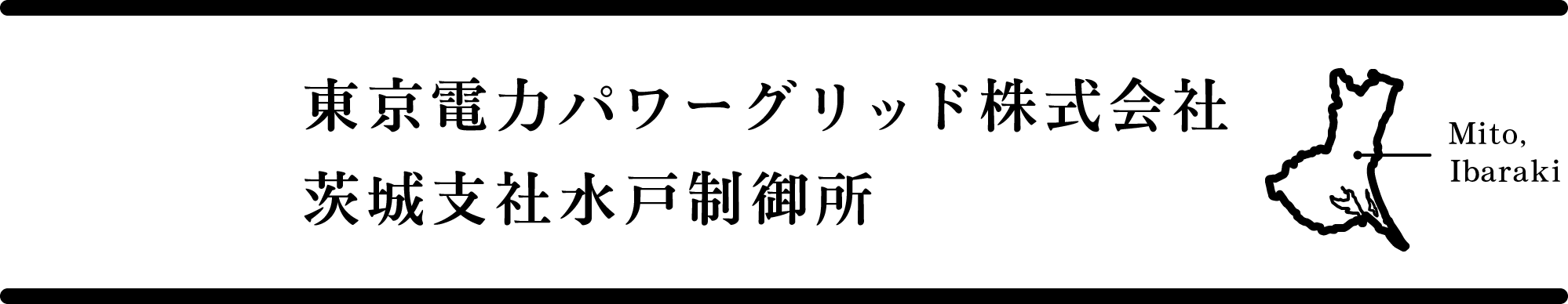
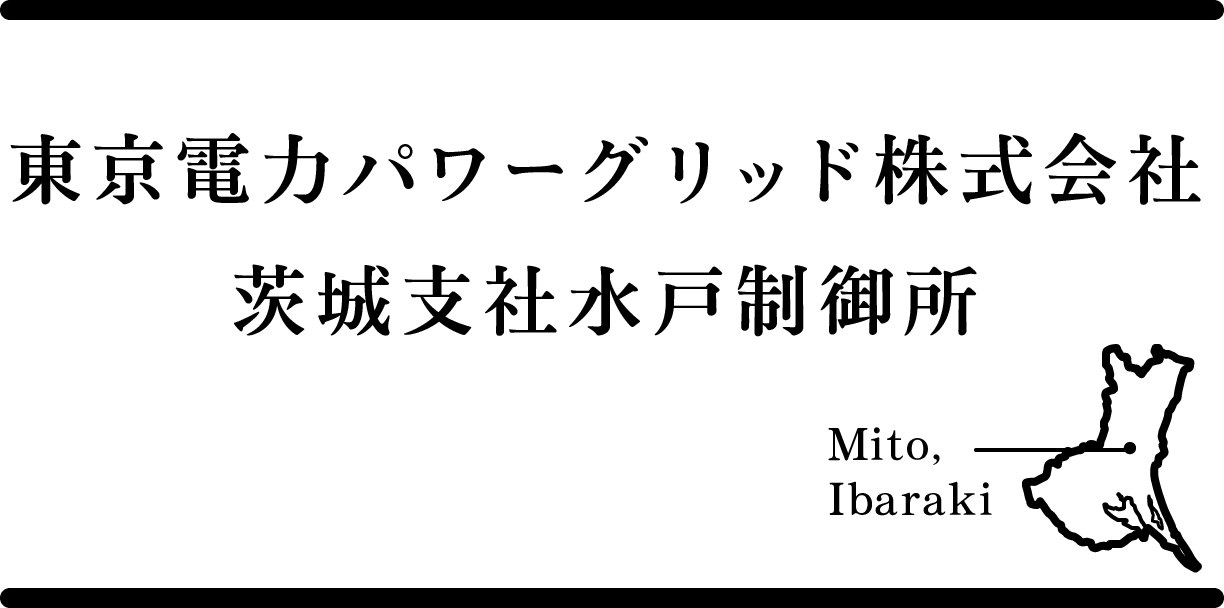

保全チームリーダーの長谷川治さん。
東日本大震災によって、
茨城県は、じつに90パーセントが
停電した状態だったという。
東京電力パワーグリッド株式会社で
配電のスペシャリストとして働いていた長谷川治さんは、
当時のことをこう振り返る。


- 長谷川
- 「揺れがあって、建物から出ると、
近くで火災が発生していて、煙が上がっていたんです。
ふだんだったら、火災が起こると、
まずそこに向かうことになるんですが、
なにしろそこだけでなく被害が甚大でしたから、
どこからかかっていいのか‥‥という状態でしたね」
茨城県のほぼ全域が停電しているから、
有事の際に県全体の復旧を指揮することになっている
事務所も電力を喪失していた。
配電マンである長谷川さんは
あちこちから呼ばれることになる。
- 長谷川
- 「まずは指揮をとる事務所の
電源を確保しなきゃ作業員に指示が出せない。
それで行ってくれって言われて
高圧発電車に乗って出動したんですが、
1キロ先の事務所に辿りつけなかったんですよ。
すべての信号機が停止していましたから、
交通が麻痺していて、もう、大渋滞なんです。
それでけっきょく引き返してきたら、
今度は、福島に行ってくれ、と」

長谷川さんが担当したのは
福島第二原子力発電所の冷却用電源の確保。
発電車に乗って現場に着き、
発電対応に追われていたころ、
またしても長谷川さんは呼ばれる。
- 長谷川
- 「茨城がたいへんなことになっているから、
帰ってきて復旧に回ってくれ、と言われまして。
それで福島のことは引き継ぎをして
茨城の対策本部に戻ることになったんですが、
乗ってきた発電車はそこに置いていってくれ、
ということで、帰る足がなくなってしまったんです。
ちょうど千葉支店のクルーの人たちが
同じように引き継ぎをして帰るところだったので
その車の脇に乗せてもらって帰ってきました。
そうやって、現場の人どうしで協力し合う、
という動きは自然にできてましたね」
戻った茨城はまだかなりの地域が停電していた。
電柱の倒壊も多く、利根川の下流では
液状化現象も発生していた。
まさに問題山積、という状態のなかで
どのように作業を進めていったのか
長谷川さんに振り返ってもらった。
- 長谷川
- 「まずはチェックですね。電線や電柱がどうなっているか。
そこはもう、パトロールして、目視です。
直さなきゃいけないと判断したものは、
さらなる災害につながる可能性があるものは
その場で直しますが、だいたいは記録しておいて、
あとで一括して直すことにしていました。
震災の直後は、どちらかというと、
『無事だったところを確認する』という
意味合いのほうが強かったと思います。
ここは大丈夫だから、ここから送っていこう、
というように確認しながら電気をつないでいく。
優先の順位は、まずは指揮系統の中枢。
大洗町という海辺の町が津波の被害を受けたんですが、
電源を喪失していて指揮命令がとれなかったんですね。
福島から帰ってきたあと、まずはその復旧をしました。
あと、役場と消防署は最優先で直していきました」
お話をうかがっていると、長谷川さんは
震災の直後からほとんど休んでいないように思える。
- 長谷川
- 「福島から帰ってきたのが14日の零時ごろでした。
そこから仮眠を取ろうとしたら、
電力復旧が済んだところが
また止まってしまったというので、そこの操作をして。
で、数時間、ちょっと目をつぶったかな
っていうぐらいのときに、
今度は、北茨城市と高萩市あたりの復旧が
まったく進んでいないという情報が入ってきまして。
で、そこの巡視をやってくれといわれてすぐ行って。
そこから帰って来ても自宅に帰る交通手段がないので、
詰め所で仮眠して、そうすると夜中にまた起こされて、
呼ばれてどこかへ出かける‥‥
みたいなことをしばらく続けていました。
たいへんでしたけど、なんというか、
疲れは感じなかったんですよ、そのころは。
個人的には、その‥‥燃えていたというか(笑)。
疲れを感じるようになったのは、もっと後ですね」

長谷川さんのご家族は、奥様と、お子さんがふたり。
奥様のご両親とも同居されている。
震災後、ご自分のご両親も含めて無事を確認し、
そのあとはほとんど自宅に帰っていない。
- 長谷川
- 「震災のあと、安否を確認して福島に行って、
自宅に戻ったのは‥‥3月17日ですね。
あ、でも一度、高萩市に向かう途中に、
通り道だったので許可をもらって一回寄りましたね。
まあ、でも、息子と娘が『お帰り』って言うくらいで、
とくに劇的な再会もなく(笑)。
逆に、ふつうでよかったという感じでしたね。
毛布にくるまってテレビ観てましたね(笑)」
当時のことを長谷川さんに振り返ってもらうと、
つらかったことというのは、
家に帰れなかったことでも、
満足に食事ができなかったことでも、
布団でぐっすり眠れなかったことでもない。
- 長谷川
- 「やっぱり、世間の風当たりが強くて、
心のバランスを取ろうと必死でしたね。
原発の事故がありましたから、
現場で工事をしている最中にも
かなり辛辣なことを言われました。
弁当を食べるのも、あまり人目につかないように
隠れて食べてたりしてましたから。
あとは、やっぱり、被害が大きいですから、
ぜんぶは直しきれないんですよ。
で、現場で、直接声をかけられたりするんですね。
『ちょっとうちを直してくれ』と。
それはもう、しかたがないことだと思いますが、
計画に沿ってぎりぎりのスケジュールで動いてるときに
『ああ、やっとつかまった』とか言われると
やはり、困ってしまうんですね。
で、あとからかならず来ますからと言って
名前と住所をうかがったりして」

県全域の電力を復旧しなければならない、
という大きな使命と、
ああ、やっと来てくれた、ここをお願い、
という小さなお願い。
大きなことから優先していかなければならないが、
小さなお願いは心に重く残る。
加えて、福島第一原子力発電所の事故という
自社の引き起こした災害への非難を受け止めること。
身体的に疲弊しながら、そういった心のバランスが
当時いちばんたいへんだったと長谷川さんは語る。
- 長谷川
- 「倒壊しそうな家があって、
そこの2階にのぼらせてもらって、
電線を切断しなきゃいけなかったんですね。
それで、お願いして上がらせてもらって、
作業が終わって降りてきたら、
そこに住んでいるおばあさんが、
『あっちの部屋に息子が買ってくれた
新品の液晶テレビがあるから運び出してくれ』
っておっしゃるんですね。
『あなた電器屋さんでしょ』って(笑)。
それはもう、『わかった、運び出すよ』
って言って、運び出しました」
大きな規模での復旧が終わると、
今度は個々のお客様からの要望に対応していく
というフェーズに入ってくる。
カスタマーセンターから発行された受付票が
1日数百枚というペースで溜まっていく。
- 長谷川
- 「でも、最終的にはできたんだからすごいですよね。
まあ、やるべき復旧行動として、
業務を遂行したというだけなんですけど、
1000枚くらいの案件を処理したわけですから。
もちろん、私だけがやったわけじゃなくて、みんなで。
比較的被害の少ない、ほかの事業所からも
たくさんの応援が来てくれました。
東京はもちろん、東京電力エリアのほぼ全部の県から、
あと、中部電力さんと関西電力さんにも
来ていただきました」

電力会社間では、有事の際にそうやって
相互に協力し合うという協定が結ばれているそうだ。
昨年起こった熊本での地震のときは
茨城から発電車を送ったという。
そういったことについて話していたとき、
長谷川さんがふとつぶやいた。
- 長谷川
- 「6年前、たくさんの方に来ていただいたとき、
きちんとお礼が言えてたかなあ、って思うんです。
絶対に自分たちだけでは直せなかったので、
ほんとうにありがたかったんですが、
やはり疲れてよく憶えていないということもあって、
ちゃんとお礼が言えてたかな、と。
応援の人たちが来ると、朝、一列に並んで、
反対側に来てくださった方たちが並んで
『ありがとうございます!』という挨拶をして
一日の作業をはじめるというのがあるんですが、
終わったときとか、現場で、
ちゃんとお礼が言えてたかなぁ‥‥。
そういうことがあったので、どこか他の地域で
災害があったときは、あのときの恩返しを
めいっぱいしたいなという気持ちがすごくあります」
あらためて振り返ってみて、
東日本大震災の直後の仕事というのは、
長谷川さんにとってどういうものだったのだろう。
- 長谷川
- 「そうですね‥‥
やっぱり、あれを経て、いまの自分がある。
たとえば定年がきて退職するとき、
あのとき俺、こうがんばったって誇りに思えるくらい、
すごく密度の高い、濃い時間だったと思います。
自分のメンタルがちょっと弱いからか、
いろいろ、くじけそうなこともありましたが、
でも、振り返れば、自分のベストは、
90パーセントくらいはやれました」
おっしゃった「90パーセント」という数字に、
長谷川さんの自負と謙虚さの両方が表れているようで、
ぼくはなんともいえない気持ちになった。
なにか奮起しなければいけないときが来たら、
「90パーセントくらいはやれました」と
胸を張って言えるようになりたいとぼくも思う。
最後にうかがったのは、ご家族についてのことだった。
ちっとも家に帰ってこられないお父さんを、
ご家族の方たちは、どんなふうに思っていたのだろう。

- 長谷川
- 「うちの奥さんは、結構おおらかな人で。
天気が悪ければ、旦那さんは家にいない、
っていう考え方の人なんで。
非常に理解があって、
仕事をするうえでは非常にやりやすくて(笑)。
『天気が悪ければ』というのは、
地震とか、台風が来たり、大雨だったり、
とにかく天気が悪いときは、基本、いない。
子どもたちには、自分の仕事をきちんと
伝えきれていない部分もあるんですけど、
でも、『お父さんの仕事』みたいな作文を書くときには
重要な仕事をやっているっていうふうな書き方を
昔からしてくれているので、
理解をしてくれてるのかなと思います。
子どもの年齢ですか?
上が20歳、下が18で、今度大学ですね。
だから、東日本大震災のときは
中学2年生と、小学6年生か‥‥。
そうですね、大きくなりましたね(笑)」
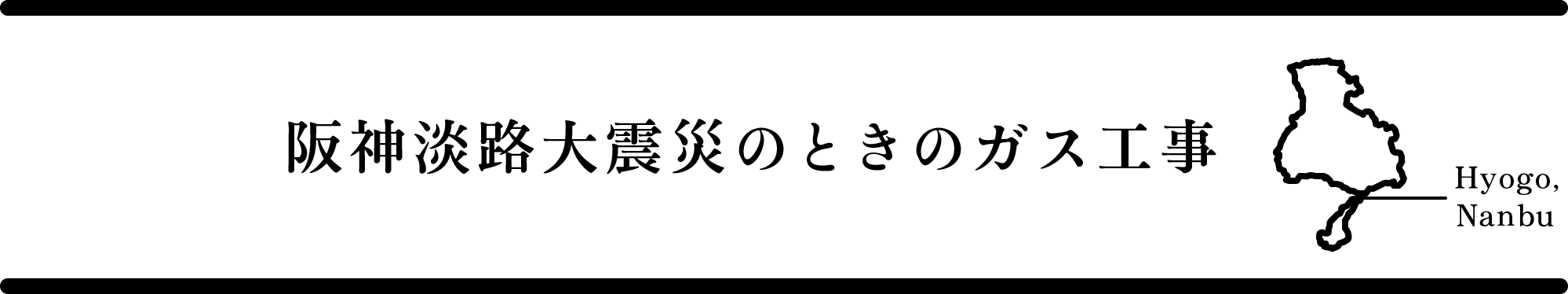
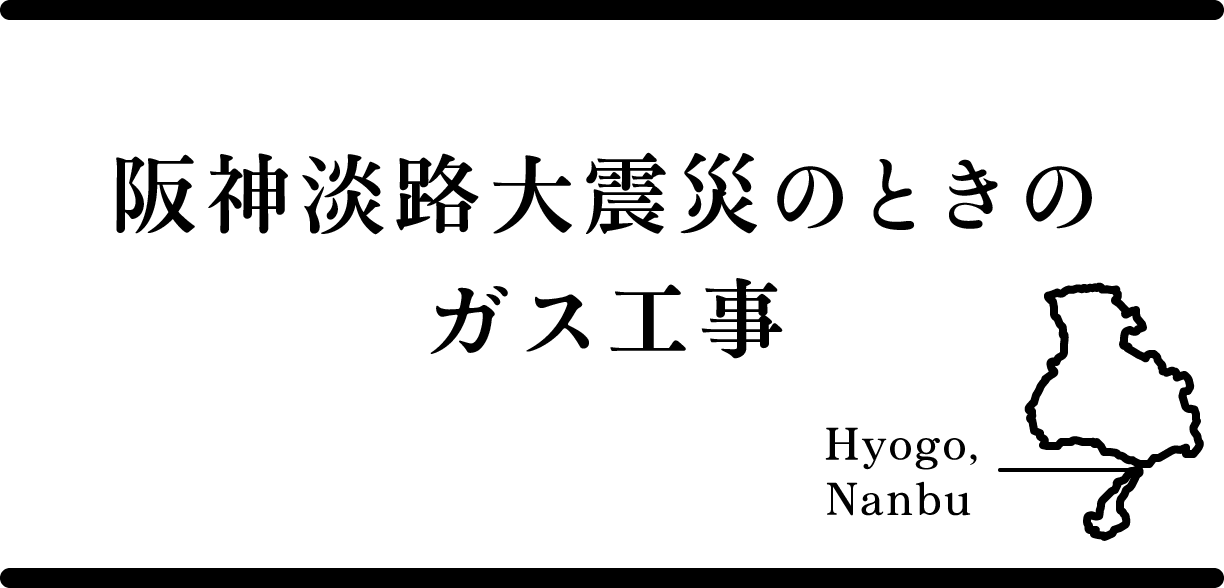
「ガス会社に勤める兄は、
震災があると家と被災地を何度も往復し、
一ヶ月以上帰ってこないこともありました。
『地震起きたら、うちら行かなしゃあないでなあ』
と言って、ひたすら
直して直して直しまくってくるそうです」
そんなメールが「ほぼ日」に届いたことがきっかけで
今回の取材ははじまった。
最後に、メールに書かれていたお兄さんに
実際に会ってお話を聞きたいと思った。
メールを送ってくださった妹さんに連絡をして、
お仕事が休みだという日に
お兄さんの時間をいただけることになった。
ご本人の意向で、名字だけ。
その方は、竹内さん。
大手のガス会社からの依頼を受けて、
まさに「現場」で作業をしている。
仕事の拠点は東海地方だ。
竹内さんは、1995年に起きた阪神淡路大震災のとき、
被災地に入ってガス管をつなげた人だった。
当時、未曾有の大震災に対して、
ほとんどの人がなんの経験もなかった。
そのときのことを中心にうかがった。
──まず、現場に、近寄れないんですよ、
と竹内さんはおっしゃった。


- 竹内
- 「あのくらいの規模の震災になると、
まず、現場に、近寄れないんですよ。
だから、周りから攻めていく感じです。
とくに、呼ばれて地方から応援に行くときは、
まず自分たちの宿泊施設を探さないといけない。
拠点をつくって、そこで自分たちの
ライフラインを確保して、資材を確保して、
準備をしてから現地に入っていく。
最初は大阪、そして宝塚、というふうに。
資料や図面を調べたりしながらね」
ガスの工事を請け負う会社は全国にあって、
それぞれにつながっているのだという。
災害などがあると、現地からの要請を受けて、
あちこちの地域から作業員が現場に入ることになる。
- 竹内
- 「あのときは要請を受けて、
こっちでチームをつくって乗り込みました。
情報をいただいて、それに基づいて作業していく。
まあ、要するに、ひとつずつ、潰していくんです。
まず、町全体を、細かいブロックに分ける。
ほんとに、道で区切られたブロック単位で区画を切る。
で、そのブロックの安全を確認していく。
たとえばあるブロックの被害が大きくて
住民さんもいなくて、危険な状態にあるなら、
そのブロックは後回しにすると決める。
住民さんが住んでるブロックのガスが止まってるなら、
まず、そこの大元がどこにあるかを調べて、
ガスの流れの大元を復旧して出すようにする」
被災地に入ったことはありますか?
と、竹内さんが尋ねる。
何回かあります、とぼくは答える。
- 竹内
- 「建物にいろんなサインがついてなかったですか。
赤い紙が貼ってあったり、ブルーのマークがついてたり。
先に乗り込んだ消防署なり、警察なり、自衛隊なりが、
そこの状況を判断して貼っていってるんですね。
だからまず、そのサインを見て、
直すのか、後回しにするのか、判断していくわけです。
で、赤いサインが貼ってあったら、
それは倒壊寸前の建物だから、
ガス管を直すんじゃなくて、そこは止めなきゃいけない。
崩れそうなビルに半端にガスが通ってると危険なんです。
そうやって、確認しながら、
ひとつひとつ、ブロックを潰していく」
途方に暮れるでしょうね、と言うと、
竹内さんは悩むこともなくこう答える。
- 竹内
- 「いやもう、やるしかないんで」
そう。だからこそ、現場に入っている。
やるべきことは膨大にある。
あれこれ迷ったり悩んだりしている場合ではない。
- 竹内
- 「かっこいいこと言うわけじゃないですけど、
お役に立ちにいくんだから。
正直、いったん現場に入ると、
ご飯も食べられないし、お風呂も入れない。
でも、やるべきことをやるしかない。
そのつもりじゃないと、やっぱり」
それは、あくまでも自分の仕事、ということなのか、
もっと人間的な、助けたいという気持ちなのか。
- 竹内
- 「両方でしょうね。
そのバランスは、作業をしながらも、
日々変わってくるようなところがあります。
こういう言い方をするとあれですが‥‥
楽しんでいる自分もいますよ」
そう、それは、取材を通じて知った大切なことだ。
どの現場にも、やり甲斐や達成感がある。
どれほど悲惨な風景に囲まれていようと、
危険が障害が立ちはだかっていようと、
現場で作業する人の胸には前向きな動機がある。
- 竹内
- 「嫌だ嫌だと思ってたら、正直、続かないです。
1ヵ月とか2ヵ月とか缶詰になって、
毎日、ここはどうすればいいかって、
考えながら、判断しながら、やっていくわけです。
やり甲斐や手応えを見つけていかないと、
やりきれないと思いますよ。
ガス管を地道につないでいくにしても、
ここまでできたという達成感を感じながら、
あるいは、自分の経験を活かして、
いろんな状況を乗り越えて、
そこに自分なりの楽しみを見出していく。
やっぱり『やった!』ということがないとね」
阪神淡路大震災のとき、作業はだいたい、
朝の6時から暗くなるまで続いたという。
休みは2週間に1度あったかどうか、という感じ。
- 竹内
- 「でも、嫌々やってる人は、たぶんいなかったと思う。
来ちゃえば、もう、やるしかない。
もう、『よし、行くか!』って思って
現場に来ている時点で、やるつもりで来てるから。
なんていうか、そういう、
ちょっとハイな状態にいないと続かないですね。
それは、自分ひとりのことだけじゃなくて、
現場で身体を動かしている人たちみんなの
テンションを下げないようにしなければいけない
という意味もあるんですけど」
前向きに、やり甲斐をもって取り組むことは、
自分ひとりが困難を乗り越えるための鼓舞ではなく、
一緒に働く仲間への気遣いでもある。
復旧の現場に、そんな、
精神的に「プロ」な世界があることを
ぼくははじめて知った。
- 竹内
- 「やっぱり、ずっといるわけですからね、
テンションが下がったらやっていけません。
そこにいるひとりひとりがそれを思ってますね。
だから、嫌じゃないし、恐怖もない。
ここは危ないぞ、ということは冷静に判断しますけど、
それは、いわゆる恐怖とは違います。
‥‥あ、でもね、宿に帰って、風呂に行って、
さあ寝ようかと思ってエレベーターに乗ったら、
余震があってエレベーターが止まったりする。
これは、けっこう、怖くて(笑)」
自分が知らない領域は、素人だから、
やっぱりふつうに怖いんだよ、
と竹内さんは笑った。
竹内さんは、6年前の東日本大震災のとき、
現場には入っていない。
竹内さんが当たり前のように語った
「東北に自分が行かなかった理由」を聞いて、
そういう視点もあるのかと驚いた。
- 竹内
- 「神戸のときの経験から、
大規模な災害のときにどうするかという
心得、マニュアルのようなものが、少しは確立しました。
ぼくらはそれをつぎの世代に
つないでいかなくてはならない。
そういう意味では、災害の現場を、
たくさんの人間に経験させなければいけないんですね。
だから、東日本大震災のときにチームを組むときも、
ちゃんと経験のあるリーダーのもとに
若手を組み込むようにしました。
神戸のこと、あるいは、
自分が行った柏崎の新潟中越沖地震のことも、
いまの現場に活きていると思います。
自分は行ってませんが、去年の熊本の地震のことも、
これからのことに役立っていくと思います」
いまでも、どこかで大きな地震が起きたりすると、
誰が現場に入るかということを
当たり前に意識されるという。
- 竹内
- 「いまは情報が早いのでニュースになると同時に
ケイタイが鳴りますね。『見ました?』って。
はい、準備してください、っていうことで(笑)。
それはもう、仕事としてふつうのことですね。
『はい、仕事だよ』っていう」
いま、阪神淡路大震災のことを振り返るとどうですか、
とお訊きすると、竹内さんは少し考えた。
つまりそれは、22年前のことになる。
- 竹内
- 「ぼくが行ったのは、35歳のときで、
まだ身体も元気で、イケイケで動けるとき。
でも、20年以上も経ったとは感じないですね。
あのときは、ものすごい人数で行きましたから、
当時の仲間と会うと、よくその話になります。
当時は必死でも、いまになったら笑い話として
しゃべれるようなことがたくさんありますから。
現場では、喧嘩もよくありました。
それはもう、どっちも真剣だからね。
たとえば、入っちゃだめだ、と守る人がいて、
直すんだからちょっと入らせろ、という人がいる。
自分がやらなければいけないことに真剣だから、
余計喧嘩になるんですね。
いい加減にやってれば、たぶん喧嘩にならない。
それは、ねちねち長引くようなことじゃなくてね、
一回ぶつかって結果が出てしまったら、
まあ、お互いしょうがないか、ってなるんですけど」
竹内さんからうかがった話は、
どれも「人」についてのことだったように思う。
最後に、こんなふうにおっしゃった。
- 竹内
- 「やっぱり人が直してるんですよ。
流れ作業で自動的に直っていくんじゃない。
そこに人がいるから、衝突も起こるし、
いっしょに前に進むこともできる。
相手のことを思わなかったら、
たぶん、本気でできないんじゃないですか」