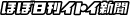第1回
「泥船に乗ったつもりで」
<序>
「ほぼ日刊イトイ新聞」がうまれる13年前、
1985年にインタビュー誌「SWITCH」は
誕生しました。
発行は株式会社スイッチ・パブリッシング、
編集長は新井敏記さん。
以後、「Coyote」「MONKEY」を創刊、
3つの雑誌を定期的に刊行しつづけます。
(「MONKEY」の編集長は柴田元幸さん。
「Coyote」はいちど休刊したのち、
約2年後に復刊をなしとげます)
村上春樹さんや小泉今日子さん、荒木経惟さんなど、
魅力的な著者の単行本も数多く発刊しています。
出版不況と言われてずいぶん経ちますが、
「SWITCH」は独自の編集姿勢をつらぬき、
ゆるがない活動を続けている印象があります。
なぜ、こんなにもビビッドな活動を
続けることができるのでしょうか?
いっぽう「ほぼ日刊イトイ新聞」は
糸井重里を主宰としたWEBメディアで、
1998年の創刊以来、毎日更新をしています。
「ほぼ日」もまた、
独自の制作姿勢をもつと言われます。
ふたつのメディアに共通するのは、
「まるであそんでいるように見える」
「やりたいことをやっている」
ということかもしれません。
新井敏記さんと糸井重里は、どうして
自分でメディアつくることにしたのでしょうか。
そして、ふたりはいまに至るまで、
何を大切にしてきたのでしょうか。
新井敏記編集長と糸井重里の対談を入口に、
今年いっぱい、
「SWITCH」と「ほぼ日」は
さまざまにあそんでいきたいと思っています。
(2016年9月 ほぼ日編集部記)


- ほぼ日
- 今日は「SWITCH」と「ほぼ日」の
代表の対談ということで、
まずは、新井編集長におうかがいしたいのですが。
- 新井
- はい、どうぞ。

- ほぼ日
- 「ほぼ日」では、ミーティングなどで糸井重里が
全員の指針となるようなことを言うことがあります。
たとえば
「やさしく つよく おもしろく」や
「頭は低く 視線はまっすぐ そして志は高く」
というようなことです。
- 新井
- はい、なるほど。
- ほぼ日
- スイッチ・パブリッシングで、
新井さんは、スタッフのみなさんにいつも
どんなことをおっしゃっていますか?
- 新井
- ぼくは
「泥船に乗ったつもりで」
というふうに
言うことがあります。
- ほぼ日
- 泥船に‥‥。
- 糸井
- ああ。うん、うん、
いいですねぇ。

- 新井
- それは要するに
「自分で漕いでください」ということです。
うちはちっちゃな会社なので、
誰ひとりとして頼れる人はいない。
ほかに依存しません。
みんなが即戦力みたいなものなんです。
- 糸井
- なるほどねぇ。
- 新井
- じつは「SWITCH」という場所には、
丁稚制度のようなものがあるんですよ。
インターンではなく、
ちゃんとアシスタントとして雇って、お金も払います。
そのかわり「新入社員」のような採用はありません。
新人はアシスタントとして入って、
アルバイトで1年ほど働いていただきます。
そうすると、だいたい
その人の性格がわかります。
何に向いてるか、
その人にどういう方向があるのかが
わかってきます。
その段階を経て、正式なスタッフとして
「SWITCH」に入ります。
そのときは、もう即戦力のイメージです。
ですから、ぼくはそこで
「泥船に乗ったつもりで」
「自分で漕いでください」
ということを言います。

- 糸井
- それはつまり、
「ぼくは頼りにならないよ」って
言ってるわけですよね。
- 新井
- そうそう、そうです。
- 糸井
- それ、いいなぁ。うちもその言葉を借りたいな。
そうすると、自然に
若い人が来てくれるような気がする。
- 新井
- そうですね。
- 糸井
- まずは、妻子持ちの人が
丁稚をやるわけには
なかなかいかないですもんね。
- 新井
- なかにはいますが、
でもまぁ、年をとった人はなかなか来ないですね。
その丁稚制度の期間で見える部分が、
ぼくはとても重要だと思っているんです。
ぼくらのような小さな会社では、
新入社員といっても
そんなに応募が来るわけではないし、
優秀な大学を出ていても、あまりあてにはならない。
しかも、編集は
「1に体力」みたいなものですから、
もちろん体力が重要です。
丁稚の期間に「がんばり加減」を見て、
「この人は編集にいいな」とか「営業にいいな」、
「販売にいいな」と、判断していきます。
- 糸井
- なるほど、その方法もいいなぁ。

- 新井
- いや、よくはないです。
そうせざるを得ない、というほうが合ってる。
- 糸井
- いや、その「せざるを得ない感」はほんとうに、
「その気になっている人」が
集まるようなやり方ですよ。
- 新井
- そうですね。
- 糸井
- そのやり方だと、
「ぼくはあんまり仕事したくないんですよ、
どっちかというと休みたいんですよ、
で、お金はいっぱいください」
という人が、
「『SWITCH』の仕事をやりたいんですよ」
とやってきても、入れませんね。
- 新井
- はい。無理ですね。
- 糸井
- ああいう雑誌を作る集団の
入口としては、それはすごくいいですよ。
- 新井
- ぼくらは
ずっと糸井さんたちの背中を見てきた
世代なんです。
- 糸井
- そんなに離れてましたっけ?
- 新井
- 6歳違います。
- 糸井
- そうですか、
6歳ですか。
- 新井
- 6歳違うと、すごく違います。
兄弟のいちばん上の兄貴が、
ごはんのおいしいところをぜんぶ食べてしまった、
というイメージが‥‥。

- 糸井
- そうですね(笑)、年齢的にはそうですね。
- 新井
- それこそ沢木耕太郎さんもそうなんですが、
ぼくらは糸井さんたちの世代に憧れて
背伸びしてものを作ってきました。
「ビックリハウス」も
ジェラシーを感じながら見てました。
ぼくは雑誌がもともと好きで──いや、
雑誌が好きというより、
書くことが好きだったんですよ。
小学校、中学校のときから
書くことで自分を確かめるような子どもでした。
学校の先生にも嫌われてて、
ほとんど疎外されていたので、
友人に、自分の思ったことや
読んだ本や観た映画がおもしろかったことを書いて、
渡していました。
いま思えば、
コミュニケーションの道具にしてたんです。
そこから雑誌につながったんだと思います。
前提は「書く」ことだったので、
そのときから「なるべくたくさん書く」という
スタイルだったんですよ(笑)。
ほかの雑誌に持っていったら、
「ここはおもしろくない」とか「削れ」とか
言われるでしょう?
どこかの雑誌に原稿を持ち込むのではなく、
自分で書いて自分で作れば文句を言われない、
という事情で、すべて自分でやりました。
まぁ、おそらく自分に自信がなかっただけなんですが。
そこまでの道のりで、いちばん学んだのは
マガジンハウスの雑誌です。
まだ平凡出版の頃の「POPEYE」に
友人が勤めていて、
お手伝いしたことがありました。
見開きで記事を完結させることや、
ひとつのセンテンスを短くすることなど、
多くを学びました。
そんなある日、
片岡義男さんに出会うことになりました。
(第2回につづきます)2016-09-09-FRI
© HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN