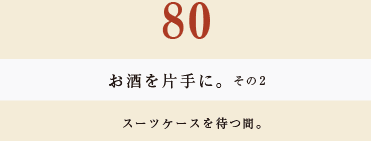ホテルの向かい側に大きなホテルがあって、
そこにバーがひとつある。
4時開店だからそろそろオープンする頃だろう。
通りに面して入り口があるから、
ホテルのロビーを通らなくても店に入るコトができる。
ほどよく安く、バーテンダーもしっかりしている。
どうだろう‥‥、と。
時計をみるとたしかに4時で、
なんとこの街についてすでに
6時間近くも経っていたというコトに、気持ちも憔悴。
ボクはバーのカウンターに座る人となった次第。
何をお作りしましょうか‥‥。
バーテンダーがそう聞いてくるのでボクはボソリと。
「ジンをオンザロックでいただけませんか」と。
飲めるものならなんでも良かった。
ジンでなくても、
ウォッカでもウィスキーでもよかったのだけど
「ウォッカ」をアメリカ風に
「ヴァカ」と発音するのはむつかしく、
ウィスキーはオヤジの酒のように思えた。
だからずっとアメリカでは
「ジンオンザロックス・プリーズ」
というのがボクの当時のスタイル。
「ジンの銘柄は何にするのか?」
とまたまた聞いてくるのでボクはぶっきらぼうに
「なんでもいいから飲みやすいのを」と答えて、
そのままボンヤリ天井を仰ぎみた。
大きなオンザロックグラスにかち割り氷。
透明なジンがトロリと氷を撫でるように注がれ、
ボクはひと舐め。
そしてふた舐め。
飲んで酔うのが目的ではなく、
バーというその空間で自分を必死に取り戻そう。
そしてもし、最悪の事態に陥ったら
一体どうすればいいのだろう‥‥、
と考えるための相棒として片手にお酒が必要だった。
だからグラスの半分ほども飲んだとき、
頭も気持ちもすっかりやさしく温まり
もう酒の力は必要なくなる。
オンザロックグラスの存在もほとんど忘れて、
ただボンヤリと。
それで1時間ほどが経ったでしょうか。
「メイアイヘルプユー」とバーテンダーの声がします。
何かお役にたてませんか?
という、アメリカ的なるサービスフレーズ。
ハッと我に返って声の方をみると
彼がニッコリしながらボクのグラスを見つめていいます。
「ジンオンザロックスが
ジンの水割りにそろそろなってしまいますが‥‥、
どういたしましょう?」とやさしく一言。
たしかに氷はほとんど溶けて、
せっかくのお酒が薄まっている。
申し訳なく思って一口。
飲むと、ジン独特の
ヘアトニックのような匂いのする水が
口の中に流れ込んでくる。
苦味ばかりを感じてまるでおいしくなくて、
ボクは思わずしかめっ面。
「ごめんなさい、せっかくのお酒を
無駄にしてしまって‥‥」
そういうボクに、バーテンダーはなおもニッコリ。
いやいや、よかった。
まだ明るい時間から若い紳士が切羽詰まった顔をして、
バーに飛び込み、「ジンをくれ」。
銘柄なんかはこだわらないから
「飲みやすいのをくれればいいんだ」。
そんな風に注文されたら、
あぁ、飲みつぶれたくなるような
何か不幸があったんだろう。
と、まずは警戒するものなんだ。
そんな輩に酒を売るか売らぬか、
その判断もバーテンダーの大切な仕事の一つで、
だから、じっとあなたを見ていたけれど、
一向に飲み干す気配も無くて。
一体、どうしたというのですか?
ボクはココに至った理由を説明し、
ひとりの時間を共に過ごす相棒としての
お酒が欲しかっただけなんですと、しめくくる。
なるほどならば、ジンはバッドチョイスのひとつ。
なによりオンザロックは
「グラスを早く空っぽにしろ」
と飲み手を急かす飲み方だから、
今日のあなたの気持ちを裏切る注文だった。
そんなときにお薦めの、酒があるけど、
一杯ためしてみませんか‥‥。
ハウストリートにしてあげるから。
ハウストリート‥‥、お店のおごり。
断る理由は何もなく、
なによりまだまだカバンが届く気配もなくて、
お願いしますとボクは頷く。
さて来週。
何がボクの目の前にやってくるのでありましょう。
そしてボクのスーツケースの運命や、
いかにであります‥‥、ごきげんよう。
|