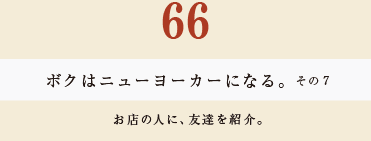みんなおいしいモノとたのしいコトが大好きな
ボクの友人なのですけれど‥‥。
エヴァ・ガードナーのような凛々しい女性が、エマ。
そして彼女のボーイフレンドのジャン。
ベルギー出身で、
おいしいモノをスゴクよく知ってるんです。
それから‥‥、と言いかけるボクを遮って、
「ケンイチと言います、もし呼びづらければ、
ケンとでも呼んでいただければ」
と、立ち上がってボクの先輩が支配人に握手する。
エマがすかさず、
「彼、トウキョウ出身で
別にカリフォルニアから来たワケじゃないんだけれど」
と言ってジャンと大笑いする。
お名前までお教えいただけて‥‥、
とニッコリしながら支配人は
「ブライアンとおよびいただければ
すぐに飛んでまいりますから」と。
そして、今日は白のシャルドネが
よき状態で冷えております。
会話のお供に、まずはデカンタで
それをお飲みになられては‥‥、と
とてもうれしいサジェスチョン。
スッキリとした白いワインで乾杯をして、
さて何を食べましょうかとメニューを手にする。
ジャンがそっとボクに聞きます。
ところでなんでこのテーブルを選んだの?
支配人に薦められたんだ。
小さなテーブルは社交的なテーブルで、
しかも丸いテーブルは
友人同士のカジュアルな食事に
ピッタリでしょうから‥‥、って。
へぇ、ブライアンってやるじゃない。
このお店のことと、お客様の気持を熟知している人。
この店、結構、見つけものかもしれないねって、
彼はちょっと感心しながら
「スターターは田舎風のパテにしようかな」という。
「ニース風のサラダを食べたいんだけど、
ツナとオリーブが嫌いなんだよ‥‥、
それを抜いてってお願いしたら変かなぁ‥‥」
って言うケンに、
それならグリーンサラダをたのめばいいじゃないって、
エマはピシャリと言い放つ。
そしてボクに向かって言います。
もしシンイチロウが私とふたりでココに今いるとして、
私をどこに座らせてくれるかしら?
|