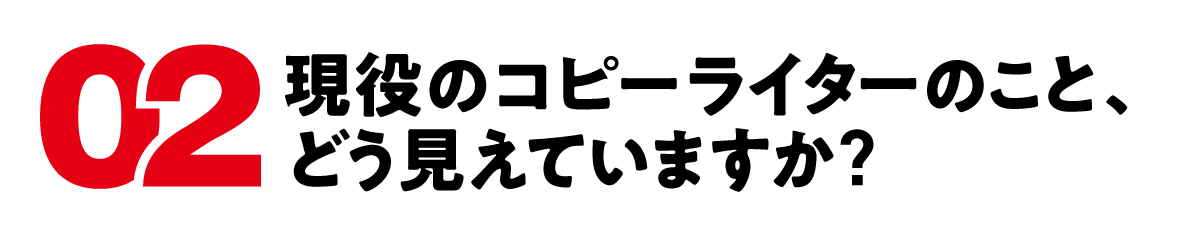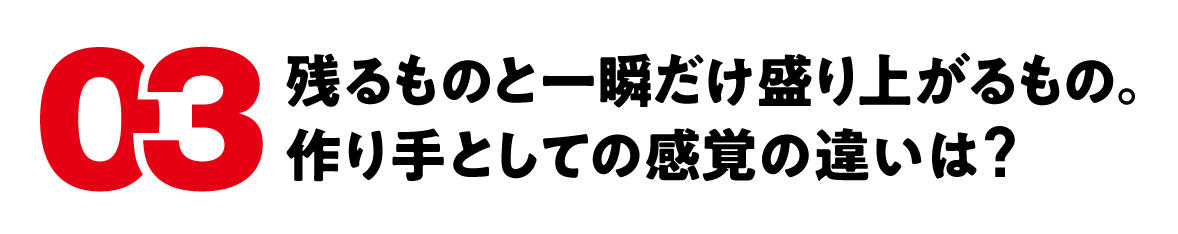糸井重里が1975年からいまも所属している
コピーライターやCMプランナーの団体、
「東京コピーライターズクラブ(TCC)」。
その60周年を記念したトークイベントの
ゲストとして招待いただきました。
TCC会長の谷山雅計さんが進行役で、
2022年に新人賞を受賞した
若手コピーライターのみなさんから
糸井重里に聞いてみたいことをぶつけ、
なんでも答えるという90分間でした。
広告の世界からは離れている糸井ですが、
根本には、広告で培った考え方をもとに
アイデアを考え続けています。
若いつくり手のみなさんに届けたい、
エールのような読みものです。
- 糸井
- きょうは若い人たちと何かやる場なんで、
どんどん行きませんか。
- 谷山
- そうですね、じゃあ次に行きましょう。
次の質問は都竹玲子さん。
- 都竹
- 糸井さんは売るためのお手伝いをする
広告屋から引退されて「ほぼ日」を立ち上げて、
売れるものを作る仕事に軸を置かれています。
そんな糸井さんから、
私たち現役のコピーライターはどう見えていますか。
糸井さんはもうコピーライターと広告に
興味がないんだろうなって勝手に思っていたので、
なんでこのイベントに来てくださったんでしょう。

- 糸井
- これはね、そのまま答えるのは難しくて、
コピーライターで「売るための手伝いをしている」
つもりはなかったんですよ。
もちろん、売るための手伝いになるから
ギャランティがもらえるわけだけどさ。
たとえばね、迷惑になるようなものの
コピーを頼まれたとしたら
その手伝いはしないじゃないですか。 - 昔の広告の教科書では、
「アラスカで冷蔵庫を売るのがいいセールスマン」
という言い方をされていました。
つまり、要らないかもしれないものでも、
なんとか売ってみせる仕事なんだと。
頼んできた人の欲望を満たせば、
ギャランティがもらえるっていうことですね。 - アメリカの広告業界のほうが
日本よりも進んでいたって言われます。
昔のアメリカの広告業界を描いたドラマでも、
競争に次ぐ競争が描かれていました。
クライアントが来たら夫婦でもてなして、
ライバルを追い落として、
社内の競争でも勝ち抜くような物語が続いていく。
でも、日本の場合って、
わりとそういう展開じゃなかったんですよ。

- 糸井
- 自分がユーザーである立場から、
「どういうものであったら受け入れやすいかな」
ということを考える仕事だったんです。
ぼくはコピーライターの仕事を説明するとき、
劇場の形を想像してもらうんですよ。
ステージの上にクライアントがいて、
最前列の席にいいコピーライターがいて、
後ろの席にはいろんな人が座っています。 - そのとき、檀上にいるクライアントが
言いたいメッセージに対して、
お客さんはいろんな文句を言うんです。
「そんな言い方じゃ聞こえないんですけど」
「そう言われても買う気になりません」
「それは迷惑にならないですか」とか、
そういう声をかけられる場所にいるのが
ステージ上の人たちなわけですよ。 - じゃあ、どうなると後ろの人も前の人も
満足するんだろうって考えるのが
コピーライターの仕事なんです。
その意味でぼくは、
ユーザーの先頭にいる人みたいな気持ちでいました。
いまだったら笑い話みたいだけど、
クルマの広告をするたびにクルマ買ってたからね。
ぼくもちょっとバカだなって思うけど、
本気にならないとやっぱり乗れなかったんです。

- 糸井
- それでも、広告の仕事が
つまらなくなってきたなと思ったのは、
クライアント側の強さが増していったから。
つまり、景気が悪くなったんですよ。
その広告が効くか、効かないかを
数字で問われるようになりました。
今のことばでいう、エビデンスですよね。
マーケティング的に、この層に向かって
こういう要素で言うことが大事だから、
それでコピーを書いてください、
という風潮になっていきました。
そうすると、ぼくが得意なことは
もうやれないなって思ったんですよね。
それだったら、もっと得意な人がいるよっていう
気持ちがだんだん出てきたんです。 - 理想の広告というのは、
黙っていても売れる商品の広告なんですよ。
逆算して考えてみると、
最高にみんなが喜ぶポスターを作って、
そのポスターに出ている商品はなんだろうって
考えたら、それがいちばん売れる商品。
そうやって考えているうちに、
作っていく側に向かっていったほうが
本当はおもしろいなと思ったんです。
- 谷山
- はい、はい。
- 糸井
- で、ぼくも途中でいくつか失敗してますね。
サントリーの仕事をしているときに、
「ペンギンズバー」というライトビールを作りました。
あれは、“ライトビールの広告”というものを
先にイメージして、そこから遡って作った商品です。
それから、もっと売れなかった
「サスケ」という商品がありました。
「コーラの前を横切るやつ」とか
「謎の冒険活劇飲料」とか言ってみたの。
あれはね、ちょっとまずいものが
売れないかなと思って相談して作ったら、
ほんっっとうに売れなかった!
- 会場
- (笑)
- 糸井
- そうやって失敗もしたけど、
もっとこういうものがあればいいのになって
関われるような広告を作るのが、
これからの広告だろうなと思ったんですよ。
そっちのほうに行きたくなったら、
自分がクライアントになっちゃうのが早かった。
そこで、今「ほぼ日」でやっている
仕事のしかたになったんですよね。 - 広告の仕事ではいつからか
競合プレゼンがものすごく増えて、
広告代理店の人は1週間に6日ぐらい
競合プレゼンの用意をしてるわけです。
ボツになるのが10分の9で
そのうち1個だけ採用されるとしたらさ、
それって日本の生産性の邪魔ですよね。
それまでは社長決裁で「いいですね」って
言われたところでスタートできたんですよ。
10分の1じゃなく、1分の1で仕事できた時代は
とっくに終わっちゃったんだなと思って、
ぼくは広告の世界から身を引いたんです。 - 広告を作る仕事はやめちゃったけれど、
人が何をしたら喜ぶんだろうとか、
どう伝えられたら嬉しいんだろうとか、
それについて考えることは
一回もやめたことはありません。
その意味でぼくは
「コピーライター」って名前じゃないけれど、
コピーライターとして別の道に
泳いでいったような気がしているんです。

- 糸井
- あとは、もうひとつの質問ですね。
現役のコピーライターがぼくからどう見えているか。
お伺いを立てる技術ばっかりが
磨かれていったんじゃないかなと思います。
クライアントがいて、その前に上司がいる、
マーケティングがいる、テストがある。
そんな環境でどういう表現をしたら
クリアできるんだろうかっていう練習を
ものすごくさせられていると思うんです。 - ここにいるみなさんは
大きな会社に所属していますから、
就職試験を受けたと思うんです。
採用者が何を選ぶかわからないから、
どんな採用基準でも自分が受かるように、
やみくもな勉強をさせられていますよね。
その勉強によって自分が持っていた
いいものが壊されていったとしても、
一回入ればなんとかなると思って就職試験を受ける。 - コピーの作り方も、ほかのいろんな企画も、
建物なんかでも、みんなそうなんですよ。
「個性」に見えるような引っかき傷をつけておいて、
あとは全部の条件が通りますよ、
というものを作る練習を、
みんながやっている気がします。
それは表現でも、アートでも、技術でもなくて、
「調整」じゃないかなと思うんですよ。 - いまの時代ってやっぱり、
説明の一番上手な人が出世する時代ですけど、
説明からは新しいものって生まれないんですよ。
説明を超えたところに、次のものが用意されます。
「あなたも見たことがあるようなあれですよ」
と言えちゃうような企画はもう、
右から左に場所を動かした説明にしか過ぎません。 - 広告が持っていた、
新しい何かを開拓する部分がありますよね。
「遊び場はもっとあるぜ」って見せる、
「その商品が活躍できる場所はもっとあるぜ」って
見せるおもしろさがあるはずなんですよ。
それを出さないように
させられているんじゃないかなって思うと、
若いコピーライターはちょっと気の毒だなと思う。
- 花田
- ひとつ聞いてもいいですか。
「調整」がメインになっている空気は
感じているんですけど、
昔は調整じゃない仕事のやり方が
なぜできたのかなって気になりました。
- 糸井
- 昔の意味の調整はね、
同じになり過ぎちゃうってわかってたから。
気をつける場所が少なかったんです。
「クライアントはあのタレントが好きだから」とか、
少ない情報のなかでやっていたから、
みんなが考えることがふつうになったの。
それじゃダメだろうってなって
ちょっと変なこと入れたほうがいいよってなりました。 - 今は、どんどん細かくなっていますよね。
変な案を出せる人よりも、
調整がいっぱいできる人のほうが
総合点で勝てるようになっているんじゃないかな。
でも、本当に重要なことは
調整が得意になることじゃなくて、
新しい質問と答えが見つかるかどうかだと
ぼくは思っているんですけどね。
- 都竹
- こういうイベントに来ていただけたのは、
そういう期待も込めてですか?
- 糸井
- そうですね。
何十年もやっていて懲りちゃっている人だったら、
調整のほうがうまくいくって信じているから。
「現実ってのはこうツラいんだよ」って
言いたがる人は山ほどいますし、
ぼく自身も半分はそうなってますからね。 - 若い人だと、そこのところをもっと野放図に、
おもしろさを優先したバカな企画が出せるんです。
いろんなことを考えると無理なんだけど、
その「バカ」が次の何かのヒントになります。
「やっぱりダメだったね」って
言われるかもしれないんだけどね。
ほら、さっきの谷山くんの
新人賞のコピーとか見たじゃない?
- 谷山
- えっへっへ。
- 糸井
- ぼくだって、もっと知っていれば、
「とうさん、あんたは不幸な人だ!」っていう
コピーは書かなかったと思うんです。
あのコピーってじつは技術でできていて、
そんな言い方をする青年はいないんですよ。
アメリカの翻訳文学のパロディーで、
おそらく若いみなさんがつくる広告も、
やっていることはほとんどパロディーだと思います。
そこに、パロディーじゃなくて
何か新しいものが見えるきっかけというのは、
「バカ」がやったことの中に大体入っています。 - 今だったら、若い世代の人たちが、
ダンスのグループを作って
BTSみたいなことをやるわけじゃない?
あれ、ぼくらの世代にはできないわけですよ。
お父さんやお母さんの大好きな
「勉強好きのいい子」になっていたら、
ダンスよりも勉強して、
紺のスーツを着て就活すればいいんだから。
でもそうしたら、みんなに求められるような、
おもしろいもの、うれしいものの
ほとんどはなくなっちゃうんだよ。 - 若いうちに、どんどんバカをしたらいいと思うんだ。
そういう人たちと会うチャンスがあるんだったら、
ぼくも、いい意味での発展が作りたくて
こういうイベントに来ているんです。
- 谷山
- いや、いきなりこんなに
しっかりとお話しいただけるとは。
- 糸井
- まじめだろ、おれ。
- 谷山
- いやあ、はい。
- 糸井
- 谷山くんとふたりなら、こうじゃないよね。
- 谷山
- 新人相手だとこうなるんだなあと
ちょっとぼく、驚いています。
もっと軽い話になるんじゃないかと、
実はちょっと思っていたところもあって。
- 糸井
- 軽い話にしましょうか?
- 谷山
- いやいや、本当にいい話です。
(つづきます)
2023-02-04-SAT