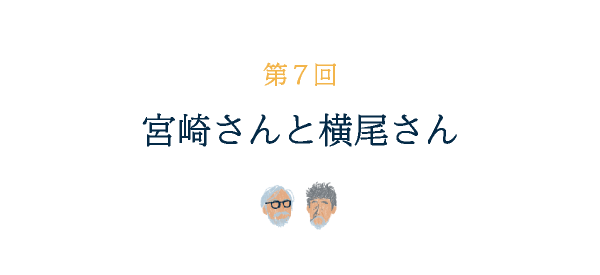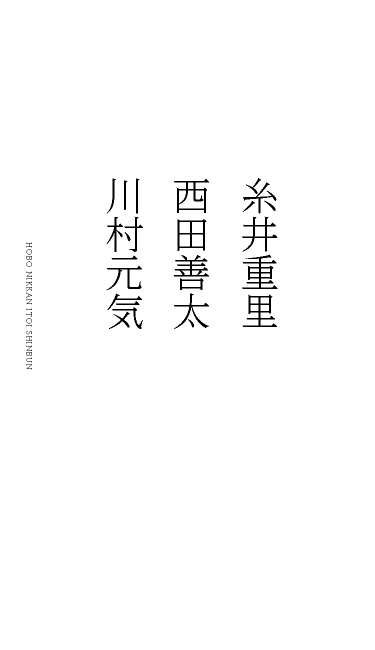
ずっとものをつくってきた人たちも、
立ち止まらざるをえなかった数ヶ月。
新型コロナウイルスの影響はいまもあり、
これからも簡単にはなくならない。
未来を予言したいわけじゃないけれど、
これからのことを話しておきたいと思いました。
雑誌をつくっている西田善太さんと、
映画や小説をつくっている川村元気さんと、
ほぼ日をつくっている糸井重里が話しました。
西田善太(にしだ・ぜんた)
1963年生まれ。早稲田大学卒業。
コピーライターを経て、1991年マガジンハウス入社。
『Casa BRUTUS』副編集長を経て、
2007年3月より『BRUTUS』副編集長、
同年12月より『BRUTUS』編集長に就任。
現在は第四編集局局長として『BRUTUS』
『Tarzan』の発行人も務める。
川村元気(かわむら・げんき)
1979年生まれ。『告白』『悪人』『モテキ』
『おおかみこどもの雨と雪』『君の名は。』
『天気の子』などの映画を製作。
2012年、初小説『世界から猫が消えたなら』を発表。
2018年、佐藤雅彦らと製作した初監督作品
『どちらを』がカンヌ国際映画祭
短編コンペティション部門に出品。
著書として小説『四月になれば彼女は』
『億男』『百花』『仕事。』など。

- 糸井
- 物理的なものが残らなくても、
記憶には残るっていうこともありますよね。
たとえば花火って必ず消えるじゃないですか。
でも、「長岡で見た花火は忘れられないね」
っていうふうに憶えてる。
だから、消えるものも、残る。
- 川村
- そうですね。
- 糸井
- あと、残したつもりはなくても、
もっといえば残したくなかったものでも、
それを含めて自分なんだ、
ということもありますよね。
「恥ずかしいものつくっちゃったなぁ」
というものも、どうしても混ざる。
でも、やっぱりそれも俺なんですよ。
だから、残しておいたほうがいいんだよね。
- 西田
- それを聞いて思い出したんですが、
ぼくはかつてほぼ日手帳の発売イベントで、
糸井さんと松浦弥太郎さんと
3人で話したことがあるんですが、
そのとき糸井さんに言われたことが
忘れられないんですよ。
まずぼくが持論として
「日記を書く人って自己愛が強いと思う」
って言ったんです。
手帳とか日記に自分で書いたことを
あとで自分で読み返すって、
ある種のナルシシズムじゃないか、って。
そしたら、糸井さんに
「チッチッチッ」と指を振られて。
「わかってないよ、君、君、君」と。
- 糸井
- やってないよ(笑)。
- 西田
- それは違うよ、と。
そのとき糸井さんが言ったのは、
「じつは、昔の自分のほうが
答えを出してることがあるんだよ」
っていうことで、
それがぼくにはとてもショックで。
つまり、自分は常に進歩してるわけじゃなくて、
同じことを繰り返してるんだって。
だから、自分のアーカイブを残したほうがいい、
ほぼ日手帳に書くのがいいのは
そういうことなんだよ、って言われて。

- 糸井
- ああ、そうそう、言った言った。
よく憶えてる人だねぇ。
- 西田
- 糸井さんは、
けっこうぼくに爪痕を残すんです。
- 糸井
- (笑)
- 川村
- 西田さんって、よく憶えてるんですよね。
ぼくが思うのは、
西田さんって「記憶の人」なんです。
- 糸井
- あああ、そうだねぇ(笑)。
- 川村
- さっきの、海辺にドラム缶を置いて、
900号ぶんのBRUTUSを読んで燃やしながら
ずっとお酒が飲めるって、
まったく嘘じゃないと思ってて(笑)。
自分が「記憶の人」だから、
人の記憶に割り込みたいんですよ、たぶん。
- 糸井
- はーー、なるほどね。
- 西田
- なんか、川村くんの胸の上で
小鳥のように眠りたい気分だ(笑)。
なるほどね。自分も記憶だから、ね。
- 川村
- そう、自分がいろんなことを忘れられない、
まあ、ある種の病のようなものだから、
人の記憶にも割り込んで、
そのひとのなかに、なにかの特集が
引っかかればうれしいっていう。
- 西田
- はい(笑)。
- 川村
- どんな形でもいいんですよね、残れば。
花火も、どういう色だったかとか、
どういう形だったかは思い出せないけど、
誰と行ってどういう気持ちになったかとか、
そのあと食べたものとかは
憶えてたりするじゃないですか。
だから、割り込み方は
いろいろあると思うんですよね。
ぼくも人の記憶や人生に
割り込みたいという欲望はあって、
たとえばそれって、極端にいえば、
嫌な気持ちでもいいんですよ。

- 西田
- なるほどね、うん。
- 糸井
- 嫌な気持ちでもいい。
- 川村
- はい。
『告白』とか嫌な気持ちにさせる映画なんで。
- 糸井
- ああ、そうか、そうか。
- 川村
- 『モテキ』とかは、
観る人たちに自分の切なさや
しょっぱい経験を思い出させるものだし、
記憶にどう割り込んでいくかで。
- 西田
- ぼく、『天気の子』は個人的に
割り込まれまくりなんですよ。
家の近所がたくさん出てくるんです(笑)。
いつも歩いてたりするからさ、いつも。
- 川村
- ああ、それは、もろですね。
- 西田
- 「ここだ」みたいな(笑)。
- 川村
- そういうふうに記憶に残したり、
あるいは残されたりするなかで、
もとの話に戻っていきますけど、
15年くらいずっと働いてきて、
この数ヶ月間の、
なにもなかった真っ白いページは、
とにかく記憶に残るだろうなと。
- 糸井
- うん。
- 川村
- 家から出られなかったのって、
数ヵ月間しかないんですけど、
真っ白い、これまでにない
記憶の残り方をするだろうなと。
- 糸井
- だって、たとえば
家族のアルバムがずーっとつくられててさ、
2ページくらいなくなってると、
やっぱりそこは引っかかるよね。
- 西田
- そのほうが記憶に残るし、
何度も記憶をたどるかもしれない。
- 糸井
- すごみがあるよね、それは。
- 川村
- 前向きに言うと、このなにもできなかった
空白の期間みたいなものって、
たぶんエンターテインメントの仕事において、
絶対に意味があると思って、
それを手がかりにいま、いろいろと物語を
つくりはじめているんです。
- 糸井
- それはかならずそうだよね。
たぶん、西田さんの仕事もそうだよね。
- 西田
- 記憶に残りますからね。
- 糸井
- 「記憶の人」だから(笑)。
あと、西田さんの場合は、お父さん
(西田善夫氏。NHKのスポーツアナウンサー)
と同じことをしてる感じはすごくある。

- 西田
- 実況ですか(笑)。
- 糸井
- 実況でしょう、
時代時代の雑誌をつくっているというのは。
- 西田
- ちょっと泣いちゃいますよ、
そんなこと言われたら(笑)。
- 糸井
- あ、この人は実況をずっとやってんだな、
って思うもの。
「あのときなにを思ったの?」ってときに、
「この雑誌を見てください」
って言える、みたいなさ。
- 西田
- 自分のことばで
実況できてたらいいんですけどね。
ちょっと墓参り行って、
「糸井さんにこう言われたよ」って
墓前で報告してきます(笑)。
- 糸井
- 行って、行って(笑)。
そういうのは似ちゃうんだろうな。
- 川村
- きっと、いいところも、
嫌なところも似るんでしょうけどね(笑)。
- 西田
- ああ(笑)。
- 糸井
- 川村さんも似てるの?
- 川村
- うちの父親も映画やってて、
まあ、挫折した口なんですけど、
やっぱり、いいところも
もらってると思うんですけど、
自分が歳を取ってくると、
子どものころ嫌だなと思っていた
ところが似てくる(笑)。
- 西田
- そうそう(笑)。
- 川村
- たとえば、ディテールなんですけど、
うちの父親がビデオデッキ買ってきて、
テレビとコードでつながなきゃ
いけないじゃないですか。
で、人に頼めばいいのに自分でやるって言って、
裏に回って配線とかしながら
「あー、もう!」とかって怒るわけです。
自分でやるって言ったのに。
で、最近、まったく同じことを自分が。
- 西田
- (笑)
- 糸井
- (笑)
- 川村
- そういう嫌だったところが
似るなとは思いますね、本当に。
- 糸井
- でも、その嫌なところを、いま、
大嫌いじゃなくなってるでしょう?
- 川村
- ま、そうなんです。
これ、嫌だったんだよなあと思って(笑)。
- 西田
- ぼくも、しゃべってるときに思い出しますね。
「これがホントの◯◯ですね!」みたいな
オチのつけ方とか、あのときの父親みたいな
ドヤ顔を自分がしてるんだろうなって(笑)。
- 糸井
- (笑)
(つづきます)
2020-07-25-SAT