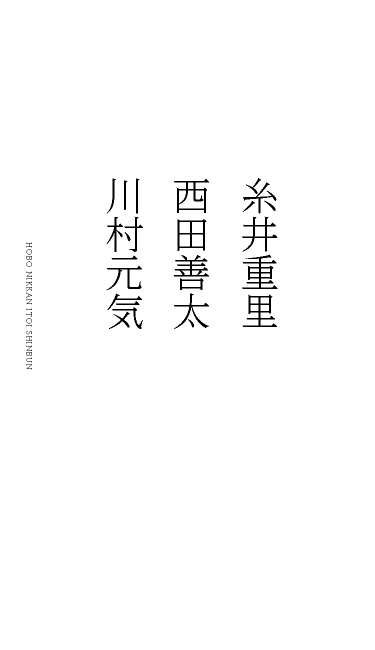
ずっとものをつくってきた人たちも、
立ち止まらざるをえなかった数ヶ月。
新型コロナウイルスの影響はいまもあり、
これからも簡単にはなくならない。
未来を予言したいわけじゃないけれど、
これからのことを話しておきたいと思いました。
雑誌をつくっている西田善太さんと、
映画や小説をつくっている川村元気さんと、
ほぼ日をつくっている糸井重里が話しました。
西田善太(にしだ・ぜんた)
1963年生まれ。早稲田大学卒業。
コピーライターを経て、1991年マガジンハウス入社。
『Casa BRUTUS』副編集長を経て、
2007年3月より『BRUTUS』副編集長、
同年12月より『BRUTUS』編集長に就任。
現在は第四編集局局長として『BRUTUS』
『Tarzan』の発行人も務める。
川村元気(かわむら・げんき)
1979年生まれ。『告白』『悪人』『モテキ』
『おおかみこどもの雨と雪』『君の名は。』
『天気の子』などの映画を製作。
2012年、初小説『世界から猫が消えたなら』を発表。
2018年、佐藤雅彦らと製作した初監督作品
『どちらを』がカンヌ国際映画祭
短編コンペティション部門に出品。
著書として小説『四月になれば彼女は』
『億男』『百花』『仕事。』など。

- 糸井
- コロナの影響でなにもできなかった時間を
どういうふうにとらえるかって、
けっこう大きいと思うんですね。
いま、みんな、この時間を
無限に続くように感じているけど、
何年かあとに振り返るときが来るんだ、
っていうことは意識していたほうがいいと思う。
- 西田
- この数ヵ月間になくなってしまった
クリエイティブって、すごい数だと思うんです。
それはもう、クリエイティブの墓場というか。
たとえばオリンピックに向けて
2月くらいまで死ぬ思いでつくってた人にとって
唯一のカタルシスはオリンピックだったわけで、
そこが突然ゼロになってしまったというのは
ものすごい徒労感ですよね。
それは忘れられないし、忘れなくていいと思う。
でも、またモチベーションを上げなきゃいけない。
なにもできないときにも、
なにかしなきゃいけない。
というときに、ぼくがよく言ってるのは、
ちょっとくだらないんですけど、
あるクリエイティブ・ディレクターが
やったことなんですよ。
彼が、在宅でなにをしようかと考えたときに、
1時間という時間を決めて、
いままで名刺だけもらった人と
「話しませんか?」って言って
全国のあちこちの人たちと
ZOOMで飲み会をやってたんです。
それだけでノート1冊分のネタをつくった。
- 糸井
- あー、いいですね(笑)。
- 西田
- いいでしょう(笑)?
だから、なにをすればいいんだろうって
オロオロする前に、いま自分ができることを
最大限にやるのがいいんだっていう、
いま、ぼくを支えてくれてる話なんですよ。
- 糸井
- それは健康的ですよね。
やっぱりその時間をどう過ごすかだから。
たとえば、川村さんはさっき、
バックパッカー時代にインドで電車が来なくて
9時間待たされた話をしてたけど、
その9時間って、川村さんにとって
無駄じゃなかったと思うんですよ。
- 川村
- そうですね。
実際、ぼくも駅で9時間待たされたときに、
ただボーッとしてたわけじゃなくて、
そこにいる人たちの物語を想像していたんですね。
駅で待たされているおじさんとか、
おびただしい数の乗客をさばいている駅員とか、
彼らを家で待ってる家族の人生を勝手に。
こういう学生時代を過ごして、
子どもたちはこういう性格で‥‥みたいなことを、
勝手にフィクションでつくって書いたりしてた。
携帯の電波も通じなくて、
あまりに暇すぎたからなんですけど(笑)。
でも、それがのちに小説を書くときの
ヒントになったんです。
- 糸井
- あ、やっぱり(笑)。
- 川村
- この数ヵ月も同じことだと思うんです。
コロナがなかったら、
たぶん予定通りに旅が進んで、
目的地にすぐ着いて、
ガイドブックに載っているものを
解像度の高いカメラで撮って‥‥
っていうふうに動いていたと思うんですけど、
1回、止められたことによって、
立ち止まって横道に入って子どもたちと遊んだり、
人懐っこい野良犬にエサをやったり、
そういうことができるようになったと思うんです。

- 糸井
- 都会にずっといると、目的がないと動けない、
っていう感じになりがちじゃないですか。
絶えずつぎの目的、つぎの目的、って。
今回のことでそういうやり方ができなくなって、
たじろぐ人もいるんだろうけど、
一方で、もともと遠くを目指している人は
あんまり関係ないんじゃないかと思うんですよね。
5年先にこうなっていよう、みたいな人は、
ふつうにそこへの道が続いてると思うんですよ。
だから、目の前のことだけじゃなく、
その向こうが見えているかどうかというのが、
けっこう重要な気がする。
- 西田
- あとは、この時期に、就職とか入学とか、
大切な時間を過ごした若い世代が、
どういうふうに今後を過ごしていくか。
たとえばぼくの息子は会社が決まって、
この春から出社だったんですけど、
2ヵ月半くらいずっと家にいてリモートで
レポートとかを書かされていたんですね。
たぶん、「コロナ世代」みたいな
言い方をされると思うんですけど、
それが独自のなにかを生み出すか、
ちょっと遠回りしたねみたいに言われるかは、
彼らにかかっているわけで。
そこはちょっと興味がありますね。
- 川村
- そういうふうに、
世代によって価値観が変わってきそうなところも、
震災やテロと違う部分だと思うんですね。
たとえば、いま、おとなたちは
可能な限りコロナ以前の状態に
「戻りたい」と思ってる気がするんです。
ほんとうはオンラインじゃなくて
居酒屋で飲みたいし、会社行って働きたい、と。
満員電車すらやりがいだと感じてる可能性がある。
そこに一生懸命、戻そうとしている。
だから、いまを代替としてとらえているんだけど、
子どもたちはもう、
ずっと夏休み、みたいな気分でいたりする。
もちろん、そうじゃない子どももいると思います。
でも、おとなたちが右往左往しながら
慣れないZOOM会議をしている後ろではしゃいでる
子どもとかを見ると、この意識の差って、
これからも開いていくだろうなと。
既存のシステムが壊れて混乱しているおとなたちと、
壊れたあとの世界を
たのしんでる子どもたちがすでにいて、
それがそのまま10年経ったら、
いま子どもである少年少女たちが自分たちだけの
「リモート王国」をつくりはじめる、
みたいなSFだってあるかもしれない。
- 糸井
- それはフィクションとしては
あるんじゃないですかね。
- 川村
- そのくらい、世界のとらえ方が、
世代でも大人どうしでも違う。
だから、現実に戻していくといっても、
なかなか一丸となりにくい。
- 西田
- まあ、もともと、子どもは
親の世代のカウンターとしてあるのが
ふつうだともいえるよね。
だから、逆にぼくは川村くんに
いまみたいに言われると、
いきなり自分がオールドスクール側に
いることを自覚させられて、
「やっぱり会わなきゃ!」とか言っちゃう(笑)。

- 糸井
- 言うよ、俺も言うよ。
たぶん3人とも言うんじゃない(笑)?
- 川村
- あ、もちろん全然「会わなきゃ」世代です(笑)。
- 西田
- ゴリラ学に詳しい後輩に聞いた話ですけど、
ゴリラの家族って、10匹とか15匹とかの
コミュニティーなんですけど、
そのメンバーとボスが1日に1回はかならず、
互いの顔をのぞき込むみたいにして
目を合わすそうです。
そうやって全員の気分とか体調を
しっかり確認するらしい。
だから、1匹がしばらく群れを離れたりすると、
そのゴリラはもう群れに戻ってこられない。
毎日確認することで、群れ全体が生き残る
バランスみたいなものを調整してるんです。
この「顔を合わせないと保てない」って、
人間の世界でもいえるんじゃないかなって。
- 糸井
- 身体感覚として、それはあるよね。
- 西田
- だから、どんな役割の人でも
やっぱり会わなきゃダメだっていうのを、
その後輩が言ってたんですよ。
アラスカ大学クマ学科出たやつなんですけど。

- 糸井
- ほんとかよ(笑)。
- 川村
- やっぱり、直接会わないと、
情報量が絶対落ちるじゃないですか。
- 西田
- 落ちますよ。
- 糸井
- そりゃ落ちます。
- 川村
- たとえば、ZOOMで
クリエイティブのミーティングしてると、
いかにあいづちが大事か、
みたいなことを痛感するんですよね。
「ああ、なるほど」とか、
ポロッと言ったひとことから、
大事なことが広がることってあって。
「なんかわかんないんだよな‥‥」って
誰かが独り言みたいに言ったときに、
「え、どこがわかんないの?」ってつっこむ。
そういうときに、
意外なアイディアが出てくるとか。
直接会っていないとそういうのが
なかなか発生しないんです。
おもしろいものをつくるときって、
正解、不正解を大枠で
決めていくことじゃなくて、
そういう些細な引っ掛かりを
掘っていくことのほうが大事だから、
それができないのがとてもストレスで。
- 糸井
- リモートでやってる会議っていうのは、
言葉が記号のやりとりになるんだよね。
で、会っておしゃべりしてるときって、
ある種の「歌」なんだよね。
だから、何言ってるかよくわかんないけど、
「なんか機嫌がよさそうだな」みたいな。
- 西田
- (笑)
- 糸井
- その雰囲気だけで十分に
相手を気持ちよくさせたりするからね。
「やあ」だけでいろいろ済んじゃうとかね。
そういうのは、さっき川村さんが言った
SF的な文化圏が衝突したとしても、
共通するものなのかもしれない。
- 川村
- そうなんですよね。
だからそのSFも、大人と子どもの
分断そのものがオチになるわけじゃなくて、
たぶん、どこかに着地点があるんだろうなと。
おじさんたちのゴリラ的なコミュニティが
そのままでいられるはずもない。
子どもたちがデジタルとリモートで
ぜんぶを済ませちゃうというのも、
それはそれでファンタジーだと思うんです。

- 糸井
- そうじゃないよね、うん。
- 川村
- もし物語で解釈するとしたら、
そこで1回、完全に分断しちゃって、
それぞれ国をつくっちゃって戦争したあげく、
思いがけない第三国におもしろく
着地させてあげなきゃいけないと思います。
だから、分かれたままなのも違うし、
かといってまんま元通りというのも違う。
- 西田
- なんか、『ブラック・ミラー』
(Netflixなどで配信されている
イギリスのドラマシリーズ。
多くの場合、近未来や異世界を
舞台にした1話完結もの)の話みたい。
- 糸井
- ああ、『ブラック・ミラー』だ(笑)。
(つづきます)
2020-07-22-WED

