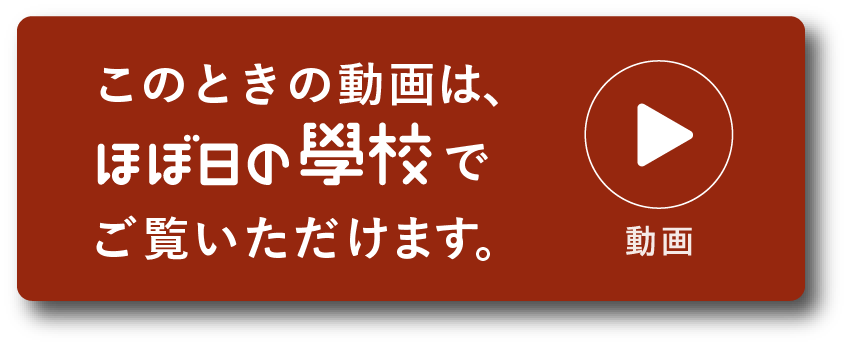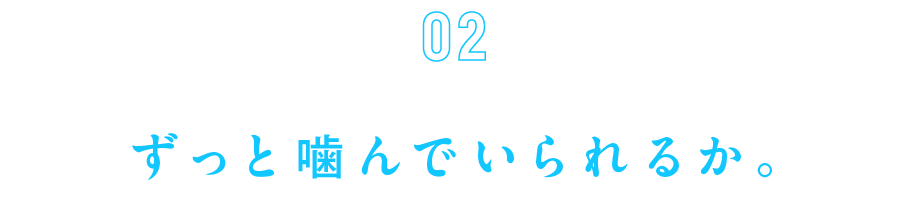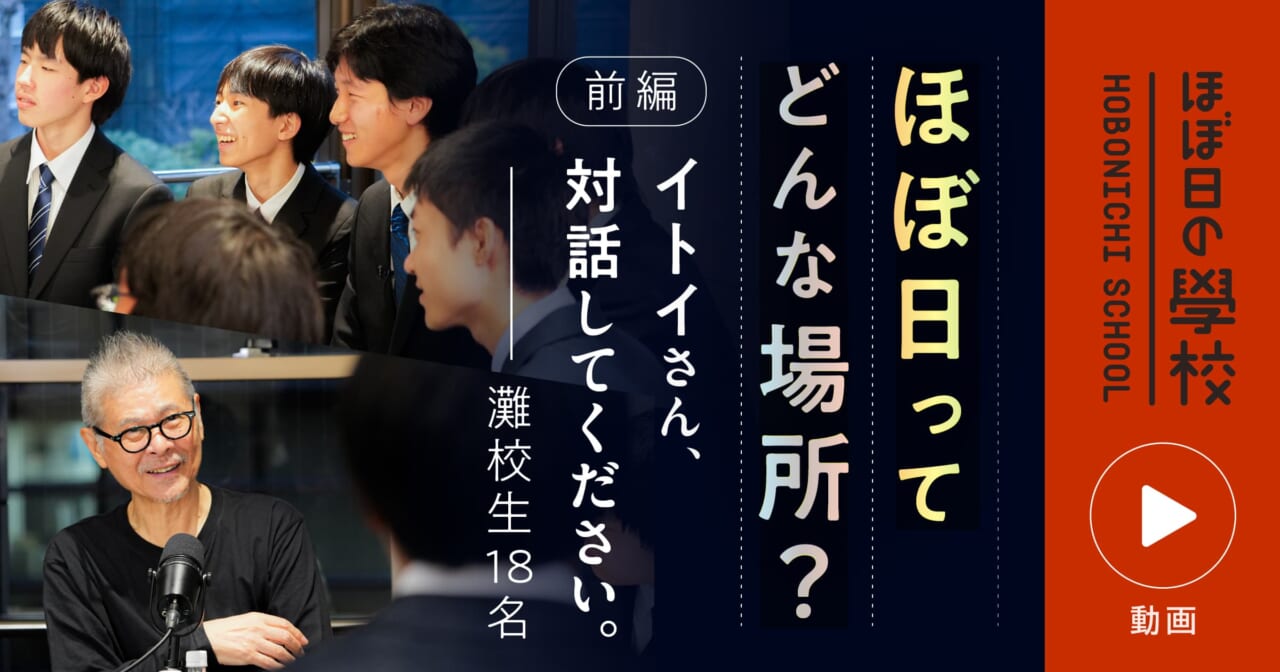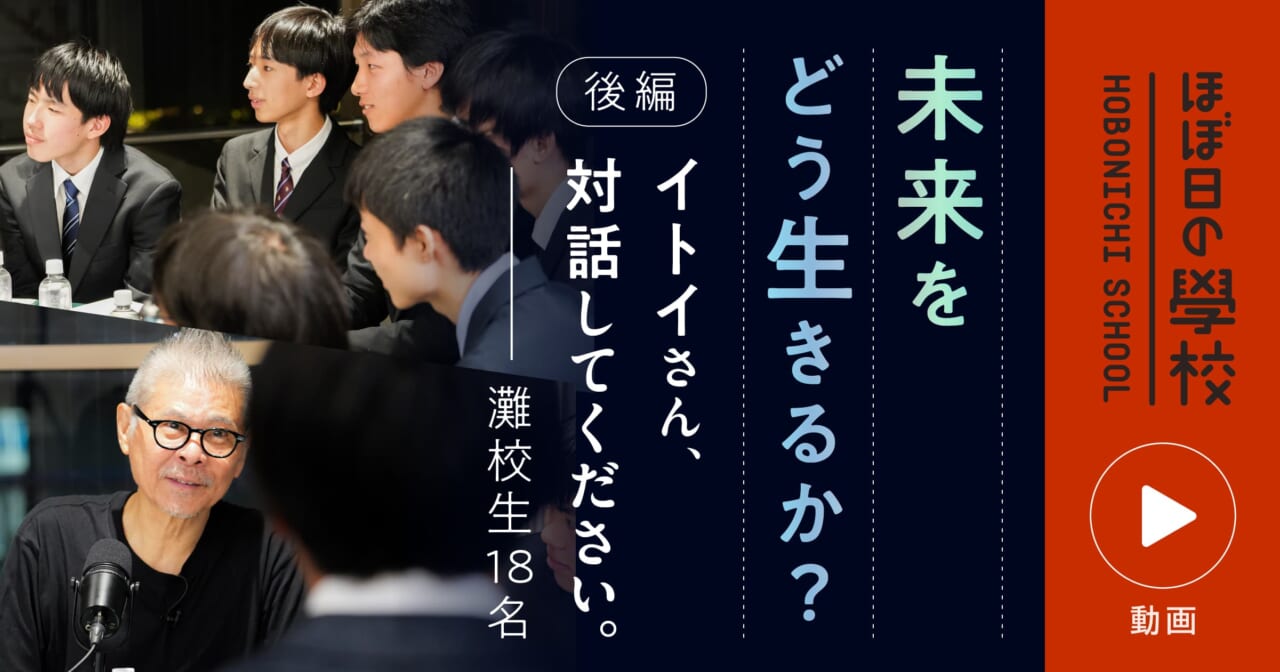- 糸井
- (マイクを付けながら)
もう始めちゃおうか。
- Iさん
- はい、よろしくお願いいたします。
僕は、灘高校の新高校3年生のIと申します。
本日はお招きいただき、
どうもありがとうございます。

- 乗組員たち
- (拍手)
- 糸井
- こちらこそ、ありがとうございます。
みんな、仕事をサボって聞きに来ています。
- 一同
- (笑)
- 糸井
- いままでいろんな方が来てくださりましたが、
こんなに乗組員たちが
緊張して待っていたのは初めてです。
あ、でも、一度だけみんなが
ずーっと待ち構えていたときがあって、
それは木村拓哉さんが来た日でした。

- 糸井
- みんなは「大人は平気なんだろうな」と
思っているかもしれないけれど、
きょうは大人も緊張しています(笑)。
それはなぜかというと、みなさんが、
可能性に満ちた大事な宝だからです。

- Iさん
- 光栄です。
今回、僕が糸井さんに依頼状を
お送りした理由は、
高校一年生のときに「ほぼ日」に出会い、
メディアとしてのあり方に
衝撃を受けたことでした。
糸井さんの対談や、
ほかの方のインタビューを読んで、
書き手の「好き」という気持ちが
文字に現れているのを感じて‥‥
そういうふうに、個人の「好き」を会社として
しっかりと形にしているところに
強く惹かれています。
なので、ほぼ日のみなさんから
ご承諾のお返事をいただいたときは、
うれしくて叫んでしまいました。

- Iさん
- 事前に糸井さんへの質問事項をお送りしましたが、
それはあまりお気になさらず、
会話の流れにまかせて
お話しさせていただければと思います。
- 糸井
- わかりました。僕も、そのほうがありがたいです。
僕はいつも、対談の前に答えを用意しないんです。
実際に会ったとき、新鮮にやりとりができるように、
ある程度話すことを考えたところで、
いったん考えを止めます。
どんなにいい答えを思いついたとしても、
なるべく忘れるようにしています。 - みなさんも、頭のなかで
「こんなことを話そう」と
準備してきたことがあるかもしれませんが、
なるべく、いまここで思ったことを
大事にしてください。
「そうじゃないよ」と突っ込みたくなる
話になったとしても、
それは広がる余地を持っているということなので、
突っ込みどころはあればあるほどいいです。
「こう来たらこう出る」と
予想していたとおりにはならず、
「思わずこう言ってしまった」ような言葉が
たくさん出る場になればいいなと思っています。
ということで、とにかくやってみましょう。

- Iさん
- はい。僕がいま一番気になっていることは、
「ほぼ日は、次はなにを始めるんだろう?」
ということです。
僕たちが生まれる前から更新しているほぼ日ですが、
「生活のたのしみ展」や「老いと死」特集など、
常に新しいことをしようとしている印象を受けます。
- 糸井
- ほぼ日がいつも変化していることや、
新しいものを考えようとしていることは確かです。
でも、じつは、なにか始めるときは毎回
「『ほぼ日はもうだめだ』と言われるかもな」
という気持ちがあるんです。
それは僕たちだけではなくて、
ほかのいろいろな業界を見ていても、
「なんとかして、絶対に新しいものをつくろう」
という考えから新しいものが生まれることは、
あまりないように感じます。 - 自分にも、仲間たちにも
「新しいものを出そうよ」と言うことは
よくあります。
誰かが、あまり代わり映えのしない
アイデアを出してきたときは
「それではおもしろくないね」と意見もします。
でも、
「少しでも『あ、これ、いいかも』と感じるものを
試してみたい」という気持ちのほうが、
僕のなかでは大きいんです。
新しいかどうかを試すよりも、
試すこと自体をのびのびと喜べるような場面を
つくるほうが重要なのかもしれません。

- 糸井
- いま例に挙げてくれた「老いと死」特集も、
テーマそのものは、まったく新しくないですよね。
きっと、人類は二足歩行を始めたころから
「老いと死」を考えていますから。
だから、ほぼ日が
「『老いと死』をテーマにします」と
言い出したとき、
「そんなこと、大昔からみんな考えてるよ。
いまさら、なに?」
という反応があってもおかしくなかった。
だけど、僕ら自身が
「死について、このあたりのことは
読んだことがないな」とか、
「読んだけど、理解できなかったな」と思うことを
やっていけば、
きっといままでの人がやらなかった触り方の
「老いと死」特集になると思ったんです。
隣にいる人同士が、
ご飯食べたあとにおしゃべりするみたいに
「老いと死」のことを話したり。
あるいは、知識の水準が近い人たちが、
「老いと死についてはいろいろ考えてきたけど、
そういえば、この部分は考えたことがなかったな」
ということを話し合ったり。
そういったコンテンツができるとしたら、
すでに老いや死についての重要な考えとして
残っている思想以外の「老いと死」を、
自分の問題として考えられますよね。 - たとえば、「老いと死」特集のなかで、
以前ほぼ日で働いていた人が
老人ホームに入ったという話がありました。
「自分はどう考えてどうしたか」という話は、
統計のなかではただの一例にしかすぎません。
だけど、あるひとりの話をよく聞いたら、
「自分と同じこと考えてるな。
あ、ここが考えの分岐点だったんだ。
じゃあ、自分はどうしようかな」と、
自分の問題としてとらえられるんです。 - 「年金の問題はどうなるのか」、あるいは
「人生100年時代を人間はどう生きるべきか」
といった一般的なテーマと違って、
死に対する個人的なイメージは話題になりにくいです。
でも、聞かれないからといって、
みなさんも「老いと死」について
考えていないわけではないと思います。
誰かひとりが
「自分にとって、老いや死はこういうイメージです」
と言い出すのをきっかけに、
みんなが考えを話し出すことで、
だれもいままで見たことのない会話が生まれます。

- 糸井
- そう、「いままでにない会話」というものが
重要なのかもしれません。
「老いと死」特集の最初登場していただいた、
養老孟司さんのお話がまさにそれでした。
養老さんが「老いと死」をどう考えているかは、
すでにいろんな本に書いてあるんですよ。
実際に、対談当日にお話しくださったことも、
本の内容とずれていませんでした。
でも、それは「知っている話を聞いただけ」
ではなくて、僕たちは
「その日のその話の流れからしか出ない、
養老さんの話」を聞いたんです。
その1回しかあり得なかったことが起こった。
それは、いままで世の中になかった、
ある日のある時間が出現したということなんです。
その話をどういうふうに伝えるか、というところに、
僕たちの仕事があります。 - つまり、新しさを求めなくても古くならない。
「いままでになかったこと」
「その場所でなければありえなかったこと」は
身の回りに数え切れないほどあります。
たとえば、Iさんが生まれてから
きょうに至るまでに、
ある曲がり角を曲がったか曲がらなかったかで、
変化した未来があると思います。
同じあみだくじは二度と引けない、
そのことの貴重さみたいなものを、
僕らは大事にしようと思っているんです。 - 新しさを目指してはいないけれど、
古くなる心配はいつもしています。
「変わらない」というのは、
究極的に言えば、死んでしまうことなので。
最後はみんな同じく死ぬとしても、
そこまでは全員違います。
その違いを、なんていうかな、
大事なことだと思ってるんです。
「ふたつとない」ということを。 - 同じように見えるものでも、
ほんとうに同じものはふたつとないんです。
そのような前提でものごとを考えると、
「新しくなければ」というプレッシャーから、
いつの間にかひょいっと逃げることができています。
ほぼ日の「新しいことをやる方法」は、
そうやって身につけてきたものだと思います。
(明日に続きます)
2025-06-06-FRI