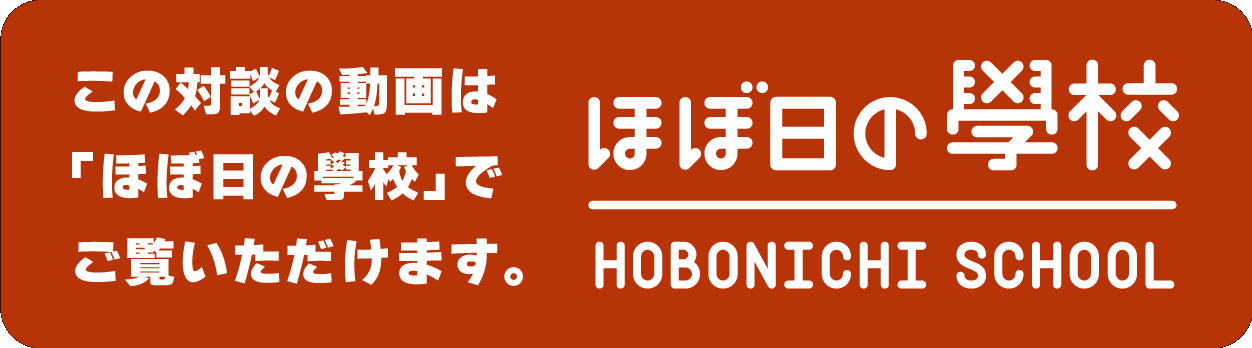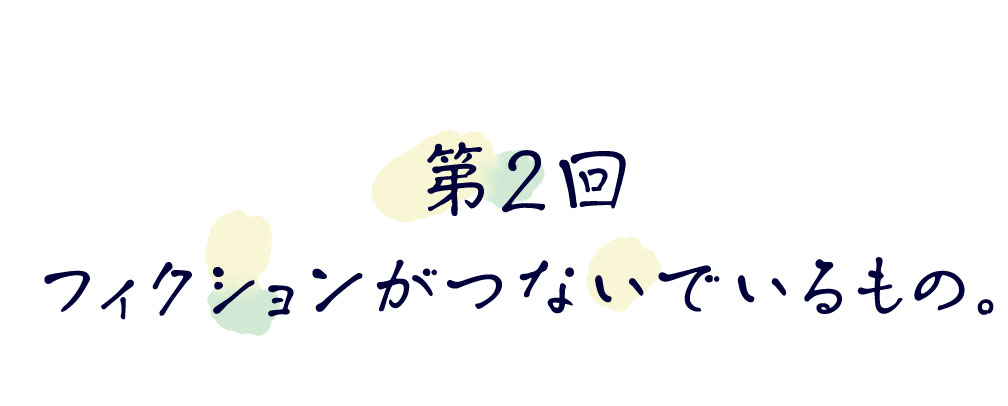昨年の前橋ブックフェスで、
作家の岸田奈美さんと糸井重里が
トークショーをおこないました。
岸田さんが本を出版される前から
何度もおしゃべりしてきたふたりですが、
ふたりだけで、多くの人の前で、
じっくり話すのはこれがはじめて。
書くだけで生きていくには、枠線、
悲しみから芽吹くもの、家族についてなど、
話はどこまでも広がっていきます。
岸田奈美(きしだ・なみ)
作家。
Webメディアnoteでの執筆を中心に活動。車いすユーザーの母、ダウン症の弟、亡くなった父の話などが大きな話題に。株式会社ミライロを経て、コルク所属。
主な著書に『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』、『傘のさし方がわからない』、『国道沿いで、だいじょうぶ100回』など。Forbes 「30 UNDER 30 JAPAN 2020」「30 UNDER 30 Asia 2021」選出。
岸田さんのnoteはこちら。
- 岸田
- 糸井さんが、もうひとつわたしに言ってくださったのが
「転んでも、ただでは起きてない」と。
でも、たぶん、そういうことです。
わたしがやってきたことは。
- 糸井
- そのとおりですよ(笑)。
- 岸田
- お母さんが心臓病を2回やってて、
そのことをわたしはずっとエッセイに書いてるんです。
『もうあかんわ日記』にも書いたんですけど、
2回目なんておばあちゃんが認知症になっちゃって、
お母さんが心臓病で入院して、
もうほんとに大変な時期で。
- 糸井
- そうでしたね。
- 岸田
- そのエッセイは本になるくらい、
たくさんの方に読んでいただけて、
すごい応援されて、
わたしはものすごく救われてたんです。
- 糸井
- 書きながら救われていたんだ。
- 岸田
- でも、頭の片隅で、
「家族が健康であっても書けるのか」っていうのは、
糸井さんが言ってくださったので、
ずっと考えていたんです。
それで思い出したのが、
パリのパラリンピックに行ってきたんです。
- 糸井
- ああ、夏にやっていた。
- 岸田
- そこに、ウクライナの代表選手が出場されてて、
『13歳からの地政学』の田中孝幸さんが
選手に取材されていたのを
横で聞かせてもらったんですけど、
選手の方のなかには戦争の前線で戦って、
片腕になったばっかりの兵士が大会に来てるんですよ。
- 糸井
- ああ、そうなんですか。
- 岸田
- うわ、すごいなと思ったんです。
うちのお母さんって、
大動脈解離っていう病気を起こして、
後遺症で歩けなくなっちゃったんですけど、
歩けなくなった自分を受け入れるのに、
10年ぐらいかかってるんです。

- 糸井
- 10年。
- 岸田
- 今は明るく生きているんですけど、
歩けない自分を認めるまでにそれぐらいかかってる。
なのに、ウクライナの選手は、
腕をなくしてすぐに
「スポーツ選手になろう」って頑張って、
国の代表になって大会に出てるんですよ。
- 糸井
- すごいなぁ‥‥。
- 岸田
- なんで、そんなに立ち直りが早いのか聞いたら、
他の選手も同じ戦場で
腕や足をなくしたばっかりの人が集まっているから、
孤独じゃないと。 - あと、もう一つ理由があって、
国のために戦いたいと言っていました。
選手たちが試合に出るのは、花の都・パリですよ。
めちゃくちゃきれいな街並みで、
平和の祭典だから陽気な雰囲気なんです。
でも、ウクライナの選手は、
「すぐ戦場に戻る」と言って、本当に戻って行きました。
- 糸井
- パラリンピックに代表選手として出ている人が。
- 岸田
- 国の代表選手なので、
戦争に戻らなくてもいいんです。
負傷兵だし、帰らなくていいんです。 - でも、攻撃に使えるドローンの免許を取って、
すぐに戦場に帰りたいんだって言っていました。
日常に帰るのが怖いんだ、とも。
- 糸井
- そうか、日常に帰るのはむしろ怖い。
- 岸田
- ウクライナって、前線以外は平和な、
攻撃を受けてない地域もあるので、
平和な場所に留まれる権利が彼らにはあるんです。
でも、そこにいると、
戦ってた日々のことを思い出したり、
置いていった仲間たちのことを思ったりするから、
日常にいる方がつらい。戦争がなければ
普通の生活のほうがいいに決まってますけど、
今の状況では、戦地の方が自分は幸せなんだと言って、
戦場に戻っていきました。 - それは、その人の話ですし、
戦争という壮絶な状況なんですが、
私はけっこうそこに自分を重ねてて、
つらいことや苦しいことがあったときの方が、
やっぱり書けるんですよ。
- 糸井
- ああ。
- 岸田
- 何も起こらない状況になったときに
「書く」っていうことの方が、きっと難しくて。 - だから、人って非日常に慣れちゃうと、
日常に戻ってくることの方が難しくて、
勇気のあることなんだっていうのを、
なんか、その時にものすごく、
共感って言ったらちょっと浅いですけど、感じました。
- 糸井
- それは、悪い言い方をすれば中毒ですよね。
- 岸田
- そうですね。
刺激にも慣れちゃって。

- 糸井
- 非日常依存というか。
- 岸田
- そうなんです。
- 糸井
- だから、よく男女関係で問題ばっかり起こしてる人は、
普通に安定した暮らしになったら、
「私って何なんだろう」と不安になるから
問題を起こしちゃうんでしょうね、きっと。
- 岸田
- それは、わからん(笑)。
- 糸井
- でも、岸田奈美の場合、
不安な気持ちを「書く」っていうことで、
解消するっていう言い方はあれですけど、
書くことで誰かが読んでくれると、
根が生えていくみたいに
自分の不安定な心とか事件が、
収まるじゃないですか。
- 岸田
- そうですね。
- 糸井
- 気持ちが穏やかになったら、
「おいしいサンドイッチを食べました」っていう話も
混ぜられるようになっていますよね。
- 岸田
- そうですかね、無意識ですけども。
- 糸井
- さっき、前橋の「たまごサンド」を食べて。
- 岸田
- おいしかったー!
- 糸井
- でも、世の中には、
不幸な人はおいしがらないでください
っていうような、世論もあるわけで。
- 岸田
- そんなこと言うかな(笑)
- 糸井
- いや、あるんですよ。
- 岸田
- あるんですか。
- 糸井
- かわいそうな目に遭ってる人だと思って応援してたのに、
高級料理店でコースを食べてたら‥‥
ね、見え方ってあるんですよ。
- 岸田
- ああーー。
おしん的な感じをわたしは演じないといけない
っていうことですよね。
- 糸井
- かわいそうだと思って応援してたのに、
本当はわたしよりおいしいものを食べてる、みたいな。
それで、どんどん自分のイメージの方に
依存的に突っ込んでいってしまう。
- 岸田
- ありますね。
- 糸井
- それは、責める側も間違ってるんですけど、
岸田さんが表現するものが
あっちにもこっちにも芽を出したり、
根を張ったりできているのは、
「フィクション」というものを
つなぐことなのかなと思っていて。

- 岸田
- フィクション。
- 糸井
- 夏井いつき先生と前橋高校でお話したときに、
「思ったことだけを俳句に書くわけじゃない。
美しい俳句とか、
自分でいいと思ってる俳句を作るのに、
誰かの魂に仮託して表現する
みたいなことも俳句だ」と。
- 岸田
- お話しされていましたね。
- 糸井
- だから、松尾芭蕉が
実際にカエルを見てたとは限らない、と。
- 岸田
- 本当に思ったこととか、
本当に悲しくてわかってほしいことって、
事実だけをそのまま書いても
人の心に入っていかないというか、
わかってもらえないと思います。
でも、わかってほしい気持ちも
ものすごくあるので、
そのためにはすこしフィクションを‥‥。 - あの、でもお父さんのことは、やっぱりつらすぎて、
すごい忘れてるところがあります。
だから、そうすると、
わたしのエッセイにお父さんが、
一切出てこなくなっちゃって。
- 糸井
- ああ、そうなるでしょうね。
- 岸田
- だけど、わたし、
お父さんはいなくなったけど、
めっちゃおもろい人やったんやでっていうのを
本気でわかってもらいたくて、伝えたくて、
でも中高のとき話を聞いてくれる人が
まわりに誰もいなくて、
インターネットだったらみんな耳を傾けてくれたんです。
- 糸井
- それが、岸田さんとインターネットのつながりなんだ。
- 岸田
- わたしもお父さんのことが言えてうれしくて、
お父さんが言ってない一言や、言われたかったこと、
こう思ってた“はず”だ、みたいなことを
嘘もちょっと混じってしまっているんですけど
書くことはあります。 - でもそれは、書くことによろこびがあるんじゃなくて、
伝わることによろこびがあるからだと思います。
(つづきます。)
2025-05-03-SAT