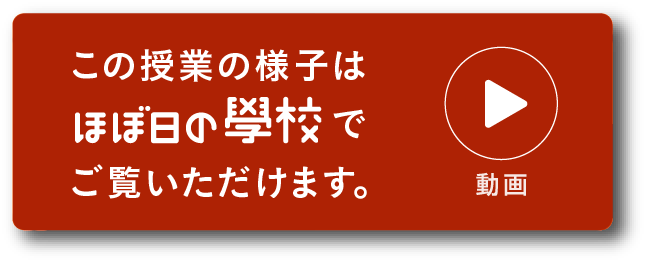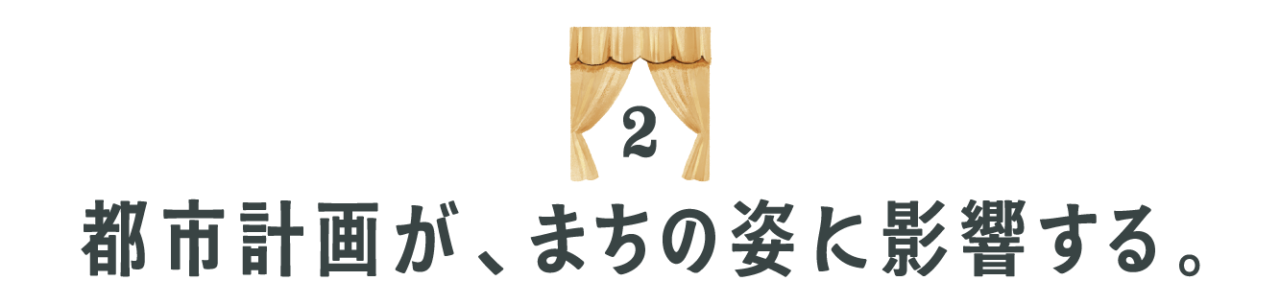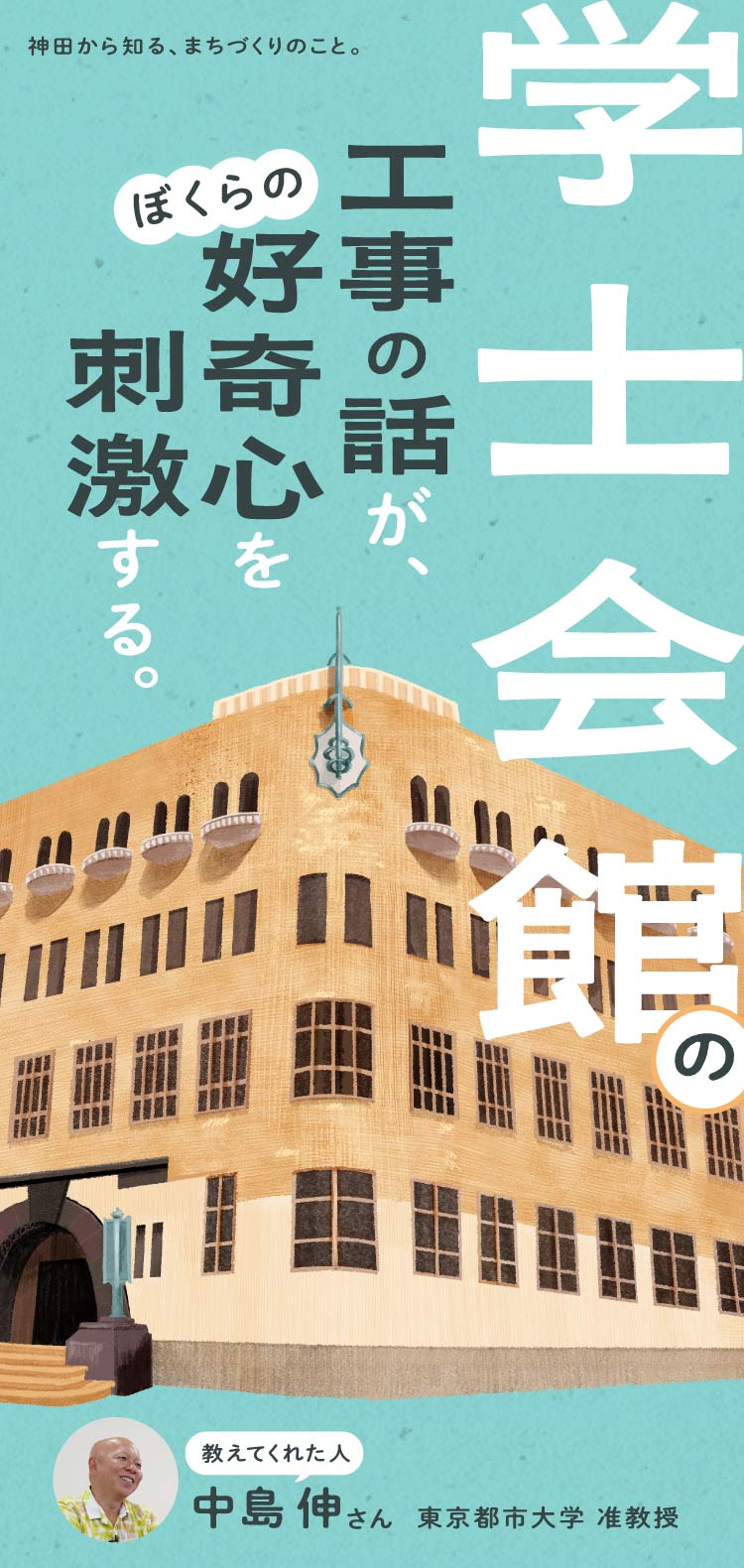
「学士会館」のこと、知っていますか?
東京・神田、ほぼ日の本社から徒歩数分の
場所にある、歴史あるかっこいい建築です
(『半沢直樹』の最終回をはじめ、
さまざまなドラマのロケ地にもなっています)。
実はいま、道路拡張計画に伴い、
建物全体をガガガッと引いて動かす
「曳家(ひきや)」という方法での、
再開発工事がはじまっているんだとか。
そんなことできるの? いったいなぜ?
そのあたりについて、ほぼ日の乗組員みんなで、
神田のイベント「なんだかんだ」でも
お世話になっているまちづくりの専門家、
中島伸先生に教えていただきました。
中島伸(なかじま・しん)
1980年、東京都中野区生まれ。
都市デザイナー/東京都市大学准教授。
東京大学大学院工学系研究科
都市工学専攻修了、博士(工学)。
専門は、都市デザイン、都市計画史、
都市形成史、景観まちづくり。
中野区政策研究機構研究員、
(公財)練馬区環境まちづくり公社
練馬まちづくりセンター専門研究員、
東京大学大学院工学系研究科
都市工学専攻助教を経て、現職。
- ──
- 今日はまちづくりの専門家、
中島伸先生にお越しいただきました。
中島先生は「ほぼ日の學校」があるビルの前で
おこなわれている路上実験イベント
「なんだかんだ」の運営メンバーでもあり、
ほぼ日はそちらでもお世話になっています。

- 中島
- お世話になってます(笑)。
今日はよろしくおねがいします。
- ──
- よろしくおねがいします。
今日は神田のまちの話をきっかけに、
まちづくりのいろんな話を
教えていただけたらと思うんですが。 - きっかけはほぼ日の近所にある古い建物
「学士会館」の工事の話なんです。
建て替えがおこなわれると聞いて、
気になって調べていたら
「曳家(ひきや)」というキーワードが出てきて、
面白そうだなと思ってお越しいただきました。
 学士会館
学士会館
- ──
- まず、この工事のそもそもの背景を
教えていただきたいです。
- 中島
- はい。私も事業の直接の関係者とかでは
ないんですけれども。 - いま、学士会館の街区(がいく)と
後ろの街区を一体化した
再開発事業が動き出していまして、
ビル取り壊しの工事がはじまっています。 - 「街区」というのは道路で囲まれた
敷地の集まりを言う単位ですね。
英語だと「block(ブロック)」って言いますけど。
- ──
- 学士会館と隣の街区を一緒にした
再開発がはじまってるんですね。
- 中島
- はい。それを聞くと
「学士会館なくなっちゃうの?」とか
思うかもしれませんが、
むしろ、学士会館を残していくための方法として、
一体化した再開発という手段が取られているんです。 - 学士会館の建物そのものを残し、
後ろに大きなビルをセットでつくる。
ひとつの建設事業としてやることで
「それによって捻出された費用で、
学士会館の建物の保存をしよう」って、
そういう方法。
- ──
- 再開発によって保存をする?
- 中島
- そうですね。
- ざっくりした言い方ですけど、
敷地って、それぞれに建てられる容積が
決まっているんです。 - そのとき、いくつかの敷地を合わせて再開発して、
それまで低層で敷地いっぱいに
ワーッと建っていた建物を集約して高いビルにすると、
そのぶんスペースが生まれますよね。
だから「手前側に空地(くうち)を作って
広場にするよ」とやると
オープンスペースが作れる。 - そうすると、まちの人たちも自由に使える
スペースになるので、公共的な価値が上がる。 - 「そのぶんだけ、まちに貢献してくれてるので、
通常の容積より割り増しして
建物を大きく作っていいですよ」
みたいなルールがあって、
それを取り入れた事業なんですね。
- ──
- まちのためになることをやると、
おまけがついてくるってことですか?
- 中島
- はい。そして、建物が大きくなると床分も増えるので、
それを誰かに貸したり売ったりすると、
利益が出ますよね。
その利益で、建物を残す費用に充てるという発想です。 - 大事な建物を残したいときに
「大きなビルと一体の開発事業をやって
費用を捻出する」って、
都市計画のひとつの方法なんです。
- ──
- やっぱり学士会館は、そのくらい
価値がある建物だということですか?
- 中島
- そうですね。学士会館自体は、
国の「登録文化財」として登録されています。 - 建てられたのが第二次世界大戦(1939~45年)前、
関東大震災(1923年)後の近代建築です。
新館と旧館があって、建設時期は3年くらい
違いがあるんですけど、
旧館の完成が1928年(昭和3年)とか。 - 今回、残念ながらいろんな条件から
新館は取り壊すことになって、
旧館の部分だけ保存する形なんですけど。
 左側の5階建て部分が新館、右側の4階建て部分が旧館
左側の5階建て部分が新館、右側の4階建て部分が旧館
- ──
- その学士会館の保存や再開発と、
「曳家」の話って、どうつながるんですか?
- 中島
- はい。「学士会館の保存をしたい」だけなら
そのまま残せばよくて、
「曳家」はしなくてよかったんです。 - でも実はもうひとつ、別の都市計画の都合で
「曳家」が必要になったんです。
- ──
- 別の都市計画。
- 中島
- 「都市計画道路」という、
学士会館の前にある白山通りの道幅を
広げる計画がもともとあって、
学士会館の建物がそこに引っかかっていたんです。
- ──
- 道路を作るために、建物を下げなきゃいけない?
- 中島
- そうなんです。学士会館ってもともと、
道路の拡幅事業がはじまったら、
取り壊さなくちゃいけない場所に建っていたんです。 - で、普通であればそこで建て替えたりとかの
選択がされますけど、歴史的な建造物だから、
やっぱりもとのまま残したいとなった。 - ならば「曳家」しよう、となったけれど、
そのためには後ろに土地が必要。
学士会館の街区だけでは敷地がないので、
「曳家」をすると反対側の道路にはみ出してしまう。
学士会館単体ではどうすることも
できなかったんです。 - そこで、後ろ側の街区の人たちと一体になって
再開発することで、建物を残せるようになったんです。

- ──
- 協力し合うことで土地も確保できて、
壊さなくてよくなった。
- 中島
- そうです、そうです。
- ──
- 「曳家」って、どういうことですか?
- 中島
- 「曳家」の「曳(ひ)く」って、まさに
「綱引き」とかと同じ「引く」ですね。
建物を、建っているままズルズルズルと引いて、
実際に動かすんです。
- ──
- へえーっ! 引けるんですか。
- 中島
- それが、引けるんです。
そういう技術がありますね。 - 地下までそのまま持っていこうと思うと
全部穴を掘らなくちゃいけないんで、
だいたいは地上部分の所の土台を一回切るんですけど、
まあ原始的な方法ですよ。 - 車のパンクを直すときに
「ジャッキアップ」って全体を持ち上げますよね。
それと同じで、いちど持ち上げてから、
あいだに「コロ」を挟んで、
ゆーっくり、ちょっとずつ建物を動かすんです。 - 当然「コロ」だけじゃなく、それを支えるものも
いろいろ動かないようにするものも、
いろいろあるんですけど、それで動くんです。
- ──
- どのくらい時間をかけて動かすんですか?
- 中島
- 本当にゆっくりゆっくり、
目で見てもわからないくらいです。
場合によりますが、たとえば1時間に何ミリとか。
当然壊れたら困るので、チェックや調整もしながら、
数日とか数週間とかかけて動かします。 - 僕もこれだけ大規模な、学士会館クラスのものが動く
「曳家」の現場って、まだ見たことがないんですけど。 - やっぱり大事な建物だからこそ、
そこまでしても「曳家」するっていう。
- ──
- 土地さえあれば、どこまででも動かせますか?
- 中島
- 動かせますよ。
コンクリートの土台を切って持ち上げ、
浮いた状態で基礎の部分をブレないように
固めた土台に組み直し、
「コロ」を挟んで動かしていきます。
最後に抜いて、ゆっくり下ろしていくと。 - 僕も「曳家」の施工の専門家ではないので、
これはだいぶ大雑把な説明ではあるんですけど。
(つづきます)
2025-04-15-TUE
-
「学士会館」って、こんな場所。
旧帝国大学の出身者などによる同窓団体
「学士会」の親睦の場として建てられた建物。
現在は会員以外の一般利用者にも開放。
宴会場、結婚式場、ホテル、レストラン&バーなどの
機能を持つ複合施設として活用されていた。
2025年現在、老朽化による再開発のため
閉館中(一次休館)。2030年頃再開予定。また、学士会館は2025年3月26日付けで、
「東京都指定有形文化財(建造物)」
に指定されました。


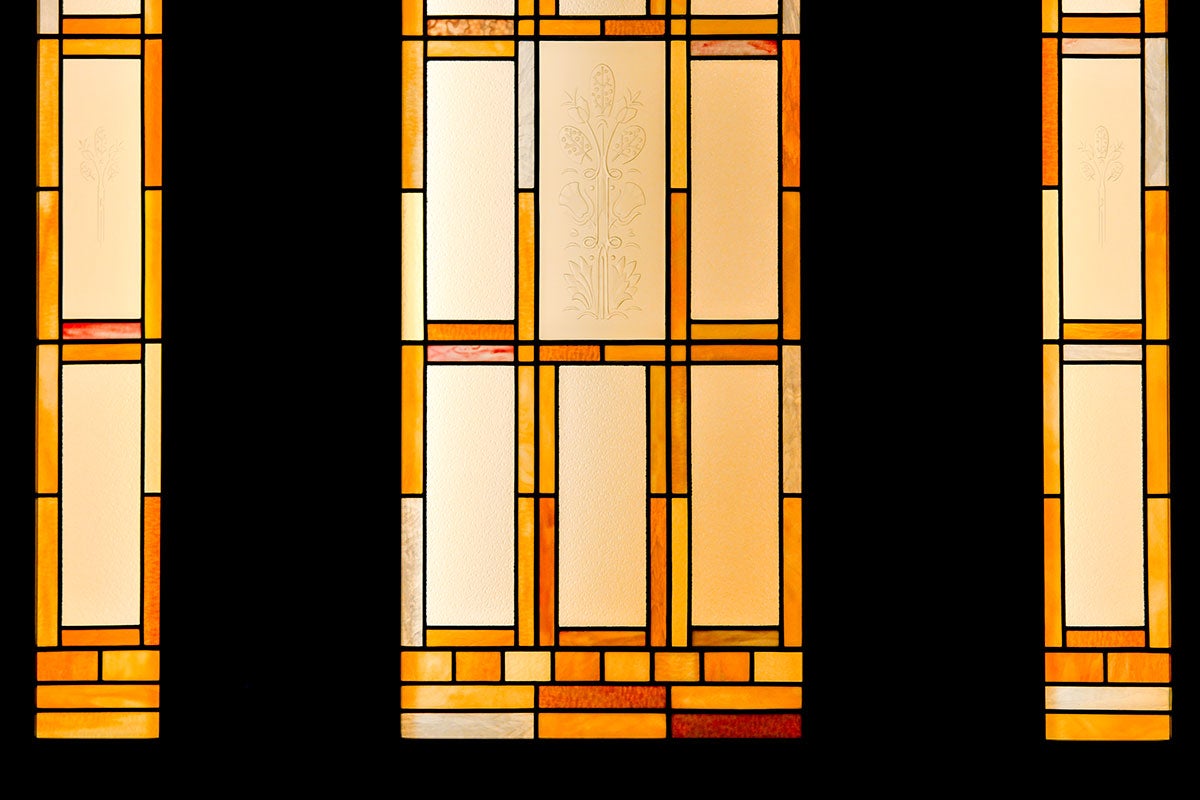
「なんだかんだ」のこと。
中島先生は、神田の路上実験イベント
「なんだかんだ」の運営メンバー。
神田ポートビル(「ほぼ日の學校」スタジオが
入っている場所)の前の道路に200畳の畳を敷き、
通行止めにして、さまざまなパフォーマンスや
ワークショップなどが行われる楽しいおまつり。
「道路でこんなことができるんだ!」があって
たのしいので、ぜひ来てみてください。
ほぼ日も、毎回参加させてもらっています。
(詳しくはこちら)