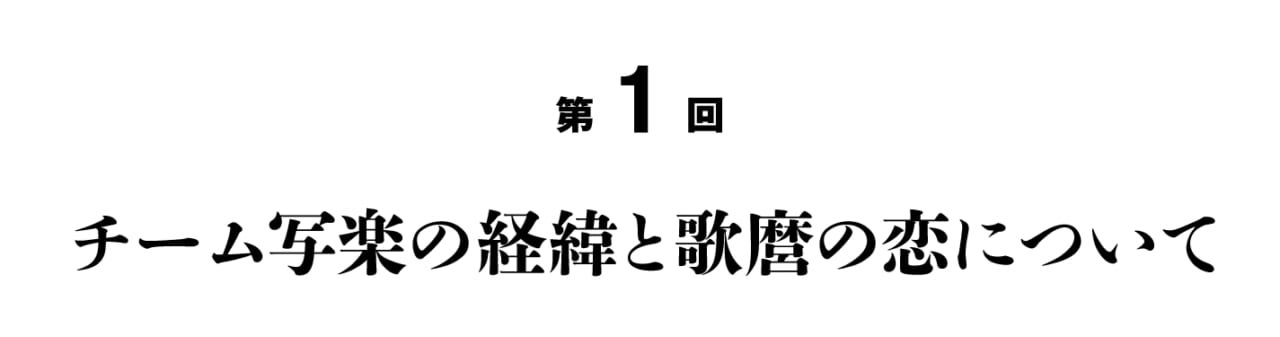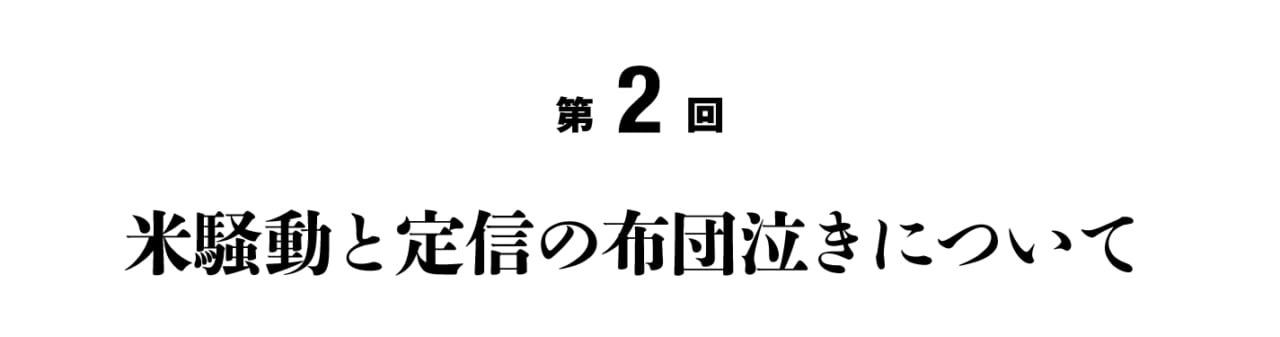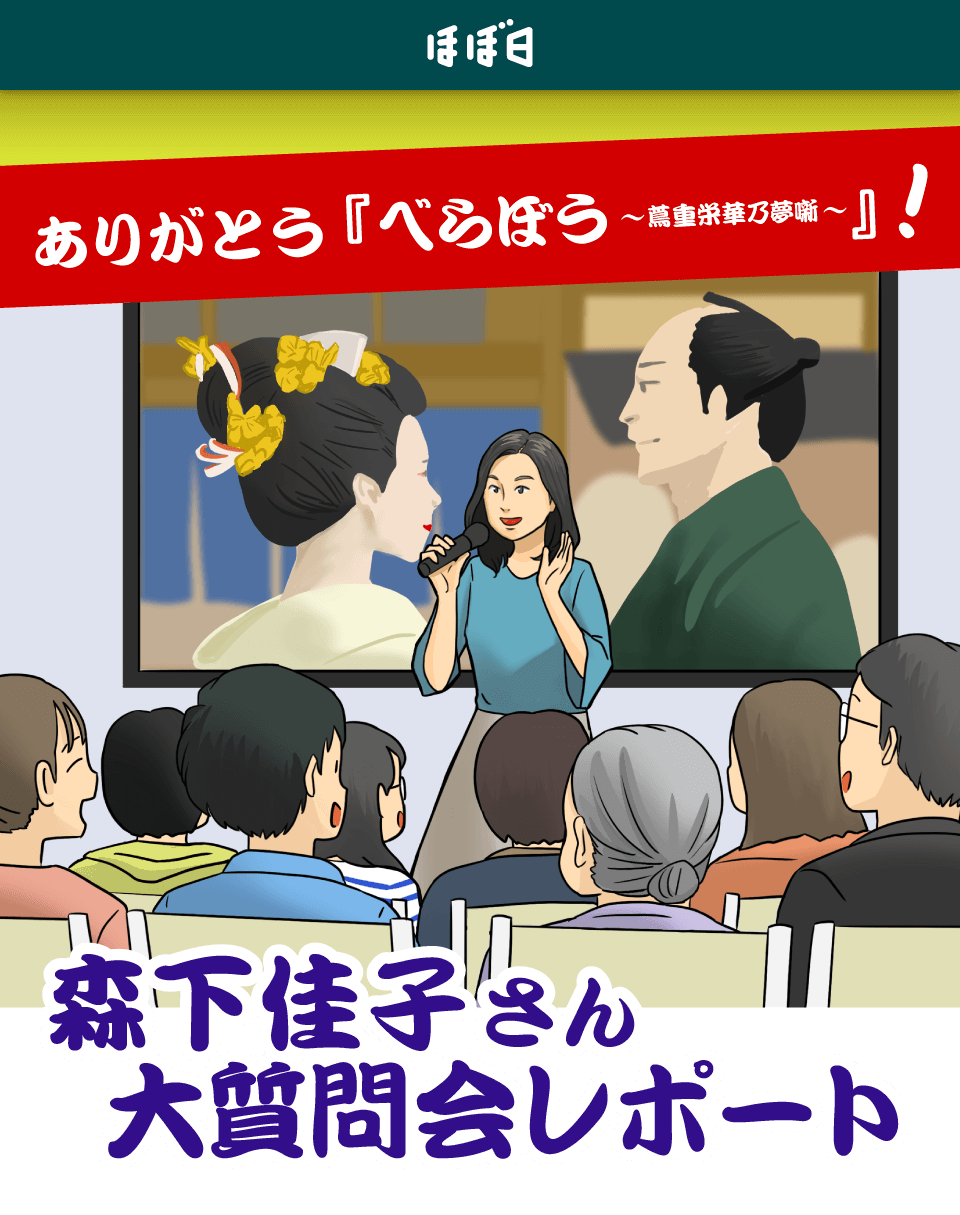
2025年のNHK大河ドラマ、
『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』が
おもしろかった! 終わるのが惜しい!
ということで、最終回放送直後、
シナリオライターの森下佳子さんを熱いファンで囲んで
大質問会を開催しました。
これがもう、予想以上にたのしくて‥‥!
質問者募集のときにお約束していたとおり、
当日のやり取りを大急ぎで
コンテンツにしましたのでお読みください。
森下さん、ありがとうございました!
ちなみに、最後の質問者は糸井重里です。
魂と味わいのイラスト/サユミ
森下佳子(もりした・よしこ)
シナリオライター。2000年デビュー。
代表作に『世界の中心で、愛をさけぶ』『JIN -仁-』
『義母と娘のブルース』『天国と地獄~サイコな2人~』
連続テレビ小説『ごちそうさん』
大河ドラマ『おんな城主 直虎』ドラマ10『大奥』など。
第32回向田邦子賞、第22回橋田賞受賞。
ほぼ日には、なんと2008年から、
なにかといろいろ登場してくださっています。
- 森下
- 森下佳子と申します。
私ももう年で、物覚えがわるく、
忘れて答えられないことも
いろいろあるかと思うんですけれども(笑)、
みなさんとたのしくお話ができたらいいなと
思っております。
本日はよろしくお願いいたします。
- 一同
- (大きな拍手)
- ──
- ほぼ日の永田です。
森下さん、『べらぼう』ファンのみなさま、
どうぞよろしくお願いいたします。
今日は12月18日、『べらぼう』の最終回が
放送されてから4日後ですが、
森下さん、いま、終わってどんな感じですか。
- 森下
- まあ、いまは、何もしてないんですけど、
なんて言うんですかね、
NHKの公式サイトに「こぼれ話」という
コラムを書いたりとか、
取材でしゃべることなんかが意外と多くて、
終わったんだけど、ずっと私、
『べらぼう』のことやってるな、みたいな。
- ──
- 公式サイトのコラム
(「脚本・森下佳子の大河べらぼうこぼれ話」)、
全話にわたる解説で、すごいですね、あれ。
- 森下
- そうなんです(笑)。
あれがね、けっこう時間がかかったんですよ。
- ──
- まだ読んでない方はぜひお読みください。
さあ、それではさっそく
質問会をスタートさせたいんですが、
今回、応募のときにみなさまから、
どういうことを質問したいかという
だいたいのところをうかがっておりまして。
そのなかで大きく2つ、
質問が集中したテーマがありましたので、
まずはそれに答えていただきたいと思います。
- 森下
- はい。
- ──
- それではまず1つ目です。
写楽に関して、質問したい方が
たくさんいらっしゃいました。
- 一同
- (深く深くうなずく)
- ──
- 観客席の、うなずき方がすごいですね(笑)。
- 森下
- (笑)
- ──
- ええと、質問の内容としては、
写楽をなぜああいうふうにしたのか。
つまり、ひとりではなく、
チームにしたということについて、
経緯や思いなどを教えてください。
- 森下
- そうですね。
写楽が誰かというのは、
いま、学術的には「斎藤十郎兵衛」説で
一応は落ち着いているんですね。
でも、実際は、落ち着いているっていうだけで、
「決定打」はまだない状態なんですよ。 - ひと昔前には、もっと、
「写楽は誰だ?」というテーマで、
創作も含めていろんな説が出ていて、
それを調べていくとほんとうにいろいろな人が
「写楽じゃないか?」と言われてるんです。
それこそ、歌麿とかもそうだし、
十返舎一九とかの名前もあったし、
谷文晁とか、松平定信とか、
ほんとうにいろんな人の名前が出ていて。 - で、なんか、まあ、
「こんだけ出るんだったら、
もう、全員でいいんじゃないかな?」って
思ったりもして(笑)。

- 一同
- (笑)
- 森下
- 真面目な資料とか、謎解きの小説とか、
かなり、読んだんですけど、
どれもおもしろかったんですよ。
こんなにおもしろいんだったら、
もう全員でいいんじゃないか、
っていうのがまず思ったことで。 - あと、真面目なことをいうと、
そもそも浮世絵って、
ひとりではつくれないんですよね。
下絵があって、彫師さんが彫って、
摺師さんが摺ってくれないと、
完成しないわけじゃないですか。
そういう意味ですでに工房状態なんですよ。
- ──
- ああ、なるほど、なるほど。
- 森下
- こういう「工房スタイル」って、
いまのアニメとかにもつながってる気がして、
そういうことも感じられたらいいなと。
もともと「写楽複数人説」というのもあったので、
そのかたちにしようかなと、
なんとなく思っていたんです。
- ──
- じゃあ、はじめからその構想が。
- 森下
- いや、でも、はじめはやっぱり、
「斎藤十郎兵衛説」を軸に考えてたんです。
だから、たとえば、斎藤十郎兵衛という人がいて、
つくろうとするもののコンセプトは
斬新ですごくいいんだけど、
絵があんまりうまくなくて
歌麿たちが手伝うことになる、とか。 - そういうふうにしようかなと思ってたんですけど、
なんか、こう、なんですかね、
「一橋治済をこのままにしていいのかな」
っていう気持ちがだんだん大きくなって‥‥。
- 一同
- (笑)
- 森下
- そっちを考えていくうちに、
「斎藤十郎兵衛がそっくりだったら?」
っていうことを、思いついてしまいまして。
そこから、あの本編のような形になったんですよ。
- ──
- それって、脚本を執筆中にってことですか。
それともドラマの撮影前から構想があった?
- 森下
- いや、違います、撮影に入ってからです。
えっとね、撮りはじめて‥‥何話ぐらいかな?
源内さんが死んだあとくらいだったかな。
写楽って、蔦重の人生においては、
出てくるのがけっこう後半なんですよ。
で、そのころのことをいろいろ調べていて、
「一橋治済は悪いなあ」とか思ってるなかで
あれを思いついて。
- ──
- 具体的にはどのへんからどういうふうに
発想が広がっていったんでしょう?
- 森下
- ええとね、まず、
「松平定信が写楽のパトロンだった」
という説があって、
前々からそれは知ってたんですけど、
定信のことを調べていたら、
「定信の息子の嫁は、蜂須賀家から来てる」
っていうことがわかったんです。
で、蜂須賀家と言えば、
「栗山先生じゃないか!」と。
- ──
- 嶋田久作さん演じる、柴野栗山先生。
- 森下
- そうそうそう、で、栗山先生って、
ずっと定信の横にいますよね。
その栗山先生が
蜂須賀家から来ているということは、
蜂須賀家お抱えの能楽者である、
斎藤十郎兵衛のことは知ってるよね?
ってなって。
- ──
- ほう!
- 一同
- (どよめく)
- 森下
- あ、じゃあこの人たちが、
こうやるとかあるかな? みたいな。
そうするとこう、こう、って、
だんだんこうハマっていったんですよ。
- ──
- はーーー!
それってつまり、
栗山先生が一橋治済をはじめて見て
「‥‥お顔が」って言うあの場面、
あの場面までは写楽を含む最後の展開は
決まってなかったということですね。
- 森下
- そうなんです。
- ──
- なんてスリリングな。
- 森下
- スリリングでした。
とくにあの栗山先生の場面を書くときは、
「もうこれを書いたら後戻りできない!」
みたいな感じがあって。
- ──
- はーーー、おもしろい。
- 森下
- そんなふうにして、
あの敵討ちが決まったものですから、
いざ敵討ちさせようとすると、
意外に人がいないということが発覚したりして。 - で、そこから、なんか敵討ちに
力を貸してくれる人いないかって探したら、
「家治の弟、生きてたじゃん」とか、
「上様、家治の最後のことば聞いてたよ」とか、
「大崎はまだいるよね?」とか、
もう本当に敵討ちをするために、
人をあっちこっちからこう掘り起こしてきて。
だから、あの、私、本当に
敵討ちしてる人たちと同じ気持ちでした。
「どこかに味方はいないのか」って(笑)。
- 一同
- (笑)
- 森下
- だからなんか私自身も、
敵討ちのところはハラハラしながら書いてましたね。
本当、人おらんなあ、みたいな。
もうみんな、もう治済にやられてもうてるやんけ、
みたいな感じでしたね。
- ──
- 書いている人もそんな状態。
- 森下
- そうなんですよ。
- ──
- はー、おもしろい。ありがとうございます。
どんどんこのような調子で、
答えながらも脱線も大歓迎ですので。
それでは、ふたつ目の質問に移ります。
これもみなさん聞きたがってました。
歌麿と蔦重の関係。

- 一同
- (深く深くうなずく)
- 森下
- ああー。
- ──
- ふたりをあのように描いたのはなぜでしょう、
という質問がたいへん多かったです。
- 森下
- そうですね。
あの、すごく大きなはじまりをいうと、
美術監修をしてくださった、
松嶋雅人先生という方がいらっしゃって、
ものすごく歌麿に詳しい方で、
浮世絵の見方なんかも
いろいろと教えてくださったんですね。
その松嶋先生が、製作のすごく初期のころに、
「これはね、論文に書くような
論拠がある話ではまったくないんだけど、
ぼくは喜多川歌麿の絵の中に、
すごく、女性に対する理解とか、
女性っぽい感覚を感じるんだ」
っていうことをおっしゃっていて。 - あの、私、若干、ちょっとその、
腐ってるところがあるもので(笑)。
- ──
- つまり、いわゆる腐女子成分が。
- 森下
- そうそうそう。
- 一同
- (笑)
- 森下
- だから、それを聞いて「えっ!」みたいな。
「え、いまなんとおっしゃった?」
みたいなところが、こう、ありまして。
もちろん松嶋先生は、
「いやいやいや、もう何の論拠もないし、
ぼくの感覚でしかないんだけど、
そういうこともあるかもしれないよね」って、
あくまでも個人の感覚として
おっしゃったことだったんですが。 - あとね、松嶋先生がさらにおっしゃるには、
「蔦重も、歌麿も、あの時代の、
あの環境に生きた人にしては、
その蔦重も、あの歌麿も、
女性の影がすごく少ないんだよね」って。
- 一同
- (どよめく)
- 森下
- もうどんどん私が腐っていくようなことを
おっしゃるわけですよ。
だから、もう、私としては、
「先生がそうおっしゃるんだったら、
やっていいんじゃないか」と!
- 一同
- (笑)
- 森下
- で、ああいう、なんですかね、
恋なのか、もっと根源的な何かなのか、
執着とか依存なのか、あるいは信頼なのか、
いろんな言い方があると思うんですけど、
まあ、そういうものを含んだ関係にしようと。 - 史実的なことでいうと、
蔦重って蔦屋重三郎ですけど、
「蔦屋」は屋号で、姓は「喜多川」なんですね。
喜多川氏の養子に入っているので。
で、「喜多川歌麿」っていう
名前をつけたのも蔦重。
やっぱり「義兄弟」というか、
特別な関係だったんだろうなと思うんです。
だから、「名前をあげる」みたいな
そういう感じに書いたんですけど。
- ──
- そんなふうにはじまった蔦重と歌麿ですが、
とりわけ、喜多川歌麿の人生については
ていねいに描かれているように感じました。
- 森下
- そうですね。歌麿に関しては、
まず、彼の絵をぜんぶ並べて、
そこから話をつくっていったんです。
ひとつひとつの絵を見ると、
初期の頃の歌麿ってすごく器用で、
もう本当に人の真似がうまい。
まあ、あの時代は模写から入るので、
人の真似がうまいのは当たり前なんですけどね。
ただ、器用なんだけど、
パッとしない期間も意外と長くて。 - そんな歌麿が出した画期的な作品が、
「画本虫撰(えほんむしえらみ)」という、
虫や花を写生したものなんですけど。
どれも、すごく、きれいなんですね。
当時、浮世絵の人がああいうふうに
写生をすることはあまりなかったそうです。
みんな、だいたいの記憶で描いちゃって、
そのもの自体を見て描くというのはやらない。
でも、この「画本虫撰」はおそらく
見ながら描いたんだろう、っていうことを
松嶋先生がおっしゃっていて。
その後、貝や鳥なんかも歌麿は描くんですけど、
たぶん、そういうものを描いているときが
いちばんよい時代だったんじゃないかなあと。
- ──
- ああ、つまり、歌麿の絵の流れに沿って、
彼という人が表現されているというか。
- 森下
- そうなんです。
あと、歌麿は春画も描いてるんです。
有名なのは『歌満くら』という、
女性の背中越しに男性がちらっと、
ほんとうに目だけが見えている絵が有名なんですが、
なんていうか、特徴的なのは、
ストーリーの面でも、テイストの面でも、
統一性がないんですよ。
ほかの人が描いた春画って、
なんかストーリーがあったりとか、
テーマがあったりとか、
なにかしら統一感があるんですけど、
ばらばらなんですよ。 - で、そのばらばらの絵のなかに、
これは完全に私の個人的な感覚なんですけど、
この人は性に対して嫌な経験があったんじゃないかな、
と感じてしまう絵が2枚ほどあって。
なんか、その絵がなんのために
描かれたかわからないっていうか。
たしかにそういう場面が描かれてはいるんだけど、
ちっともエロく感じないというか。
いやらしさよりも嫌な感情のほうを
先に感じちゃうような絵なんですね。 - なんか、この絵を描くことが、彼にとっては
すごくたいへんだったんじゃないかな‥‥
っていうふうに思えたので、
じゃあなんかそういう過去を書いてみよう、
っていう感じで書いてみたり。
- ──
- ほんとうに絵から感じ取りながら、
それをお話に落とし込んでいくという。
- 森下
- そういう感じでしたね。
後半、おきよさんが出てきたところも、
歌麿の絵の遍歴を追っていくと、
美人絵に行くあたりで、
なんか、彼にとってのミューズが
現れたんじゃないかな、
というのを感じられる時期があったんです。
女性の見方みたいなものが変わっているような。
資料を調べてみるとその時期に
なんかああいう人がいた形跡があって。
じゃあやっぱりこの人は
歌麿にとってそういう存在だったんじゃないかな、
と思ってそういう話をつけて。 - そして、蔦重との最終盤の仕事で、
喜多川歌麿の最高傑作といわれる、
『歌撰恋之部(かせんこいのぶ)』
っていうのができるんですけど、
これが、なんか、すばらしいんですけど、
「売り方がわからない絵」なんですよ。
蔦重の手掛ける絵って、何がテーマで、
どこに売るんじゃ、っていうのが、
いつもはすごくはっきりしているんですけど、
これに関しては、どこに売ろうとしたのかが
よくわからないっていう。
市井の女の人の、恋のため息とか、よろこびとか、
表情とか仕草を見事に表現しているんだけど、
当時、どこに売ろうとしていたかわからない。 - で、このころに、歌麿と蔦重は、
袂を分かっているっていうこともあって、
『歌撰恋之部』というタイトルも含めて、
私にはこれがもう本当に「恋文」にしか思えなくて。
- 一同
- (深く深くうなずく)
- 森下
- だから、ふたりの最後は、ここに行こう、
っていうのがまず決まったんですよね。
で、そこに向かって書いていったんです。 - あと、彼のいちばんはじめの、
お母さんとの悲惨な話っていうのは、
彼が晩年に取り組んだ
「山姥と金太郎」という
シリーズを下敷きにしていて。
このモチーフをもう、しつこいくらい、
40数枚、描き続けているんですよ。
これはもう絶対何かあるだろうって思って、
まあ、お母さんに対する、
かなえられなかった思いっていうんですかね。
そういうものを絵に描くことによって
昇華していったのかな、と。
だから、もう、歌麿の話は、ほんとうに、
ぜんぶ彼の絵からつくっていったんです。
(つづきます!)
2025-12-30-TUE