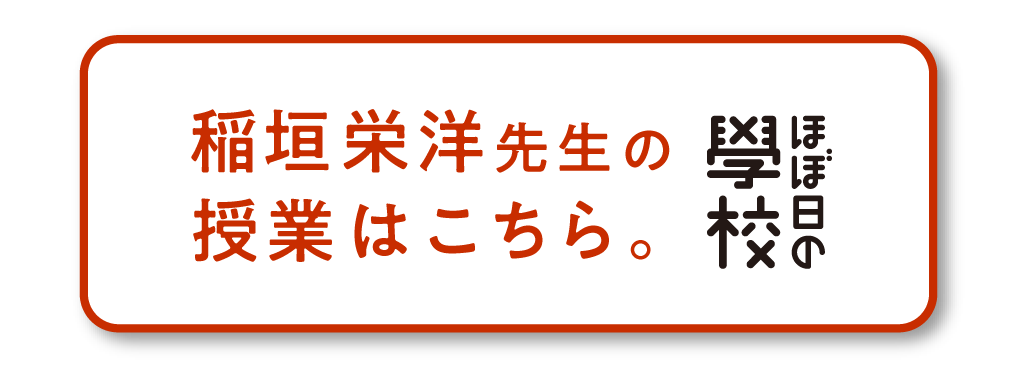あけましておめでとうございます。
とつぜんですが今年、ほぼ日は雑草に学びます。
農学博士(雑草生態学)の稲垣栄洋先生の
「ほぼ日の學校」でのお話や著書をきっかけに、
急速に雑草に興味が湧いてきた
糸井重里と、ほぼ日のメンバーたち。
さらにいろいろなお話を聞けたらと、
先日みんなで、先生が普段から研究をすすめる
静岡大学の藤枝フィールドに行ってきました。
そのとき教えてもらった、たのしくて、
元気のもらえる生物のお話の数々を、
新春第1弾の読みものとしてご紹介します。
雑草のように、戦略的にクレバーに、
やさしく、つよく、おもしろく。
さぁ、新年のほぼ日、はじまります。

稲垣栄洋(いながき・ひでひろ)
1968年、静岡県静岡市生まれ。
静岡大学大学院教授。農学博士。
専門は雑草生態学。
自称、みちくさ研究家。
岡山大学大学院農学研究科修了後、
農林水産省、
静岡県農林技術研究所などを経て
現在、静岡大学大学院教授。
『身近な雑草の愉快な生きかた』
『都会の雑草、発見と楽しみ方』
『身近な野菜のなるほど観察録』
『身近な虫たちの華麗な生きかた』
『生き物の死にざま』
『生き物が大人になるまで』
『手を眺めると、生命の不思議が見えてくる』
『敗者の生命史38億年』
など、その著書は50冊以上。
- 糸井
- 最後にうちの人たちから、質問などありますか?
- 田中(ほぼ日)
- ぼくは親から「雑草のように生きろ」と
言われてきたんですけど、お話を聞いていると
「雑草のように生きる」ってどういうことなのか、
ちょっとわからなくなってきて(笑)。 - 先生がいま思う「雑草のように生きる」って、
どんなイメージですか?
- 稲垣
- 一般的には「雑草のように生きる」って、
がむしゃらにがんばるとか、
踏まれても踏まれても立ち上がるみたいな
イメージですけど、
実際に雑草を見ていると、それはもう全くの間違いで。 - 雑草の生き方って、
すごく戦略的で、クレバーで。
「がむしゃらにがんばる」
みたいなこととは、ぜんぜん違うんです。

- 糸井
- 違う(笑)。
- 稲垣
- よくお話しするのは、雑草って
「踏まれても踏まれても立ち上がる」
とか言われますけど、あれは完全に嘘で。 - 雑草って踏まれたら立ち上がらないんですね。
「踏まれたら立ち上がらない」が
ほんとの雑草戦略だって話をしてるんです。 - それじゃ情けないとか思われるかも
しれないですけど、じゃあそもそも
「なぜ立ち上がらなきゃいけないのか?」
という話で。 - 植物にとっていちばん大事なのは、
花を咲かせて種を残すことですね。
だとすれば、踏まれても踏まれても立ち上がるって、
ものすごく無駄なことに
エネルギーを使ってるわけです。
雑草って、そういう無駄なことはしないんです。 - ただ彼らってそのとき、踏まれながらも、
花を咲かせて種を残すというところは、
絶対ぶれないんですよ。 - 一方で、花壇の苗とか花って、
踏まれても踏まれても立ち上がってくるんです。
そういう植物は結局、種を残せなかったり、
あまり花が咲かなかったりするんですけど。 - 雑草はそんなことないんですよね。
踏まれても、踏まれながらも、
どう種を残そうか、どう花を咲かせようかと、
種をひと粒でも残すことにエネルギーを注ぐんです。
- 田中(ほぼ日)
- はぁー。
- 稲垣
- また雑草って
「どんな場所でも答えを見つけて、
型にはまらず自在に形を変化させる」
という性質があるんです。 - どうしてそんな自由に変化できるかというと、
最終的に「種を残す」という目的が
決まっているからですね。
そこがぶれないから自由に変化できる。
それがほんとの「雑草魂」だなって
私は思うんです。 - だから、途中の道のりはどこ行ってもいいよね。
別に立ち上がらなくてもいいし、
横に伸びてもいいし、茎が短くてもいい。
最後の「種を残す」ところがぶれないなら、
それ以外はなんでもいいんです。 - なので大事なのはその
「大切なものがぶれない」というところですね。

- 田中(ほぼ日)
- ありがとうございます。
ずいぶん見え方が変わりました。
- 糸井
- その大切なものを最低限まで絞り込むと、
「ただ生きる」になりますね。
- 稲垣
- そうですね。それさえあれば、
あとはもうなんでもいいよねっていう。 - もしかしたらそれは、
人間にとっても同じかもしれませんよね。
もちろんそれぞれ、別に
大切なものがあるかもしれませんけど。
- 糸井
- 明石家さんまさんが娘のIMARUさんの
名前にこめた
「生きてるだけでまるもうけ」
ってあるじゃないですか。
あの名前はその思想ですね。
- 稲垣
- そうですね。
生物の世界ではもう、生きていれば勝ちなので。
- 糸井
- あと今日お話を聞きながら思いましたけど、
やっぱり雑草の話って、物語として愉快なんですよ。 - みんなが「気の毒になぁ」とか思ってる間に
ひっそりと違うことをやってて、
「おまえ、そういうことやってたのか!」
みたいな(笑)。 - 園芸用のガーベラとか、作物とかだと、
育て方をわかってる人がいて、
ガーベラも「そうですよねえ」みたいな感じで
育つわけです。
そういうことがあるおかげで
「このパイナップルおいしい!」があるので、
それはそれで嬉しいし、大好きなんですけど。 - だけどドラマとしてはやっぱり雑草の
「あんたの知らないとこで、俺、実はね‥‥」
って、おもしろいんだよなあ。

- 稲垣
- おもしろいですよね。
- 糸井
- それは会社もそうなんです。
うちでもやっぱり、作物を育てるようなことと同時に、
みんながそれぞれに雑草のような、
「実は‥‥」みたいなことをやっていくと
ますますおもしろくなると思うんですよ。 - だからうちも「企業」というより、
「雑業」とか言ってみたいですね。
- 全員
- (笑)
- 糸井
- 企業の「企(き)」って、企画の「企」でもあり、
「あなたは何を企んでるんですか?」
みたいにいつだって質問されるわけです。
あなたの会社の存在意義は何で、
どう儲けるんですかとか。 - だけど「雑」って、いろんなものが混じってて、
どうなるかもわからないですよね。
雑草がそういうことを堂々とやってるみたいに、
自分たちが「雑」みたいなことを
やっていけるようになれば素敵ですよね。
- 稲垣
- ああ、いいですね。
- 糸井
- まあ、まずはぼくらが置いてみたプランターに、
雑草が来てくれるかどうかが、運試しかな。
ぜんぜん1年来ない可能性とかもありますけど、
それはそれで、いろんな発見があると思いますし。 - あとは全国の方が
「私も雑草プランター、はじめました」
なんて教えてくれても嬉しいですよね。
「うちはセイタカアワダチソウが
こんなになりました!」みたいな報告に
「え、いいなあ」とか思うわけでしょう? - セイタカアワダチソウについて
人がうらやんでくれることって、
そんなにないと思うんですけど。
- 稲垣
- たしかに(笑)。でもプランターに
あんな大きいのが生えたら、嬉しいですよね。
- 糸井
- 嬉しいですよ、雑草部からしたら。
逆にすごく小さいものとか、
よくわからないものが生えても、また嬉しいし。 - ぼくはこの価値の逆転は、ある意味、
(美術家の)マルセル・デュシャンのような
おもしろさのものだと思うんで。
社内のみんなも、これから
雑草のこと、どんどんやりましょう。
- ほぼ日乗組員たち
- はーい!
- 糸井
- 稲垣先生、今日は本当にありがとうございました。
みんなで来れてよかったです。
- 稲垣
- こちらこそ楽しかったです。
どうもありがとうございました。
 「ざる菊は揺らすとかわいい」と揺らしてくれる稲垣先生。
「ざる菊は揺らすとかわいい」と揺らしてくれる稲垣先生。
雑草コラム10
もともと、何の意味もないんだから(笑)
(「ほぼ日の學校」稲垣先生の授業より)
(雑草や生き物に学ぶなら、
私たちはどうすれば「よく生きる」ことに
なるのでしょうか、という質問に対して)
すごくいい質問ですね。
それはもう、基本的には、何も考えなくても
「生きてればそれで正解で、
人生の役割をちゃんと果たしてる」
ということになると思います。
だからもう自分がおもしろければいいし、
楽しければいい。
「生きる意味」とか、
「何のために生きていくんだ」とか、
「なぜ自分は生まれたんだ」とかは何もなくて、
他の生物と同じように、
ただ生きてればそれでいいんです。
あとのことはほんとに全部おまけ、
プラスアルファの部分で、
せっかくもらった命であり人生だから、
「もう楽しんだりすればいいんじゃないの?」
ってことですよね。
私自身は自然に対して
「なぜ?」を投げかけるのがすごく楽しいので
そういう研究をしてますけども、
別にそれをしなかったからといって、
私の価値がなくなるわけでもないのかな、
と思ってます。
私も実はほんとに若いときとかは、
無駄がすごく嫌いで、生産性を追いかけて、
スキマ時間にも仕事を詰め込んで、
自分の血肉になるようにとにかく勉強して‥‥
みたいな時期もあったんです。
だけどこの年になると、
なんだかあまりそういうことを考えなくても
いいのかな、と思うようになって。
なにかやるときに、
別にうまくなろうとも思ってないし、
それはお金にもならないし、
何の成長にもつながらないけど、
そのことを楽しんでる人っているじゃないですか。
あの姿勢が正しいなって、
ここ最近すごく思うようになりました。
こんなこと言ったら身も蓋もないんですけど、
どうせもともと、何の意味もないんだから(笑)。
いや、がんばることで充実感を味わえるとか、
幸せになれるとか、それはもちろん
すごく意味のあることですけど、
そのあたりもまあ、プラスアルファのご褒美で。
だからもうすべて
「なんでもありなんだな」みたいなことを
思っています。
たとえば昔「論文100本書こう!」と決めて、
がんばって書きあげたことがあるんです。
だけどそれで100本書いたあとで
なにかすごいことが起きたかというと、
何も起こらなかったわけですよ(笑)。
別に書いても書かなくてもよくて、
自己満足で書いただけの話だったんです。
でも、それはそれで自分のいろんな
モチベーションになったり、
がんばること自体も、人生のプラスアルファの
ご褒美の部分だと思うので、
全部いいんだなと思ってます。
(質問者より「‥‥となると私も実は、
いまこうやって生きてるから、すべて正解?」)
そうです。いらない遺伝子は
どこかでなくなってるはずなんで、
いま遺伝子を引き継いでる自分が
生きているということは、
もう答えのひとつなんですよね。
生物の世界ってそういうことですから。
できるだけたくさんの答えを用意しておく、
その答えのひとつだということですね。
自然界って、別にお金持ちになるために
生きてるわけでもないし、
名声を得るために生きてるわけでもなくて。
生物の世界は、究極の
「命をつないでいく」ですよね。
そのつながれてきている遺伝子が
いまここに存在してるとしたら、
それはそれでもう、成功してるので。
もちろん、いまいる環境以上に
自分を活かせる場所って、ほかにもあるかもしれないし、
それを見つけられれば居心地よく
しあわせに過ごせるかもしれない。
だけどたとえそういう場所に巡りあえなかったとして、
意味がないかと言ったら、そんなことはないですよね。
やっぱり「いま生きてる」、それだけで
すでに意味があるんじゃないですか。
雑草を見ても、ほかのどんな生物を見ていても、
私はそんなふうに感じます。
(おしまいです。2025年のほぼ日も、よろしくお願いいたします!)
2025-01-11-SAT