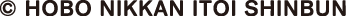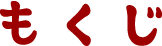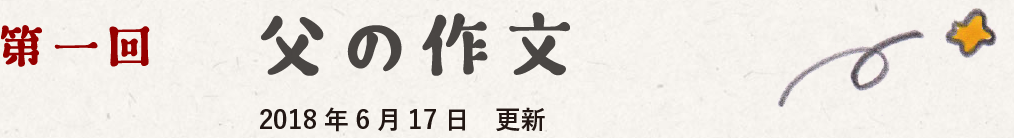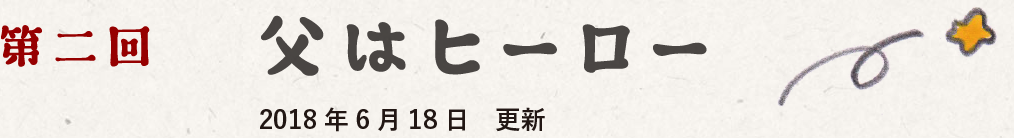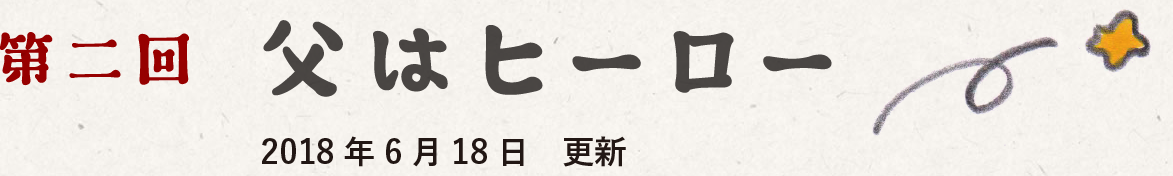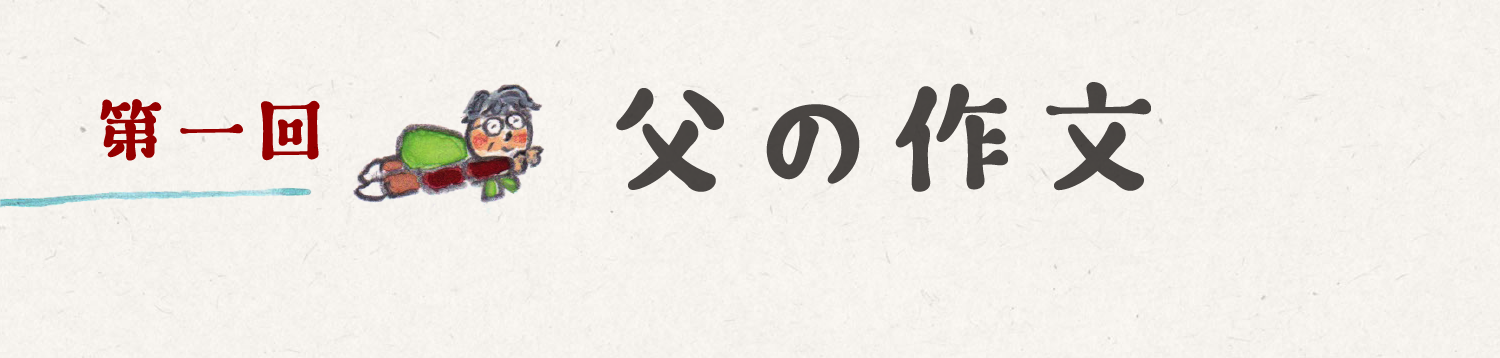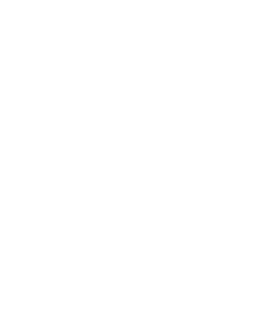中前結花
ほぼ日の塾◉第4期生
イラスト◉ちえ ちひろ
日ごろ、誰かの暮らしや仕事、
時には人生の話をうかがいながら、
記事にまとめるような仕事をしています。
そんなわたしが、「ほぼ日の塾」ではじめて
自分について語る記事に取り組んでみました。
これを「エッセイ」と言うのでしょうか。
わたしにとって、なんともおもしろい体験でした。
それから数ヵ月後、塾の集まりのときに、
「中前さん、なにか書いてみたら?」と、
うれしいお誘いをいただきました。
「なにか」と聞いて思い浮かべたのは、
いちばん近くて、いちばん遠い、父のこと。
父のことをお伝えしたところ、
「せっかくですから父の日に掲載しましょうか」と。
みなさんにも、みなさんのお父さんのことを
ふっと思い出してもらえたらなあ、
とそんな思いで、書いてみます。
父とは、ほんのすこし気まずい関係が続いている。
と言っても「ほんのすこし」なので、
特に気にすることはない。
旅行をすれば土産物を選ぶし、
丁寧な手紙を送ることもある。
先月は、森高千里の切り抜きだってあげた。
けっして仲を悪くしているわけではないのだ。
ただ、なんとなく気まずい。
その小さなきっかけの多くは、
「母」に関わるものだった。
母はひとり娘のわたしを、それはそれは可愛がった。
幼いころから何をするにもいっしょで、
四角いこたつを囲むときも、
わたしと母は窮屈をしながらその一辺に並んで座った。
出かけるときはいつも手をつないで前後に揺らし、
まるで女子学生のお泊まり会のように毎晩毎晩話し込んだ。
他愛もないことを、さも可笑しそうに、くすくすと。
二十歳を超えても相変わらずだった。
東京で働くようになってからも
毎晩のように電話でそれを続けたせいで、
父は、「おい」と「ゴホン」を
ちょうど半分ずつ混ぜたような
おかしな咳払いばかりが上手くなった。
母とわたしは「仲良し」が過ぎたのだと思う。
父はといえば二十数年間、ひとり蚊帳の外側に寝転んで、
野球とボクシングの中継ばかり見ていたのだ。

母が亡くなって4年。
変わらずわたしは東京で仕事に追われ、
父とは離れて過ごしている。
父の住む奈良の町は穏やかでいいところだが、
ここ数年、足は遠のくばかりだった。
父とふたりで過ごす時間は「母がいなくなったこと」を
改めて確かめるような残酷さがある。
それを堪えるには、わたしの器は足りないし、
なによりも、父とは話すことがないのだ。
なんとなく気まずくて、まいってしまう。
もっとも後悔しているのは、暇をつぶすように
「すこしだけ柴田恭兵に似てるね」
と言ってしまったことだ。
以来、父は連絡事の電話の最後に
「柴田恭兵でした」などと加えるようになった。
半端に褒めたりしてはいけない。
調子に乗りやすいその性格もまた、
「気まずい」原因のひとつかもしれなかった。
そんな父から不思議な便りが届いたのは、数ヶ月前。
かしこまったおかしな文章からはじまる。
「これは、自治会が発行する新聞に頼まれて、
お父さんが書いた文章である」
そして、『喜んでもらえる喜びを味わいたい』
というタイトルの寄稿文が続いた。
どうやらわたしはこれを読まねばならぬらしい。
仕事からの帰宅後で疲れてはいたが、
正直ちょっとおもしろそうだ。
「かるく添削をしてあげても良いけれど」
カバンを下ろして髪を結びながら、そんなことを思った。
ところが読み終わるころには、
首を真横にかしげるほどの「不思議」に襲われる。
これを書いたのは、ほんとうにあの父なのかしら‥‥。
父の住む部屋には
「管理人室」という小さな看板がついていて、
マンションの「管理人のおじさん」を仕事にしている。
8年ほど前に夫婦ではじめたが、今は父ひとりだ。
その作文には、マンションに住む人々に
頼られ、愛され、
生き生きと暮らす父の生活が綴られていた。
誰かに喜んでもらえることが、
父のいちばんの喜びなのだという。

思えば、わたしは
「ひとり」になってからの父をよく知らない。
母の手料理を食べたあとは、だらりと横になり、
ピッチャーやボクサーにいちいち
文句を連ねる父しか知らないのだ。
飼い犬によく吠えられ、それを叱るものだから、
余計に吠えられていた。そんな父だ。
たった200文字の作文だったが、
そこには、まるでわたしの知らぬ父がいた。
たったひとりの家族を他人のように感じて、
心細い思いもあったのかもしれない。
なにより、自信家の父のことだから
「これは本当なのかしら」と心配になってきたのだ。
父はいま、いったいどんなふうに暮らしているのだろう。
週末、わたしは奈良を訪ねてみることにした。

父の部屋を訪ねるといつも、
線香とコーヒーが混じった独特の香りがする。
決して嫌うような香りではないけれど、靴を脱ぐ前から
「もう、ここに母はいませんよ」
と言われているような気がして、
「はいはい、知ってますよ」
と、すこしいじけた気分になる。
仏壇には、ピンクのガーベラやジニアが飾られており、
どこかでもらったお土産なのか、
ハイカラなお菓子がいくつか並べてあった。
 物は多いが狭い部屋の中は整えられていて、
物は多いが狭い部屋の中は整えられていて、
わたしが訪ねると、夕方だというのに
すでに客用の布団が用意されていた。
「ちゃんとしてるなあ」
と聞こえるようにつぶやくと、
「あのお母さんが、選んだ男やからな!」
と隣の部屋で大きめの返事をした。
これは父の口癖に近い自慢のことばで、
母を失くしてからは、
ほとんど決め台詞のようになっている。

父は、大抵のことに自信たっぷりだった。
この理屈のわからぬ自信もやはり、
母によるところが大きいらしく、
料理上手で愛嬌にあふれた母のことを、
それはそれは鼻にかけていた。
そのせいで
「“あの”お母さんが選んだ男や」というのが、
父のきっての自慢であったけれど、
銀婚式の祝いを父が忘れていた夜に
「あかん、相手まちがえた」
と母が盛大にため息をついていたことも、
わたしはちゃんと知っている。
四角いテーブルの上には金魚鉢が置かれており、
中では金魚ではなくメダカがすいすいと泳いでいた。
「何匹いるの?」
「6匹よ」
愛犬を亡くして、「ペットはもういい」と言っていたが
一人暮らしで気が変わったのだろう。
「日記は書いてるの?」
「書いとるけどな」
毎年1月1日に、父には手帳を贈っている。
「ほい」と見せるので開いてみると、
読めぬほどの走り書きで、
毎日の食事が朝・昼・晩と記されていた。
「ブリの照り焼き」や「麻婆豆腐」、
驚いたのは「スペインオムレツ」だ。
「料理してるの?」
「完璧や。お母さんの次に上手いんちゃうか」
知らぬことばかりだった。
「マンションの人とそんなに仲がいいの?」
いちばん聞いてみたかったことを聞いてみる。
「なんちゅうか、お父さんは
マンションの英雄と言うのか、
ヒーローみたいな感じやなあ」
またはじまった、と
奥歯で歯ぎしりしたくなるのを堪えながら、
「直接聞きに行こかなあ」と顔色をうかがった。
内心、ちょっと意地悪な気持ちもあったのだ。
ところが、意外にも返事は
「ほな、挨拶がてら行こか」だった。
そしてわたしは、マンションに住む人々から
驚くほど多くの逸話を聞かせてもらうことになる。
授業参観ならぬ、「父の仕事ぶり参観」で
わたしはわたしの知らない父と、
たくさんたくさん出会う。
なにを隠そう、
父は本当に「マンションのヒーロー」だったのだ。

2018-06-17-SUN